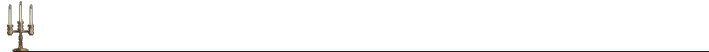クスクス 前編
アリス Side
遠くで鳴る鐘の音を聞いたような気がした。
寝呆けたままの脳味噌が今は何時なのかと訊いてくる。重たい瞼を押し上げて、僕は薄暗い室内の様子を窺った。
奥の方では一組しか無い客用蒲団へ包まったマリアが軽い寝息を立てていた。最初に酔い潰れたのと唯一の女子部員であるということから、我が部にしては珍しい好待遇となった次第である。望月と織田はその手前にある炬燵の脇へ寝転がり、身体に毛布を巻きつけて眠っていた。
この部屋の主である江神さんの姿を探した。窓際に腰を下ろして外界の様子を覗う人のシルエットが僕の視界を横切った。
被っていた毛布の中から抜け出す。音を立てないよう注意しつつ、四つん這いで江神さんの方へ擦り寄った。
「アリス・・・か?」
眠れる他の酔っ払い達を起こさないようにという配慮からだろう。囁くような声が僕の耳元を掠めた。吐息ともつかない声で「はい」と返事する。
江神さんの隣りへ座り込み、壁に背を預けた。
「何、見てはったんですか」
訊ねると、彼は黙ってカーテンの裾を持ち上げた。
なんと、雪が降っているではないか。
真綿のようなそれは、吹きすさぶ突風に翻弄されつつも優雅な軌跡を描き、舞い落ちる。街灯の放つ淡い光がスポットライトとなって、しんと冷えた闇の中へその様を鮮やかに映し出していた。
辺りを支配しているのは厳かな静寂ばかりだ。
「・・・寒い訳ですね」
口をぱくぱく動かしただけにも拘わらず意味は伝わったようだ。手前に置いてあった毛布へ江神さんが手を伸ばす。大雑把にたたんであったそれを手早く広げ、僕の膝上に掛けてくれた。
「風邪、ひいたらあかんやろ」
こちらが何か言うよりも早く、布端を肩の上まで引っ張り上げられた。それから江神さんは僕が置き去りにした一枚を手繰り寄せてその身を包み込んだ。
こうしていると二人して蓑虫みたいだ。その格好のままで僕たちはカーテンと窓の間に頭を差し入れ、外の景色を見遣った。
「どうせなら、クリスマスに降った方がええのに・・・」
思ったままを口の端にのせる。隣の人は微かに表情を歪めた。
「積もるまではいかんやろ。そのうち雨に変わる。けど、明け方まで雪のまんまやったら、朝、道が凍っとるかもな」
「はぁ・・・だとしたら、あまり早い時間に出歩かない方がええですね」
望月の履いていた革靴やマリアのハイヒールが僕の脳裡をチラリと掠める。どちらも、凍結した路面には著しく不向きな装身具であろう。とはいえ、気象庁が発表したのは夜半の降水確率40%という曖昧なものに過ぎなかったのだから、それ相応の支度無しでやって来た彼らを不心得だと決めつけるのも酷である。
「そんなに飲まんかった筈やけど、皆、疲れとったんかもな。『紅白』も『ゆく年くる年』もとっくに終わってしもうたわ」
江神さんは軽く顔を捩り、安穏たる眠りへ身を委ねきっている三人の様子を確認した。
「一応、予報では日中晴れる言うてたし、この分やと、あいつらもそう早くに起き出してくることはなさそうやから―――出歩く頃には地面の方もなんとかなっとるやろ」
そうですね、と相槌を打ってから僕は飲み会の有様を思い返してみた。
最初に眠気を催したのはマリアである。まだ早い時刻だったし、我々男性陣の意識もハッキリしていたので、雪崩れる寸前であった本の山を解体し、部屋の奥へ客用蒲団を敷いた。続いて望月が目を瞬かせ出した。江神さんが隣の部屋(主は既に帰省しているのだが、不在時には予備の毛布や客用寝具を借りて良いという協定があるらしい)から持ち込んであった毛布を彼に手渡す。その後、僕の身体にも暖かいものを掛けられたような記憶がある。
織田がそれ以降、どのくらい持ち堪えられたのかは判らない。しかし、彼が睡魔に打ち負かされた後も江神さんは一人でずっと起きていたのではないか。ふと、そんな気がした。
「江神さん、もしかして寝てはらないんですか?」
訊ねると苦笑混じりの小さい声が返ってきた。
「なんや、寝るのが勿体のうてな」
皆で新年を迎えられるのはこれが最後だから。
誰彼ともなく言い出して決まった年末年始のスケジュールだった。大晦日を一緒に過ごし、初詣へも行こう―――ただそれだけの為に望月と織田とマリアは帰省を年明けへ伸ばし、大学が休みに入った後も京都での生活を続けていた。そして江神さんも、毎年バイトで埋まっていたこの時期を珍しく休むことにしたのだ。
あと何回、こんなふうに皆で飲めるだろうか。
例会と称して集まり、杯を傾けながら話す内容はいつだって多種多様に富んでいる。五人もいれば、ミステリに限らずいろいろな話題が飛び出すから、それはそれで楽しく面白い。傍からはくだらないと思われることにでも大真面目に取組み論じ合うのが、推理小説研究会というサークルの特性であり莫迦莫迦しさなのだ。
だから昨夜も他愛ない雑談に始終していた筈だった。そう、話すのはいつだって出来る。けれども―――
その気になれば、社会人となろうが院生となろうが、また皆で集うことは可能であろう。しかし、同じ英都の学生として過ごせるのは今この時しか無いのだ。同じ立場で同じ経験が出来る最後の機会。八年の長きに渡って在籍していた江神さんはそれを一番強く感じているのではないか、と思った。
五人揃っての年越し時に、敢えて語り合いたいことがあったかもしれない。
きちんと言葉にしておきたいことがあったかもしれない。
そう考えたら、なんだかとても申し訳ない気分になってきた。
「あの―――皆して早うに潰れてしまって・・・すいません」
江神さんはきょとんとして、こちらを見返してきたが、すぐに表情を和らげた。
「ああ、違うんや。そういう意味で言うたんやなくて―――確かに、起きてて話したり飲んだりしとる方が過ごした時間としては有意義なのかもしれんけどな。アリス達がここで寝てるのを見とって、俺も結構幸せやったんやな、と思うたんや」
僕たちの寝顔を見ながら、炬燵上に散乱していた皿や空き瓶の類いを片付けていたらしい。それを聞いた途端、このひとも大概悪趣味だなと思った。
「ニ、三回、缶を取り落として、結構、大きな音させてしもうたんやけどな。誰も起きんかったわ」
やれやれ、なんとも呆れた後輩達である。四人もいながら揃って眠りこけているあたりが、不甲斐なさを通り越して情けない。
「その・・・手伝いもせんで―――すいません」
慌ててそう詫びた僕に江神さんが笑いかけた。
「アリスが謝ることあらへんやろ。煩くして目ぇ覚まさしてしもうたら、それこそこっちが謝らなあかん」
淡々とした口調の中に、普段と変わらぬ優しさが感じられる。彼は更に言葉を続けた。
「片しながら、この八年を振り返っとったんや。長いことおったからなぁ―――いろいろなことがあったし、いろいろな人とおうたけど、EMCにおって良かったと思うとる。モチも信長もマリアもほんまにええ仲間やったわ。それに・・・」
にっこりと微笑んで、江神さんは僕の頭へ腕を伸ばした。長い指が髪に絡められる。
「アリスと逢えたんやから」
「江神さん・・・」
彼の掌が首筋をつたい、肩へと降りてくる。身体ごと抱き寄せられ、掠めるようなキスを受けた。
唇へ指の腹をあて、触れられた部分を確認するかのようになぞった。その手を移動させてそうっと江神さんの頬へ添える。
部長が静かに目を閉じる。気がつくと、自分から唇を合わせていた。
息継ぐ間もなく、深い口付けへとって変わられた。口腔を弄られ、唾液の分泌量が急激に増える。瞑った瞼の奥は熱さを増し、絡まり合う舌の感触に酔わされてとろけそうになる。
長い長いキスを終えて、やっと唇を離す。
やや高い位置にある彼の肩へ手を回し、ありったけの力をこめて抱きしめた。ずり落そうになる毛布を気にしていると、その上から江神さんが腕を回してくれた。
どれくらいそうしていただろうか。
唐突に部長が呟く。
「そうや、忘れとった」
「何をですか?」
問い返すと、大真面目な顔で挨拶された。
「新年、おめでとう」
ああ、そういえば―――日付けはとっくに変わってしまったのだ。既に今は新たな年の第一日目である。
「今年もよろしゅうな」
「こ、こちらこそ、よろしくお願いします」
同じような言葉を急いで返す。
本来ならキチンと三つ指をついての礼を尽くしたいところだが、毛布ごと抱きすくめられているのでそうもいかない。
首から上だけを動かして、精一杯かしこまったお辞儀をする。つられてか、江神さんも頭を下げた。
次の瞬間、コチンと音がして僕たちは額をぶつけ合っていた。
二人揃って瞠目し、互いの瞳を覗き込む。まるでそれが合図であったかの如く、失笑が洩れる。
江神さんと僕の間で『何か』が弾けた。
クスクス、クスクス―――額を合わせたまま極力声を殺し、二人して一頻り笑い合う。
直截に触れている面積は少なくても其処から確実に伝わる江神さんの体温、存在、そして―――気持ち。その暖かさは僕の中へ確かに沁み込んで、余すところなく体内を拡がってゆく。それと同時に、くすぐったいような幸福感が後から後から湧き上がってきて僕の全てを満たしてくれる。
人を好きになったのはこれが初めてではないけれど。
恋をして悩まなかったことなど一度だってないけれど。
何があっても失いたくないと思うほどの人に巡り合ったのは初めてだから。
もの物静かで穏やかで黙っている姿がナチュラルに男っぽい七つ年上の謎めいたひとは、普通の学生が有り体に通過する大学生活を倍にして経ている。成績不良や怠惰な生活が原因で進級を阻まれるのなら納得もするけれど、江神さんにそのような要素は見当たらない。何か事情があって留年を繰り返しているとしか思えなかった。
単刀直入に訊ねたなら、長いこと大学へ留まり続けた真の理由について、案外サラっと明かしてくれたのかもしれないが、部員達はそれを部長へ問いかけたりせずに歳月を過ごしてきた。
どうして、江神さんは卒業しはらないんやろう―――
初めは単なる好奇心だった。後にそれが尊敬と憧れに変わり、気がついた時には彼に恋していた。切ない想いを随分長いこと抱え続けたけれど、幸運なことに僕の気持ちは拒絶されることなく、受け容れてもらえた。
恋人同士となって一年弱。それでも、謎は相変わらず謎のままだ。気にしていないと言えば嘘になるが、その反面、どうでもいいと感じている自分がいるのもまた事実だった。
このひとが自ら匂わせたり話したりしない事柄を探ったり調べたりするつもりなど、僕には皆無だから。
嫌われたくないという気持ちによって己を無理にも納得させた訳ではない。江神さんと多くの時間を過ごすうち、漠とそう思うようになった。彼が現役で入学を果たしていた場合、僕たちが出会えた確率は四分の一にまで減ってしまう。そんなことへも気づいたから尚更、浪人および留年するに至った経緯や事由について詮索する意欲が失せていったのかもしれない。
いつしか相応しい時が来たなら、なぜ長いこと学生であろうとしたかを江神さん自身が教えてくれるだろう。或いは、どうしても話したくない、または話す必要もないこととして、ずっと口を噤み続けてゆくのかもしれない。
そのどちらでも、僕は構わない。
理由(わけ)を知りたいという気持ちは今でも確かにあるけれど、それは個人の領域へ属する事柄だから。
秘されたものを強引に暴いたところで彼の全てが手に入る訳ではない。それよりも、まだ知らぬ一面をそのうち垣間見ることができるかもしれないと夢見る方がはるかに建設的だ。
どうか、これからも、あなたと共に歩んでゆけますように。
歓びや悲しみを分かち合う相手として、その傍らにいられますように。
願うのはその二つのみにしておこうと日頃から心砕いているにも拘らず、想いが募るばかりで。
「好きだ」という一言で済ませられないほど恋しい存在を知ってしまった以上、時として心が熱く疼き、身体には震えさえ走る。
更には、分かれて毛布へ包まっているこの状態が僕の意識を掻き乱し、複雑な心境にさせる。
着衣以上の厚みを持つ布地へ阻まれ、相手を直に感じられないでいるもどかしさ。かといって、一つ毛布の中へ納まるという訳にもいかなかった。下手に身体を密着させたら最後、互いの肉体が揃って厄介な変化を遂げかねない―――過去にも何度かそういう経験をしていたからこそ、今は我慢と己へ強く言い聞かせるものの、掌にはじっとりと汗が滲んできている。
まずい。
警鐘を鳴らしはじめる意識へ反し、肌を重ねたいという欲求が強い力で僕を捻じ伏せようとする。それに屈しないためにはまず、寄せていた身体を離せばいいのだけれど―――今の僕にとっては、それもまた辛い。
もう、駄目だ・・・
合わせていた額をとりあえず離し、江神さんの頬へ軽く口付けた。
「アリス、あかんて」
慌てて顔を逸らした僕の耳へ、少し困ったような声が響いた。
「これ以上何かしたら、我慢できへんようになるやろ」
いったん火がついてしまった生理的な願望を理性で抑え込めれば苦労などしない。眠っているとはいえ、他人が同室内にいるというこの状況が、返す返すも恨めしい限りである。
このままだと、今夜はいつになく寝苦しい夜を過ごすことになりそうだ。悶々とした心を抱え、視線を落とす。それ以上身動きせず大人しくしていると、躊躇いがちな声で切り出された。
「隣、空いとるけど―――行くか?」
微かな衣擦れの音をさせて何やら弄っていた手が二組のキーホルダーを取り出した。一つは僕もスペアを預かっているこの部屋の鍵である。それを炬燵の上へ置いた後、江神さんは見慣れない方を手許に残した。毛布を借りたくらいだからお隣りの合鍵も預かっていて然りであることにやっと気づいて、僕は速攻で頷いた。
緩慢な動作を心掛け、極力音を立てないようにして動いた。かなりの時間をかけて廊下へ出た時には、緊張の余り手足の関節がおかしくなったような錯覚を感じたほどである。カチャリという音をさせないよう細心の注意を払って隣室の鍵を開け、ドアノブを静かに回す。室内へそろそろと入った後、これまた音に気をつけて施錠した。
人気の無い空間は冷え切っていた。その、あまりの寒さに思わず身震いしそうになった。
江神さんに何度も泊めてもらっているせいで、僕はこの部屋の住人を少しく知っていた。衣笠山麓にある大学の四回生。恰幅が良く性格も大らかなその彼とは、数回ほど言葉を交わしたことがある。
そのまま突っ立っているところを背後から抱きしめられる。うなじに柔らかなキスが降り注ぐ。
戒められた腕を解いて後方へ向き直った。正面から抱き合い、口付けを交わす。
離れたくなくて、江神さんにしがみつく。よく動く優しい手がシャツのボタンを外し、肌の上を滑る。直に触れてもらえて漸く、この身も心も落ち着きを取り戻しはじめる。
江神さんが耳元で囁いた。
「声、出したらあかんで」
こくん、と頷いてから、僕は目を瞑った。熱くなった身体のラインも、指先の律動も、微かに喘ぐ息さえも、辛うじて判別がつく程度の暗闇へ溶けてゆく。カーテンの隙間から洩れいずる雪明りに照らされて、時折かいま見える表情は、泣けてくるほどに愛おしく感じられた。
「あと少ししたら、戻らんと―――」
胸に僕を抱いたまま壁に凭れていた江神さんが、ポツリと呟いた。
解っている。あまり長いこと、向うの部屋を空けている訳にはいかない。こうしている間に三人のうちの誰かが目を覚ましでもしたら厄介だ。まぁ、僕たちの関係は既に知れているから、夜中に抜け出したことがバレたとしても別段驚かれたりはしないだろうけれど。
「本当は・・・したいんやけどな」
やや低めのよく通る声で紡がれた言葉に、心臓がドクンと跳ねる。
「江神さん、それ―――言うたら、あかんです。僕かて我慢してるのに・・・」
口をついて出た科白と声色の未練たらしさに、我ながら呆れる。そんな僕の頭を部長は宥めるかのように撫でてくれていた。
元々、最後までするつもりはなかった。
隣室で眠っている三人のことも頭にあったし、合鍵を託されていたとはいえ、勝手に上がり込んだ他人の部屋でそういう行為をするのは気が引ける。だから、互いの欲求を手と口で処理するだけにとどまった。
それでも、触れられないで、触れてもらえないでいるよりは、ずっといい。
毛布や服越しに伝わる感触では満足できないから。
肌上を滑るようなキスでは物足りないから。
顎を捉えられ、今一度、深く口付けられる。重ねた唇から微かに洩れる吐息が淡い靄となって僕たち二人の周囲を漂った。
手を繋いだまま、廊下へ出た。鼠小僧さながらに気を配りつつ、江神さんの部屋へ戻った。
辛うじて横になれるスペースが二箇所あるにはあるのだが、そうすると離れ離れになってしまう。僕たちは先程この部屋にいた時と同様、窓際の壁へ凭れ、並んで座り込んだ。再び毛布を被って各々暖をとる。
少し前まで直に感じていた温もりがひどく名残惜しい。そっと頭を傾け、隣に居る人の肩へ預けた。江神さんが僕の顔を覗き込み、柔らかく微笑んだ。
眠る前のひと時くらい、こうしていてもいいだろう。
毛布の下、見えない位置でこっそり握られた手から伝わる暖かさが、僕にささやかな歓びを噛み締めさせてくれた。
へ戻る
すいません。たった一晩の話にも拘わらず、またもや長くなってます。なんでだろ(涙)
視点分けたのが仇になったかも。どうか、続きを読んでください…