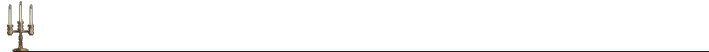傘 後編
「何・・・やて?」
「ああ、間違いない。先週、俺の目の前でマリアが買うたんやから」
その日、授業が終わってバイトへ行くというマリアと、人との待ち合わせで四条河原町へ出る予定のあった私は共に出町柳駅まで歩き、京阪地下鉄を使った。揃って三駅目で下車した私たち二人は、突然降り出した雨に慌てふためいて高島屋へ駆け込んだのである。天気予報に促されて折畳み傘を用意していた私とは反対で、降ったら新しく買うつもりでいたマリアが一階東側出入口脇に設けられているコーナーへ直行した。約束までまだ時間のあった私は、彼女の傘選びに付き合い、落ち着いた色味が好印象を与える青い一本を購入した瞬間へ立ち会っていたのだ。
「ということは―――あの青い傘は、マリアが江神さんかアリスに貸したもんっちゅうことか」
「そうなるやろうな」
相槌を打った私に織田はふむふむと頷いてみせたが、すぐに不思議そうな顔をした。
「けど、そしたら今日、マリアは傘を二本持ってきとったんやろか?」
彼の言いたいことは、私にも伝わってきた。
いくらマリアが先輩または同級生思いだとしても、こんな天候の最中に自身のことを後回しにして傘を貸してしまうとは考えにくい。しかし織田が首を傾げるように、今日に限って傘を二本持ってきていたというのも何だか釈然としなかった。更に―――
借りた傘があるにも拘わらず、なんでまた、あの二人はそれをたたんで、雨の中を走っていったのだろうか?
私がそれを口に出すと、織田も同意した。
「大体、店の傍に来るまでは、相合傘やったやろ? 判らんなぁ」
「これは謎やな」
ほとんど口癖になっている科白を私が唱えると、織田は「何でもかんでも『謎や』言うから、事態がややこしなるんやろ」と、本格ミステリファンの探求心に対して水を差すような発言をしてから、ちょっと考えて続けた。
「ポイントはいくつかあるな。あの傘が間違いなくマリアのもんやと仮定した上でやけど、こんな天気にも拘わらず、どうしてマリアが傘を貸したのか? どうして江神さんとアリスが一緒におったのか? 濡れ鼠になるのが一目瞭然やのに、どうしてこの店の前から走り出したのか?」
誰がまとめてもそうなる問題点を一通り指摘した織田は、更に言葉を投げかけてきた。
「お前がクラブノートに書いた『傘』よりは、気の利いた謎やと言えるんやないか? 案外、北村薫風の真実が待ち構えてるかもしれんぞ」
全く、失礼な言い草である。私は織田の顔を軽く睨んだ。
青い傘のことはともかく、アリスと一緒に江神さんが走っていった以上、部長から傘を借りるという案は諦めざるを得なくなった。二人で下宿にいるところを誰が呼び出したりできるものか。
しかし、これ以上もたもたしていると八萩書店の方も閉まってしまう。そうなってしまっては、こうして雨が小降りになるのを待ち続けていた意味がない。大きく溜息を吐いた私は、店の中をビニール傘が置いてある方へ移動した。
私が品物に触れるより早く、織田の手が二本の傘を鷲掴みにした。
「ああもう、傘代くらい、俺が恵んだるわ」
レジの前に立った太っ腹の同期は、素早く支払いを済ませてしまった。
「なんや、悪いなぁ・・・信長、ええんか?」
「これくらい、構わん―――けど、俺はお前と相合傘なんて、ゴメンやからな」
手に持ったうちの一本を私の前に突き出し、憎まれ口を叩いてくる。私も負けじと応えた。
「それは、こっちの科白や」
大体、小さなビニール傘一本で大の男が二人、驟雨を避けようとすること自体、相当に無理があるではないか。
随分、長いこと居座らせてもらった店からの脱出を果たした私たちは、全く衰えない降り方に辟易しつつ、八萩書店へ足を向けた。
路面を大量の水が洗っていた。一歩踏み出す度に流れる川の中を進み行くような錯覚を感じさせられるほどだ。凄まじい勢いで落下してくる水量は、あまりしっかりした作りでないビニール傘の表面を滝の如くに打ちつけてくる。先程、店の中から見えていた江神さんとアリスがそうだったように、私たちもゆっくりと歩かなければならなかった。
地を這うようなスピードで進みながら、青い傘の謎について論じ合う。
まず、マリアが傘を貸した相手は江神さんだろう、という部分で一応、意見の一致を見た。
大阪から通学しているアリスは、大学の西門を出て地下鉄へ潜り込んでしまえば少なくとも最寄駅へ着くまで濡れないでいられる。また、帰り着いた先で雨が酷いようなら、家族に迎えを頼むことも可能だろう。それに比べて、徒歩で帰る江神さんの場合、傘が無ければ相当のダメージを被ることになるというのが根拠となった。しかし、なぜマリアが傘を貸したのか―――或いは傘を貸せる状態にあったのか、ということは依然として謎のままである。
だが、傘を貸してもらったのが江神さんだと仮定すると、湧き上がってくる疑問があった。
「なんで江神さんにアリスがくっついておったんやろうな?」
私がそう言った途端、織田は鼻白んだような表情になった。
「なぁ、その部分は詮索しても意味ないんやないか? 部長が誘うたか、アリスが行きたいて言うたか判らんけど・・・個人的な感情から出た行動かもしれんやろ」
「いや、違うんや。そういうことを問題にしてしてるんやなくて―――」
私は自分の中でまとめ上げていた推論を口に出した。
「信長、ちょっと頭働かしてみぃ。部長が傘を借りたんやとしたら、二人であの時間に歩いていた理由が判らんようにならんか? そら、俺だって、アリスが江神さんの部屋へ行った理由については勘繰るだけアホらしいと思うぞ。けど、普通に考えたら、キャンパス内から移動する間だけ一緒の傘に入って地下鉄の入口でアリスを落してったら済む話やろ」
「せやから、二人のうちのどっちかが言い出して、江神さんの下宿へ向かうことになったっちゅうだけなんやないのか?」
「確かに、それも考えられる。けど、傘を借りてたのがアリスの方やったとしたらどうなるか―――俺たちが見かけたのはアリスが江神さんを送ってく途中ということになる。で、部長を下宿まで送り届けてから家に帰るという図式が成り立って、なんも問題あらへんやろう」
「そらまぁ、そうだわな・・・ということは、アリスがマリアから傘を借りたという可能性も捨てられなくなってくる訳か」
「そういうことや。しかし、マリアの性格考えると、俺は絶対江神さんに貸してると思うけどな」
「おい、モチ。言うとることが矛盾しとるぞ。マリアから傘を借りたのは、江神さんとアリスと―――どっちやねん」
呆れ声を出した相方を尻目に、私は新たな推理と取り組み始めた。
あの傘の借り主が江神さんであったということと、二人が一緒にいた事実をきちんと説明できる、なにかいい解答がある筈だ。そんなふうに頭の中で捏ねくり回していた自説を、織田に向かって披露した。
「せやから、こういうのはどうや? 江神さんはマリアから傘を借りたけれど、アリスが傘持ってないのを知っとったんやな。それで、授業が終わるまで待っておった。まあ、四限を受講しとった確率が高いのはアリスの方やろ。で、こんだけ降っておるし大阪へ着いて傘が無かったら困るやろうから、アリスに向かって、下宿まで一緒に来てくれれば傘を―――さしてたマリアの傘でも江神さんの傘でも―――貸したるわ、言うたんや」
「ううん・・・話としては考えられなくもないが、苦しいな」
織田は真面目くさった顔で感想を述べた。
「大体、傘を借りに行くっちゅう理由で、ここまで凄い雨の中をわざわざ西陣まで歩くんか? 俺だったら御免被るがな。アリスかて、大阪に着いて雨が止んでおらんかったら、それこそ、こういうビニール傘を買えばええことやろ」
それはどうだろうか。私は反論した。
「傘代が無かったんやないか? アリスの場合、500円玉に事欠いてイネスの本を買い損ねおったくらいやからなぁ、充分有得るケースやと思うぞ」
「そんならいっそ、江神さんから傘代、借りたらええやないか」
「部長は、ここのところ金欠やろう」
私が織田を見返すと、反論する気が失せたのか、彼は曖昧に頷いた。しかし、「真相がお前の言う通りやったら、アホらしぃわ」と付け加えることも忘れない。そして新たな難問を突き付けてきた。
「そうなると、この世で起きることには全て論理的な説明がつくと豪語するエラリー・クイーンマニアとしては、あの二人が雨の中を走っていったことをどう解明してくれるんや?」
「う・・・」
さすがの私も口を噤む。なぜ、江神さんとアリスは、あのような―――この天候に於いてはまず正気の沙汰と思えないことをしたのだろうか。
濡れるか濡れないかのパラつき方であれば、走っていってしまおうという気持ちになるのも判る。だが、数メートル先の視界も霞むような集中豪雨の中を走破したら、数秒も経たぬうちに全身ずぶ濡れとなるだろう。賢者の部長がそれに気づかない筈はない。ならば、走ろうと提案したのはアリスだろうか? しかし、年齢の割には達観した感のある、あの後輩がそんなことを言い出したというのもあまりピンと来ない。
「この雨ん中、とろとろ歩くのが面倒になって、ええい走ったる!と思った―――とか、言うなよ」
黙り込んでしまった私に、織田がからかうような口調で告げた。
「お前が言うことの方が、よっぽどアホらしいやないか」
私が言い返すと、織田は、
「けど、まあ・・・なんや相変わらず仲良うしとるみたいやし、俺としては、真相なんてどうでもええんやけどな」
こう言って、少し照れくさそうに笑った。
それは、私だって同じだ。大体、彼ら二人が私たちの前でとった動作の一部に喚起される『謎』に対し、本気で取組むつもりなど最初から無い。ただ、私自身の性分からくるものと我がクラブの病から、ついつい推理癖が出てしまっただけのことである。
「なあ、モチ」
暫く黙っていた織田が私を呼び、更に問いかけてきた。
「あの二人が雨の中へ飛び出す直前の顔、見てたか?」
「ああ、見とった・・・笑い合っておったな。幸福そうな顔やと思った」
「なら、もうええやろ。青い傘を借りたのが誰やったかは明日マリアに訊けば済むことやし、なんで一緒におったか、どうして走っていったかは、別に俺たちが知らんでも」
「ええことやな」
相方が全部言う前に科白をひったくった。どちらからともなく互いの顔を覗き込んで、私たちは頷き合った。
敬愛する先輩と無邪気な後輩と。彼ら二人が共にいて、幸せであることを願う。このサークルに於ける部内恋愛がまさかこういう組合せで発生するとは予想もしなかった。しかし、江神さんとアリスの間がどういうことになろうとも、二人が仲間である以上、私を含めた他の三人はそれを否定したりしないだろう。江神さんが江神さんであり、アリスがアリスとしていられるなら、私たちは彼等の関係を黙認するに違いない。
なぜなら、五人でいることの愉しさや心地良さを知ってしまったから。私たちの中から誰かが抜けた状態なんて、もはや想像できないし、考えたくもないからだ。
江神さんを筆頭に織田、私、アリス、マリアの五人で構成される、ささやかな我がサークル。今後、新入部員が増えることも考えられるが、今は五人揃っていてこそのEMCなのだ。
鬱陶しい上空を見上げながら、私はほんの少し悔恨の意をこめて呟いた。
「『謎』はEMCの外に求める方が気楽やな」
「そういうことや。ま、ちょっとした暇潰しにはなったけどな」
熱きハードボイルド魂をこよなく愛する男は、そう言ってにんまり笑う。
前方へ視線を戻すと、八萩書店の庇がやっと視界に入ってきた。さて、その翌日。
織田と私は示し合わせて一講目開始時刻よりも三十分早く登校することにした。マリアが一人でいるところをつかまえ、青い傘について訊ねるためである。
地下鉄利用のアリスは西門を通ってくることが多い。大学の西側から通学している江神さんもまた然りだ。しかしマリアは登校してくる時、概ね正門から入ってくる。待ち伏せするには非常にありがたい状況なのだ。それでも万全を期して、織田に西門へ回ってもらったが。
正門にて、張り込み始めた。すぐに、赤っぽいセミロングを朝日に光らせながらやって来るマリアの姿を見つけた。
「あら、モチさん! おはようございます、早いんですね?」
「おはよう―――マリアを待っとったんや」
朝の挨拶もそこそこに、彼女のスケジュールを確認した。
織田とマリアと私、三人揃って空き時間が重なることもあるのだが、あいにくそれは望めなかった。本日、マリアは二講目が空いているという。しかし、織田も私もその時間には必修科目があった。一講目と二講目を挟んだ休み時間をギリギリいっぱい使うべく、私たちが取っている二限の講義が行われる教室から一番近くて尚且つ人目につかない場所―――図書館裏手のベンチで落ち合う約束を取り付けた。
西門で立ち番していた織田と合流し、図書館の自習室へ向かった。早く登校してしまったことで生じた空き時間を勉学に充てようという殊勝な気持ちからではない。烏丸通を隔てた学生ラウンジや生協の書籍部よりも待ち合わせ場所に近いという、ものぐさな理由に因っていた。
自習室の一番奥で、私たちは時々申し訳程度にノートを開き、後は居眠りをして過ごした。
一講目が終わる直前に、裏手のベンチへ移動する。
5分遅れでマリアが姿を現した。講義終了が数分オーバーしたので、教室から駆けてきたらしい。
荒い息遣いをなんとか整えたマリアは、私たちの顔を交互に見た。
「で、お二人が、江神さんとアリスのことで私に訊きたいことって、何ですか?」
私たちは、昨日、雨宿りに寄った店の中から目撃した一連の出来事について、話した。
黙って聞いていたマリアは、最初、驚いたように見開いていた目をだんだんに細め、実に嬉しそうな表情になった。
「そう・・・江神さんとアリス、相合傘で歩いてたんですか―――そうだったんだ、良かったわぁ・・・」
私と織田は顔を見合わせた。
「おい、マリア。一体、何があったんや?」
「一人で判っておるなんて、狡いぞ」
口々に責め立てる私たちを面白そうに見回しながら彼女が話してくれた内容は、とても興味深いものだった。
どうやら、昨日は大変だったらしい。やはり、世の中、そう簡単にはいかないのが恋の道ということか。
好きだという気持ちだけで突っ走れるのなら、どんなに幸せだろうか。恋情の赴くままに振舞うことがいつも許されるとは限らない。相手を愛おしく想えば想うほど、相手のためを考えれば考えるほど、踏み出せなくなる恋愛だってある。だから、人のする恋は切なくて、時に哀しい結果となるのではないだろうか。
相手を愛(いつく)しみ、思い遣り、江神さんとアリスは傘の下で身体を寄せ合ったのだ。そして、それはあの二人とって必要な通過点だったのかもしれない―――なぜか、そんなふうに思った。
「今日のお昼は、全員揃いそうですね」
マリアが笑顔で言った。つられた訳ではないが、こちらの表情も自然と綻ぶ。
空き時間を学生会館で過ごすつもりの後輩と別れた織田と私は、二講目開始ギリギリに教室へ潜り込んだ。
そして、昼休み―――ラウンジで、五人が顔を合わせる。
江神さんが青い傘をマリアへ、アリスが黒い折畳み傘を江神さんへ返し終えたその後に、私たちは五人揃って『リラ』のタラコスパゲティを目指し、駆け出したのだった。(2000/9/15)
へ戻る
うわーん、なんでこんなに長いんでしょおおぉぉぉ〜 モチ一人称ってのがまずかったんでしょうか……(死)
毎度のことながら、書き出した時はここまで長くなると思ってなかったんですが…もう、どうにもならなくて。これでも、推理合戦(?)の箇所は大分科白を削ったんです。本当はもっとショーモナイ茶々が入ってました←オイコラ
ところで、信長が手に入れたハメットの短編集『探偵コンチネンタル・オプ』(ハヤカワポケットミステリ刊)は、現在本当に絶版です。私もずっと探してるのですがなかなか見つからないので、せめて信長に買わせようと思いました。
それから、"『ガモフ著作集』上下巻"というのは、多分存在しません。『ガモフ・コレクション』(全四冊。十冊以上あった『ガモフ全集』を再編したもので今はこちらの方が手に入り易い)というのはありますけど、このガモフなる人物、実は物理学者なんですよね(爆) でも、トムキンスシリーズとか、江神さん読んでそう〜と思ったので。
あと、文中で言及している、モチがクラブノートに書いた『傘』という作品については、原作短編『老紳士は何故・・・・・・?』に於いてその内容が明らかにされています。脱力すること請合いですから、未読の方は是非ご一読くださりませ(大爆笑)