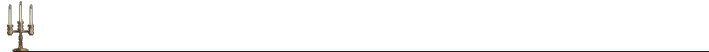晩夏 前編
嘉敷島からの帰りしなに江神さんの部屋へ泊めてもらって以来、暦は嘘のような穏やかさで捲られつつあった。
既に8月も後半に入ったが、暑さは一向に衰えない。夏まっ盛りであることを誇示するが如く、太陽は上空へと居座り続けている。
滞ることを知らぬ日常は確かな足取りを見せ、時間は万人の上を等しく流れゆく。
闇に浮かび上がる五山の送り火が、ブラウン管の中で輝き、消えていった。球児たちも甲子園を後にした。やがてNHKの番組編成は平常に戻り、夏という季節が残り少なになっていることを知らしめる。
すっきりしない心を携えて送る毎日は、白々しいまでの長閑さに包まれている。出かけるのはバイトがある日くらいで、後はひねもす、のたりとするばかりだ。
日頃、そのような生活態度を取ろうものなら黙っていない母親も、今は息子の素行に目を瞑ってくれている。旅先でまたも殺人事件に関わってしまったのを不憫に思っているのが、言われずとも判る。
気を遣わせていることを申し訳なく感じるものの、こればかりはどうしようもない。自発的に何かやろうという気になんか、なれない。
そんな心境へ当てつけるかの如く、蒼穹が日々遙かなる高みで輝いている。眩しさへ耐えられず、目を背けてしまうのは、窓外の青すぎる光が過日の辛い記憶を呼び覚ますから。
大自然の中に取り残されし者たちが咀嚼させられた、残酷すぎる結末。
最悪の幕切れ。
あの、音ひとつ立てるのさえ憚られた朝―――僕は一生、忘れられないだろう。その日、昼食を終えてから篭りっぱなしの自室は冷房が効きすぎ、肌寒いまでになっていた。読んでいた本がキリの良いところへ差しかかったので、いったん止めようと思った時、
「有栖ー、ちょっと来なさい」
母からお呼びがかかった。エアコンの電源を落としてから部屋を出、ゆっくりと階段を下りた。
リビングのドアを押しやると、宅急便で配達されたらしき段ボール箱がテーブルの上に鎮座しているではないか。
「おかん、何や用か」
「これ、あんた宛てに届いたんやけど」
続けて、配達票 兼 受領票を渡された。確かに宛先は"有栖川有栖様"となっているが―――
「この、『もくもく食材農場』って・・・何やの?」
差出人欄へ指を滑らせながら問うた。すると、驚いたような表情で、逆に訊き返された。
「まあぁ、自分で注文したんと、違うの?」
知らない。全く心当たりの無い名称である。
首を捻りつつ、荷物へ近づく。梱包を解いて、ますます判らなくなった。
詰め込まれていたのは、その名の通り『食材』だった。内訳は、真空パックされたステーキ用豚肉が6枚にチャーシューの塊一つと異なるソーセージ三種の詰め合わせ。そして、白い封筒が一通。表にこそ僕へと判るよう宛名が記されているけれど、裏は綺麗なものである。氏名はおろか、差出人を匂わせるものも何一つ無い。
しかし、その字体には見覚えがあった。時たま見かけていることは確かだ。丁寧に書いてはいるのだけれど達筆とは程遠く、お世辞でも、せいぜい味があると評する程度か。
まぁ、誰の筆跡なのか思い出せないのなら、こうして悩んでいてもしかたがない。
とりあえず封を切り、本文を読むのは後回しにして、文末へ目を走らせた。意外な名前が僕を待っていた。
「信長さん・・・?」
便箋を広げている手許のすぐ脇から、覗き込まれる。『織田光次郎』という名を見つけた母が「あら、ほんまや」と呟いた。推理研メンバーのことは家でもよく話しているから、先輩たちの呼び名もとうに知られている。
それにしても―――どういうことだろう。
リアクションに困っている僕の目前へ、親子電話の子機が差し出された。
「なんにしても、忘れんうちにお礼の電話、しときなさい」
言われたことはすぐにやっておかないと、この母は後々煩さい。僕は無言で頷き、コードレスホンと封筒を手にして自分の部屋へ戻った。
手帳のアドレスページを開いて織田の実家の電話番号を拾い出した。呼び出し音が耳の奥で鳴り始めると同時に書簡本文へ目を走らせる。それほど長い内容ではなく、すぐに読み終わった。南の島で惨劇へ遭遇してしまった後輩への見舞い品であることが知れた。
プツリと小さな音がして、誰かが向こうの受話器を持ち上げた。
「はい、織田」
無愛想な第一声に少々怯んだが、とにかくこちらの名前を告げる。
「あの、大阪の有栖川といいますが」
「おおー、アリスか! なんや、澄ました声出しよってからにぃ。どうでゃあ、元気でやっとるかー?」
いきなり声のトーンが一段跳ね上がり、受けたのは織田本人と判明した。イントネーションも言い回しもすっかり名古屋弁に戻っている。帰郷したことで再び地元訛りに感化された結果か。
まず、本来の目的を果たすべく、品物を受け取った旨と御礼を述べた。
「そうか、届いたか。そらまぁ、えーとこ良かった。けどがよぉ、アリスんとこがいっちゃん最後とはちぃと驚いたぁな。その農場、三重にあるでよぉ、てっきりもっと早ぅに着いたと思ってたんちゅうこったけどが」
実はここ数日、我が家は無人だった。毎年、この時期には父方の親戚を泊まりで訪問することとなっているのだが、いつもは同行しない僕も今回に限り引っ張られていったのだ。孤島で事件に巻き込まれたダメージが今だ日々の生活に大きく影響している息子を一人、家に残していくのはどうかと両親が心配し、強制連行されたのである。
だから、自宅へ戻ったのは昨晩遅くのことだった。
ポストに入っていた宅配便の不在連絡票を見た母が本日在宅であることを伝え、再配達してもらったに違いない。普段は「自分のことは自分でせな、あかんよ」と口やかましいものの、今現在、著しく生気に欠けている我が子に代わって連絡を入れてくれたのだろう。
そんな訳で、受け取ること自体が遅れた理由を説明すると、織田は納得した。
「そらまぁ、そういうことならしかたがにゃあな。京都はともかく、東京よりも遅いってのはどういうこったと思ったんでにゃあきゃ」
おんなじもんを江神さんやマリアにも送ったんだけんどが―――と、柄にもなくしんみりした声が、言う。
それにしても、この『もくもく食材農場』というのは何なのだろう?
僕が訊ねると織田は笑った。
「突然、そんなもんが届いて驚いたやろ。姉貴の旦那の親戚が勤めとりゃがる。ま、ほんなこた、どうだったてええけどがなも。品質は間違おれせんでぇ」
無菌の飼料しか与えず、しかも無菌室で飼育するゆえに無菌ブタと言われる豚肉が『売り』とのこと。まだ出来て間もないが既に口コミなどで噂が広まり、評判は上々らしい。盆暮れには贈答品としての出荷数もかなり伸ばしているということだった。
「まぁ、用事がありゃがったせいで当事者にならなて済んだ俺たちからの気持ちでにゃあきゃ。肉だったって食って元気つけてくれちゅう感じでゃーなも」
ありがたき心遣いへ素直に感謝する。まさに、今となっては、行かなかった方が良かったと思いたくなる孤島の休日だった。全く―――あんな経験、誰がしたくてするものか。
しかし、"俺たち"とはどういう意味だろう。
僕かそう口にすると、織田は不思議そうに、「あれっ、荷物ん中に封筒、入っとらんかったか」と、聞き返してきた。
「いいえ。ちゃんと入ってましたけど、手紙には信長さんの名前しか・・・」
言葉を投げつつ、きったない文字をしげしげと見返した。そう、僕はよく、クラブノートの中でそれを目にしている―――
電話線の向こうで吐かれた特大の溜息がこちらへも伝わってきた。
「・・・あんの、どアホ」
最初に言いだしたのはモチの方やったんやで、と続けて、遥か彼方の尾張にいる先輩は苦笑した。
「南部の梅を送る、言いだしてなぁ。けどが、夏に山ほどの梅干ってのもどうしたもんかと。かといって名古屋かて名産といえや、ういろうか味噌漬か―――見舞いとしては合えせんみたゃあな気がしてなぁ。ほいで・・・」
チャーシューやソーセージなら食材として使えるし、真空パックされていれば日持ちもする。僕たち三人がベジタリアンでないことは明白だから、こういうものの方が良いだろうといことになった。それで先輩二人はお金を出し合い、望月が簡単にしたためた書状をそれぞれに同封してもらった上で件の食材工房から直接配送されるよう、手続きしたのだそうな。
「しかし、テメェの名前書き忘れるたぁ、しょうもにゃあ奴でゃーなも。何にしてまったって、アリスが電話してきてくれてよかったわ。江神さんたちみたゃあに礼状だったら判らなんだちゅうこったろーし」
二人からは、すぐに書状が届いたそうである。両人とも葉書で、それぞれに簡潔な御礼文が書かれていたそうだ。
「けど、江神さんとマリアは郵便でお礼を言うてきたんでしょう? その・・・」
「ああ、そっちゃは大丈夫なんでにゃあきゃぁ。一昨日、ハガキが届いたちゅぅて、電話してきよったからにぃ」
京都と東京で投函された謝意は、時を同じくして、贈り主たちに配達されたようだ。
ならば、三通のうちの一つにだけ自分の名前を書き損なったということか。几帳面なようでいて、どこか抜けている望月がやりそうな失態ではある。
「ほなら、モチにも電話しといてやってな」と最後に念押しして、織田は電話を切った。
続けて、紀伊の望月宅へかけた。僕も一度会ったことがあり、お世話にもなった望月の母親が送話口に出、息子へと取り次いでくれる。
織田の時と同じく、開口一番で品物の受領とその御礼を伝えた。到着が遅かったことを谺しまれる前に、諸事情も説明した。
望月は小さな声で「そうか、それで受け取るんが遅れたんやな」と独りごちてから、
「何にしても無事、届いたようで何よりや。けど、礼を電話で済ませよったのはアリス、お前だけやな。江神さんとマリアはちゃんと礼状、寄越したんやで。常識が違うな」
と宣った。
粗忽者がよく言いますね―――と返したいところをぐっと抑える。そのまま僕が沈黙していると、
「ははは、冗談や。冗談。別に礼状が欲しくて、送った訳やないしな。気にせんといてや」
瓢々とした声が響く。もちろん、誰が気にするものか。だいたい、僕が江神さんたちと同じようにお礼を葉書か何かにしたためていたなら、その書簡は織田宛てにしか郵送されない筈だ。それもこれも、自分の名前を書き忘れた誰かさんが間抜けなだけなのだ。
そんなこちらの心中を知る由もない先輩は、
「けどまぁ、少々読み違ったなぁ」
と呟いた。
「何がですか?」
「いや、なぁ。さっき、"礼状は常識や"なんて嫌味を言うてしもうたけど、逆なんや。部長はまだしも、マリアが葉書で言うてくるとはなぁ。俺も信長もてっきり、アリスみたいに電話かけてくるとばかり思っとったから、なんや、面食らってしまってな」
ああ、そうか。
嘉敷島で起きた事件の詳細を江神さんと僕から聞いて以来、二人の先輩はマリアのことをひどく気に懸けていた。とはいえ、いきなり東京に電話して「大丈夫か?」と聞くのも憚られる。それで、見舞い品を送る事にしたのだろう。気持ち的には、そのお礼にかこつけてマリアが電話でも寄越さないかと期待して。
受話器越しの声を聞けたからといって、安心できる訳ではない。だが、両先輩の心情は手に取るように判る。
被害者も加害者もマリアの良く知る者であり、親しかった人たちだ。皆、浅からぬ付き合いと因縁を持っていて、それが今回の事件を引き起こした。完全なゲストだった江神さんと僕だって凄まじいショックを受けたのだから、部内者といえるマリアのダメージは相当なものだろう。想像するだけで心が重苦しくなり、圧しつぶされそうになる。
「そうそう、アリス。レンデルの最新作、読んだか?」
突然、話題を切り替えられた。言葉を選ぶ必要のある会話から離れたくなったのだろう。
だが今の僕には読書ですら辛い。ましてやミステリなど論外だ。事件の記憶を直に刺激するような"謎解き"という単語から、今暫く遠ざかっていたかった。
あいにく未読で―――そう告げると、望月はあからさまな落胆を声に慘ませた。
「うぅ、そうか・・・ミステリマガジンの書評が歯切れ悪かったから、どうしようか迷ってるんやけどなぁ」
「どんな批評やったんですか」
「ずばりとは書いてへんかったけど、全体の出来がレベルダウンしとる、と言いた気な評やったで」
仮免所得後、路上教習へ出る際の待ち時間を潰す為に沢山の本を買いこんだらしい先輩はボソボソ付け加える。
「新刊ばかりこうたもんやから、もう、余裕あらへん。せやからアリスに期待してみたという訳や。信長はまず読まんやろうし」
確かに―――筋金入りのハードボイルドファンである織田の読了など、あてにするだけ無駄だ。
「それやったら、江神さんの方がまだ可能性あるんやないですか?」
文学部哲学科ということもあってか、幅広い読書傾向を有する部長である。加えてその読書量もハンパではない。
しかし、望月はやけにあっさりと否定した。
「まぁ、江神さんなら最終的には読むかもしれんけど、今、この時期は絶対に有り得んやろう」
・・・?
そんなに忙しかっただろうか。
自分が知っている限りの、部長のバイトスケジュールを思い出してみる。
学費はもちろん生活費までをも自身の労働で賄っている江神さんは、複数のバイトを並行してこなしている。それで、こういった長期休暇時には、日頃から続けている仕事の他に、短期集中で稼げるバイトを入れることが多々あるのだ。けれど、今夏はそういう仕事が見つからなかったと聞いた。さしあたり逼迫してもいないし、つつましくやっておれば問題ないやろ、と彼は僕にそう話した。
尤も、週に二日ないし三日、近所のコンビニで数時間勤しむだけの自分と比べるまでもなく、江神さんの生活がかなり多忙であることに違いはない。だとしても本一冊くらい、読む時間はあるだろうに。
そんなことをつらつら考えていた挙句の間合いをこちらの疑心と受け取ってか、望月は説明するようにこう言った。
「今は間違いなく、荻野教授の原稿しか読む余裕あらへん筈や。専門外なのに気の毒やってんなぁ」
何だって?
一瞬、頭の中が真っ白になった。
「荻野教授・・・?」
おそるおそる反芻した自分の声が微かに震える。だがそんな僕の狼狽に全く気づいていないのか、受話器の向こうの先輩は「法学部やと知らんかもなぁ」と呟いた後、いつもと変わらぬ調子でこう教えてくれた。
「人使いが荒いんで有名な、工学部の教授や。専門は知識工学で数学の授業を持っとる。俺は一年の時、必修であの先生にあたったことがあったんやけど、エラい目におうた」
「はぁ、そうなんですか・・・でも、なんでまた、江神さんがその教授の原稿を読まなあかんのですか」
「江神さん、荻野教授の研究室で臨時のバイトしてるんや。なんでも、センセ本人が暮れに本出すとかで、原稿の手直しに追われとるらしい」
え・・・
何や、聞いてないんか?という声が耳元で響く。
そう―――知らなかった。初耳だ。
急遽、体内へ湧き起こった、おそろしく不快な感情をまずは押し留め、僕は望月に訊ねた。
「けど、なんでまた、江神さんなんですか? そら、部長なら大丈夫やと思いますけど・・・そういうのって普通、工学部の学生に打診するもんやないんですか?」
「まぁ、俺もそのへんはよう判らんのやけどな。とにかく、人手が足らんということで、話がまわってきたらしい。ほれ、江神さんの場合、こういう休みの時はいつもやっとるバイト以外にもいろいろしとるやろう。今回はたまたまそれが空いてたんやな」
それくらい、判ってる―――
思わず噛みつきそうになる口を抑えた。
引き続き、望月が自身の近況を語り出したけれども、僕は半ばうわの空だった。心はすっかり動揺していて、相槌を打つのもやっとである。今、自分がどんな顔をしているか、鏡を見なくても容易に想像はつく。声だけのコミュニケートで済む電話という文明の利器に今更ながら感謝したいほどだ。
一つ上の先輩は、どこまでも呑気な口調で、
「そろそろ江神さんも、誰かに愚痴りたい頃やろうなぁ」
などと言う。何気ない科白にも八当りしかねない自身を懸命に宥め、やっとのことで受話器を置いた。
無事に会話を終えられたこと自体が、今の僕の状態からすれば奇跡といえそうである。尤も、嘉敷島で起こった事件内容を知る望月にすれば、僕の様子が多少おかしく感じられたところで詮ないことと思っているのだろうが。
胸中へ、複雑な想いが押し寄せてくる。
一体、なんなんやろう―――
然して頭を悩ませるまでもなく、一つの感情が僕の中へ導き出される。
まさか―――嫉妬してる、とか。
しかも、望月に・・・?
「なんでやねん。何が悲しゅうて、俺がモチさんにヤキモチ妬かな、あかんねん・・・」
情けなくて脱力しそうだ。けれど多分、それが真実なのだ。
心が、痛い。
一度、認識してしまった『キモチ』はあっという間に膨れ上がり、僕の中をじりじりと侵食し始める。もはや、不愉快という単語で片付けられはしない。江神さんに関するより詳しい情報を自分以外の誰かが所用しているという現実―――それが鋭利な刃(やいば)となって、容赦無く内腑を抉る。
一体、いつからこうなってしまったのだろうか。
なぜ、あのひとを恋しくおもい、その瞳に映る唯一の存在でありたいと願うようになったのだろうか。
自覚してからは何度となく考え、悩んでいるけれど、未だその答えは出ていないし、今後、出るとも思えない。本来、好意や嫌悪といった感情は、当人の意のままになるものではないのだから。
大体、想うだけなら自由なのだし、後ろめたく感じることはない筈である。けれども、世の中に厳然と横たわる常識は今だすこぶる頑なさだ。それゆえ、多くの当事者たちが、その関係を世間の目から隠そうとするのだ。
親や友人から白い目で見られるかもしれない恋愛に、あのひとを引っ張り込むなんて、できない。
それ以前に、彼が僕をどう思っているか―――確かめようもない。
確かに、江神さんは僕をとても可愛がってくれている。でもそれは、兄貴分として当然示される情に過ぎないのだろう。いくら頭ではそう理解していようとも、僕の欲深な心は、今だ僅かな可能性を見出そうとしてあがいている。
ええかげんにせぇ、有栖。
己を諌めるつもりで、強く目を瞑り、頭を振ってみる。でも、何の効果も無い。
電話機を手したままベッドへ倒れ込んだ。冷気にあてられたシーツが、ひんやりとした心地を肌へ直裁に伝えた。
へ戻る
すいません。今回も、またまた長いです。確かに日は跨ってますけれど、
だからと言ってこんな長くなっていい訳では(泣) どうか、続きを読んでください…