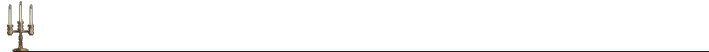晩夏 後編
翌日、早めに昼食を摂った僕は、ぐずぐずと思い悩む心を叱咤し、家を出た。
夏休みの、しかも真っ昼間の車中は驚くほど空いていて、奇妙な気怠さをそちらこちらに漂わせていた。窓へ映る空の青さだけが、相変わらず眩しい。
京都駅へ降り立ったのは、午後2時を回った頃だったろうか。割に混み合っている構内を足早に抜け、さっさと地下へ潜った。四つ目の駅で降り、そこそこ歩きなじんでいる出口を目指した。
陽光が頭上でさんざめく。
レンガ壁へ様々なレリーフを描く青葉は、この炎天下でも然程の衰えをみせず、その生命力を鮮やかに誇示している。降りそそぐ蝉時雨も相変わらず盛況だ。
西門をくぐって、すぐ右手の図書館へ向かった。夏休み中も普通に開いている場所で、少しく冷房にあたろうと考えたのだ。
入り口のある一角で歩みを止めた僕の目に、『臨時休館日』というサインが飛び込んでくる。
「・・・なんやて?」
どっと吹き出す汗を拭いながら、キャンパスを出た。
とりあえず烏丸通りを渡り、我がEMCが部室の代わりとして根城に定めている学生会館の前へ足を運ぶ。しかし、仲間の誰もいる筈のない、ニ階のラウンジに行く気が起こる訳がない。そのまま、ロビー左手にある学生課の扉を推す。
なんと、ここの受付カウンターにも、『夏季休業中』の札が立てられているではないか。
せっかく来たのに、あんまりである。
つれない文字列を一瞥し、背面の壁へ目を向けた。
そこには、ごく簡単に仕切られた棚が横長に並んでいて、大学内の各種団体宛に送られてくる様々な書類を区分けるのに使われている。早い話がメールボックスである。
尤も、独立した部屋が与えられている集団、つまり研究室やゼミ宛てのものは該当教室へと配達される。部室のあるサークルの場合もそうしてもらえるらしい。だが、EMCのような宿無しサークルや、臨時で設立される委員会などへの郵便物はここで受け取るようになっているのだ。
元々が総勢五名という規模であるし、他大学の同好会等と積極的なやり取りがある訳でもない我が部は、数えるほどにしかこの棚を利用していない。望月がエラリー・クイーン誌へ送った雑文に対して届いた、編集部からの儀礼的な返信とか、犯人探しの正解を当てた江神さんに届いたささやかな賞品とか、そんなものを受け取った程度だ。
だから今日も、何かがあると思って見たのではなかった。しかし何気なく走らせた視線は、推理研専用のコーナーにあった一枚の葉書を捉えた。
手を伸ばし、間違いなくEMC宛てのものであることを確認した。端正な文字で、"英都大学 推理小説研究会 御中"と綴られている。差出人は―――見坂夏夫。
予想すらしなかった名前を突きつけられて、周りの空気が薄くなる。眩暈がしそうだ。
あの、悲惨過ぎた昨夏の記憶は、決して廃れることなどない。
遭遇した事件の凄まじさは、今年のそれといい勝負だった。目に焼きついたシーンの断片が即座に蘇ってきて絡みつき、僕の全てを呑み込んでしまいそうになる。
二夏続けて殺人事件を経験するなどと、誰が予見できだだろう。尋常じゃない。けれども、それは江神さんにも当て嵌まることで―――そのどちらをも解決へと導き、片をつけたあのひとの心中を思うとやるせなくなる。
胸ポケットへ夏夫からの便りを滑り込ませ、学生課を出た。
特にどうという目的があってこの街へ来たのではないからと、己に言い訳してみてもはじまらない。ゴチャゴチャと考えるまでもなく、足は既に西陣へ向いている。あのひとに逢えるかもしれないという、仄かな期待を抱いて。
昨晩、望月から聞かされた江神さんの近況は、今だ、僕を苦しめている。
彼が望月にだけ語ったのか或いは織田も知る事なのか、といったことはどうでもよかった。だが、"『僕に』知らせてくれなかった"という現実がひどく重い。
いくら親しくとも、所詮ただの先輩後輩というだけの間柄。逐一、近況を伝え合うこともないというのが常識的な見解だろう。しかし僕の場合、対江神さんとなったが最後、お手上げになる。心は途端に平衡感覚を失い、すべてが狂いだす。そして、あのひとに切なく焦がれる自分を否応なく自覚させられるのだ。
なるべく日陰を歩いたが、目指す下宿へ辿り着いた頃には全身汗だくだった。強すぎる光を壁に受けて、町ぜんたいが白っぽく浮き上がる。すべてが陽炎のようにゆらぐ。
ためらいもせず、玄関の扉へ手をかけた。
直裁に陽射しが差し込まないにも拘わらず、外気で熱された廊下はひたすら蒸し暑い。すたすたと歩いて、いつもそうするようにノックしようとしたその時、突然、ドアが開いた。
「ア・・・リス・・・?」
「―――え、江神さん!」
僕たちが互いにその名を口にしたのは、ほとんど同時だった。
まさか、こんな風に鉢合わせるなんて、思ってもいなかった。続く言葉が出てこない。吹っ飛びそうな意識をどうにか繋ぎ止める。
気怠そうな所作でトレードマークの長髪を掻き上げたひとは、柔らかい眼差しで僕を見た。
「まぁ、入りや」
「けど・・・どこか、出かけるんやなかったんですか」
「―――すぐに戻ってくる。せやから、中で待っとってくれ」
そう促され、棒立ちになった身体が漸く歩き出す。長身の後ろ姿を見送りつつ中へ入り、ドアを閉めた。
山と積まれたCDや本を避けながら腰を下ろした。外の景色がまるで残骸のようだ。扇風機は開け放された空間からなだれ込んでくる熱風を申し訳程度にかき混ぜるばかりである。
江神さんは、ほどなく帰ってきた。
「丁度、きらしてしもうてな」
キャビンの封が切られる。長い指が火を点けると、紫煙はすぐに拡がった。
あれほどに逢いたかったひとが、今、こうして目前にいる。
ゆるりと吐き出した靄を追っていた視線がこちらを向いた。彼がタバコを口から離すより早く、葉書を取り出して渡した。
無言で受け取った部長は、無言で本文に目を通している。
わざわざ届ける口実にしてはツライという感も否めないが、学生会館の一階でこれを見つけた時に内心「やった!」と思ったのも事実だ。あの棚を常用していない我が部の場合、ともすれば学期が始まっても全く気がつかないという可能性が大いにある。ならば見つけた時に、長期休暇中はクラブノートを持ち帰っている部長宅へ届けておいた方が安全、という筋書きが成り立つ。
漸く、江神さんが口を開いた。
「夏休みが終わったら、返事書かんとな。みんなで寄せ書きしたらええやろ」
ひらひらと葉書を翳す手つきにすら見惚れそうになる己に苦笑しつつも、しっかりと頷く。
「けど、これ持ってきた―――ゆうことは、大学まで行ったということやな・・・なんや、用でもあったんか?」
・・・。
結局、訊かれたか。
たまたま見つけたEMC宛の書簡を持ってきたという理由はいいとしても、なぜ英都へ出向いたか―――問い質したくなって当然だろう。何しろ、ここは盆地特有の気候が幅をきかせる町だ。どうにも外せない所用がない限り、午後の一番暑くなる時間帯に出向く輩は、まずいない。だから今、京都をうろついている人間は観光客か余程の酔狂人ということになる。
とはいえ、何かもっともらしい事情を考える気力も知力も今の僕には無く―――かといって、昨晩、受けたショックのせいで上洛してしまったという情けなさ満載の本心を吐露できる筈もない。
「図書館で涼めるかと思ったんですけど・・・」
恨めし気に、それだけ言った。あやすような声が返ってくる。
「休みやったろ?」
「はい・・・あまりの非情さに、泣きたくなりました」
「そないなこと言うてもなぁ。今日び、この時期は盆休みと称して休みよる会社も割とあるようやから、しょうがないやろ。所詮、大学かて一企業に過ぎんのやし」
そうか。
職員が休みなら教員サイドも足並みを揃え、休業するのは極めて一般的な措置だ。ということは―――
「大学組織そのものが休みやったら、研究室も、当然、休みになるやんか・・・」
江神さんが小さく笑った。
一人ごちたつもりが、彼の耳にも届いてしまったらしい。うう、失言だ。
「なんや、もう知っとるのか―――地獄耳やな。どこで聞きつけたんや?」
さらりと問われ、どう答えたものかと暫し逡巡する。そっと江神さんの方を盗み見た途端、爽やかな笑顔が視界へ飛び込んできた。心臓がドキドキし始める。
努めて平静を装いつつ、望月から聞いた旨を告げた。考え深げに瞳を眇めた部長の口から、意外な名前が飛び出した。
「酒巻教授・・・やな」
は?
「まぁ、このバイト自体が酒巻教授経由で持ち込まれたんやけど」
きょとんとしている僕に、ことの成り行きがざっと説明された。
嘉敷島から戻った翌々日、大学図書館で鉢合わせしたのが事の始まりで。腕を掴まれるような勢いで荻野教授の研究室へ連行されたらしい。そして、江神さん自身の都合はついに訊ねられぬまま、労働契約締結と相成ったそうだ。
「せやから、教授からモチに伝わったんやろな。そういや先日、君の後輩から電話があったぞと言われたような気もする」
淡々と紡がれる言葉の一つ一つに、僕の意識がくすぐられる。さっきまでの鬱屈感はどこへやら。目前の霧がすっかり開けたような気分だ。
「・・・ってことは、モチさんと直接話、した訳やないんですか?」
「ああ、話しとらんよ」
そろそろと切り出した質問には、至極簡単な答えが返ってきた。
なんや、そうやったんか―――
悶々としていた魂は、かくもあっさり救い出され、一挙に第七天国まで駆け上がる。
今になってみれば、江神さんが望月と、僕の知らぬ話をしていてもおかしくはないと冷静に考えられる。部長と部員、個々の付き合いがあって当然なのだから。だけどあの時の僕は、とてもそんな風に思えなかった。それだけ、僕の中にこのひとの占める割合は大きいのだ。
放心していると、
「どないしたんや、緩んだ顔しよって」
優しい声が降ってきた。
「いえ、その・・・」
返す言葉に詰まりながらも、いいようのない幸福感が僕の中へ拡がってゆく。
拗くれていた神経の束がゆるやかに解ける。爽やかな風が体内に入り込む。ああ、僕は心から江神さんが好きなのだと―――改めて感じさせられる。
すっかり惚けている僕を前に、彼は研究室での出来事をポツポツ語りはじめた。
「何しろ、専門やないからなぁ。読んでてもさっぱり内容が頭に入ってこないんや。そんな状態で校正してる、いうのも凄まじい限りやけどな」
「モチさんの話やと、えらく人使いが荒い先生やそうですね」
「ああ、評判通りやった。ほんまに、次から次へと原稿が降ってきよる。引用する予定の図版や資料もまだ最終稿やないから、随時、差し替えになってなぁ。まぁ、思ったより頭使わん仕事やったけど」
「そうなんですか? 原稿直したりするんは頭脳労働やとばかり・・・」
「それはどうやろな。実際にやってみると単純労働としか思えんぞ。確かに、手だけ動かしてたらええ、という訳にはいかんが、作業そのものは所詮"繰り返し"やろ」
いつもと変わらぬ調子でそう言った先輩は、二本目に火を点けたが、こっちはつい不服そうな口調になってしまう。
「なんや勿体ないなぁ。部長の優秀な頭脳が出番無しやなんて」
「―――その方がええ」
らしからぬ渇いた声がした。胸騒ぎとともに視線を上げると、軽く目を瞑っている江神さんの横顔が見えた。
訪れた沈黙は心なしか重たく感じられる。
何か気の利いたことを言わなければと焦る反面、下手に会話を続けない方がいいようにも思う。真夏の太陽に蒸し上げられた六畳で、僕はひたすら押し黙り、時をやり過ごす。
そして。
再び江神さんから発せられた言葉は重かった。
「頭なんて使わんで済めば、それにこしたことはないんや。いろいろ考えたりせなあかん時というのは大概、ロクな状況やない」
僕は唇を噛んだ。
共に体験させられし悲痛な夏の日々。傍にいながら、何も出来なかった自分が不甲斐ない。
けれども、殺人者の心中で渦巻いていた、もの悲しく狂おしいまでの憎悪を誰が否定できようか。
深い絶望と憤怒に苛まれていた人が、期せずして三年前に起きた事件の真相を知った時、何もかもが宿運となったのだ。そんな彼女が、すべてをやり遂げるつもりで孤島の生活へ臨んだ事を誰が咎められようか。
果たして、江神さんという類い希な頭脳の持ち主があの場に居合わせた事は、幸いだったか不幸だったか―――今となっては知る由もない。だが、結局、僕たちの存在は露ほどもあの人の決意を揺るがせられやしなかった。二人の部外者が闖入したからといって、計画を思いとどまる気など端から無かったのだ。
尤も僕たちだって、あんな事件が起こるなどと夢にも思わず島へ出向いていったのである。仮に何かしら、事前に感づけたところで、おそらく止められなかったに違いない。でも、手を拱いて見ていたくはなかった。そして、それを一番痛感しているのはきっと―――目の前にいる、僕の大切なこのひとなのだ。
一体、どうしたら。
過ぎたあの日のことを思い出さずに暮らせようか。
惨劇の記憶を封印し、知らぬ事として生きられようか。
この世に生を受けた以上、様々な悩みがついてまわる。それが人生というやつで。けれど、人が人を故意に死へと至らしめた、あの非日常をも『生きの悩み』などと片付けて良いかどうか―――僕には判断できない。
他人の痛みを己のものとして感じられぬ性(さが)は、今日も数多の事件を引き起こしているに違いなく。そうして、いつの日も愚行は繰り返される。
それでも―――僕たちは、この世で生きてゆかねばならない。
率先して自らが命を絶てるような種族として、神様は人類をお創りにならなかったのだから。
きつく噛み締めた唇が痺れ出す。小さく痛む辺りを舌先でそっと触っていると、江神さんの声がした。
「なんや、空気が澱んでしまったな。飯、食いに行くか?」
「は、はい」
慌てて返事をしたけれど、改めて時計を見たら18時になろうかとしていて、驚いた。ついさっき、この部屋を訪ねたばかりなのに・・・江神さんと一緒の時だけ、僕の時間は駆け足で逃げてゆく。
簡単に戸締まりし、二人して西陣の下宿を出た。
夕凪が僕たちの背をゆっくりと押した。陽炎にゆらぐ街並みは、奇妙に傾いでみえた。木屋町まで出れば、店は選び放題である。そうは言っても、まず財布の中身と相談しなければならない。結果として、貧乏学生である身が落ち着く先は、概ね居酒屋となるのだが。
盆休み期間中のせいか、どの店も心持ち空いているようだ。
席についてからは、努めて明るい話題を口にした。なんだか、少し前にもこんな事があったように思う。それでも、その気になれば随分長いこと差し障りの無い会話を続けられるもので、僕たちは既に3時間近くも居座り続けていた。
「時間、大丈夫か?」
江神さんの気遣いが、僕の一般常識をつついた。
家には何も言ってきていない以上、さすがに腰を上げた方が良いだろう。後ろ髪を引かれる思いで、席を立った。
一足先に外へ出ていた部長は、こちらを見るなり苦笑した。
「全く・・・そないに恨めしそうな顔せんでも、なぁ―――飲み干すまで、待っとった方が良かったか?」
「そ、そんなん違いますって!」
赤くなった顔と、思わず尖らせてしまった口と。
確かに、グラスの中身は三分の二以上残っていたし、半分しか食べていないつまみもあった。仮に注文した皿がハズレだったとしても「残すんは、恥や」と宣う経済学部コンビを筆頭に食べ尽くすのは我がEMCの常だから、その解釈が間違いだとは決して言い切れないのだけれど・・・今宵に限っては、とんでもない誤解だ。
だって、しかたないやないですか。
あなたと別れるのが、ひどく辛いのだから。
しかし、そこまで読まれ易い表情(かお)をしているのだろうか・・・昨夜から何度も数えさせられている情けなさが体内へこみ上げてくる。
そんな僕の本音など露ほども想像していないであろうひとが、宥めるように続けた。
「手土産持たせてやるから。いい子にして、帰りや」
「手土産やなんて・・・ええです、ええですから」
慌てて手を振った。冗談やない。何で、こうなるんや?
「いや、別に大袈裟なもんやないんや。今日、アリスの顔見たら、何となく持って帰らしとうなってな―――」
穏やかな瞳が少し、物憂げな色を孕んだ。ジーンズの後ろポケットへ手をやった彼は、一冊の文庫本を取り出すと、僕の手中へそれを押し込めた。
「ほれ。道中の友くらいにはなるやろ」
パラフィン紙のようなカバーのかかった、ごく薄い冊子だった。縁の擦れ具合や色褪せた紙質からして、相当な年期が見受けられる。初めて、その書名を知った時に直感した通り、このひとの愛読書であるに違いない。
「今度、学校でおうた時に、返してくれればええから」
「・・・ほな、借りてきます」
漸く、僕たちは大路をゆるゆると歩きはじめた。街中の喧騒が、変わる日付の境界へ向かって加速しつつある。あと数十メートルも行けば四条河原町へ着く。
地下の駅へ下りる階段がぱっくりと口を空けている手前で、江神さんと別れた。
改札を潜り、タイミングよく滑り込んできた車両へ乗り込んだ。やや目立つ空席の一つへ腰掛け、本を開いた。
ゆらめきとともに残像が甦る。強い日射しと深い碧。咽せるような草の匂い。光る風。くっきりと染め抜かれた花鳥の影。いつの間にか、僕の意識は詞書の狭間へと落ち込む。
耳奥へ響く轟音が、微妙に変化した。電車が地上へ走り出たのだ。上げた視線の先で都市部の薄い闇は窓外を飛び遊び、町の瞬きが次々と切り刻まれてゆく。
単調に繰り返されるリズムが時々車体を傾ける中、僕は、江神さんを想う。
文字通り『賢者』と呼ぶに相応しい彼のこと、理性では割り切れていると思う。しかし、気持ちは、そう簡単にいくまい。部外者にもかかわらず、事件そのものを誰よりも正確に捉え、その痛みも直裁に感じられた分、きっと時間がかかる。尤も、それは、僕や―――マリアにしても、そうなのだろうけれど。
本来、癒えない疵は無いと解っていても。
それは一体、いつのことになるのだろうか?
時を友として薄れてゆくのが人の記憶であると解っていても。
それは一体、いつのことになるのだろうか?われらの後にも、世は永遠に続く。
われらは影も、形もなく消える。人影も疎らな夜汽車に揺られながら、僕は、再びルバイヤートを捲りはじめた。
(2005/1/16)
へ戻る
ううっ、今回もシャレにならないくらい長いですね。いちおう一日半の出来事となりますが、場面構成的に見ると一日目が夜のみ・二日目は午後のみ。それって正味、一日ってことなんじゃ…にも拘らずこの長さって、どうよ(爆)
元々、この駄作の前話にあたる『あの夏、いちばん静かな海。』で断念した、"ルバイヤートをアリスに貸す江神さん"を書くことが目的でした。とはいえ、それは嘉敷島から帰ってきた直後でなく、少し時間が経ってからでしょう、という気はしていて、当初から完全な後日談の位置付けだったんですね。
そんな訳で、改めてストーリー構築を思い立ったものの、夏休み中にアリスをまた上洛させる理由が要るなぁと考え、前フリに"不本意なヤキモチを妬くアリス"というコンセプトを追加(爆笑) まぁ、原作世界のアリスとモチってくだらないところでよく張り合ってますから、信長よりもモチに対して嫉妬心を感じる方が自然かなーということに。
で、もうお判りかと思いますが、執筆当時、信長とモチのパートの脱稿にはまたもや予想以上に時間かかってます(泣) 最早、彼らに勝てる日は永久に来ないような気がしてきた………