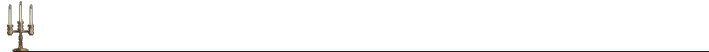夏祭り 前編
全ては、マリアの発した一言から始まった。
「男の人って、日常生活で浴衣着ること、あります?」「「「へ???」」」
共に経済学部四回生である望月周平、織田光次郎の両先輩と、法学部三回生の僕、有栖川有栖は揃って頓狂な声を上げた。
英都大学推理小説研究会(通称EMC)という総勢五人の弱小サークルは部室を持たないので、専ら学生会館二階ラウンジ最奥のテーブルを集合場所にしている。文学部四回生も五年目を迎えた江神二郎部長だけがまだ此所へ来ていないものの、残る四名は我が部の指定席となって久しいこの場所にいつものごとく腰を落ち着けていた。
少し前まで、今年の夏合宿をどうするかと皆して考えていたのだが、今は沈黙が横たわっていた。別に意見の対立があった訳でもなく、気まずくなるようなことを誰かが言ったのでもない。ただ、なんとなく会話が途切れて、銘々、口を噤んでいたというだけであった。
だが、我が部の紅一点―――これまた法学部三回生の有馬麻里亜が突如投げかけたこの科白は、男性陣の意識を完全に撹乱してしまった。
浴衣ねえ。さて、なんと答えたものやら。再び押し黙ってしまった僕たちは、それぞれの胸中で彼女の問い掛けに返す言葉を探して固まっていた。
最初に覚醒したのは望月である。
「浴衣かぁ・・・まず、着ることはあらへんな。旅館にでも泊っておったら別やけど」
続いて、良き相方の織田が答えた。
「ガキん頃なら着たこと、あるで。うちはお袋が姉貴のを縫うついでに俺のも仕立てとってくれとったからな。尤も、ここ十年はそんなもん着たことあらへんし、着たいとも思わんな」
マリアの縋るような表情が僕の視界を掠めた。けれども、こっちだって似たようなものである。二人の先輩が述べた意見に頷きながら、
「そうですね。一般的には、男が普段着るもんの中に『浴衣』っちゅうのは無いですよ」
と言い置く。僕は更に言葉を繋げた。
「俺も着た記憶、ないわ。修学旅行の時かて、ジャージーで就寝やったし」
僕たちのつれない返事を耳にした質問者は、はっきりと判る溜息をついてみせ、呟いた。
「やっぱり、そんなもんですよね」
それにしても、何故に彼女は突然こんなことを言い出したのか。向かいに座っている先輩たちも同じことを考えたらしく、「キイテミロ」と目線で合図してくる。従順な後輩である僕は両手で頬杖をついている同級生へ疑問を差し向けた。
「けど、なんで急に浴衣の話なんか持ち出したんや?」
ほんの一瞬、逡巡するような間が訪れたものの、マリアはすぐに口を開いた。
「さっき、夏合宿の話をしていたでしょう? もうじきあちこちでお祭りや縁日があるなぁ・・・って―――そうしたら、男の人も浴衣着て出向いたりするのかな、って考えたの」
「そりゃ、浴衣着てくる野郎もいるかもしれんけど、寧ろ、祭りの空間は一種の非日常なんやないか? さっきマリアが言うたのは、普通に生活してて浴衣を着ることがあるかどうかやろう」
論理の申し子、エラリー・クイーンマニアの望月が鋭い突っ込みを入れた。織田と僕もこの発言に追随し、頷く。マリアはちょっと困ったように眉根を寄せてみせたが、僕たち一同を軽く見回してから再び話し始めた。続けて、彼女が語った内容を要約すると次のようになる。
マリアの父が所属するロータリー(※各界の名士で構成される非営利団体。企業の役員が個人名で加盟することもあり、その地域社会に於ける奉仕活動を目的としている)の会員に呉服屋の御曹司がいるそうだ。業界で名を知られた老舗はれっきとした会社組織になっており、直営店舗が関東一円と京阪の主要都市部に散らばっている。
その若社長が新しい試みとして『和服仕立て引換え券』の導入を検討しはじめた。
ごく普通に市井で生活している人間からみた場合、和服は然程入用なものではない。着て歩く機会があまりにも少ない上に、一式揃えるとなればそれ相応の出費を余儀なくされる。更に着付けの問題も立ち塞がる。そういったことが原因で、日本の伝統的な民族衣装は多くの一般人から七面倒なものとして見られるようになってしまっている。
今や、七五三の衣装も成人式の振袖もレンタルで済まされるご時世だ。世間の人々に対して出入の店という立場がとれなくなった呉服屋は、一人でも多くの顧客を獲得する為に知恵を絞り様々な販売促進手段を講じようとする。それはどこの大店でも避けられない変革といえよう。
気軽に店へ立ち入ってもらうには、まず、価格の不透明さをなんとかしなければならない。反物の値段に仕立て代その他がプラスされるというシステム自体、現代人には既に馴染みにくいものとなって久しいのだ。昔は洋装だってオーダーするのが当り前だったろうけれど、既製品がこうも身の回りに溢れている今、人々はそれを購入するだけで精一杯なのである。
そんな風潮を考慮してか、一部の品に於いては縫製済みのものを販売する反面、和服本来の『注文し仕立ててもらう』という要素にも触れてもらおうということで発案されたのが、くだんの引替え券であるらしい。
幸い、昨今の浴衣ブームで若い女性を中心に着物への関心が高まりつつある今、それを見逃す手はない。女性に受けたなら、彼女らの恋人や夫子供にも効果の波及する可能性は存外高い。そもそも各家庭の被服管理は女性の手になるのが圧倒的だからだ。
そのあたりの事情も鑑みて、まずは、とっつき易くお手軽な浴衣を仕立て券の対象にという企画が考えられたのは甚だ納得のいくことであったが―――
「Yシャツのお仕立て券ならともかく、着物のお仕立て券なんて、需要あるのかいな」
織田の疑心に合わせ、望月と僕も首を捻った。
「だから、実験的なものなんですよ。試しに使ってもらって、反応次第では本格的に実施するつもりなんじゃないのかしら」
ロータリー例会の席上で一部の会員へ配られた『試験的・浴衣お仕立て券』がまず有馬竜三氏の手に渡り、着物を作るつもりの無い父親から娘のマリアへ回ってきた。しかし、マリア本人も浴衣は既に二枚―――以前、買ってもらった分と、高校時代、家庭科の授業でマリア自身が仕立てさせられた分とを所有していた。さすがに、浴衣三枚は過分なワードローブである。そういう訳で、その『お仕立て券』を使ってくれそうな人間を友人知人の中から探そうということらしい。
「それやったらその券、女の子にあげる方がええんやないの? 語学のクラスで一緒やった子とか・・・」
支店が京都市内にもあるそうだから、引替える場所に困るということもなかろう。僕がそう言うと、マリアは恨めしそうな視線を投げて寄越した。
「それが―――男物の場合は帯代も込みなんだけど、女物は別料金になるの。だから女友達には言いにくくて・・・」
ははん、そういうことか。確かに、一通り揃えられるというのならともかく、自分の方でも幾らか持ち出すとなれば「じゃあ、いいわ」と言いたくなる。それが人の心理というやつだ。第一、帯が無ければ浴衣そのものを着られまい。
「なるほどなあ・・・そんなら、既に一着持っている娘へあたってみたらどうや?」
望月が思案顔で言った。
「洋服と同じで、浴衣も何着か持ってて構わんのやろう? 前に買うたことがあるんやったら、帯はその時の分で間に合うやないか」
それを聞いたマリアは「判ってませんねぇ」と言いたげな表情で、僕たちを見返した。
「今持っている帯を基準に考えたら、自然と二枚目の浴衣生地も似たような色合いになりますよね。それだったら要らないってことになるんですよ。大体、着ていく場所だって多くないんですから、何枚もあったってしょうがないし」
織田が呆れ声を出した。
「なんや、女子からして着ていく場所が限られるんやったら、男はそれ以下やろ。着る機会なんかあらへんわ」
マリアは可愛らしい舌をペロリと出した。
「それはそうなんですけど―――中には普段着にする人もいるかな・・・って」
「あー、おらん、おらん」
大袈裟な手振りを交えつつ、二人の先輩が口々に打ち消す。僕の方をチラリと見たマリアは肩を竦めた。
彼女の気持ちも判らないではなかった。元々が『ただ券』とはいえ、出来るなら有効利用したいということだろう。だが、織田の言葉通り、女性ですら着る機会が限られる浴衣へ我々男が袖を通す回数がそうあるとも思えない。つまり、生活必需品の範疇には入らないということだ。
「これ、プレゼントとして使えないかしらってずっと考えてたんですけど―――難しそうですよねぇ。『日常生活で滅多に着ない』のが一般的なら、却って迷惑になるでしょうし・・・あーあ、どうやっても駄目なのかなぁ」
マリアにしては珍しく往生際が悪い。それが引っ掛かったので、僕は聞き返した。
「プレゼント――― って、誰か、あげる人を具体的に考えておったんか?」
「うん、江神さん」
その名を聞いた僕たちはあっけにとられ、かわるがわる顔を見合わせた。男三人、またもや暫し金縛り状態に陥る。
「なんでまた・・・江神さんなんや?」
まず、蘇生して質問したのは、今回も望月だった。マリアはしゃあしゃあと言ってのけた。
「だって、うちの部の中では一番着物が似合いそうだから」
それだけの理由で部長へ浴衣券を押し付けようとしていたとは―――全く、女の子の考えることは解らない。
少々驚かされはしたものの、僕はすぐにそうかもしれないと思い直した。こう言っては悪いが、望月や織田の着物姿なぞ、とんと想像がつかない。けれど江神さんなら、あの穏やかな雰囲気と二枚目然とした風貌で浴衣はもちろん羽織袴まで着こなしてしまいそうな気がする。
更にマリアは言葉を続けた。
「それに―――江神さん、背が高いじゃないですか。だから、ちゃんと身体に合う寸法のものを着たことないんじゃないかな・・・って思って。旅館の浴衣なんかだと、つんつるてんでしょう?」
そういえば夏森村でただ一軒の旅館へ泊った最初の晩、部長の脛が目についたのを覚えている。まさに"規格外"という有様だった。更に、望月や僕の足許もひんやりしたことを思うと、日下部屋が用意していた浴衣は昨今の日本人男子の平均身長を全く考慮に入れていない代物だったといえる。尤も、山間部のひなびた宿ではそれもしかたあるまいが。
「うーん・・・」
織田が考え考え、喋り出した。
「そら、ま、身長のこと考えたらマリアが言うように寸足らずのもんばっかやったろうし―――夏は浴衣の方が涼しいやろしな。案外、ええかもしれん」
顔上で傾いでいるメタルフレームの眼鏡位置を直しながら、望月も同意する。
「俺らは帰省することが可能やけど、部長はずっと京都におるんやからな。江神さんの部屋、クーラー無いやろう」
「あれ、モチさんの実家だって、クーラーつけてなかったんやないですか」
僕がまぜっかえすと、望月は「せやけど、海が近いから」と涼しい顔で言った。
確かに、盆地の京都と海岸線へ面している南部では、体感する暑さにかなりの開きがある。海原を渡る風が吹き抜ける町の夏と、篭った熱気が不快指数を高め続ける都のそれを同列に捉えてもはじまらない。「この、くそ暑い町でやったら、一着あっても邪魔にはならんやろう」と結んだ望月の見解もあながち的外れではなさそうだ。
思わぬ観点から好意的な意見が出てきた。先輩二人の賛意を得たマリアはにっこり笑った。
「良かった、私の一人よがりな考えじゃなくて」
しかし、突如、浴衣を受け取らされる江神さんの都合は考えなくてよいものか。僕がそう言うと、
「なァに、かさばるもんやなし―――大丈夫やて」
「賢者の部長のことやから、貰えるもんは、黙って貰ってくれるやろう」
経済学部コンビはいい加減かつ無責任に言い放った。やれやれ、である。
今や、すっかりその気になっているマリアも悪戯っぽい表情で言う。
「部長の身長は判ってますから、注文は私がしてこようと思うんですけど―――このこと、江神さんには黙っていてくれます? 内緒にしておいて驚かせたいんです。あ、アリス、生地選ぶの、お願いね」
急に自分の名前を呼ばれ、僕は慌てた。
「ち、ちょっと待てや。生地って?」
「最初から仕立て地が決まったものもあるんだけど、この『お仕立て券』は、お店に出向いていって好きな生地を選べるようになっているのよ。だから・・・」
「せやかて、なんで俺が」
「だって私、江神さんの好みなんて判んないもの」
当然のように返された。それで僕に選べというのか? 冗談じゃない、そんなこと僕にだって判る筈がないではないか。
「着物の生地なんて、よう判れへんわ。俺が行ったところで、役に立つ訳ないやろ」
「あら、大丈夫よ。店内には和服用の生地しかないんだから、その中で『これ』というのを決めてくれればいいの。大体、こういうのは下手に女の目で選ばない方がいいような気がするのよね」
確かに女性が見立てるのと男性のそれとでは、かなり異なった結果になることもあり得よう。だが、その重責を一人、担わされるのではかなわない。焦った僕は先輩達へたたみかけた。
「それやったら、信長さん、モチさんも――― 一緒に行ってもらえませんか!」
「アホ、なんで俺らがついていかなあかんのや。下手に何人も意見したら、却って決まらなくなるやろが」
織田に一蹴された。まぁ、それはそうかもしれないが。なおも追い縋るような気持ちで望月へ視線を移したところ、もう一人の先輩はニヤニヤしながらこう宣った。
「なに、大丈夫や。アリスが選んだもんやったら、部長も文句言わんやろうし」
「そうなのよね。私が選んでハズしたらどうにもならないけど、アリスの見立てだったら江神さん、怒らないと思うの―――正確には"怒れない"、かな」
更にマリアからも追い討ちをかけられる。僕は心中へ大きく溜息を吐いた。
まぁ、いい―――どうせバレているのだ、江神さんと僕の関係は。
もちろん、改たまって報告などしていない。しかしいつの頃からか、それは彼ら三人の知るところとなった。確かに、まがりなりにも推理小説研究会と名が付くサークルの仲間へそういつまでも隠し果せるものでもなかっただろう。尤も、何が何でも秘密にしようとしていれば出来たことかもしれないけれど。
だが、こういう関係が他の三人から不快な目をもって見られるかもしれないという危惧は、僕自身、殆ど抱いてなかったように思う。
今思えば、僕たちが互いに片想いだった頃から、望月も織田もマリアもそれとなく気遣ってくれていた。そんな気配を随時感じ取っていたせいで、江神さんも僕も殊更に隠そうという気が起こらなかったのかもしれない。
そして、二人の間柄が普通の先輩後輩から少し違ったものになった後も、皆でいる時の空気に殆ど変化は生じなかった。ごく偶にひやかし気味の発言が混じるようになったものの、三人とも江神さんや僕の"個人的な事情"へは立ち入らないでいてくれている。本当にありがたく、また、かけがえのない仲間達だと思う。
望月がマリアへ訊いた。
「で、頼んでからどれくらいで出来上がってくるんや?」
「ええと・・・最短で一週間ですね。それ以降なら、受取日を先延ばして指定することも可能みたいですけど―――それが、何か?」
「いや、どうせやったら江神さんの浴衣姿、見てみたいもんやなぁ・・・と思ってなあ」
「そうや! 江神さんにその浴衣着てきてもろて、皆で夏祭りにでも行くっちゃうのはどうや?」
織田が割って入った。ハードボイルドな男は少し照れくさそうな顔でこう続けた。
「今年は最後やから、なるべく一緒に―――て言うとったやろ」
そう、今は僕たち五人が一緒に行動できる最後の年なのだ。
来年になれば織田と望月は英都大学を卒業し、社会人への一歩を踏み出すことになる。八年間、文学部哲学科に居座り続けた江神さんも、この学び舎を去る。今だ就職活動もしていない部長は卒業後、院へ進む可能性が高いけれど、まだそうと決まった訳ではない。そもそも英都の大学院に進むとは限らないのだから。
古墳発掘のアルバイトをしていたこともあり、江神さんは百万遍にある国立大学の教授達とも交流があるようだった。基本的には今在籍している大学の院を選ぶのが普通だろうが、優秀な人ならばより高いランクの大学院への進学が可能となる。だから、江神さんが卒業後をどうするかは今だ五里霧中で、僕もはっきり知らされてはいなかった。
とにかく、僕たちが"五人揃って"英都の学生としていられる最後の年であることには違いなかった。だからこの一年は出来るだけ皆で一緒に過ごし、そのひとときを分かち合おうと約束していたのである。
「それ、いいですね」
マリアの同意を受けて、織田と望月が俄然色めきたつ。
「せっかくやから、他にもいろいろ行ってみたらどうやろう。なあ、信長」
「そうやな、イベントの方は俺らで調べてみるか。花火大会とか縁日とか」
話題が京都界隈の夏行事へスライドしかけたその時、ラウンジの入り口に見慣れた姿が見えた。僕の視線が動いたのに気づいたマリアは後方を見遣ると、軽く会釈した。望月と織田も振り返って、部長の姿を認めた。
やってきた江神さんは僕の隣りに腰掛けた後、「なんの話、しとったんや?」と一同に訊ねた。望月が『浴衣お仕立て券』の部分だけを飛ばして、今までに一通り出た話題を部長へ説明した。
今度は全員で夏合宿も考慮に入れた今夏のスケジュール調整を図ることにする。
共に過ごせる最後の長期休暇なのだ。五人でいた夏の記憶が、いつの日か遠い夢の中へ失われてゆくことのないように―――沢山の思い出が欲しいと、切に願った。
へ戻る
すいません、毎度のことながら長いです。一応、日にち跨ってますが(言い訳)
申し訳ありませんが、続きを読んでください…