Text by Terry Minamino Music by IKO-IKO
|
|
●1998/8/1(土) ウェブを眺めていると、私が Jenna号で使ってるサウンドカード HARMONY 3DS724A は結構な人気のようでめでたい。しかし、このボードのドライバはまだバージョンアップしていないと思われているようだ。実際、A-Trend のウェブサイトにはそれらしきものが見当たらない。 ところが、ここの FTP サイトを覗くと、Driver(NEW) 以下の、Card/SOUND/ATC-6655/Win95Win98/ というフォルダに ATC-6655.zip という書庫があって、これが最新ドライバなのだった。なぜウェブで見せていないのかは不明だし、無茶苦茶重いサイトだからダウンロードはそのつもりで。ちなみに、NT用のドライバも同じ日付でアップロードされている。 引き続きサウンド関連の話。 Windows98では、コントロールパネル→マルチメディア→オーディオ→詳細プロパティから、使っているスピーカーのタイプを指定することができる。 つまり、OS側でヘッドフォーンやサラウンドスピーカーといった区別がつけられるわけだ。ただうちの環境では、ここでいくら設定を変えてもデスクトップステレオスピーカーに戻ってしまい、他の設定で音質が変わるかどうかは確認できなかった。もしかするとうまく機能していないのか、あるいはものすごくうまく機能しているか、なんだが。 ●1998/8/2(日) この日記に出てきたリンクを抽出し、一枚のHTMLファイルにしてくれるPerlスクリプトを書いてもらった。適当な形式でリンクを張っていたので、結局、手作業で書き直さなければならない部分が多いが、スクリプトそのものは良くできたものである。そのうち公開されるかもしれないから、要望等あったらわしにメールしてちょ。 →修正途上のお笑いパソコン日記リンク集。 まだ分類まで手が回っていないのでよろしく。
●1998/8/3(月) 以前ここに、Productiva G100 のスクロールが遅いと書いた。それを読んだある方が、自分も使っているが確かに遅いという報告をしてくださった。そればかりか、その方はスクロールを早くしてくれるツールまで作って(!)くださったのである。 導入後、確かに早くなって感じる、というか、ふつーのレベルになった。いやあ、素晴らしいなあ。こういうツールがひょこんと出てくるから、この世界は面白くてやめられない。 ちなみに、このツールを作ってくださった方の名は、jellyfish さん。ご存知の方はご存知であろう。PC-9801シリーズのキーボードエンハンサーとして絶対的名作だった JFKEY の作者である。もちろん私も愛用させていただいた。改めて氏に深く感謝。 ●1998/8/4(火)
● DirectX 6.0 は、まだ正式公開ではない。それにこれ、Windows98に入れようとしてもバージョンチェックで蹴られる。98ユーザーはWindows Update でやってくれだってさ。 ●1998/8/5(水)
そゆわけでこれは私の愛用ツールなのである。お勧め度☆☆☆★ ●1998/8/6(木)
●
Windows用だけではなく、Mac版も用意されている。あ、そっちが本命なのかな(笑)。いずれにしても、お試し版で読めるのは独自フォーマットのファイルだけなので、T-Time のウリであるすべてのテキストファイルやHTMLファイルを縦書きで読むという機能は使えない。 そういうわけで、ダウンロードしたパッケージに入っているサンプルを読んでみたのが上の図(左の場合もあり)である。 ざっと試した感想としては、これ、なかなかいいのではないか。インターフェイスもアクロバットリーダーなどと比べるとはるかにスマートでわかりやすく、機能的にも必要充分である。ってゆーか、今までに見ることのできた縦書きビュワーの中ではベストだ。これなら商品版を買ってもいいかと思わされた。いや、多分買うだろう。安いし。 欠点は、非常に重いこと。P5 MMX 200MHz 相当のマシンでは少々ストレスを感じる場合があった。
ただし、冒頭に書いたように、私はすでに縦書きにこだわっていない。縦書きが適してると思われるようなテキスト、例えば小説、をコンピュータで読みたいとも、読もうとも思わない。それでも、今後コンピュータで文章を読むという状況は間違いなく増えていく。だいたい紙で読みたくとも、もはや手に入らない本の方が多いのだ。そういった観点で見れば書物のデジタル化は必須だし、コンピュータ用のテキストリーダーが発達することは自然の成り行きである。 コンピュータで文章を読む時に発生する問題のいくつかは、アクロバットリーダーや T-Time その他を使うことで解決に近づくだろう。現状の解としてはこれが精一杯としても、いつの日かモニタの解像度が書籍のそれと変わらなくなる日がくるかもしれない。そうなった時、まだパソコンなんかで小説を読むものかといっていられるかどうか、はて。 ●1998/8/7(金) 仕事でパソコン画面のキャプチャをしなければならないことがよくある。通常は問題ないのだけれど、DirectX を使うスクリーンセーバーが困るのですね。つまり、どのキーにキャプチャツールのホットキーを割り当てても、それを押したとたんにセーバーが終了してしまうからだ。 PrintScreen キーにホットキーを割り当てられればなんとかなりそうなのだけど、DirectX 対応のキャプチャツール HyperSnap-DX では割り当てられないようなのだ。 そういうわけで長年困っていたのだったが、ある偶然から解決方法を発見したのでご報告したい。すでに常識かもしれないし、そもそもそんなことをする必要のある人間がどれほど以下略。 まず Directx.cpl を手に入れる。方法は、DirectX の開発者向けパッケージをダウンロードしてインストールするか、親切にも単体で配布しているサイトからゲットしてくる。単体でまくなんてことをしてもいいとは思えないので(笑)、配布先は書かないが、調べる方法はいくらでも以下略。 さて、無事 Directx.cpl がインストールされたら(単体で拾ってきた場合はシステムフォルダに入れること)、コントロールパネルから起動する。すると DirectDraw というタブがあるから、オプションで Enable PrintScreen Key をチェックして終わり。以上で通常どおりPrintScreen キーを押すだけでキャプチャされているはずだ。 え? ということは、HyperSnap-DX とかいらないんちゃう? そうなんですよ、あーた。しくしく。 ●1998/8/8(土) ●japan.bbs.pc-van なんてものがニューズグループに。 いまさら何を語り合おうというのか? すげく謎。 マイクロソフトから ENCARTA98 の不具合修正 CD-ROM が送られてきた。でもこのファイル、だいぶ前にウェブで配布されているし、サイズも217キロしかないの。どうしちゃったんだ?>MSKK 最近感じたことの覚え書き(今思い出したので、忘れないように自分のために書いておく) ●鴨川の橋問題 先日、フランス風の橋を鴨川にかけるという計画が白紙に戻った。京都に外国風の橋は似合わないという京都人の意見を私も支持する。しかしそれなら、あの京都タワーを容認しているのはなぜなんだ、とも思うのであった。 ●1998/8/9(日)
インターネットウォッチの成功を受け、メールマガジンは続々と作られたけれど、ブラウザが作られたものは皆無であったはずである。 しかーし、ここに初の特定メールマガジン専用ブラウザが登場したのであーる。対象は ZDNet Wire で、ブラウザは ZDView ちう名前。 サンプル画像を見てもらえばわかるとおり、メールを読みこんで解析し、タイトル部分と記事部分を分けて表示してくれるわけですな。馬鹿みたいに長いメールマガジンをいちいちスクロールしながら読む必要がないのと、読みたい記事だけ読むといった使い方ができるのでありがたい。 ただこれ、今のバージョンはまだまだ簡易的なもので、メールの格納フォルダのパスを覚えてくれないとか、記事の表示ペインの左側に少し余白を作ってほしいとか、記事表示部分でテキストの行間が広げられたらなお素敵とか、URLの表示を一般的なクリッカブル方式にしてほしいとか、あれこれ要望はある。 だがそういったことはともかく、こういうものがあったらいいなと感じているのが私だけではなかったと確認できたのがうれしい。 もう一つ付け加えておくと、メールマガジンにフォーマットの変更が加えられると、当然ブラウザにも変更が必要になる。そこらのメンテナンスの面倒くさささが、今までこういうものが作られてこなかった理由の一つでもあるだろう。その意味で、本当はメールマガジンの提供元が作ってしかるべきソフトだと思う。ZDNet Wire はぜひそのあたりを考慮し、できたら作者にお金を払ってでも以下略。 ●1998/8/10(月) Windows98に付属のMS明朝(Msmincho.ttc)は、バージョンが2.30になり、ファイルサイズも8メガに膨らんでいる。それだけならいいのだが、なぜかスムーシングが効かないという謎を抱えているのである。 左は 95、右は98上で、あるページを表示したときの様子。 最初はビデオカードのせいかしらんなどと思っていたけれど、95上でスムーシングを切ると右の例と同じように表示されることから、98でこの機能が生きていないことに気がついたというわけである。 この謎を追求しようと思いつつ忘れていたのだが、fj.os.ms-windows.win98 を読んでいたら報告があがっていた。 結論から書くと、フォントのサイズによってスムーシングが行われるか行われないかが決まるようだ。このあたりは解像度やシステムフォントのサイズといった条件を変えて厳密に調査すれば決まったパターンが導き出せそうである。誰かやってみてくだされ。ちなみに、この症状はフォント依存で、95やNT4に98のMS明朝を持っていっても再現するとのことだ。 ●1998/8/11(火) ●ZDView バージョンアップ。 その他、Visual J++ 6.0 Technology Preview 2 が出てたとか、DEC の日本サイトで DIGITAL FX!32 ユーザーフォーラムが開設されたとか、しばらく前から噂されていた Solaris の無料化がついに始まったとか、本日は業界注目のニュースが多かったわけだが、そんなことより問題は今日の雨、んではなくて、長年使っていたテレビがいよいよ本格的に不調になってしまったことなんであ〜る。 うちのテレビは三菱電機製で、使い始めてから9年目に入る。大体こういったものは10年ぐらい持つものだけど、うちでは一日24時間、一年365日つけっぱなしだから、9年も使えばふつーの家庭の20年分ぐらいの稼働時間になる。そう思えばやや早めに壊れても仕方ないんだろう。 しかしこのテレビ、不調になってから実はすでに2年ぐらいたってるのである。だましだまし使ってきたが、今回はもう我慢できない症状が発生した。かくなる上は買い換える以外に道はない。 大石恵がCMをやっているからまた三菱電機を、などとはこれっぽちも思わず、電気屋に走って SONY の WEGA を買いに。ところが、こやつってば一番の人気商品ちゅうことで、納品に一週間もかかるといわれてしまった。しくしく。まあ間に盆休みが入るからのう。 この機会だから、最近のテレビ受像機について考えを述べておきたい。いや、そんなもの一言でいえるんだ。 ワイドテレビを買う人の気がしれない である。ワイドテレビで横に引き伸ばされたいんちき映像を見続けるなど、あたしには耐えられませんことよ。 ●1998/8/12(水)
も少し正確にいうと、SP Wrapper は名前から想像できるように SP のフロントエンドで、英語のコンソールアプリに GUI な日本語インターフェイスを被せたもの。エディタやブラウザの起動機能などもある。 しかしいまさらなぜ、こういうものを紹介したかというと、これ、SGML のチェックにも使える、ってゆーか、元がSGMLパーザなんだから当然とゆーか、そっちの方があらまほしき使い方であった。 ともかく、私の現在の最大の興味はXML にある。そして XML は SGML のサブセットだから、両方とも勉強しておくと吉だが、何をするにしてもまずパーザが必要、というわけだすねん。なお、SP には、SGML から XML へのコンバート機能があったり XML パーザとしても使えなくはないようだ(そりゃそうか)。まあ XML パーザなら XML for Java の方が良いでせう。プラットフォームを選ばないし、なんといっても作者が日本人だ。 昨日書き忘れたこと。 以前からサムスンのこのテレビが気になっていて、新しいテレビを買うときは選択肢に入れようと思っていた。ところがこれ、まだ実機を見たことがないのよ。コンセプトはまったく私好みで、これこれ、こゆのを求めていたのよとか思ってたんだが、現物を見ないで発注できるほどまだ韓国製品を信用し切れないっすよねえ。
今使ってるテレビ(壊れたやつ)は極悪で、右の図の黄色い枠の内側部分しか表示されていない。もちろんどんなテレビでも、安全サイズの関係で送出された映像がすべて見えることはない。番組制作側でもそれを想定したフレーミングをしている(はずだ)。だからこそサムスンの商品コンセプトが生まれたわけだが、うちのテレビみたいに中心が大幅に偏ったものも珍しいのではないか。 もう一つ、このテレビは偏ってるだけではなく、リファレンスに使うモニタより明らかに寄り気味の絵になっている。これは画面を大きく感じさせるためにメーカーが使う姑息な手段である。安全サイズよりさらに安全なサイズってわけですな。うちのは29インチだが、一般的には小型テレビでやられることが多い手法。 これらの極悪仕様のため、画面上部に表示されるテロップが半分切れて表示されたり、テレビゲームではスコアが見えないなどといった悲惨な結果になるのだ。さらにうちの場合、右がやや上がった(または左が下がった)傾いた画面なのよ(とほほ)。 昔のテレビはそのあたりの調整も多少はできたんだが、今のはほとんどブラックボックス化してるためどもならん。それやこれやで、三菱のテレビなんか二度と買うものかと心に固く誓っているのであった。 ●1998/8/13(木) ●QX 評価版と QTClip がバージョンアップ。 キーワード関連の改訂、保存できる書式設定の増加、などなど。 ●1998/8/14(金) ●DocBar がバージョンアップ。 改訂内容は不明。Windows98対応が目的だと思われる。 予定より早く WEGA が届いたので表示をチェックしてみた。
左がこれまで使っていた三菱での表示範囲で、右がWEGA。 もう明らかに違いますな。おかげで画面を少し小さく感じてしまう(笑)。だがこれが本当なんだからしょうがない。 それと、WEGAには画面の傾きを調整する機能がついていた。地軸の影響うんたらかんたらとマニュアルに書いてあったけど、なかなかうれしいファンクションである。 ショップで見るとへこんでるように感じられる平面ブラウン管も、単独だと思っていたほど違和感はなく、これまで球面周差のある映像ばかり見てきた目にはなかなか新鮮でよろし。こうなるとパソコン用のモニタも平面にしたいところ。液晶モニタにすれば自動的に平面になるのだけど、1280x1024 が表示できるやつは高くて手が出ない。そのクラスがリーズナブルになるのは2年ぐらい先か? 画質その他でほとんど文句のない WEGA だけど、3つあるビデオ入力のうち、後ろと前の1つずつにしかS端子が用意されていないのはペケだす。 ●1998/8/15(土)
● Chic-98号に IE4.01 を入れてみた。何を今ごろって思われるだろうが、これ、旧石器時代の486マシンなのよ。そこに青銅器時代の83MHz 版ペンティアムODPを挿して Windows95 で運用してはいるけど、実態はただの ZIP ドライブサーバーである。それ以前にはプリンタサーバーとしても使っていたのだが、色々あって現在は Liz にプリンタがつながっているのだ。 このマシンにWindows98を入れてみようかと思い、その前に IE4 で試したと、ゆーわけだす。 〜中略 IE4.01にこれといって問題は出なかったけれど、このマシンのAドライブが決定的に容量不足であることに気づき、Windows98の導入は断念。ZIPのためだけにこのマシンの電源を入れておくのも馬鹿らしいので、いっそ廃棄処分にしようかなと思ったことであった。 ●1998/8/16(日) iMacの発売を報じる CNN (本物)の論調はアップルに対して少々シビアで、安いマシンが売れると(高級機の売れ行きが減って)かえって収益を悪化させる可能性もあるといった分析をしていた。 ●1998/8/17(月) 記憶なし。 ●1998/8/18(火) 記憶なし。 ●1998/8/19(水) 記憶なし。 ●1998/8/20(木) 記憶なし。 ●1998/8/21(金) ●1998/8/22(土)
● Go!Zilla がいつの間にバージョンアップしたか不明。私の勘違いの可能性あり。IrfanView32 は、AVIファイルをBMPに分解できるようになったり、キャプチャ機能がついたりしてる。 ●1998/8/23(日) VHSのデッキが壊れた模様。毎年毎年こうやって何かが連続的に壊れていく。そうやって機器をリプレースしていくから、壊れる時期がまた重なり、いつまでたっても悪循環。ぶつぶつ。 ●1998/8/24(月) 特定マシン上にあるIEの Favorites を、複数のマシンで共有する方法をこのところずっと考えていた。 Windows98のレジストリをサーバー用マシンの Favorites へパスを書き換えても反映されないし、再起動後にはレジストリは元通り修復されてしまう。つまりOSが起動されたドライブ以外は指定できないようになっているわけだ。
そんなわけでフォルダ同期ソフトをいくつか試したところ、As you like..という作者の SYNCDIR が最も気に入った。かなり高機能だし、フリーなので、これを使っている。ただし同時に3台以上は同期させられないから、AマシンとBマシン、次にBとCという具合にするしかないのが面倒であるのことよ(笑)。同時に3つ以上のフォルダを同期させられるソフトってないのかしらん。 ●1998/8/25(火) 勉強すればするほど、一般人に XML は必要ないという結論になるんだが、このまま学習を続ける意味があるのか(笑)?>をれ なぜ必要ないと思うかについては長くなるのでパス。 ●1998/8/26(水) うう、明日がデッドっす。みなさんさよーならー。 ●1998/8/27(木)
● なんつーか、ファイルをダウンロードさせることが目的のサイトで、いつ何がバージョンアップしたかがわからないとこってタコよね。アダプテックジャパンや富士フィルムみたいに多数のファイルが置いてあるところでそうなってるとかなりむかつく。 しばらく前に、アドビジャパンから DMが送られてきて驚いた。だってあそこからそんなものが来るのは珍しいのだ。その直後、売上不振による人員整理のニュースが流れ、特にアジア地区の伸び悩みが原因と聞いて海よりも深く納得した私だったが、今度は買収の話ときた。さもありなん、ってゆーか、業界的には QuarkXPress 圧勝だもんなあ。 そうそう、QuarkXPress といえば、Windows 版の登場により、マックでなければならない理由がまた一つ(全部か?)減ったよね。まあすでに出来上がったシステムがあり、不景気とか償却といった問題もあるから、あの業界が一気にプラットフォームをリプレースするわけはない(できない)けれど、じわじわと侵食されていくのだろうなあ。 BIGLOBE 側のホームページ容量が一杯になったので、また2メガ追加した。しかし発作的にやったので今日が何日かを考えていなかったのは大きな間違いである。今月は5日しか残っていないのに、料金は一月分加算されるんである(笑、、えない)。 ●1998/8/28(金)
● こんな生活をしているせいで、さまざまな機器のファームを度々バージョンアップしているわけだが、Aterm は専用インストーラーが良くできていてすごく簡単である。そのかわりインストーラー自体もバージョンアップするため、最新のファームを入れるには最新のインストーラーを使わなければならない。でもまあ、ファームの書き換えは少々危険を伴う作業だから、初心者には安心なインストーラーだと思う。 ViperV330 英語版ドライバのページを見ていてふと気がつくと、BIOS のバージョンもうちのより新しい。んまー、これはとっとと導入せねば(良い子は真似しないように)とダウンロード、引き続き FD をフォーマットし、、。あれ? NT4.0 のエクスプローラーからフォーマットする時って、DOS のシステムを転送できなかったのね? このボードの BIOS をアップデートするには DOS でブートする必要があるのよ。 よく考えると、NT マシンから FD をフォーマットするのは初めてである。一瞬、方法を探して みようと考えたがすぐに思い直し、95 マシンでフォーマットした(DOS窓からやればいいのか)。 で、そのディスクに BIOS アップデート用のファイルをコピーし、リブートする。終了後、ディスクを抜いてまたリブート。以上でアップデートは完了である。この作業も特に難しくはないのだけれど、英語と DOS の知識を要求されるわけで、95 以降の世代にはつらいかも。 DOS の話で思い出したから書いておくけど、PC UNIX 系の OS を導入しても、本体のマザーやその他の機材の BIOS をアップデートする時、DOS のシステムディスクが必要だったりするわけです。このごろでは 95 用のアップデータしか提供されない場合もあるから、やっぱり Windows もインストールしておかねばならないという、なんだか悲しいお話。 ●1998/8/29(土) やー、今日は iMac の発売日ですねえ。大人気らしいから、Windows 98 の発売に引き続き集客力の高い商品が出てきて、電気街の人々はうれしいことででありましょう(地方の人はお気の毒)。 このマシンについては以前も意見を述べたように、あんまり興味はない。あたしはそうは思わないが、仮にあのデザインがすんげーカッコいいとしても、中身はおんなじなんだもん。それに VRAM 2メガで 15 インチモニタなんて以下略。 んまー、世の中にはクラシックカーのレプリカを欲しがる人もいるわけで、スタイルにグっと来てしまった人に何をいっても無駄ではありましょう>わし あ。マックのこと書いてて思い出したから続けて書く。 一部で、マックのほうが簡単だなどといった意見があるように聞いているが(わはは)、それが本当なら、なぜいしかわじゅんは毎週あんなにトホホなことをし続けているのだろう(俺もだけどさあ)。そう思いませんこと? も一つマックネタ。 先日、あるショップから Office98 Macintosh Edition の案内が来てた。でもわし、そのショップでマック関連の買い物をしたことないのだ。ねえねえ、どーしてをれがまっくゆーざーだってわかったの? なぞてきなりー。 ●1998/8/30(日) Windows98 マシンに MS-Office97 SR1 を導入したのだが、驚いたことに他に何もディスクを要求されず、するするとインストールが終了しちゃったんである。このマシンには Office 系のソフトや一太郎系のソフトが一切入っていないのにである。不思議だ。 ここで、話は Office2000 に。 恐ろしいことに、こやつの標準ファイル形式は html になった。ってーことは、ワードで作った文書もエクセルで作った文書もパワーポイントもアクセスも、なにもかもすべて hoge.htm というファイルを吐くってことである。それだったら XML 化してくれた方がなんぼかうれしいぞ>わし もしかして拡張子連動という概念を捨てる気なのか?>MS ちなみに、そのあたりはメタタグで区別をつけるようになっている。それでどのアプリケーションを立ち上げるか決めるわけね。ワードで作った文書がアクセスで編集できるわけではない。そんなもんにどれほどメリットが? そもそもメタタグなんていくらでも書き換えられちゃうぞ。なーんか漠然とした心配がっ。 ●1998/8/31(月) 28日に書いたことの補足。 PC UNIX 系の OS を使う場合でも、DOS なり Windows 9x が必要になるという事実の意味するところは、Linux や FreeBSD がタダで手に入ったとしても、それがホントーにメリットなのかどうか、ということである。 つまり、すでに Windows 9x を使っている人間はともかく、これからパソコンを始めようという人に Linux を薦めてどうするんだ、と主張したいわけです。ハードルの高い OS を使うために色々なものが必要とされるのは PC UNIX の宿命とあきらめましょう。でも、Windows 9x より安く上がるから PC UNIX がいいのだという説には疑問があるってことね。 もちろん、旧型マシンで充分なのだから、結局安く上がるという見方も可能だ。それでも、X を使うならやっぱりある程度は速いマシンがいるし、だいたいやねー、旧型マシンを持っているのはほとんどが Windows ユーザーであろう。え? それ以前に旧型マシンでないと PC UNIX では各種デバイスを動かせない可能性があるって? わはは、それもそうだな。 というわけで、一部のアジテーションじみた主張を信じるのは勝手だが、これから初めてパソコンをやろうという人は、素直に 98 なり Mac なりを買ったほうがええですよ、というお話でした。 |



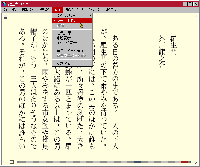
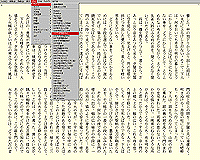 右の図は全画面表示してみた時のもの。自動的に段組表示になった。やはりある種のテキストは縦書きのほうが読みやすく、すっきりと頭に入ると思うのはもう若くないせいだろうな。
右の図は全画面表示してみた時のもの。自動的に段組表示になった。やはりある種のテキストは縦書きのほうが読みやすく、すっきりと頭に入ると思うのはもう若くないせいだろうな。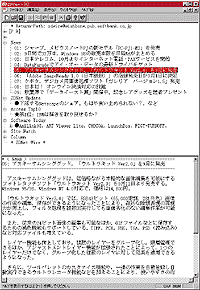 インターネット暦ではすでに古代の話になるけれど、日本初(多分)のメールマガジンであるインターネットウォッチが創刊されたとき、私は専用のブラウザを作ってほしいと思った。でも誰も作ってくれず(笑)、そのまま現在に至っている。
インターネット暦ではすでに古代の話になるけれど、日本初(多分)のメールマガジンであるインターネットウォッチが創刊されたとき、私は専用のブラウザを作ってほしいと思った。でも誰も作ってくれず(笑)、そのまま現在に至っている。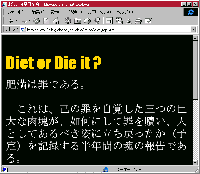
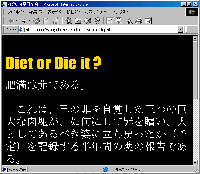
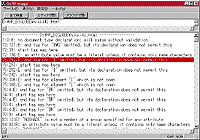 SGMLパーザの
SGMLパーザの  ついでだからテレビネタを続ける。
ついでだからテレビネタを続ける。
