 ホイール始めました。5/19 ホイール始めました。5/19
写真は現在製作中のスズキ・ジムニー用アルミホイールじゃなくって・・・EECのKV-1SやKV-85に入っているタイプの転輪。キットには2種類入ってますが簡単な形の方を現在作ってます。
EECの転輪はタミヤと比べて直径が小さいのですが、EECの方が正確っぽいのでこちらに寸法を合わせるつもりでした。が、途中で何回か型取りするので大きめの方が良いだろうと思って修正したところ、ほぼタミヤと同じ径になってしまいました。・・・最終的には両者の中間になる予定。もともと見た目じゃ解らない程度の差だし、どっちが正確か確証も無いので良いでしょう。
この後リブのモールドを付けていくのですが、リム部分と同じく薄いモールドなので、量産出来るかどうかチト不安。 |
 手抜きと見るか・・・5/15 手抜きと見るか・・・5/15
オリジナルヘッドのうち2つは既にDKWバイクのフィギュアに使ったので、残り6つを一気に作っています。 私はドラゴンから新作フィギュアが出ると、パーティングラインなんかはそのままに一気に組んで様子を見るので、既に組んである胴体は沢山転がってます。それの頭を付け替えただけなので実質「作っている」のではなく、「塗っている」だけですね。
今回のヘッドは店で売って貰おうという野望があるのですが、聞くとヘッドの作例写真が有る方が良いだろうということで、こうして作っているのです。全身を写して顔が小さくなっては意味がないので、バストショットか顔のアップを撮る事になるでしょう。・・・そうなると、下半身や背中は塗らなくて良いので「手抜きできる。」のです。しかし、アップになる分、上半身は「手抜きできない。」のです。・・・結果がどうなるか。皆さんに手にとって見て貰える日が来ることを願ってます。(笑)
|
 成功率がスゴイ5/10 成功率がスゴイ5/10
左の写真は、現在量産中のオリジナルヘッドの失敗作です。鼻の先なんかにちょっと気泡が入っている「惜しい物」が約80個。この他、捨ててしまった完全なダメ品も多くあります。でも、成功作は250個以上あるので、まぁまぁの成功率だと思います。実は、失敗作の大半は最初に作ったシリコン型による物で、型を作り直してからは非常に高い成功率なので先が楽しみです。
しかし・・・レジンのガスで顔の皮膚がまたヒリヒリし始めました。今回は事前に顔にクリームを塗って作業したのですが塗り残しがあったみたい。これがなきゃ型取りも少しは楽になるのですが・・・ |
 待望の書5/4 待望の書5/4
おお、この2人のオッサンの後ろの車はオースチン装甲車ではないか。いよっ!待ってました!
この本は第一時世界大戦当時のロシア装甲車の写真集で、可愛いいシャロン装甲車を初め、ランチェスター、パッカード、オースチン、ロールスロイス、といった有名所の輸入装甲車。オースチンプチロフ、ガーフォードプチロフ、ムゲブロフ、といった有名ロシア製装甲車。その他何が何だかわからない無名装甲車・・・がゾロゾロと出てきます。
この本を見ていると、当時のロシアが種々雑多な装甲車を使用しているのが分かります。「第一次大戦の世界の装甲車」と言っても通用しそうな内容(ドイツ側は抜きですが)。過去に無かった内容の本で、貴重だと思います。
105ページ。本文は全てロシア語。図面も多い。マムートさんで3200円で購入。好きな人は是非見て欲しい本です。 |
 カーベーだべ〜4/30 カーベーだべ〜4/30
なんとか塗り上がり。成り上がり。そこんとこよろしく。
本当は3色迷彩なのですがイロイロ塗り重ねているうちに2色迷彩みたいになってしまいました。まぁ、私の場合この逆のパターンも含めてよく有る事なのですけど・・・。取りあえずこんな感じで展示に出します。
展示の後は足回りを中心に思い切った汚しを試してみようと思っています。失敗したらもう2度とこのHPに出てこないでしょう。去年のチハ2台や3突のように(爆)。
|
 やっぱりKVは良いねぇ。4/28 やっぱりKVは良いねぇ。4/28
地元での(最後の?)タミヤ・モデラーズ・ギャラリーに展示する為にKV-1Aを作っています。これで一応タミヤ製KVの3キットは制覇。今後もフィンランド仕様のエクラナミや、KV-1m1939、KV-2m1940といった所は作りたいと思っています。
何故こんな物を今頃作っているかと言うと、EECがKV-1S、KV-85、及びSU-152(予定)というナイスな商品展開を行っていて、これらキットをストレートに組むだけで見応えあるコレクションになる事が予想されるからです。以前からこのコレクションは夢見ていましたが、実際にやるとなると非常に骨が折れる作業が待っていました。それが今ではKV-85からJS-2、JS-3までも作れてしまうのだから凄い話です。
こうなると・・・BT-2〜T-34〜現在まで、のラインもコレクションして見たいですが、こちらはKVより数が多くて、出来のばらつきがあって、T-44が欠けているという問題があるので、30年後くらいに揃えば良いかなって感じです(笑)。 |
 むむ!ポルシェ!?4/21 むむ!ポルシェ!?4/21
車で走っていると、右手の草むらにトラクターを発見。おお!あの丸くて赤いノーズは、ひょっとしてポルシェのトラクターじゃないか!・・・と言う事で、今日写真を撮りに行きました・・・。いや、ポルシェにトラクターが有って、こんな形しているんです!本当です!
・・・でも、今日、改めて見てみると、なんか妙に小さいボディで、剥がれてしまったマークの跡が「イセキ」とハッキリ読めるシロモノでした。実は井関農機は過去、ポルシェディーゼル社と提携して輸入販売すると同時に、日本向きの小型モデル自社生産しました。設計にはポルシェサイドの協力もあったとかでソックリです。もっとも、両社の提携は短い間でした。どうやらポルシェがトラクター業から撤退したらしいのです(不確か)。
このTB-20型は名機らしく、1964年と以外と古い機種のワリに当地では結構見かけます。個人的にも大好きです・・・でも、ポルシェかと思ってワクワクしてたのでがっかり。その帰り道、この近所にあったイタルデザインのランボルギーニのトラクターを見て帰りました。 |
 OH モーレツ!・・・4/18 OH モーレツ!・・・4/18
前回、1番強烈なスタイルと書いたのがこのモンディアルです。これもプロターの箱絵です。余談ですが、シルバーの部分が銀色で印刷されていてスキャン向きじゃないと判断、デジカメで撮りました。古いキットですが、カルトグラフ製の美しいドライデカール(?)が入っていたりしてプロターはやっぱり変わっていると感激。
伝説
モンディアルはスタイルだけのこけおどしでは有りません。コレは1957年型で、世界で最もモンディアルが強かった頃のマシン。カウルの下のメカは非常に進んでいた為に、逆に今の目で見ると面白みが無いくらいに後のスタンダードとして普及した物で、当時、マン島TTレース参戦へ向けて急ピッチでマシンを開発していたホンダがコレ(の仲間)を入手し解析、多大な影響を与えたと言われています。(ホンダ・コレクションホールにそれが現存)
さて、ホンダは1959年にいよいよマン島TTレース125ccクラスに参戦。チーム賞を取るのですが、ホンダで最高位の谷口が6位でトップのMVアグスタに7分遅れの1時間34分という記録でした。その時優勝したMVアグスタのライダーがタルキニオ・プロビーニ。・・・プロターの社長さんです。
プロターのモンディアル。ホンダファンにはちょっと気になるアイテムでは?残念ながらプロター・ジャパンHPによると、20年以上再販されていないそうです。 |
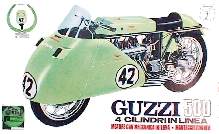 脱いでも凄いんです。4/14 脱いでも凄いんです。4/14
どうも一般的に男の子というのは、見慣れない乗り物を目にすると気になる様です。
私はカウルの付いたバイクは皆同じに見えてあまり魅力を感じないのですが、50年代後半あたりの前輪まで覆った大きいカウルのバイクは「見慣れない乗り物」として妙に惹かれます。この手のバイクで現在キットが売られているのは、プロターのDKWとBMWサイドカーだけです。大昔には、モトグッチ2種類と、モンディアルが出ていた事が(持っているので)判っています。
さて、スタイルが1番強烈なのは、ホンダコレクションホールでも異彩を放っていたモンディアルなのですが、私が一番気に入っているのは、この「モトグッチ4気筒」です。なんと水冷4気筒DOHCを縦置きに積んでいて、カウルを取ると排気管がずらっと並んでいてムチャクチャ格好良いのです。
さて、もう1種類のモトグッチはというと・・・これがビックリ「モトグッチ8気筒」です。僅か500ccのV型8気筒を横置きに積んでいます。私は他にこんなバイク知りません。しかし、これがエンジンのお化けみたいな異質な感じで、カウルで隠した方が格好いいというシロモノでした。本当は全部の画像を見て欲しいのだけど・・・。
プロタージャパンの見応えあるHPを見つけて、ちょっと盛り上がっている私。
http://www.jade.dti.ne.jp/~protar/index.html
|
 思わず組んでしまった。4/11 思わず組んでしまった。4/11
昨日、キット紹介に記事を追加したクリルーのAUTOCARRETTAですが、いつの間にか基本形だけは組んでしまいました。荷台に載っているバイクはDKW、ギリギリの大きさです。
このキット、まず一体型の床パーツがあって、そこにボディたる「壁」を立てていく構成なのですが、一見問題無く見えた土台となる床パーツに酷い歪みがあって、瞬間接着剤で部品を付けては外し、付けては外し、を繰り返して泥縄式に修正、ちょっと汚い仕上がりになってしまった様です。この手のトラックは荷台等が歪んでいると見栄えが悪いので、納得いくまで水平、平行、直角、を出し、細部の仕上げについてはその後に考える方が出来映えが良くなると思います。基本形の歪みは、後で気が付いても修正出来ません。 |
 M-113の秘密3/24 ・・・・うそうそ。秘密でもなんでもない。 M-113の秘密3/24 ・・・・うそうそ。秘密でもなんでもない。
左図はM-113系車両のオペレーターズ・マニュアル(TM 9-2300-257-10)に載っている図。変な形をした板(ゲージ・赤で描かれている)を起動輪(白い部分)に当てているところ。ゲージは2ヶ所が丸く切り欠いてあり、起動輪のボルトにうまく合わさる様になっている。こうやって所定の位置に置いたゲージの『歯』と、起動輪の『歯』を重ね合わせる事によって起動輪の摩耗状況を判断する訳だ。
ゲージの『歯』の反対側に2ヶ所出っ張りがある。この出っ張りの間隔はキャタピラのピンの間隔と同じで、ピン穴に当てる事でキャタピラの伸びを調べる事ができる。また、このゲージを転輪上部とキャタピラとの間に置き、キャタピラのたるみ量を確認し、テンション調整をする。
このゲージ(ストックナンバー5120-01-041-9920)、持っていても意味無いけれど、なんか欲しいなぁ(笑)。
(註・赤と白以外の色は見やすくするため勝手に着色しました。)
|
 T-60転輪。3/21 T-60転輪。3/21
現在製作中のT-60転輪です。
この様な画像は、形を把握し易いように大抵は加工(明暗を強調したり・・・)して張り付けるのですが、その過程で現物と違う印象になる場合があります。「本当はもっと良いのよ」と言いたくなる反面、意外と間違いを強調してくれる場合があるので侮れません。
例えば、この画像では、リム部分がハッキリしないし、ディッシュ部分がふっくらとした丸みのある形に見えます。けれど、現品はそんな事はないのでOKと思っています。一方、ゴム部分の幅が足りなかったり、ゴム部分にテーパーが付いて外周に行くほど薄くなる「タミヤの旧IV号戦車の転輪」的間違いがある事は、改めて現品を見直して画像どおりである事に気付きました。
いや〜。外径をそのままにゴム部分を増すとなると、リム部分はやり直しだな。そこが一番面倒なのに・・・。
|