大輪ヒマワリ咲く
1999年8月11日(水) ジェムフリエット大学
1999年8月11日(水) ジェムフリエット大学
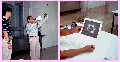 日食当日。始まりは午後なので、朝食後はツアーに同行している日栄先生による皆既日食の直前講習が行われました。
日食当日。始まりは午後なので、朝食後はツアーに同行している日栄先生による皆既日食の直前講習が行われました。
 観測地は大学の構内にあるサッカー場。
寮や食堂からはかなり離れているので、荷物があるときは結局バス移動することになります。
ただこのツアーの貸切で、他の人は入ってこないようになっているので、機材や荷物を置きっぱなしでも大丈夫なのが便利。
かなり広いので一人あたりの面積は十分です。
観測地は大学の構内にあるサッカー場。
寮や食堂からはかなり離れているので、荷物があるときは結局バス移動することになります。
ただこのツアーの貸切で、他の人は入ってこないようになっているので、機材や荷物を置きっぱなしでも大丈夫なのが便利。
かなり広いので一人あたりの面積は十分です。
フィールドは芝なので、地面からの照り返しがなく長時間いる場合は楽です。
芝の丈が長いので機材は安定しない危険もありますが、
それほど気にするほどではありません。
気になる人はフィールドの周りの砂利部分に機材を設置していました。
時折、なぜか日本の琴の音がスピーカーから流れてきます。
サービスのつもりなのでしょうか。
 私の撮影機材は、望遠鏡にカメラをつけて2台。風景用に対角魚眼レンズが1台。
2月のオーストラリアとほぼ同じ体制です。
時間の無駄は少しでも減らしたいので今回は風景用カメラにもワインダーが付きました。
私の撮影機材は、望遠鏡にカメラをつけて2台。風景用に対角魚眼レンズが1台。
2月のオーストラリアとほぼ同じ体制です。
時間の無駄は少しでも減らしたいので今回は風景用カメラにもワインダーが付きました。
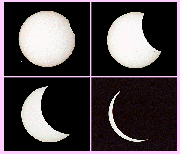 部分日食が始まりました。天気は快晴。このまま皆既日食が見られるのは確実です。
部分日食が始まりました。天気は快晴。このまま皆既日食が見られるのは確実です。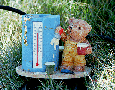 シヴァスのスーパーマーケットで買った寒暖計(Made in Chine)で気温測定。
日食開始時の気温は30℃を越えています。
シヴァスのスーパーマーケットで買った寒暖計(Made in Chine)で気温測定。
日食開始時の気温は30℃を越えています。
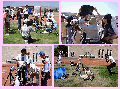 フィールド内の人たちは、欠けた太陽の形を思い思いのやり方楽しんでいます。
日食メガネを使って肉眼で見る人、双眼鏡の前に減光フィルターを置いて拡大して見ている人、部分日食撮影中のカメラのファインダーを覗く人。
フィールド内の人たちは、欠けた太陽の形を思い思いのやり方楽しんでいます。
日食メガネを使って肉眼で見る人、双眼鏡の前に減光フィルターを置いて拡大して見ている人、部分日食撮影中のカメラのファインダーを覗く人。
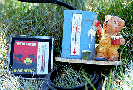 空が急激に暗くなりました。何度体験しても緊張する時です。
カウントダウンの声が大きく響いています。
空が急激に暗くなりました。何度体験しても緊張する時です。
カウントダウンの声が大きく響いています。まだ隠れきらないうちにコロナが見え始めました。 これまで体験した皆既日食よりも早いように感じます。 太陽が活動期のため、コロナが大きく広がっているためでしょうか。
わずかに残っていた太陽が隠される瞬間、縁に赤い彩層が輝き、
いよいよ皆既日食の始まりです。
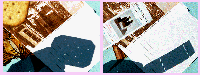 皆既が終わり、あちこちから拍手が湧き上がります。
皆既が終わり、あちこちから拍手が湧き上がります。
動作しなかったカメラを調べると、オートフォーカスのスイッチを入れたまま望遠鏡につけたため、シャッターが下りなかったことがわかりました。
今までは何気なく切り替えていたのに、チェック項目をまとめていなかったためのミス。
残った撮影は部分日食のピンホール。
毎回現地で使えそうな物を調達していて、今回はクラッカーと切手です。
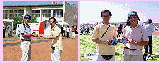 他の人たちの一部は残りの部分日食を撮影中ですが、大部分は片付け初めています。
他の人たちの一部は残りの部分日食を撮影中ですが、大部分は片付け初めています。
近畿日本ツーリストも終了モードになり、この旅行期間中に誕生日を迎える人へ
記念品を渡す恒例行事を始めていました。