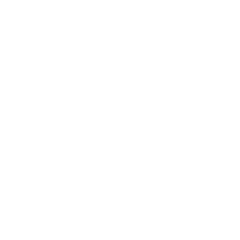三人が手を取り合い、喜びにむせび泣いたのは言うまでもありません。
しかし、香玉はまるで影のようで手応えがないのです。
「今の私はまだ花の幽霊なので、ふわふわしているのです。一年間肥料をくだされば元の花の妖精にもどれます」
ということでしたから、黄は毎日牡丹の芽にハイポネックスなどをそそいで丹精しておりました。
|
そして香玉のたのみで、絳雪が夜のお相手をして一年がたちました。
冬に家にもどるときは、道士にお金を贈って牡丹の手入れを頼んだものでした。
四月に戻ってみると、すでに牡丹のつぼみが大きくふくらんでいました。
見ているうちに花が開き、花の中に坐っていた手のひらにはいるほどの女が地上に降りると、それが香玉だったのでした。
その後、黄の妻が病気で亡くなると、黄は道観にこもったまま家にもどらなくなってしまいました。
そして、その頃には香玉の牡丹はもう人の腕ほどにも太くなっておりました。
黄はいつも牡丹をなでては
「私は、いずれ死んだら君たちの間に芽を出すつもりだ」と言い、
香玉たちも「忘れないでくださいね」と笑ったものでした。
|