今回は
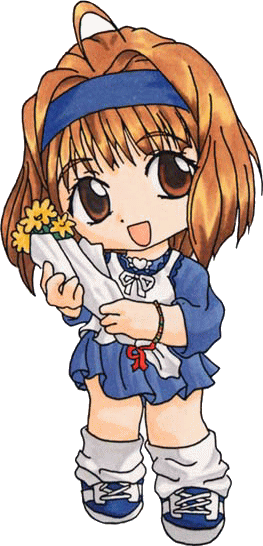 のお話だよ。見捨てないでね。お兄ちゃま。
のお話だよ。見捨てないでね。お兄ちゃま。平安兄氏絵巻
段の一 花乙女
今回は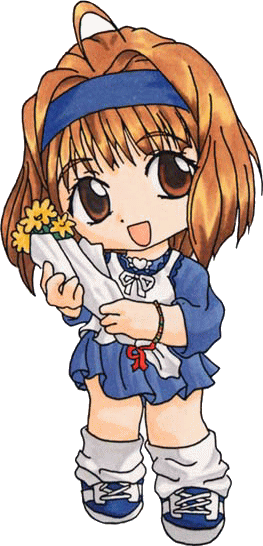 のお話だよ。見捨てないでね。お兄ちゃま。
のお話だよ。見捨てないでね。お兄ちゃま。
都の東、内裏から半里ほど離れた所にその乙女が暮らす庵がある。
「今日もお花を摘みましょ。綺麗なお花を。」
乙女は庵の脇に拵えた花畑で嬉しそうに花を摘んでいる。
明日は乙女にとって最も大切な人の来訪日である。昼餉を済ませた彼女は明日の来訪者の喜ぶ顔を思い浮かべながら着物の裾の汚れも気にせず、夢中になって花を選び、摘んで行く。
「兄氏ちゃま、喜ぶかなあ。」
楽しそうに花を摘む乙女の名は花の穂。時の天皇の娘である。その姿は周りに咲き誇る花達がまるで彼女の引き立て役にならんばかりに愛らしい。摘んでいる仕草はまるで花たちと会話をしているようにも見え、花の精がいるのであれば恐らく彼女を模して言うのであろう。畑の周りには2名ほどの衛兵が曲者に対して目を光らせているが、時折視線に入る彼女の姿に目を奪われ、職務を一瞬でも忘れさせるほどだ。
花の穂は花を名に冠しているためか、幼い時から花と触れ合うことが好きで、花の種類は勿論、育て方などにも精通し、花に関するあらゆる知識を身に付けていた。無論、今回摘んでいる花は、明日来る来訪者に捧げる物と、住まいに飾る物とに分けている。
一刻ほど時間が過ぎたろうか、あらかた作業を終えた花の穂は、摘んだ花を持参した花篭に収め、住まいである庵に帰ろうとした。
「今日もいっぱい摘んじゃった。あれ?」
見ると、摘んだ花の量は花篭に溢れんばかりになっており、花篭を抱えては両手が塞がってしまい、それ以上に摘んでしまっていたのに気がついて、残りの花達をどうするべきか悩み始めた。摘んでしまった以上、元の場所に植え直しても再び根付くことは難しく、詰まるところは早く庵に帰って、水鉢の中に入れないと花は枯れてしまうのである。彼女にとって素敵に咲き誇る花達を明日の来訪者である兄氏に差し上げ、兄氏の喜ぶ顔を見ることが最優先事項なのだ。
(どうしよう。お花、溢れちゃった。持って帰りたいけど、それじゃお花さん、潰れちゃう。ここに置いてっちゃったら、枯れちゃうし、でもでも、兄氏ちゃまにいっぱいいっぱいのお花、あげたいし。ふえ〜〜ん。どうしよう・・・)
花の穂は懐にしまってある花を包むための懐紙の事などすっかり頭の隅に追いやってしまい、考え込んでしまっていた。
(花の穂ちゃん、連れて行ってくれないの?)
「え?」
花の穂は誰かに話し掛けられたような気がして、思わずその声に反応していた。
(僕達、連れて行ってくれないの?)
「誰?」
周りを見ても衛兵が二人いるだけで、話し掛けて来る相手はいない。不安になって声の聞こえた方を伺う。そこには先ほど彼女に摘み取られ、花篭から溢れてしまった花達があった。
「あなた達なの?私にお話したの・・・」
(そうだよ。僕達さ。花の穂ちゃん。)
「え〜〜っ。」
花達が自分に話し掛けている。そうとしか思えないと悟った花の穂は驚いた表情で目をぱちくりしている。
やがて視線を集中すると、白い花が声の主であることが分かった。いたずら好きの少年のように聞こえる。
(びっくりした?)
「うん。花の穂、お花さんとお話、してるの?」
(ああ、そうさ。)
(私達はね、大切にしてくれる人には一生の内、一回だけその人とお話が出来る機会が神様から頂けるの。)
今度は今話をしていた花の隣にいる黄色い花からだった。優しいお姉さんのように聞こえる。
「ふうん。」
半信半疑だが、花の穂は次第に状況が掴めて来た様で、自分が好きな花達と会話をしている事が嬉しくなったのか、会話を楽しむ事に決め込んだようだ。
(花の穂ちゃん、私達を摘み上げる時、楽しそうな事を思いながら摘んでたでしょ?)
「うん。」
黄色い花の言葉は、自分の気持ちが分かっていてくれた事の嬉しさが半分、その思いが世界で一番想いを寄せる兄氏のためと気付かれちゃった恥ずかしさが半分で、ちょっぴり頬を赤らめながら花の穂に相槌を打たせた。
(私達はその思いを感じて、”私を摘んで”って花の穂ちゃんに思いを届けるの。そうして花の穂ちゃんは摘むの。)
「そうなんだ。花の穂、知らない内にお話してたんだね。」
(そうさ。でもちょっぴり今回は俺達が頑張り過ぎたようだな。)
黄色い花に代わって今度の声は白い花の下になっている紫色の花だ。張り切り過ぎたおじさんの様に聞こえる。
(俺達の気持ちが大きすぎちまったな。お嬢ちゃんを困らせちまった。まったく持って面目ない。)
少し寂しそうに呟く。花の穂は気持ちを察してか、同じように表情が辛くなる。
「ううん、花の穂こそごめんなさい。明日の事が楽しみでついはしゃいじゃって。」
(いいんだぜ、お嬢ちゃん。親切の押し売りをしちまったのはこっちなんだから、何も心配する事はないよ。そんな辛そうな顔しないでおくれ。)
「でも、でも・・・」
花の穂は今にも涙が溢れそうになる。その涙の量を加速させたのは落ち着き払った物腰のまるで祈祷師のようなおばさんのような声の緑色の花だった。
(私達はのう、この畑でお嬢ちゃんと出会い、育てられ、摘まれた。そして量らずも私達の想いがお嬢ちゃんのそれを上回った。これも必然から紡がれるさだめじゃ。摘み残されて朽ちるのもさだめ、ここに捨てられて朽ちるのも皆これさだめと言うものかのう。)
「そんな、そんなあ。」
花をいとおしむ花の穂にとって、せっかく摘んだ花達を捨てる事なんて出来ない、胸が締め付けられる思いだ。気がつくと日が傾きかけて夕方になってきている。心細くもなって、涙がぽろぽろと頬を伝う。本当なら庵に帰っておやつのお饅頭を口にしている頃でもあるのだ。
緑の花はふとある気配を感じたのか、諭すように、別れを惜しむように花の穂に語り続ける。
(じゃがのう、お嬢ちゃん、さだめと言ってものう、それは私達の世界での話じゃて、お嬢ちゃんの世界とはわけが違う。一つだけ言って置くがの、お嬢ちゃんの世界には偶然と言うさだめもあるようじゃ、もうすぐその偶然がお嬢ちゃんの前にやってくる。おっと、神様のお許しもここまでじゃ、ここらでお嬢ちゃんともお別れじゃ。それじゃの。)
「え、待って、どうしたらいいの?お花さん・・・」
緑色の花の声が途切れ、すべての花の声が聞こえなくなった途端、遂に花の穂は大きな声で泣き始めてしまった。
急に泣き始めた花の穂の様子に気付いた衛兵達もどうしたら良いものか、逡巡してしまう。庵に走り、事態を伝えるべきか、今すぐこの場で走り酔ってお声を掛けるべきかと。
「お花さん、お花さん・・・うわーん!」
そこへ彼方から(と言っても内裏の方からではあるが)小走りに花畑に駆けてくる紫の装束を纏った貴族が現れた。
「こら、お前たち、何をしておる。」
「あ、皇子様、姫君が急に泣き出しまして、如何したら良いかと・・・」
「相分かった。後は私に任せておれ、庵に下がってよいぞ。」
「はっ。」
皇子は俯いて泣きじゃくっている花の穂に近づきます。
「どうしたの?花の穂ちゃん。」
突然現れた兄氏皇子に花の穂はびっくり。
「兄氏ちゃま!あのね、あのね・・・」
「ほらほら、泣いてちゃ、せっかく摘んだお花に笑われちゃうぞ。」
そう言うと、袂に入れてある懐紙を取り出し、涙を拭う兄氏。まるで今までの様子が分かっていたような口振りに、花の穂は目を丸くします。兄氏が花の穂から事情を聞く頃にはすっかり泣き止み、改めて花の穂の周りの様子を兄氏は確認すると、胸元に懐紙の端が見て取れた。
「花の穂ちゃん、そこの懐にあるのは、何かな?」
花の穂は懐の懐紙を手に取ると、両手で広げて見せた。
「これはね、お花を包んでおく紙なの・・・あーっ!」
懐紙の事をすっかり失念していた花の穂はこれで包んで花篭に乗せれば持ち帰る事が出来ると気付き、思わず声を上げたのでした。
「ここにある花も持って行こうね。」
そう言うと、兄氏は花の穂が持っていた懐紙で花篭の脇にある今まで花の穂が会話をしていた花たちを包むと、その花束を花の穂に渡し、自分は花篭を方に背負いました。
「さ、帰ろうか。」
そう言って兄氏は優しい笑顔を花の穂に向けます。花の穂はその笑顔だけで元気に、そしていつもの笑顔に戻る事が出来るのでした。
「うん。」
花の穂は花束を抱え、嬉しい気持ちでいっぱいです。
ふと手にした花束を見ると、懐紙の中から見える花たちは心なしか嬉しそうな表情をしているように見えました。
「早く来いよ、置いて行きますよ。」
「あ!待って!兄氏ちゃま!」
そう言って兄氏の後を追い駆ける花の穂は、畦に躓いて尻餅をついてしまいます。花束は無事でしたが、その様子を大好きな兄氏に見られ、恥ずかしさで真っ赤になってしまいました。しかし、夕日のお陰で真っ赤な顔は気付かれなかったようです。
(これもまた、さだめじゃのう。)
緑色の花はぼやいたか否かは今の花の穂に聞こえたかどうか・・・
花摘みし 乙女の心 一筋に 愛しき兄の 笑みを夢見て
溢れし花の 想いくみせば
段の一 花乙女 終幕。