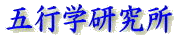
五行図による安田式四柱推命学(五行推命)に関する情報サイト
| 浅野内匠頭 (忠臣蔵) |
| ■浅野内匠頭ののの命式について 1667年09月28日(旧暦:寛文07年08月11日)生まれ |
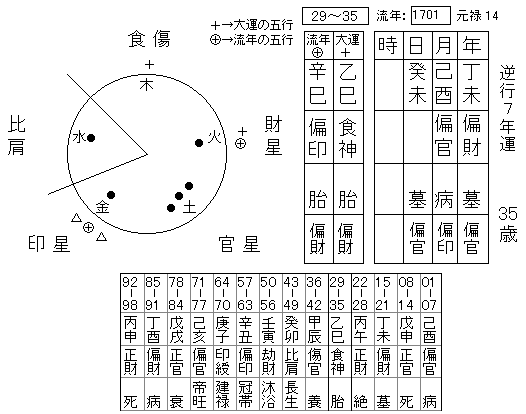 |
| 上図の浅野内匠頭の命式表を見ると分かるように、彼の命式の特徴の第一は中心星である月上が
「偏官」で、且つ五行図の「官星」の所に星が3つ(●●●)もあり、「官星太過」の様相を呈し、
大変バランスの悪い五行となっていることです。表の四柱月上「偏官」と裏の「五行官星太過」に
よって、元来荒れる星である「偏官」が大変に強くなっている上に、(三柱で見ると)偏官を和ら
げてくれるべき「食神」や「印星」があり
ません。また偏官と尅しあってバランスを取るべき比肩星も1つ(●)しかありません。
これは抑制されていない偏官であることを意味していますので、正に「七殺」と呼ぶべき暴れる偏官
となっています。そして、この「偏官」は自分(比肩)を尅する星なので「敵」「仇」を出現させ
る作用をしているのです。 第二の特徴は十二運の並びで、「二墓が病を挟差」していることです。これは年支と日 支の「墓神」が月支の「病」を挟んでいるということです。これは真ん中の星が悪く働く形、又は 真ん中の星が暴れることがあります。特に内匠頭の場合前述のように、自分(比肩)を尅する官星 に当たる五行が偏向していることと、この「二墓が病を挟差」していることによって、持病を抱え てこれが精神と身体のバランスを悪くし、更にはそれが自ら運を壊して行くことに繋がっています。 引いては早く「墓」に入ってしまうことになりかねません。生時に吉星がでて、三柱の凶意を和ら げてくれる星が出てくれれば、決して短命というわけではありません。 実際、内匠頭には心因性の神経症である「痞え」(つかえ)という持病がありました。痞えの発 作が起こると、長矩は顔の右側がひきつり、こめかみに青筋を立てて痙攣を繰り返し、次第に体の 全体をよじる発作を起こしたとのことです。 特に時柱は①生命線、②子孫運、③晩年運を意味する柱なので、寿命の長短を見る場合には大切 です。結果として内匠頭は、短命であったことと、子供がいなかったことを考え合わせると、彼には生時に よい星(印星・食神・財星)があったとは考えられません。今回は生時をあえて推定せずに命式を 解説していますが、実際の鑑定ではある程度生時を推定して鑑定することの方が多いものです。「 推時法」は古来より、頭の渦巻きや、寝る向き等で見る方法もありますが、これらの方法はあまり 当てになりません。私の場合には、その人の①性格や人柄、②運気、③子供の性別と数などによっ て推定しています。①~③に関する確りとした情報がないと正確で自信を持った生時の推定は難し いものです。今回は300年も前の人物に関することでもあり、後世の人の思い入れや小説化によ って実像が歪められていることもあり、その人物に関する情報の正確さに欠けるため、推時に も誤差が出てくる可能性がありますので、あえて三柱で命式の分析を試みています。 以上のことから浅野内匠頭の性格を読み取ってゆくと、正義感とプライドが高く、カッと来やす い性格であったことが分かります。性格の中核となる日の干支「癸未」の性情の中にも、気持ちが 変わりやすい所があるので、このような主君に仕える家臣たちは大変だっただろうと想像されます。 バランスの取れた大石内蔵助の命式に比べ、内匠頭の命式 はバランスが悪いので、人間関係についてもバランスが悪くなります。トラブルを起こしやすい四 柱です。武人の星である「偏官」が強いので、正に武将には相応しいかもしれません。武を好み、 墓が2つあり、しかも墓の1つは財星についていることから、質素と節約型で華美なものを嫌う傾 向があります。(ケチとも言えますが…)この点、 食神が主体性の星となっている吉良上野介とはだいぶん違います。 また逆に、商売の星である財と食神が弱い為に、利で動く より、義の為に動く人となります。「大義の為」となれば血が騒いで力も沸きますが、人間的な駆 け引きや、損か得かという考えを持つ事を潔しとしない性格で、そのようなことは考えただけで情 が冷めてしまうような人です。 官星と尅しあう「比肩星」の五行に星が多ければ、根を張ったような強さ、図太さが出て、多少 の困難も乗り越えて行ける、波風に強い四柱となるのですが、彼のように比肩が弱いのに官星ばか りが太過している場合、直ぐにプッツンと切れやすく、運気の根が弱い四柱となってしまいます。 外面は鼻っ柱が強い割りに、内面に気が小さい面のある人が多いものです。所謂「身弱」の形とな るものです。おまけに内匠頭の場合、前述の如く病弱という傾向から心身のバランスが崩れやすく、 そのことが更に情緒の不安定さをもたらします。もっと比肩星が強ければ、多少吉良上野介に苛め られたり嫌味を言われても、それを跳ね除ける強さがあったことでしょう。強い比肩としっかりと した印星があれば、喧嘩しながらも冷静な判断が出来ます。 ■行運について(松之廊下事件) 暴れる星「偏官」をやんわりと尅して抑えてくれるのが「食神」です。従って、本来浅野内匠頭 にとって29歳~35歳の大運:乙巳食神胎は裏も偏財ですから運気的には良い時期に当たってい ます。運気が良かったからこそそれまでの藩の運勢もよく、特に財を生む「食神」ですから財政的 に豊かとなりました。その故に幕府が財政的な負担が罹る勅旨饗応役(御馳走役)として、赤穂藩 を選んだ訳です。また、御馳走役という役職そのものが「食神」の象意を表わしています。 しかし、この成財と食禄を意味する「食神」を壊す星が「偏印」です。この「偏印」が「食神」 を壊す作用のことを「倒食」と呼んでいます。将に「松之廊下事件」が起きた元禄14年は、流年 が壬午偏印胎となって、流年が大運を倒食して、折角の食神を壊してしまっています。それまで、 暴れる偏官を抑えて、財を生み出す作用をしていた食神のよい働きが、偏印によって尅されて停止 してしまいます。それによって、偏官が暴れ出してしまいました。 また、前述のように食神の象意によって、幕府から「勅旨饗応役(御馳走役)」を仰せつかった 訳ですが、これが「倒食」することによって、却って仇となってしまいました。 偏官が暴れ出すことによって、①性格的にカッカきて切れやすくなり、②運気の乱れと共に体調 が崩れやすくそのことが①に拍車をかけ、③前述のように偏官は「敵」「仇」を意味するので、自 分を苛める存在(吉良)が眼前に現れるようになります。偏官 によって自分(比肩)が尅されて運 が乱れるたからだけではなく、「偏印」そのものも病気をもたらす作用がある為に、元禄14年は 現代風に言えば、心身症状態となっていたのではないか、そして「痞え」の病も発症していたとも 考えられます。 更に、35歳となるこの年は、この大運の最後に当たります。よく「大運の最後っぺ」と表現し ているのですが、一定期間の大運の中で区切りとなる最後は、良きにつけ悪しきにつけこの期間の 清算の時となり、いろいろな現象が起こりやすい時でもあります。 運命の年元禄14年は、3月と4月が壬癸の月となるので、流月が劫財・比肩となり最悪の月と なっています。特に3月の劫財は宝である「財星」を尅して破ってしまいます。宝とは「財」「生命」 「愛する者」等を意味していますので、それらを失うことを意味しています。流年の「偏印」から 生じられて、更に劫財が強く働いてしまします。ただ、大運の食神とは劫達(劫財特達)の関係とな りますので、チャンスとピンチが同時に来るとも言えるでしょう。(勿論凶意の方が強いですが) そして、運命の「松之廊下事件」の日ですが、元禄14年3月14日(西暦4月21日) は「辛丑偏印冠帯(羊刃)」の日でした。前述のようにこの年の凶事は偏印が倒食を起こして、偏官 を暴れさせたことにある訳ですが、この日もやはり偏印の日でした。又この日の十二支である「 丑」が良くありませんでした。それは羊刃の「丑」が四柱本体の日支と年支の飛刃の「未」を冲尅 することによって、「墓庫が開く」こと。これは「石の冠を被る」として、墓に入るとの暗示があ ります。更に本体の「酉」と大運・流年に重なった「巳」と相まって巳酉丑の「完全金局▲」を 形成することです。この金▲(印星)は倒食性を強めますし、又その日の天干「辛(陰金)」=刀と相まって 「刃物沙汰」を意味するようになるからです。更には流月の劫財を生じて劫財の力をも強める働きをしてしま います。 刃傷に及んだのは巳の刻で時間の干支は「癸巳」。「比肩胎」となります。この日、辰刻巳尅は 劫財・比肩となり、この日では一番良くない時間帯であったのです。これらの「偏官七殺」を中心 とする凶星達の働きによって、彼に「狂気」がついてしまったとも言えるでしょう。 実際、勅旨饗応 を仰せつかってから、当日までの準備の段階で様々な問題がありました。(そのあたりの事情は長く なるので割愛しますが)その時から、彼のプライドに多少なりとも傷がついていた事と、裏で正室の 阿久利が吉良家を極秘に訪問して、良かれと思い働きかけたことに、猜疑心をもっていたことが事件 の底流にありました。そして、運気の乱調から「痞え」の持病が悪化し、その為に心身が不安定 となっていた中で、ちょっとした吉良の言葉や態度から「疑心暗鬼」が生じてしまったのです。この 「疑心暗鬼」で魔が差し、カーッと血が昇って、思わず刀を振り上げてしまったのでした。所謂、内匠 頭の一人相撲であった訳です。「疑心暗鬼」と「血気」に走らせたのが、上述のような偏官を中心と した凶星による命理の働きであったと言えます。 この時、大石内蔵助のようなバランスが取れ、且つ腹の据わった四柱の人物が、主 君である内匠頭をサポートしていたら、このような事件は防げたかも知れません。更に言えば、彼 の持病である「痞え」が悪化していたのでしたら、これを理由としてお役目を辞退していれば、こ のような事態は避けえたかも知れません。実際、この年の2月4日(西暦3月13日)に、内匠頭 は江戸城に登城し、老中・秋元但馬守から正式に御馳走役を命じられています。この日は流月「辛 卯偏印長生(食神)」、流日「壬戌劫財衰(正官)」の日で、倒食が強まる月であり、宝を奪われ る劫財の日です。これを見ても、この役目は非常に危険を孕んでいることが分かりますので、前述 のように、役を辞退するか、賢い家臣のサポートが必要でした。歴史に”if”はありませんが、もし大石内蔵助のよ うな人物が国元の城代家老ではなく、江戸家老であれば…と思わずにはいられません。 |