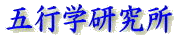
五行図による安田式四柱推命学(五行推命)に関する情報サイト
| 大石内蔵助 (忠臣蔵) |
| ■大石内蔵助の命式について 1659年3月8日(旧暦:万治02年01月15日)生まれ |
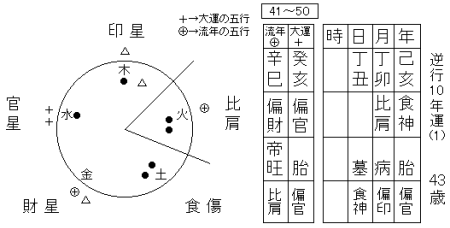 |
|
上図のように大石内蔵助の命式は表の並びが「比肩・食神」となっています。
そして五行も安定しています。この四柱は比肩の持っている個性の強さと、食神の持っている優し
さが同居する四柱で、中心星となっている月柱比肩を包容力を持つ食神がサポートしていますので、
親分肌的な所があります。
東海一の親分と言われた清水次郎長も同じ「月上比肩・年上食神」でした。清水次郎長の場合には
生時に正官沐浴になっていますので、官殺混雑的ですが、内蔵助が城代家老という要職を得ている
ことを考えると、彼にも生時に官星が出ているかも知れません。 生時にもよりますが三柱で見る限り、食神があって五行が安定していることから基本的には平和 主義者で、平時は昼行灯でも、比肩星が中心星になっていますので、いざ鎌倉という時には強い力 を発揮します。大運によっても人の性格は影響を受けるものです。内蔵助の場合、21歳〜40歳 まで印星が休囚していますので、余り評価されなかったはずですし、また評価されるような仕事も なかったと思われます。この期間は昼行灯と言われても仕方が無い時期でした。 彼が兵法学び、この困難を乗り越えて討ち入りという大業を成し遂げることが出来たのも、「比 肩」の力に負うところが大きいものです。また一面「食神」もあるので、人生を楽しみたいという 嗜好的な部分も同時に持ち合わせていたと言えるでしょう。京都山科に移り住んだ折に伏見で茶屋 遊びをしたというのは、ただ単に幕府の目を欺く為だけではなく、人生の最後に楽しんでおきたか ったし、そこで英気を養っておこうとしたのではないかと思われます。特に松之廊下事件があった 元禄14年は内蔵助にとっては、辛巳偏財帝旺で、偏財は「遊び」「妾(色情)」という意味もあ りますので、まだ討ち入りに向けて決断し行動に移す時期ではなかったのです。 この命式と五行を総合して見ると、見かけは温厚そうで控え目ですが、決して媚びへつ らいはなく、遊びと仕事を両立させ、肩の力を抜いて肝は据わっているという感じの人物です。浅野内匠頭の四柱などと比べると、酸いも甘いも嗅ぎ分けた大人の男という感じです。そして、決し て急進的ではないが、いざ鎌倉という時には立ち上がることのできる、力強さを内に秘めている命 式です。その力が爆発するのは、次項で述べる大運に大義に生きる「偏官」が出てからのこととな ります。 |
| ■行運について(松之廊下→吉良邸討入) |
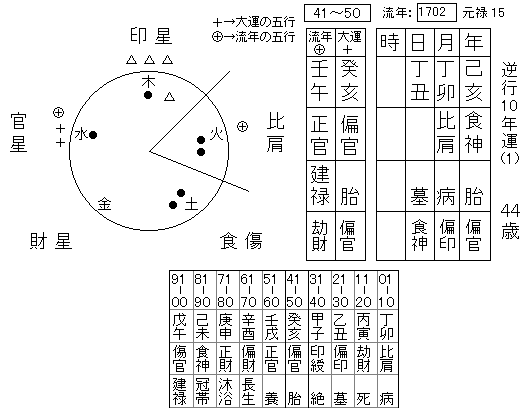 |
|
命式にもよりますが大運が「偏官」の時期は、その人の人生の転機を意味しています。前述のよ
うに40歳迄の20年間は「印星」が休囚していましたので、大したこともなく過ぎて来ました。
しかし、波乱の星偏官が現れたとたんに、風雲急を告げたのです。勿論その時の主君の運勢も関係
してきますが、まさに元禄14年は主君・浅野内匠頭が凶運となる時でもあったのです。 この「偏官」は十二運が「胎」となっていますので、一見弱そうですが、「癸亥」の偏官で専旺 干支となり、天干地支の上下が同一五行の水(偏官)ですので、強い力を持っています。更に四柱 年支の亥と大運の亥とで「自刑」となって、「突っ走って失敗」したり「刑傷刑罰」という意味が を含んだ偏官となってしまいます。 「松之廊下事件」が起きた元禄14年の流年は「辛巳偏財帝旺」となっています。初心者が見る と偏財が旺相して一見いいようにも見えますが、それは逆で、比肩的働きをする帝旺が偏財を尅し てしまいます。このことは自分にとっても大きな損失を意味すると同時に、偏財は父を意味し、こ の時代では主君をも意味しますので、主君に関係するトラブルにつながりました。主君・浅野内匠 頭が松之廊下で刃傷沙汰を起こして、即日切腹をしたその日(旧暦3月14日)の流日もまた、「 辛丑偏財墓」となっていて、主君を意味する「偏財」が墓に入っています。更に言えば、強い偏財 は偏官を生じ、強めてしまっています。 更に大運支の亥と流年支で駅馬に当たっている巳が冲尅することによって更にこの一年は荒れる 年となってしまいます。本来、大石内蔵助には四柱本体に偏官を抑制する「食神」がありますが、 このような凶条件が折り重なったために、それを抑えることが出来ません。このような偏官を中心 とする凶作用によって、主君の刃傷沙汰から切腹、そして御家断絶、俸禄を失うという、大石内蔵 助にとって、波乱の一年となってしまいました。 内匠頭切腹の後、赤穂藩の改易が決まり、内蔵助が城代家老として全てを取り仕切って、赤穂城 を開城したその日(旧暦4月19日)は、流月:癸巳偏官帝旺、流日:丙子劫財絶となり、偏官の 月で大忙しの月ではありましたが、再び財を尅する「帝旺」が重なっています。そして開城の為に 幕府の使者を迎えた日は、苦難への旅立ちの日でもあり、内蔵助にとって全てを失う「劫財」の日 でありました。その日の十二運を見れば、古いものに決別し新しいものを出発すべき「絶神」の日 となっています。 赤穂落城後、すぐにでも決起すべきであるとう急進派もありましたが、赤穂浪士を束ねるべき内 蔵助自身が偏財の流年では、まだその時ではありませんでした。勿論、内蔵助は最後まで浅野家再 興の悲願を胸に幕府に嘆願していた訳ですが、四柱推命的に見れば行動を起こすのは、翌年の官星 の時まで、期が熟していなかったと言えるでしょう。偏財は遊びや妾(色情)という意味もありま すので、元来命式に「食神」のある内蔵助が、この世の名残に京都伏見で茶屋遊びをしたとしても 無理からぬことです。後世、京都での遊興は幕府の目を欺く為であったとされていますが、前述の ように食神がある内蔵助ですから、それだけではなかったのではないかと思われます。 明けて元禄15年、内蔵助の流年が決断と行動、そして義に生きることを意味する「壬午正官建 禄」となったことから、いよいよ決起の時がやってきました。特に大運と流年に官星が重なり、官 が殺化して、正官も偏官的働きをします。五行図を見ても分かるように、大運と流年で星が3つ(癸亥壬) 増えていますので(水の所・円の外)、内蔵助の四柱本体にある食神だけでは抑えることは出来ま せん。義挙すべき時が来ました。 しかし、吉良上野介の流年が我を助ける 星である「印綬長生」となったことによって、仇である上野介の方に 護りと援助の星が出てしまい、内蔵助達は討ち入りの機を得ることができず、本来主 君・内匠頭の一周忌である三月に予定してい た討ち入りも延び延びとなって、遂に年末となってしまいます。詳しくは吉良上野介のページで述 べていますが、食神が中心星となっている上野介に偏印が出るて「倒食」し、魔が入りやすく運気 のエアポケット状態に入った12月(新暦では1月)を待たなければならなかったのです。 討ち入りの月は流月:癸丑偏官墓。やはり決行の月は偏官七殺でした。しかも墓が出ていますの で弔い合戦にはピッタリかも知れません。 また、地位名誉を表わす「正官」が「建禄」しているこの年に起こした義挙ですので、後世 まで名を残すことになりますが、前述のように大運と流年で官星が重なり、偏官が更に殺化してい ますので、切腹は免れないところです。 |