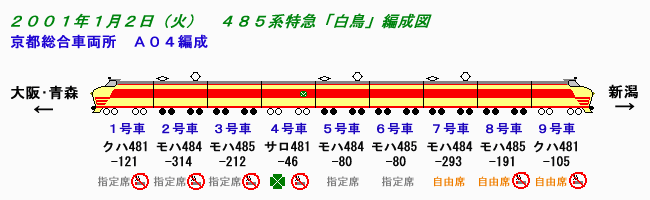 |
試 乗 記 録 (特別編) 21世紀「大乗り鉄ツアー」
取材期間 2000年12月31日(日)〜2001年1月4日(木)
Pege 4 2日目(その2)
さて金沢平野を突っ切って走った白鳥は、12:57分金沢に到着した。 ここまでの区間が、3月改正による「白
鳥」系統分離以後、大阪〜金沢間の特急「雷鳥」として走る区間である。 確かに、乗客の半数以上が一気に入れ
替わり、急に車内の雰囲気が変わってしまった。 やはり「系統分離がなされる駅であるな?」と、思わずにいられ
ない変化であった。 私の隣りの席に座っていた乗客もここで下車し、変わって新しい乗客が乗車してきた。 乗客
は小学生位の男の子だった。 やはり少し離れた席に、母親と他の兄弟が座っていた。 また車内販売の担当も
入れ替わっていた。
|
さてこの先は3月以後、金沢〜新潟間の特急「北越」として走る区間である。 今度は上越新幹線接続客を乗せ、
北陸新幹線対応の立派な高架駅の金沢を、北に向かい走り出していた。 余談だが、現状2往復の特急「北越」だ
が、3月改正以後は「白鳥」1往復および、新潟行「雷鳥」の系統分離による2往復を合せて、一気に5往復体制と
なる。 また「白鳥」及び、新潟「雷鳥」の系統分離により、大阪〜新潟間の直通昼行列車は全廃される事となる。
今度は、能登半島の付け根にあたる倶利伽羅峠(くりからとうげ)にさしかかった。 この倶利伽羅峠を越えると、
富山県内に足を進める事になる。 さてこの辺で、車内に余裕が出てきたので、車内を一巡してみる事にする。
今日の「白鳥」に使われている編成は、JR西日本京都総合車両所(京キト)所属の485系電車で、両端にボンネッ
ト先頭車を配したA04編成である。 編成は全区間9両編成で、途中4号車がグリーン車である。 車内はあちこち
手直しが入っているものの、伝統的な「国鉄特急電車」の風格を、今でも垣間見る事が出来る。 なお私は、6号車
になるモハ485−80に乗車しているが、キノコ型クーラーを装備した初期量産車の為、天井を見上げると特徴的
な冷風噴出し口が目に入ってくる。
一方乗車率は、金沢以南に比べ幾分減ったものの、まだまだ80〜90%程の乗車率の様である。 客層はやは
り正月三賀日でも、民族大移動の時期に差し掛かっている為、帰省・行楽客と思われる乗客が多くを占め、ビジネ
ス利用の乗客は殆ど居なかった様である。 また、乗車を楽しむ鉄道ファンも少数であるが見受けられた。 また、
この時点でもグリーン車は満席で、比較的長距離利用者が利用されている様であった。
県境の倶利伽羅峠を越えると、富山県内最初の停車駅である高岡に到着した。 余談だがこの高岡駅前から
は、現在第三セクター化の話も出ている、加越能鉄道の路面電車が出ている。 さて高岡の次は、富山県の県庁
所在地の富山である。 富山県内は、福井・石川県内通過時に降っていた冬の雨が止み、どんよりとした厚い雲に
覆われていた。 そんな富山平野を進む事しばし、やがて神通川を渡ると富山駅に到着した。 時刻は13:35分で
ある。 ここ富山では、富山名物の「ますの寿し」が搭載されたが、途中駅で降ろす在庫なのか「ますの寿し」と書か
れた団ボール箱も、一緒に搭載されていた。 よく見ると「糸魚川止め」とマジックで書かれていた。
  |
(左) 富山駅に到着 (右) 曇り空の富山平野 |
この「ますの寿し」は富山駅の駅弁であるが、北陸地区の多くの駅や列車車内、挙句の果てには大糸線沿線(長
野県内)でも販売されている結構メジャーな駅弁である。 去年2月、最後の165系による運転となった急行「ちく
ま」に乗車した際も、松本から併結運転となる急行「くろよん」側の編成では、この弁当が沢山食されていた事を、
ふと思い出した。 さて今回は「ますの寿し」を、「白鳥」車内で食べてみる事にしよう。 丁度富山を発車した頃に、
車販のワゴンがやってきたので、早速注文してみた。 疾走する北陸特急の車中で、この弁当を食すのが一つの
憧れだったので、やはり充実感があった。 さて「ますの寿し」が空になる頃には、次の停車駅の魚津に到着してい
た。 魚津でも短区間利用者が若干降りていった。
この魚津を出ると次は、新潟県下の糸魚川である。 この糸魚川までの間には、親不知という北陸路の難所が控
えている。 ここは丁度、飛騨山地が直接海に沈んでいる場所であり、敦賀〜今庄間の木の芽峠や、津幡〜高岡
間の親不知などと並ぶ、北陸本線の難所である。 鉄道開通以前のいにしえの時代には、余りの道の険しさに、
「親は子を忘れ、子は親を忘れる」という言い伝えがあり、それが現在の「親不知」の地名につながっていると言う。
鉄道や国道が通じた現在も、険しい道には変わりなく、国道8号線沿線は今でも落石防止の洞門が延々と続いて
いる。
  |
(左) 魚津駅の駅名板 (右) 狭い海岸沿いに 鉄道・国道・高速道路 がひしめき合う |
現在でこそ長大トンネルを介して、あっと言う間に過ぎる親不知も、複線電化以前は海岸沿いの急斜面に沿った
旧線を通っていた。 現在に比べ海岸に近いところを走っていたので、車窓は楽しかったであろうが、危険な「地す
べり地帯」を走るなど、輸送力の確保には大きな問題があった様である。 なお、旧線の一部は現在でも自転車道
として利用されており、往時の面影を垣間見る事が出来る。
入善あたりまでは、比較的平坦地を走っていた北陸本線も、新潟県との県境が近づくにつれ、山と海の間隔が段
々狭くなり、やがてトンネル主体の新線区間に入っていた。 長大トンネルの暗闇は長く、床下のMT54モーターの
唸りも、非常に悲壮感が漂うものであった。 さて、このトンネル区間で新潟県内に突入した「白鳥」は、新潟県内最
初の停車駅である糸魚川に近づいてきた。 静岡〜糸魚川構造線が生み出した谷間を流れる姫川を渡ると、いよ
いよ糸魚川に到着である。
さて、この糸魚川と1つ先の梶屋敷駅の間に、「白鳥」の旅で2つ目のデットセクションが存在する。 これは日本
海縦貫線沿線で唯一、新潟県内が一足先に直流方式で電化されている為であり、複雑な過程を経て電化・近代化
されてきた日本海縦貫線の歴史を、垣間見る部分でもある。 なお、関東・関西の直流電化区間に挟まれた北陸
地区を直流方式に変更し、車両・運用上の効率を上げようという話も時折出るが、北陸新幹線延伸が具体化した
現状では、到底実現しそうのない話の様だ。 その2つ目のデットセクションを通過すると、次の停車駅である直江
津まで、またまたトンネル区間を走る事となる。
ダイヤ上は、この先の能生〜名立間にある頸城トンネル内の筒石駅付近で、上下の「白鳥」がすれ違う事となる
のだが、今日は上下列車ともほぼ定時での運行の様で、例外もなくトンネルの中で上下の「白鳥」が離合した。
逆に言うと、どちらかの列車のダイヤが乱れない限り、日の当たる場所での上下「白鳥」の離合は見れないという
事にもなる。 確かに上下「白鳥」がすれ違う写真は、あまり見た事がない。
そんな離合劇の後も列車は進み、やがて直江津に列車は到着していた。 構内には新潟色・長野色の115系電
車の姿があり、ここで初めて直流電化区間に入った事を実感する訳である。 この直江津からは、JR東日本エリア
になる為、運転士の交替があった他、車内販売員の交替もあった。
  |
(左) 車内で買った 「ますの寿し」 (右) 糸魚川〜梶屋敷間 のデットセクションを 通過! |
直江津から次の停車駅の柏崎までは、海岸沿いに北上するのだが、途中の米山付近までは線路と海岸の間に
松林が広がる為、中々海が姿を見せない・・・。 いよいよ米山付近からは、冬の日本海を車窓に見ながらの旅とな
る。 なお、冬の時期の青森行き「白鳥」では、この付近と富山県内の魚津〜入善付近しか、日の当たる時間に日
本海を眺める事が出来ない。 夏ならば新潟・山形県境の笹川流れ付近でも、車窓に日本海が広がるのだが、こ
の時期では到底叶わない。
さて今日の日本海はかなり波も高く、冬らしい風景であった。 夏ならば、対岸の佐渡ヶ島に沈む夕日が見える
「福浦八景」と呼ばれるこの辺りも、全く人気のない海をしていた。 また、残り少ない「白鳥」の運転をフィルムに収
める為、鉄道ファンが駆け付けていると思われたが、名所と言われるこの区間でも、その姿も確認できなかった。
まあ強風吹き荒れる最悪の天候下なので、当然といえば当然であろう。
さて次の柏崎からは打って変わった様に、新潟県第2の都市である長岡に向けて、一路内陸部を走る事になる。
途中に介在する塚山峠に近付くにつれ、車窓は段々雪景色をして来るようになった。 しかし代わりに、風が穏や
かになった様なので、沿線で撮影に興じるファンの姿が多くなった。
ところで長岡に向けて、快調に峠を越えていくと思われた白鳥であるが、急にスローダウンし、やがて停車してし
まった。 車内放送では「踏み切り故障による安全確認の為、一旦停車しています・・・。」 とあった。 この停車は
短時間で、すぐに発車したのだが、それ以後も余りスピードを出さずにゆっくりと塚山峠を越え、長岡へと近付いて
いった。 車内では直江津から交替した新潟の車内販売員が、弁当の販売に明け暮れており、お土産も新潟名産
の笹団子などが、見られる様になっていた。 私はこの区間で、車販を利用しなかったのだが、後々これが元で、
ちょっと「冷や冷や」する事になるとは、考えもしなかった。
  |
(左) 長岡に到着 新幹線乗換客が 多数下車した (右) 雪化粧の新潟平野 を北へ急ぐ・・・ |
来迎寺〜前川間に流れる信濃川を渡ると、間もなく上越線の高架(下り線)が近づき、やがて宮内駅を通過して
いた。 さてここまで来ると長岡は目の前である。 なお、距離にするとこの辺で、大阪〜青森間の半分を走破した
事になる。 この長岡では、北陸方面からの新幹線乗り継ぎ客が一気に降り、急に車内が寂しくなってしまった。
金沢から乗った少年もここから乗換えの様で、母親につられて下車していった。 なおこの先終着青森まで、私の
隣りの座席には、誰一人とて座る者はいなかった・・・。 なお長岡の時点で、定刻15:38分のところ、約4〜5分遅
れの発車となった。
ここからは、夕暮れが迫る越後平野を疾走していく訳である。 越後平野は先日降った雪がまだ残り、すっかり雪
景色であった。 長岡で新幹線乗換え客が降りた為、車内は非常に閑散としており、もう既にローカル特急全として
いた。 長岡〜新潟間の短距離利用客も居るかと思えるが、実際のところ新潟〜長岡間の都市間移動は、新幹線
か高速バスによるのが関の山で、わざわざ在来線特急に乗る人はそんなにいない様である。
夕暮れの越後平野を見ながら東三条・新津と停車していくと、次はいよいよ新潟である。 新津からは意外と住宅
街の多い沿線を走り、やがて上沼垂運輸区の横を過ぎ、白新線・上越新幹線回送線が近づいてくると新潟駅はあ
と一息といったところである。 さてここから青森までは、方向転換して旅を続ける事になるのだが、新潟到着直前
の放送で座席転換の案内が有った為、車内のあちこちで、座席転換が行われていた。 結局新潟には、長岡での
遅れを引きづったまま、定刻より約5分遅れての到着であった。
  |
(左) 新潟まであと少し・・・ シートの回転風景 (右) 新潟到着 |
新潟駅1番線に到着した「白鳥」は、休む暇もなく乗務員の交代・編成のエンド交換が行われていた。 またホー
ムからは新幹線接続客が、大挙して「白鳥」に乗り込んできた。 通常では7分程新潟に停車するのだが、今日は
列車遅れの為、車内販売員の交替・搭載が済むと、全く余韻もないままに新潟駅を後にしていた。