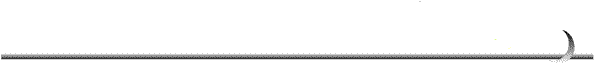百年の孤独 1
その瞬間、頭の中が真っ白になったような気がした。
目の前で何かが炸裂し、閃光が瞬いた。
耳朶にかかる、憎悪にくぐもった息遣いが激しい眩暈を促す。
振り返ったすぐ傍を狂気で歪んだ顔が覗き、そこには引き攣った薄笑いがあった。
全ての力が足許から吸い取られていき、身体の奥から痛みが叫び声をあげた。
真っ赤な血糊は、左手から噴き出していたものなのか、そうでないのか。
靄がかかったような視界の隅で、奇妙にゆらめくものがある。
遠退いていく意識の中で掴みかけた名前が誰のものだったか、遂に思い出せなかった。「気がついたか」
目を開けると、病院のベッドの上だった。
司馬江太郎は頭を捩って声の主を捜した。途端に激痛が全身に走る。微かな記憶の糸を手繰り寄せ、平賀友一に刺された自分が冷たいアスファルト上へと倒れ込む寸前に掴んだ、大きな手の存在を思い出した。
「ああ、動くな。君は丸一日、眠ってたんだ。麻酔が切れてる筈だから、痛いだろう。私がそっちに行く」
不思議な声音の持ち主だと思った。高くもなく低くもなく、それでいて一度聞いたら忘れられないような声だった。枕元にその気配を感じて、視線を合わせた男はひどく優しい顔で、司馬を見守っていた。
「あなたが、僕を助けてくれた・・・のか・・・?」
喉の奥が極限まで乾燥しているのが、声の掠れ具合で判った。男は黙って頷き、憔悴している司馬を静かに見つめている。暫しの沈黙が病室内の時間の流れを凍てつかせたようだった。
「左腎及び左総腸骨脈損傷―――傷はかなり深かったようだが、全治三ヶ月だそうだ。君を刺した男は警察に引き渡された」
淡々と一定のリズムを刻む口調に職業的なものを感じつつも、何故か気持ちが落ち着かせられた。軽く目を瞑り、今ひとたびゆっくりと瞬いてから、司馬は自分を見下ろしている男をしげしげと見つめた。
体格の良さだけでなく武道で鍛えられた筋肉が、隙のないスーツ姿からも感じられた。年齢は35、6位か。撫でつけられた髪はそれでも無造作な雰囲気を感じさせ、怪我人を前にして幾分穏やかな表情を見せているものの、通常ならその視線は鷹のように鋭く、高圧的な態度で相手をねじ伏せることもあるのだろうと容易に察せられた。
だが、司馬にはまだこの男が何者なのか、何故自分が助かったのか解らないままだった。はっきりしているのは、今自分がいるのはつい先日まで勤務していた天真楼病院ではないということだけだった。
「ここは、飯田橋の警察病院だ。君の容態が落ち着き次第、事情聴取したいと、原宿東署から申し入れがあった」
まるで自分の心を見透かすかのように告げられて、司馬は目を見開いた。その様子に見知らぬ男は口の端だけを少し引上げて、小さく笑った。
「そう、目を剥くな。今日と明日は面会謝絶にするよう、病院側に頼んである。まあ、刺された経緯に関しては既に被疑者から供述をとったらしいから、その裏付けが必要なんだろう。金絡みだけでなく、相当怨まれてたらしいな―――その若さで人を陥れるような事をするもんじゃない」
司馬の体内を戦慄が駆け巡った。何故、自分と平賀の関係をこの男が知っているのか、いいしれぬ恐怖を感じた。既に辞めた天真楼病院でどのような陰口を叩かれようが気にするつもりは無いが、幾ら自分を助けてくれたとはいえ、得体の知れぬ男から己の身辺についてこうも言い当てられるのは、不愉快を通りこして不気味なだけだった。心の内壁を冷や汗が伝うようなイヤな感触が、両の掌にじっとりとした湿り気を催させ、背筋に力を込めさせた。
司馬の瞳にあきらかな疑惑と警戒の色が浮かんだのを見てとった男は、宥めるように声色を和らげた。
「おっと、まだ起き上がるな。君は重態なんだぞ」
「・・・何で―――アンタ、一体・・・誰だ・・・?」
「ああ、そうか。まだ名乗っていなかったな・・・これは、失礼した」
男はゆるりと立ち上がった。司馬はその動きに合わせて視線を這わせ、背格好が想像していた通りであることを確認した。緩慢な仕種で胸の内ポケットから名刺を取り出し、身体を横たえたままの状態でも見えるようにと、それを顔の近くに翳し見せた男は、司馬の心に沁みいるようなあの声で正体を明かした。
「私は、警察庁警備局の一倉だ。舗道脇の街路樹の根元で蹲っていた君と、血まみれのナイフを握り締めて尻餅をついていた男とがいたところを丁度、通りかかった」
ああ、それで・・・と、漸く司馬は安堵した。警察の人間なら、自分が刺されるに至ったいざこざに関して調べ上げ、仔細に通じているのは当然である。目前の男の所属を知った途端、全身に漲らせていた緊張を解いた司馬を一倉は眩しいものでも見るかのように眇めた。
「君を刺した男はひどくうろたえていた―――駆けつけた警官に、大人しく身柄を拘束されたよ。まあ、通報した責任もあるんで、事情聴取には私も立ち会った。それで、大体の話を聞かせてもらった訳だ」
司馬は黙ったまま、一倉の方に顔だけを向き直らせた。相手を射すくめるようなその鋭い視線の底に、脆く危ういものを感じて、一倉は司馬の顔から目を逸らせなくなった。
暫しの沈黙を経て、司馬は低く呟いただけだった。
「―――そう、ですか・・・」
「明後日には、所轄の―――原宿東署の人間が、話を聞きに来るだろう。それまで、少し養生しとくんだな。君の事情聴取の折には、また顔を出させてもらうことになる」
一倉の言葉に司馬が胡散臭そうな表情を見せた。しかし、一倉はそれ以上何も言わず、入り口の近くのパイプチェアに投げ出してあったアタッシュケースを持ち上げ、苛まれる痛みに顔を顰めた司馬に一瞥をくれた後、病室を出ていった。
一人、ベッドに残された司馬は、枕元に置かれた名刺を横目で睨んだ。
警察庁警備局外事課外事調査官、警視正、一倉正和―――
具体的にはどういう職務を担当しているのか、門外漢の司馬にはさっぱり見当がつかなかった。だが、ほんの数分間同じ室内にいただけにも拘わらず、かの男がただの警官ではなく、エリートと呼ばれる人種であることを司馬の鋭い嗅覚は本能的に察知していた。
(俗にいう、『キャリア』ってやつ、か・・・)
各都道府県毎に採用される地方公務員ではなく、国家公務員採用はその名も『キャリア組』と呼ばれ、階級や出世のスピードなど、ありとあらゆる面で優遇されていることは、司馬も朧気ながら知っていた。初対面の、それもベッドから動けない人間を前にして、不必要な警戒心を起こさせないようにと一応心を砕いてはいたようだが、醸し出される雰囲気は一寸の隙も無い存在感を知らしめ、どう見ても三十代にしか見えなかったその外見が若いエリートであることの裏付けとしては充分すぎるくらいだった。
しかし、瀕死の自分を助け、恐らく呆然自失だったであろう平賀を取り押さえて通報したとはいえ、明後日の事情聴取が一倉立ち会いのもとで行われるということに、司馬は微かな違和感を感じた。
さっき、一倉は原宿東署の人間が話を聞きに来る、と言って帰っていった。つい先日まで勤務していた天真楼病院も自分が刺された路上も、原宿東署の管轄であることは司馬も知っていた。だから、其処の警官が事情聴取にやって来るというのには納得できるのだが―――警察庁という、全国の警察組織を束ねるトップクラスの、しかも警視正だとか調査官だとか如何にも多忙そうな肩書きを持つあの男が、一応被害者である自分から参考として聴取されるだけの供述の立ち会いにわざわざ出向いてくるというのは、何かそぐわない気がするのだった。
尤も、警察には警察の内部事情があるのだろうし、原宿東署に拘留されている平賀が今現在どういうことになっているのか知らされていない司馬が、これ以上いくら考えを巡らしても得心のいくような解答を得られる筈もないのだが・・・
司馬は絡まり出した思索の糸を断ちきるかのように目を閉じると、己の思考を現状認識へと引き戻した。
(これから、どうなる―――?)
自分が起訴すれば、平賀は何某かの刑を受けるだろう。何しろ、奴はこちらに全治三ヶ月もの怪我を負わせたのである。
陪審員制度の無い日本では、検察側と弁護側の応酬だけで裁判が進められる。過去、同じ職場に勤務していて確執があったことや贈賄に関しては調べられれば明るみに出るだろうが(既に平賀は一倉に多少話しているようである)、それはあくまでも別の事件として扱われる筈だった。
そして、その贈賄絡みの一件に関しては、いよいよもって平賀が自分を訴えるということも無くはないにせよ、己の手を通してオットーからの金が彼に渡っていた事実がある限り、購入委員会の際に自分が抱き込んだ理事長や中川外科部長、更には現金を用立てた星野にしても、仮にことが立件されたところでそうそう簡単に口を割るとは思えなかった。それに、もしも一連の事実が白日のもとに晒されるようなことになれば、関わった多くの人間を巻き込み、天真楼病院及びオットー製薬両者の存続が危ぶまれるのは必至となるであろう。
寧ろ、病院を去っている司馬や平賀よりも、勤務している現職員達の方が被るダメージは大きいのである。尤も、辞めた職場がどうなろうとも、今更、自分の知ったことではなかったが。
今、こうして生きている以上、これからどうするのか―――司馬にとってはそれが一番大きな命題であり、真っ先に考えねばならないことだった。
病室のドアを軽くノックする音に気付いて顔を上げると、丁度、医者が看護婦を従えて入室しようとしていた。数日前までの自分の姿をそこに重ね合わせた司馬は、術後の経過や今後の治療予定を告げる言葉に、表情を尚一層固くしつつ、無言で耳を傾けた。翌々日。
予告通り、一倉は原宿東署の刑事と共に、司馬の病室を訪れた。
患部に障らないようにと、とりあえず大きな枕とクッションの合いの子のようなものを背中にあてがわれ、軽く上体を起こしたような姿勢をとらされた後、司馬に対しての質疑応答が始められた。
原宿東署の刑事は、司馬と平賀の関係について、根掘り葉掘り聞き込んできた。司馬は、平賀と共につい最近まで同じ職場に勤務していたことと、以前自分が参事に任命された際に平賀は副主任に降格される羽目になり怨まれていた事実について、簡単に説明した。
刺される程の確執がそれだけである筈がないだろうと、質問する側は追及の手を弛めようとしなかったが、司馬自身、元々多くを語る気は無かった。尤も一昨日、平賀とのしがらみを一倉に言い当てられたことから推察して、あの男がオットーからのリベート受け渡しに関して少しく口を滑らしたのではないかと懸念していたのだが―――目の前の刑事が繰り出す質問からは、それらしいニュアンスが一切感じられない。平賀が贈賄について言及していないのなら、自分も余計なことを言う必要は無いと、司馬は判断した。
一通りの質問が終わった後、自分の意向を訊ねられた。加害者は犯行を全面的に認めており―――それはそうだろう、第一、現行犯逮捕されたのである―――後は、被害者が起訴するかどうかにかかっているのだと、原宿東署の警官は探るような視線を寄越した。
「―――起訴は、しません」
司馬の科白に驚愕した表情を見せた刑事が助けを求めるように、壁に凭れていた一倉の方を振り返った。頭を上げて司馬の方を見遣ったその顔には、先日枕元で見せた柔らかな表情の跡形も無く、突き刺すような鋭い視線をベッドの上のこれまた無表情な顔に対して向けているだけだった。
黙って対峙している二人の間に挟まれ無言の威圧感に耐え切れなくなった哀れな所轄の刑事は、目を白黒させながら、司馬に向かって念を押した。
「だって、あんた刺されてるんだよ? しかも、全治三ヶ月だ。本当に、いいんだな?」
「ええ・・・結構です」
ゆっくりと紡がれる、しかし取りつく島の無い口調が、病室内に低く響く。まるで人を突き放したような声音に、一倉は少し引っかかるものを感じて軽く目を見開いた。
―――まあ、刺されるようなことする方も悪いっていや悪いしね・・・あんた達、二人ともお医者さんなんだって? それも外科の・・・明日には供述調書作成して持って来るから、それに署名してくれれば―――後はゆっくり怪我、治すだけだわな・・・
不起訴になった事件に対してこれ以上無駄な時間を費やしたくないとでもいうように、そそくさと会話を締め括ると、原宿東署の刑事は病室を後にした。
慌ただしく閉められたドアから視線を移して、供述に立ち会うだけの筈の男がまだ其処にいるのを視界に認めた司馬は、その容赦無い眼差しを相手に投げかけた。
「―――あなたは、戻らないんですか?」
今だ、壁に凭れ掛かったままの一倉をねめつける。
「いや・・・君に、少々確認したいことがあってね」
一倉は身体を起こすと、ベッドの方へゆっくり進み出た。
「・・・何ですか?」
先程まで原宿東署の刑事が座っていたパイプチェアを更にベッド脇へと引き寄せて腰掛けた一倉は、司馬の顔を至近距離から覗き込んだ。
「君は、つい最近まで、天真楼病院に勤めていた外科医だそうだな?」
「ええ―――それは、さっきの刑事さんにも話しましたが・・・?」
「ああ、私も聞いていたが、な。その、勤務中に―――」
一倉は背広の内ボケットから一枚の写真を取り出し、司馬の目の前にチラつかせた。
「この男が、外科に訪ねて来たことは、無いか?」
見せられた写真には五十代くらいの人品卑しからぬ紳士が写っていた。はっきりした目鼻立ちの、男前とも言えなくない人物であるが、司馬の記憶には覚えの無い顔だった。
「・・・訪ねて来たこと、ですか。クランケ―――つまり、患者という意味では、無い・・・?」
司馬は一倉の目を見返して、確認した。
「ああ、患者ではない筈だ」
「―――患者でなければ・・・我々医者が、病院で顔を会わせる人間は限られてきます。医療機器メーカーや、薬品メーカーの担当者といった中に・・・この男の顔は、ありませんでした・・・」
一言づつ、確認するように単語を並べる司馬の顔を一倉はジッと見ていた。低く通る声は一倉の鼓膜を震わせ、耳にじわりと沁み込んでくるようだった。
「そうか―――手間を取らせて、済まなかった。失礼する」
写真をしまうと、一倉は立ち上がった。一昨日と同じようにアタッシュケースを持ち病室を出ようとした後姿に、司馬はふとあることを思いついて、声をかけた。
「あの―――」
一倉はドアノブに手をかけたまま、上半身だけを捩って振り返った。
「何だ」
「なんで―――僕を助けたんです・・・?」
路上に倒れている人間が血を流していれば、慌てて救急車を呼ぶことくらい一般人の常識である。ましてや市民の生活を護る警察官ならば、怪我人救助は職務として当然のことだろう。しかし、司馬には一倉がそんな当たり前の理由で自分に関わったのではないような気がしてならなかった。先程見せられた写真の男のことを確認する為だったとしても、刺されたあの舗道の上で生死の境を彷徨っていた自分が何処の誰だか、その時点でこの男に判っていた筈が無かったのだから、そんな理由が当て嵌まらないことは明白なのだが。
ならば、何故そんな質問をするのか―――と問われたところで、それは司馬自身にも、説明のつけられないことだった。一昨日ベッドの上で目覚めた時に初めて一倉と顔を合わせ、彼がキャリアであろうと本能的に当たりをつけたのと同じ理由で、それを理屈で証明することは不可能だった。
「何で―――って、息がある人間をむざむざ見殺しにする訳にはいかないだろう。警察官としても、放っておくことは出来ん」
解ってはいたものの、返ってきた答えはひどく当たり前のものであり―――司馬は自分の心に巣食っている正体不明の疑問を抱えたまま、視線を泳がせた。そんな司馬の様子を見て、一倉は面白そうに短く笑った。
「君は、変わってるな。人を助けるのに、理由がいるのか?」
その言葉を聞いて挑むように顔を上げた司馬の視界から、既に一倉の姿は消えていた。To Be Continued・・・・・
(1999/6/2)
へ戻る
−第1話に対する言い訳−
司馬センセ、刺されたの左側ですよね? 損傷箇所については実にテキトーなこと書いてますので、「もっとこういう怪我にした方がいいよ」というアイディアお持ちの人は、是非教えてください〜〜〜
医学的知識ゼロの私は、全治何ヶ月からが大怪我になるのかよく判りません。この辺も詳しい方、いらしたら、ご意見よろしくお願いします…
それから、一倉の役職ですが。
本店のHP見ると、H9年4月で警察庁情報通信局情報管理課長任命ということになっていますが、この情報通信局というのが実に書きづらい…電算情報管理とか通信施設運用とか、職務が今一つハッキリしないんですね。で、アヤシい仕事をこなす一倉が書きたい私は、勝手に外事課勤務ということにしてしまいました。そのへんのコトは第2話で書きます、多分。
ところで、警備局外事課外事調査官の役職が警視正というのは、本当のようです。
話としては、あまりに当り前な出会い編で申し訳ないです。セリフも少ないので、なんか司馬っぽくないかも(泣)