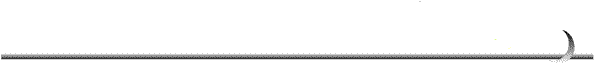百年の孤独 3
司馬はベッドの上に上半身を起こしていた。サイドテーブルには医療関係の雑誌と機関紙が五〜六冊、無造作に積み上げられている。いずれもここの医局から借りてきたものだったが、既に全部読破してしまい、今の司馬にはやることが無くなっていた。
窓に目をやると、外濠を挟んで対岸の神楽坂の商店街が見渡せた。水際に立ち並ぶ桜の木々が淡い色合いの蕾を徐々に膨らませ、今にも咲き零れそうな様子がここからでも感じられる。春の穏やかな足音は日々スピードを早め、首都圏ぜんたいをその柔らかな手で包み込もうとしていた。
司馬が入院してから一週間が経過しようとしていた。当然、見舞いに来る人間は誰もいない。
入院当初、担当医が家族へ連絡しようとしたのを司馬は断っていた。そもそも自分は怪我で入院しているのであり、ある一定の期間が過ぎれば完治するのだから、わざわざ家族を呼んで余計な心配と負担をかけたくないと、司馬は頑なに言い張った。
患者の家族に連絡するのを当然の義務として申し出た病院側は、当初、司馬の強い拒絶に大層驚いた。そういう訳にはいかないと、いったんは喰い下がったが、彼自身が医者であることや、かかる費用の徴収に関しては心配が無いこと―――自分名義の当座預金から入院に関わる全ての支払いを引き落とすように司馬は手続きしたのである―――などから、結局、本人の言い分を受け入れたのだった。
司馬は刺された傷の辺りをパジャマの上からそっと押さえた。薄い布地を通して、盛り上がっている傷痕を指の腹でなぞる。
まさか、自分がオペされる側にまわるとは思わなかった―――
天真楼病院で自分が最後に手術した、今は亡き石川もきっと同じことを思ったのだろうなと、司馬は少し可笑しくなった。
この警察病院に担ぎ込まれてから、司馬は今日初めて、ライヴァルだった石川玄のことを考えた。天真楼病院の中では誰一人刃向かう人間のいなかった自分に、石川は真正面から突っかかってきた唯一の男だった。自分とはかけ離れた倫理観を持つ石川は、司馬を否定することだけを生き甲斐とし、全ての闘志を注ぎ込んだのちにその短い命を散らしていったのである。
自分を倒す為だけだったとしても最後まで司馬にこだわり続けた石川に対して、大した奴だと思えばこそ、己の手で絶対に助けたかったと、今でも無念に思う。
司馬は決して、石川のことが嫌いだった訳ではなかった。
出会ってから、たった三ヶ月の付き合いだった。様々な誤解や嘘を自分の方からもっと積極的に解いていれば、歩み寄れぬままで今生の別れを迎えることはなかったのかもしれない。しかし、司馬は敢えてそれをしなかった。
―――君は、僕が知っている中で最高のドクターだ・・・技術の面では・・・
司馬は天真楼病院の屋上で石川からその一言を聞いたときに、何やら擽ったい感じがしたことを思い出した。そして、ほんの一瞬だが、自分の心に迷いのようなものが生じたことも、はっきりと記憶していた。
違う!! おまえは、何も解ってない―――
あの時、自分は吐き出してしまいたかったのかもしれなかった。
殺したのは、自分じゃない―――と。
俺は、あの人を庇いたかっただけだ―――と。
だが司馬には、今更本当のことを言ったところで、もはや事態は何一つ変わらないことが判っていた。そして仮に石川が真実を知ったとしても、彼はそれ故に軽蔑する人間をもう一人増やすだけに過ぎず、だからこそ、それまで通りに口を噤んだのだった。
罵られ、責められるのには慣れていた。寧ろ、自分を憎ませ続けることで石川の中に己の存在を永久に刻み付け、顔を合わせなくなってからも生涯忘れ得ぬようにさせようと、無意識のうちに行動していたのかもしれない。
そして、石川も自分のことを本心から疎み憎んでいたのではないという確信が、司馬にはあった。
本当に嫌いで関わり合いになりたくなければ、相手を無視すればいいことである。だが、石川は「君を認めない!」と何度も自分に喰ってかかりこそすれ、黙って傍らを通り過ぎることは一度もなかった。反目というのは相手の存在を認めていなければ出来ないことであるから、まあ、それは当然とも言えようが。
司馬は自分の右手を見つめた。少し骨張った指と短く切り揃えられた爪がそこにあった。
最高の技術とまで言われたそのメス捌きで何人もの患者を執刀し、救ってきた―――だが、手術が成功しても、結果的に患者が助からないことだって希にあるのだ。
石川―――俺は、君を助けたかった・・・君に、生きていてほしかった・・・
あの夜、石川が永遠に自分の前から去ってしまったことに耐えられなくなって、一足先に集中治療室を後にした。あまりにあっけない最後が全ての意識を掻き乱し、事実を認めたがらない気持ちは司馬自身をひどく戸惑わせた。呆然と玄関を通り抜け、ひたすら舗道を歩いた。
寒い夜だった。
吐く息は空中に白く放たれ、冷たい大気が身体中を取り巻いていた。車道をひた走る轟音の残響が容赦無く耳に纏わりついたが、その音が聴覚に届き、司馬の中に入り込んでくることは無かった。だが、鈍い衝撃が突然襲いかかり―――振り返ると、気弱に微笑む平賀の顔がそこにあった。
(しかし、刺された俺の方は、こうして生き延びた―――何だか、皮肉なモンだな・・・)
軽く目を瞑った司馬はあの日のことを思って、深く大きな溜息を吐いた。「何だと?!」
一倉は握り締めていた受話器が壊れるかと思うほどに力を込めた。震えそうになった語尾を必死で立て直し、なんとか息を継いだ。電話の向こうでは2係の捜査員の一人がこちらの反応に合わせて、息を呑んだまま硬直しているようである。
「間違いないのか?」
声という判断材料しかない電話の場合、僅かな動揺でも相手には確実にそれが伝わることがある。己の手足となって働いてくれている部下の、自分以上に戸惑っている現実を前にして、一倉はいつもの冷静な指揮官たりえるよう最大限に平静を装って、再度受話器に問い掛けた。
「―――はい。残念ながら」
電話線の向こうでは、一倉のいつも通りの声音に少しくホッとしたような部下が、それでも悔しそうに事実を認めていた。
「判った―――私は、上と善後策を練ろう。ご苦労だったな。くれぐれも事故に遭わないようにして、帰ってこい」
「お心遣い、感謝いたします。それでは、今から戻ります」
受話器を戻した一倉は、沈痛な面持ちで頭を抱え込んだ。外事課の奥にある小会議室で警備局長と一倉は苦虫を噛み潰したような顔で対峙していた。たった今、一倉の元にもたらされた報告により、今後調査を進めるにあたって少々問題が生じることになったのである。チームを統括する将として上司へ報告する義務を果たし、また、若干の軌道修正を考えんとしてのことだったが、予想外の展開は一倉の心をかなり不愉快なものにさせていた。
一倉が調査2係の一人に命じていたのは、偽造も含む、若林所有の複数のパスポートから本人の本籍地を確認し、その実在の裏付けを取ることだった。
若林は全部で五冊の複次海外渡航旅券を使用しており、何れも本籍地はばらばらで、それもご丁寧に全国各地に散らばっていた。部下に調査を命じた時点でその五箇所の本籍地のうち何れか一箇所が本物である確率は一割弱というところであった。偽造パスポートの場合、全ての記載が偽物ということも往々にしてありうるからである。
それでも幸いなことにそのうちの一箇所に若林の戸籍謄本が実存していることが判明し、調査員は早速現地へと飛んだ。そして、近隣の住民から話を訪くうちに、とんでもない事実が明るみに出てきたのである。
謄本上の『若林仁』という男は三年前に亡くなっていた。つまり、渡航記録上の若林は、この集落に実在していた男の戸籍を勝手に使用してパスポート申請を行った可能性があるということである。
尤もそれ自体は闇商売人として別に珍しくもない手口だったが、その本籍地が『下喜多村折楯』であったことが問題を大きくし、事態を思わぬ方向へと転がしていった。
奈良県吉野郡下喜多村折楯――― 一見する限りでは何の変哲もない筈のこの地名が、警備公安警察にとって特殊な意味合いを持つものであることは、一倉も役職上、知っていた。
現在警備局では、一倉達のチームとは別に偽造旅券発行シンジケートを追っているグループがあり、それらに使用される本籍地がある特定の住所に集中していることが明らかになっていた。その何れもが山間の交通の不便な場所であり、そのうちの一つがこの下喜多村だった。偽造旅券シンジケートは日本国内の、オンラインで謄本の確認をとるのが困難な小さな町村の人里離れた集落ばかりを本籍地に指定しており、現住所の方は揃いも揃って大都会の地番を使用していた。
精巧な偽造旅券を押収した場合、真っ先に確認される記載事項が本籍地であること(一般的に、住民票の方は移動が激しく、照会した時点で合ってなくても、そこでの最終判断を下せないのである)を知っての手口であるのが、一際悪どく、またそれは組織が国内に存在しているか、日本人もしくは日本の戸籍事情に精通している人間が関わっているという事実を物語っていた。
数的にはさほど多くないものの、密売やテロ等の、質の悪い犯罪に荷担している人間が、この組織から偽造旅券を買い取っていることが既に判明していて、東南アジアの偽造旅券グループの摘発と共に常に国際舞台の水面下で問題になっていることだった。また、この案件に関しては特に、安保を楯にとった米国から善処を強く求められており、出入国管理に関しては本来外事課の管轄ながら、実際には公安第一課が調査を手掛けていた。
そして、忍び寄る追求の手を察知してか、ここのところ目立った動きの無い偽造旅券シンジケートに繋がる情報は何一つ無く、公安第一課が死にもの狂いで情報収集に当たっていることはトップシークレットとして、警備局所属の警視以上の者へ知らされていたのである。
しかしここへ来て、若林がかの組織から偽造旅券を買い取ったかもしれないとなれば、ことが面倒になるのは目に見えていた。真っ先に上層部へ報告を挙げ指示を仰いだ代償として、自分達が有利に動けるよう警備局長からの保障を取り付けようと、一倉は今、ここにこうして座っていた。
「厄介なことになったな」
俯いていた局長はこめかみの辺りを節ばった指で軽く抑えると、漸く一倉に視線を向けた。
「とりあえず、一課の方にも報告しない訳にはいかないのでしょうが―――まさか、こんな繋がり方をするとは・・・」
一倉の声も自然と沈んだものになる。
若林本人の足取りは依然として不明であることが、問題の複雑さに更なる拍車をかけていた。
警備公安警察の異なる二つの部隊が共に一人の参考人を追うことになるのである。偽造旅券使用と臓器売買と―――どちらも、国際問題に発展した結果での調査依頼であるが、臓器売買の方はまだ犯罪として立証できるかどうか難しいところであり、既にそれを購入し使用している事自体が罪である偽造旅券所有の方が有利に働くことは目に見えていた。
同じ組織に所属するチーム同士といえども、諜報活動に近い捜査を行っている以上、相互間での情報交換は皆無に近い。目的が微妙に違えば、被疑者もしくは参考人から引き出そうとする情報の種類も違ってくるのは当然であるが、同一人物から事情聴取を試みる場合、二番手にまわった方が不利になるのは歴然としていることだった。
「もしも、若林本人が見つかったら―――局長ご自身は、どちらを優先させるおつもりで・・・?」
自分が率いる一小隊を代表して訊ねなければならない質問が、一倉自身、これほどまでに重く感じられたのは初めてだった。
「見つかり方にも、よるな・・・君のところと、一課と―――どちらが先に、奴の足取りを掴むか・・・」
「その結果次第、ということですか―――」
一倉は心の中できつく唇を噛んだ。
(狸め・・・どちらにもつかず、中立かよ?)
ことと次第によっては、対日感情を逆撫でしかねない二つの調査を請け負いながら、極力責任問題に繋がるような行動を避けようとする官僚特有の保身術はいつものことであり、別段珍しくも何ともないものだった。
でも、まあ、いいだろう・・・それなら、こっちはこっちでやらせていただくとするか―――
元々、色よい返事が聞けるとは思っていなかった一倉だったが、一縷の望みも期待出来ないと判断するや、素早く気持ちを切り替えると、つとめて冷静な面差しを装って告げた。
「では公安第一課には、私の方から報告を―――よろしいですね?」
「ああ、そうしてくれ。健闘を祈る」
目の前の老獪な俗物は、一倉の普段と変わらぬ態度に少なからずホッとしたようだった。
「それでは、失礼いたします」
本心を鉄面皮の下に隠し通したまま、型通りの首脳会談は終了し、二人は小会議室を後にした。
一倉は自分の席に戻ると、新たに挙がってきている報告書に目を走らせた。幾つかの病院の外科医に関する細かい個人情報であったが、今の自分の頭の中には何も入ってこなかった。
(結局、失敗すれば、責任はこっち持ちか・・・ま、判ってはいたがな)
我々は、絶対に出し抜かれる訳にはいかない―――
一倉は微かな溜息を吐いた。自分達は、既に明白な罪ではなく、まだ証明できない犯罪を追っているのである。捕まえて痛めつけて泥を吐かせるだけなら、わざわざ己の手を煩わせなくても、血の気の多い叩き上げの刑事達にでも任せておけばいいことだった。体力と粘り強さだけなら彼らの方が上なのだから。
オレ達は若林を追い詰め、いの一番に事情聴取し、裏組織に関わる情報を少しでも多く引き出さねばならないのだ。そして、それさえ済めば、後は公安第一課の方で、奴をどう料理しようと知ったことではない。
「全く―――やってくれるな、若林サン、よ」
一倉はバサリと音を立てて書類を戻し、カラカラに渇いた喉を少し湿らせようとコーヒーを取りに立ち上がった。一倉が警備局長と接見したあの日から十日が過ぎようとしていた。
若林の消息は未だ判らず、調査員の間にも焦りと苛立ちが少しづつ忍び寄り始めていた。
あの後、結局、一倉は公安第一課の担当課長補佐と極めて穏やかな話し合いの席を設け、それぞれが持っている情報の、自分達の追っている部分には関わらないところでの公開を約束することで一種の協定を結んでいた。つまり、一倉サイドに関して言えば、若林の出入国記録や戸籍に関する情報については一課の方に提供するが、彼が関わっていたかもしれない病院や外科医については公示する必要無しということで合意したのである。
今現在、一倉は、1係の方へ例のリストにある病院に勤務している外科医を始めとする関係者の調査を任せ、2係には引き続き若林が入国後辿ったかもしれないルートを洗わせていた。乏しい手懸りを前に苦戦している2係に比べると、1係の集めてくる病院の職員や医者に関するデータは膨大な量を誇っていたが、多ければいいという訳でもなく、その中から特に目ぼしいものは見当たらなかった。
集まってきた情報の分析は殆ど部下任せだったが、一倉は元・天真楼病院勤務だった外科医、司馬江太郎に関する情報にだけは全て目を通し、その写しを個人用のファイルに保存していた。
それから更に四日後、衝撃的とも言える真実が発覚し、一倉達を新たな混乱へと巻き込んでいくことになった。
調査1係の一人が横浜にある大倉山病院に勤務している外科医の一人が若林らしき男と接触していたことを探り当てたのである。その外科医は写真を見て、確かにこの男であると認めたが、「若林仁」ではなく「黒田清」と名乗った新事実を調査員に暴露し、事態を次なる局面へと導いたのだった。
新しい氏名が発掘されたことに俄然色めき立った一同が四方八方手を尽くして一丸となって調査を進め、今までのっぺりとした顔を持つのみだった男は着々とその全貌を一倉達の前に現しつつあった。
黒田清。52歳男性。某総合医薬品メーカー勤務。MR歴8年強。家族構成は妻と息子一人。現在、長期海外出張中―――
現時点では一外科医の証言のみが頼りで本人は依然として姿を隠したままであったが、調査員達の執念ともいえる追跡により、黒田の住居付近で得た証言や実在する各種登録証などから「若林仁」と「黒田清」が同一人物である確率は80%にまで高められつつあった。
仮に黒田が若林本人だったとして、公安第一課よりも先に身柄を抑えたい一倉側としては、もう、手段を選んでいる余裕はなく、思い切って少々危険な賭けに出ることを余儀なくされていた。疲弊している部下達の志気を低下させない為にも調査活動をスムースに遂行できる環境整備が必要であり、更には自分達が単独で動いても一課から咎め立ての無いようにしておく為に、一倉は再度警備局長を訪ねた。
「同一人物だという可能性は?」
肚の底を決して見せることのない上司は、一応型通りの質問を投げかけてきた。
「証言の信憑性から推察して、二割くらいというところでしょう。接触していたのは外科医一人だけですから」
一倉は心の中で盛大に舌を出していた。
「しかし、他に手懸りは無いんだな?」
「今のところは、こいつに賭けてみるしか―――」
局長がわざとらしい溜息を吐いた。
「一課には?」
「まだ何も・・・可能性が五割を越えた時点で彼らにも情報を提示しようと思っております」
「まあ―――よかろう。所轄との調整はどうする気だ」
「そのことなんですが・・・」
一倉は口篭もった。事情が事情だけに本来なら警察機構の中を縦横無尽に走っている東大閥の力を駆使するのが一番望ましく、後々表立たなくて都合が良いことは判りきっているのだか、今回はそれが躊躇われた。
何故なら、若林=黒田の自宅がある場所が港区台場三丁目であり―――警視庁内でも過去色々な事件に巻き込まれてきた湾岸署の管轄になるからである。
湾岸署の担当管理官である新城は自分の同窓であり二年後輩だが、こういった複雑な案件を持ち込んで、警察庁と所轄との調整役を任せることにいささか不安を感じるのは、用心に用心を重ねたい一倉の危惧に過ぎなかったが、あながち外れではないと言えよう。湾岸署全体もさることながら、あそこには新城の神経をあらゆる意味で逆撫でしてきた青島がいるのである。下手に新城に調整役を振って、事を荒立てられたら、黒田を取り逃がすだけでなく、出し抜いた公安第一課からも非難の応酬を受けるのは目に見えていた。
東大閥に関係なく、確実に湾岸署と青島を抑えられる人物でないと、今回の大役は務まらぬ―――そして、その役を無事こなせそうな人物を一倉はたった一人しか思いつけなかった。
「局長。お力添え願いたいことがあります」
一倉の声に、目の前の上司は両の眉を少しく上げて応じた。
「調整役に刑事局の室井参事官を―――湾岸署と上手く折り合うのに、彼以上の適任者は、おそらくいません」
「―――いいだろう。私から刑事局長に頼んで、室井君に動いて貰うことにしよう」
一倉の意図するところをほぼ正確に理解した警備局長は、真面目な表情で部下のたっての依頼を請け負った。To Be Continued・・・・・
(1999/6/16)
へ戻る
−第3話に対する言い訳−
何だか一倉の方の事情がスパイ大作戦並み(笑)に肥大していますが、多分今回で大筋は終わると思います…まさかこんなことになるとは、思わなかった…
組織の上の方のドロドロした部分を書いてみたかっただけなんですよう…これ以上やると本筋から離れてしまうし、私の妄想力もそろそろ限界ですので、もう、やめます。この辺りの知識は軍事マニアで自衛隊オタクの友人に協力して貰ってるので、そこそこリアリティーはあると思います(井上★律子様、感謝!)
司馬の方の心理がちょっとモタモタしているかな?という感じですが、石川に対してどう思っていたか…というのは書いておきたかったので、こうなってしまいました。
第2話に引き続きダークな話になってしまい、申し訳ない〜〜〜というところですが、次回(第4話)では、やっと一倉と司馬が久々に顔を合わせます! 青島と室井も出ます!(予告しないと、もう読んでいただけない気が…泣)
第4話は、前半のヤマ場になるんじゃないかと思ってますので…尤も、第2話と第3話、いらないじゃん!ということになるかもしれませんが…(ひぇ〜〜〜ん)