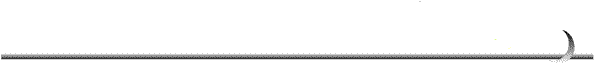百年の孤独 4
「だから、何故、私なんだ?」
公用車の後部座席へ先に乗り込んだ室井は、隣に泰然と腰を落ち着けた一倉を軽く睨み据えた。
「オレが指名したんだよ」
一倉は自分でドアを閉めると、バックミラー越しに様子を窺っていた運転手に向かって、顎をしゃくった。それを合図に車が軽いエンジン音を立て、公道へと滑り出した。
「職権乱用だ」
「おいおい、久しぶりに一緒に仕事するんじゃないか。そんな、つれない言い方は無いだろう」
軽く往なしたところで、室井の大きな瞳は少しも揺るがず、ひたと焦点を合わせたまま微動だにしない。
一倉は諦めて、早々に本心を告白することにした。
「オマエなら、湾岸署の扱いには慣れてるだろう? だからだ」
その言葉に押し黙ってしまった同期を盗み見ながら、一倉は心の中で(そして青島の扱いも、な)と付け加えた。
車は日比谷通りを南下していた。まだ午前中の早い時間である。道はさほど混んでおらず、窓外の景色も飛ぶように後方へ流れていく。
暫くして、室井が再び口を開いた。
「だが、本来なら調整は本庁がやるべきなんじゃないのか?」
一倉は喉の奥だけでクックッと笑うと、室井の方へ顔を向けた。
「オマエなあ・・・あそこの担当管理官は新城だぞ? よりにもよって、あいつにだ―――湾岸署との調整役が出来ると思うか?」
その言葉を聞いた室井は一倉の云わんとしていることをほぼ正確に察知し、困ったように黒目を少し見開いた。
そんな室井の様子を目の当たりにした一倉は満足気に軽く頷くと、正面を向いて言葉を続けた。
「なあ、室井。オマエだって以前警備にいたことがあるんだ。オレ達がやっていることが、どんな種類のモノか判っているだろう」
「ああ」
隣からは、短いがはっきりした同意が返ってきた。
「なら、協力してくれ。二年前みたいに、参考人を公務執行妨害で逮捕されちまったら、困るんだ」
室井が僅かに身体を強張らせたのを気配で感じたが、一倉はお構いなしに次の科白を吐き出した。
「奴が参考人本人である確率は八割―――絶対、先に、見つけなきゃならないんだよ」
「先に―――って、他にも追っている部隊がいるのか?」
「ああ。しかもウチの一課だ」
「対米絡みの例のあれか。しかし、お前のところだって―――」
「だから、今回は厄介なんだよ」
皆まで言わせず、一倉は強引に室井の言葉を遮った。
「今、奴の素性を掴んでいるのはオレ達の方だけだ。上には同一人物である確率が五割を越えたら向こうにも情報を流すと言ってある」
「お前、そんなことをして―――」
大丈夫なのか、という次の言葉を室井は辛うじて呑み込んだ。
警備公安警察の任務に携わる人間がどうような想いで職務を遂行しているか、概ね見当はつく。そしてその辺りの込み入った事情もまた、容易に理解できるものだった。直接の経験は無いものの、自分も一時は同じ釜の飯を食したのだ。
「オマエを引っ張り出すのはお門違いな事は、このオレが一番よく判っている。だが、何かあった時に、新城では湾岸署を―――青島を抑えられん」
室井は返す言葉を捜したが、何一つ相応しいものは見つからなかった。
「しかし、オマエなら、何とか切り抜けられるだろう?」
一倉の言う事は正に核心を突いていた。青島がいつも本庁に反抗している訳ではないにせよ、どうにも相性が悪いらしい新城が調整に当たった場合、起きなくてもいい騒ぎが起きる可能性が高くなる―――今まで嫌というほど湾岸署に関わってきた室井には、一倉以上に予想出来ることだった。
そして一倉の現在扱っている案件の複雑さとデリケートさが判るだけに、敢えて自分を指名してきた同期の信頼に応えて然るべきであると、室井は判断した。
一倉の真剣な面差しが室井の理性と感情を共にしっかりと掴んだ。
「なあ、頼む」
室井は一倉に気づかれないようにと浅く溜息を吐いて、頷いた。
「ああ、解った」
「感謝するよ、末代までな」
一倉の大袈裟な謝意表明に、車内の張り詰めた空気が少し和らいだ。その安堵感につられて、室井がぼそりと言葉を洩らした。
「お前には、年内に危ない橋を渡らせたからな―――これくらいのお返しではとても及ばないとは思うが、私で役に立つのなら・・・」
その真面目な決意に一倉が笑った。
「何、勘違いしてるんだ? あの内部告発ごっこは、偶然だと言っただろう」
相変わらずシラを切る同期の横顔を今度は室井の方が咎めるような眼差しで見つめた。
「一倉、俺は―――」
「ああ、分かった分かった! オマエがそんなに気にするなら、丁度いい―――これで、チャラにしようぜ」
煩そうに頭を振った一倉に対して、室井は心の中だけで深く溜息を吐いた。既に電話通達しておいたお陰で、二人が警視庁湾岸署に到着すると各課長以上が最上階の会議室に勢揃いしていた。お約束であるレインボー最中のお茶請けを一蹴すると、一倉は室井の方へ目で合図し、理由は一切明かさずに、自分達の要求だけを全面に押し出して説明させた。
「警察庁上部の決定で、この管内に潜んでいると思われるある人物の動向をこちらで調査しています。つきましては、あなたがた湾岸署の皆さんにも協力をお願いしたい」
言葉自体は捜査協力要請のようにも聞こえるが、実際に警察庁の人間の発言ともなれば、単語の意味合いいかんによらず、それは絶対命令になるのである。
一倉が室井の口を通して所轄に要求したのは、次の四点だった。
一、湾岸署最上階にある会議室の借用 及び 関係者以外の立ち入り禁止厳守
一、臨時通信回線の引込みと各種器材用の電源確保
一、連日湾岸署で取り調べた全被疑者および参考人についての逐次報告
一、湾岸署全捜査員について連日の作業報告書の写しを提出
最前列で大人しく話を聞いていた神田署長と秋山副署長と袴田刑事課長の三人―――通称スリーアミーゴスが果たしてどの程度、事の重大さを理解したのだろうかと、室井はふと気になった。一倉と室井は連れ立って会議室を後にした。午後には一倉の部下達が大挙してやってきて、この湾岸署に詰める為の準備を始める予定である。束の間の静けさは、嵐の前触れに首を竦めて、廊下の隅にでも転がっているかのようだった。
階段を降りて二階の刑事部屋の入口にさしかかった丁度その時、後ろからばたばたと足音が追いつき―――二人は、廊下のど真ん中で接待トリオに足留めされてしまった。
「室井参事官、一倉調査官、どうか、もう少しごゆっくり―――ただ今、お昼をご用意致しますので!!!」
三人の声が建物中に響き渡るかと思うくらいに、重なり合いこだました。室井が眉間に皺を寄せ、諦めたように目を閉じた。
「いや、結構です」
訪ねてくるたびに接待攻防を経験している室井とは違って、勝手の判らぬ一倉はまともに辞意を表明したが、それくらいで怯むスリーアミーゴスではない。室井が一倉の袖を引っ張った。
「一倉―――無駄だ。昼、食べるまで、離してくれんぞ」
「だが、時間が無い―――」
「どこかから、救世主でも現れるのを待った方がいい」
「救世主?」
「ああ。ここで言い争っても余計な労力を使うだけだ」
要領を得ない顔をしている一倉を尻目に、室井はさっさと白旗を上げたらしかった。
その時、刑事部屋の方からざわざわと気配がして、何人かが昼を食べに行こうと出入り口から出てきた。その中に人懐こい笑顔でこちらを見ている大柄な男を室井は認めた。
「あれ、室井さん?」
青島が声をかけた。
室井は黙って目だけで挨拶を返した。それを受けて、にこにこと嬉しそうな顔をしながら、青島は二人の立っているところまでやってきた。
「今日は、どうしたんですか? 何かあったんスか?」
「いや、ちょっと―――調整役で、な」
室井はチラリと隣の一倉に視線を走らせた。青島は一倉の姿を認めて「あ、どうも」と会釈した。
一倉も無言のまま目礼を返した。
「ああ、そうっすか。で、お二人とも―――ここで、何、やってんです? ハッキリ言って、通行のジャマなんスけど」
突然割り込んだ青島に毒気を抜かれた署長・副署長・刑事課長は、先程までの声高な接待の主張をするのも忘れて言葉を失っている。所轄から見て雲の上の人間ともいえる参事官と調査官という役職の人間と対等に口をきいて平然としていられるのは、ここ湾岸署でも青島一人くらいなものだろう。
室井が目だけで青島に窮状を訴えた。察しのいい青島には、それがきちんと伝わったらしい。
「そーだ! 室井さんも一倉さんも、昼、行きません? 近くに安くて美味い定食、食わせてくれるトコ、あんですよ」
『昼』という単語に蘇生しかけた署長・副署長・課長が言葉を差し挟む前に、青島は室井と一倉の両方の腕を取り、足早に歩き出した。
「早く行かないと、席、埋まっちゃうんスよ。さ、行きましょ!」
後ろではまだ何か言いかけているスリーアミーゴスの声が聞こえていたが、青島はお構い無しに二人をどんどんと引っ張って行き、玄関ロビーまで降りると漸く手を離した。
「ありがとう―――助かった」
まず、室井が礼を言った。青島が苦笑する。
「どういたしまして―――室井さんらしくないっすよ。あの三人に捕まるなんて、ね」
室井一人で来た時は、大体無事に逃げおおせているのだが、今日は一倉がいたせいもあって勝手が狂ったのだった。
「なるほど、救世主か」
一倉は小さく呟いた。自分の知らないところで、この二人がどんどんとその絆を強め、互いに寄せる想いを深めているのを目の当たりに見せつけられたような気がして、少しく心が痛んだ。たった今だって、室井が一言も言葉を発しなかったのにも拘わらず、青島は実に的確な動きをしたではないか―――
無言で視線を絡めている二人を見ながら、一倉はその間に敢えて立ち入った。
「おい、室井。オレは一旦戻る。オマエは救世主と昼でも食べにいったらどうだ―――忙しい参事官でも、飯を食う時間ぐらい、あるだろう」
青島と室井が同時に一倉の方を見た。二人の眼差しが共に(いいのか?)と自分に訊いているような気がして、一倉はなんだか可笑しくなった。
「今日のところは、ここでの用事も済んだことだしな―――ああ、そうだ」
一倉はずっと気になっていたことを訊ねてみようと、青島の顔を見つめた。視線を受けた鳶色の瞳が不思議そうに瞬いている。
「君の親戚に医者は―――外科医は、いないか?」
「はあ?」
青島が、頓狂な声を上げた。無理もないだろう。まったく予期せぬ問いを受けたのだから当然の反応である。
一倉はゆっくりと質問を繰り返した。
「外科医を職業とする、27歳の従兄弟や親戚はいないか?」
目の前の男は怪訝そうな顔をしたが、それでも一倉の質問を真面目に受け止め、正直に答えを返してきた。
「医者っすか―――医者はいないです。弁護士やってる従兄弟はいますけど・・・」
「そうか・・・変なことを訊いて、済まなかった」
一倉は正面玄関を出て待機していた公用車に一人で乗り込むと、湾岸署を後にした。
(やはり、他人の空似か―――それにしても、本当にそっくりだな・・・)
一倉は司馬のことを考えた。
あいつは、今頃、どうしているだろうか―――
担当医の話では、あと一週間で大部屋に移るということだった。
明日からまた、昼夜の無い諜報活動を強いられるのは必至である。今日の午後は湾岸署の会議室に部下達が本部設置の準備をするだけだから、自分がいてもいなくても特に問題はないだろう。
(個室にいる間に、一度、見舞いに行っておくか)
一倉は身を乗り出して運転手へ行き先の変更を告げると、車内から携帯電話で部下の一人を呼び出し、本日午後からの作業に関して指示を与えはじめた。久しぶりに訪れた警察病院の玄関口で軽く肩を揺すり、一倉は上空に目をやった。
雲一つない青空が実に晴れやかに拡がっている。都会の雑多な空気の中にも季節の変わり目は確かに存在していて、若葉の香りを含んだ風が外濠を吹き抜け、人々の周りを甘く取り巻いていた。
受付で司馬の病室が変わっていないことを確認し、一倉はエレベーターホールに向かった。平日の午後ということもあってか、さほど混み合っていない待合室を抜けて、個室が続いている病棟の一番奥の方を目指して足早に歩いた。
目的の部屋の前までくると、一倉は短くノックした。
「どうぞ」
無愛想な返事をドア越しに確認して、ノブをゆっくり廻す。
「どうだ、調子は?」
司馬はベッドに横たわったまま上体だけを起こして分厚い本を読んでいたが、顔をあげて声の主を確認すると、一瞬だけ驚いたように目を見開いた。
「・・・ええと、一倉さん、でしたっけ・・・?」
一倉はベッド脇のサイドテーブルまで進み出ると、手に提げてきたフルーツの籠を其処に置いた。
「君の好物が何だか解らなかったので、一般的な見舞いの品を持ってきた」
司馬は、面食らったような顔を一倉に向けた。
「はあ・・・それは―――わざわざ、どうも」
その眼が「何しに来たんだ?」と問いかけているのは判りきっていたが、一倉は司馬の疑問をすっぱりと無視した。そして代わりに室内を見回して、外部の人間が訪れた気配が全くしないことに気を留めた。
自分の頭の中に全てインプットされている情報からすると、過去の交友関係を鑑みても親しくしている友人・知人といった類が司馬には皆無であり、この病室を個人的に訪れる客がいるとは到底思えなかったが、それでも一応、質問を口の端に乗せた。
「なんだ、見舞客の一人も来ないのか?」
司馬は読んでいた医学書に視線を戻すと、素っ気無い口調で答えを返してきた。
「―――誰にも、ここにいることを連絡していませんから」
「そうか」
一倉は部屋の隅の方にあったパイプチェアをベッド脇に引き寄せるとそこに腰掛け、そのまま黙って司馬の横顔を眺めた。
浅黒い肌に煌きを湛えた眼差しが映え、引き締まった顔の輪郭を尚一層引き立てて、一倉の視線を釘付けにした。今は手許の本の活字を一心不乱に追っているものの、男にしては長い睫に縁取られた瞳は、時に野生の獣のような鋭さを持って相対するものを抑えつけてきたのだろう。そのしなやかな眼差しに屈した人間の心情を思うと不思議な気持ちに囚われる。
への字に結ばれた唇は、外光の乏しい室内の中で見るとやや白っぽく浮き上がり、色黒な地肌と奇妙なコントラストを為している。短めの髪は少量の整髪料で撫で付けられていたが、その隙の無さが、まるでブロンズ彫刻のような仕上がりを一倉に思わせた。
暫し、無言の時が流れていたが、司馬の方が不躾な視線に耐え続けることに対して、とうとうネを上げた。
「何か、僕の顔についてますか・・・?」
それでも目線を下方の書物の上に落としたままで、司馬は思い切り不機嫌な声を一倉にぶつけてきた。
「いいや。すまん、つい―――」
一倉は、続ける言葉を失った。
もしも、司馬がその時一倉の方に向き直ってその表情を見ていたら、今後の二人の関係に於いてお互いが相手の中に占める位置はまた少し違ったものになったのかもしれなかったが、あいにくとそうはならなかった。そしてそれは、一倉がこの後大分面目を保てることとなり、それなりに自分の矜持を手放さずに済む結果となったのであるが。
この時、一倉は司馬に見惚れていたのだった。
確かに司馬の容姿はかなり上等な部類へ入るだろうが、特別な美男子という訳ではない。視覚的に判断した場合、同性から見ても美しいと感じさせられる男性は他に幾らでもいるだろう。だが、一倉は今、すぐ傍らで自分を完璧にシャットアウトしている司馬の存在全てに惹きつけられていた。
クールで人を寄せつけようとしない、甘さを排除した雰囲気を常に漂わせているこの男が、ただただ気になった。それはつい先程僅かな時間を共有した、司馬とそっくりな外見をしている青島の明るさと屈託の無さに触れた結果の、あまりに対照的な二人に続けて対峙した軽いショックから来る好奇心に過ぎないのかもしれない。
だが、理屈で納得出来なければ行動に移すのを躊躇うほど、一倉は純情でもなく、また臆病でもなかった。
「あまり、部屋からは出ないのか?」
返事は無かったが、一倉は、構わず話し掛けた。
「もう、歩いても構わないんだろう? 少し、身体動かした方がいいんじゃないか?」
部屋の隅に立て掛けられた松葉杖を見遣りながら、相変わらず無視を決め込んでいる怪我人を非難するでもなく、ただ淡々と言葉を紡ぐ。
「それとも―――まだ、かなり痛むのか?」
心配そうな声色に、司馬が漸く顔を上げた。その顔の上をほんの一瞬だけ、煩がるような表情が過ぎったが、すぐに思い直したらしく、特に何の感情も匂わせないような独特の雰囲気を纏った。
「いえ・・・そういう訳では・・・」
当たり障りの無い相槌でその場を切り抜けようとした司馬の言葉を一倉はあっさりと攫った。
「ここの屋上へは行ったこと、あるか?」
司馬が訝しむような顔をした。
「今日の陽気なら、上空を渡る風が気持ちいいと思うがな」
少し首を傾げて、僅かに眉を顰めたその表情が、一倉に室井のことを思い出させた。気がつくと追い討ちをかけるように、次の科白を迸らせていた。
「なあ、見舞い客に付き合ったって、バチが当たる訳じゃないだろう?」
聞きようによっては拗ねているともとれなくない、一倉の科白を聞いて、遂に司馬の方が折れた。
「解りました―――お伴すればいいんでしょ?」
その声にはうんざりした色がありありと塗り込められていたが、司馬を病室から引っ張り出すことに成功した一倉にとって、そんなことはどうでも良いことだった。To Be Continued・・・・・
(1999/6/21)
へ戻る
-第4話に対する言い訳-
いや~、今回は書いてて、楽しかったっす(笑) 漸く、話が進展し出して、やっと湾岸署とも繋がりました(パチパチパチパチ) 会話が書けるって、いいですね~~~第2話と第3話であれだけ苦しんだのがウソのようです(笑)
本当は屋上の会話、大部分書き上がっているんですが、もうカンペキ字数オーバー(いつものことだよ・爆)なので、5話にまわすことにしました。ああ、こうやって話が長くなっていく…
あ、青島くんの従兄弟の弁護士はモチロン高岡淳平クンです。でも、この話ではパラレルにする気はありませんので、チョットしたお遊びってことで…織田さん三人は、さすがに手に負えない…(大爆笑)
それから、第3話で『黒田清』という名前にピンと来た方、正解です―――『黒田清』は古畑パートⅡで石黒賢さんが演った犯人の名前からいただきました。
まあ、古畑シリーズでは中川センセも愛人(←いたのか)殺して逮捕されてますからねぇ(爆)
やっと話が、らしく(?)なってきました…