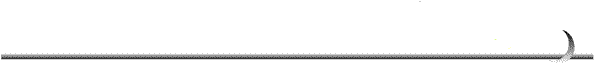百年の孤独 5
警察病院の屋上は意外に人が少なかった。
ところどころで司馬に手を貸しながら、一倉は一番見晴らしの良い神楽坂側のベンチに怪我人を注意深く腰掛けさせた。松葉杖を足許に横たえると、司馬は深呼吸して対岸の景色に目をやった。
外濠沿いの桜が満開になっていた。
普段病室から眺めている景色よりも更に高い位置から眺めるその景色は、司馬にとってひどく新鮮な気分を覚えさせた。決して空気がおいしいとはいえない都会でも、地面からある程度離れた上空を渡る風が清々しく感じるのは、やはり春という季節にだけ振り下ろされる魔法の杖によるものなのかもしれない。司馬は薄紅色の絵の具を溢したような桜並木を見下ろしながら、その鋭い眼差しをやや眇めた。
一倉は司馬が完全に腰を落ち着けたのを確認してから、自分も隣に座った。
司馬はポケットから煙草と、続いて金色に輝く小さなライターを取り出し、チーンと音をさせた。
一倉の視線を横顔に感じた司馬は、説明するように告げた。
「やっと喫煙許可、おりたんで」
「そうか。私にも一本くれないか」
司馬は黙って煙草を渡すと、一倉の方へ先に火を点けた。
二人は暫く無言で紫煙を燻らした。
柔らかい陽射しが上空から降り注いでいる。遮るものが何もないにも拘わらず、今の司馬は太陽の光をこうして直接浴びることがとても気持ち良かった。時折、思い出したように吹き抜ける風も、肌を優しく嬲るばかりで、何の障壁にもならない。毎日、持て余すほどの時間を使いあぐねている筈なのに、ここで殊更にゆったりと感じられる時の流れは、病室にいる時よりも遥かに有意義であるように思わせ、また、司馬の中にごく普通の素直な感情を湧き上らせつつあった。
隣で同じように呆けている一倉の方をそっと盗み見た。
何故、今日一倉が自分の見舞いにやって来たのか、司馬にはさっぱり解らなかった。刺されたときの事情聴取についてはとっくに片がついている筈である。その後、ある男の写真を見せられたものの、自分が全く知らない人物だったのだからそうとしか言いようがなく、その答えに納得した筈のこの男とは、もう二度と関わることは無いだろうと思っていたのだが・・・
そういえば、礼を言ってないな―――
しかし、一倉が感謝の言葉聞きたさにわざわざ訪ねてきた訳では無いだろうと、司馬は本能的に感じていた。ならば他のどのような理由に拠るのかということになると、これと言ってしっくりくる考えは無く、自分が目覚めるまで一倉が病室に付き添っていたことと関係があるような気が漠然とするだけだ。そしてそれは、何か得体の知れないものに身の回りを取り囲まれているような不安を司馬に与えたが、どういう訳か不信感とは無縁だった。
尤もここ、警察病院で初めて顔を合わせた時の事情に限れば、実際には一倉がずっと病室にいた訳ではなく、平賀の事情聴取に立ち会ったり二人の身元確認を取ったりして、ある程度時間が経った頃、再び病室を訪れたに過ぎなかった。だが、真相を知らない司馬からすれば、目を開けて最初に飛び込んできたのが担当医ではなく見も知らぬ男だったのだから(ずっと付き添ってくれていたのかも?)と誤解するのは当然であり、これも暫くは一倉側に有利に働いた。
司馬の思い巡らしていたことをまるでこの透明な空気を通して一倉に伝えたかのような科白が、何の前触れも無しに零れてきた。
「前に君が訊いたっけな・・・何で、助けたのかって」
「ああ、その事は、もういいですよ―――あんなこと訊くなんて、僕も、どうかしてたんでしょう。警察が民間人を助けるのは義務ですから」
本当はその答えを聞きたくてたまらないのに、何故か知らない方がいいような気がして、気がつくと司馬は自分の方から会話の芽を摘み取っていた。
「まあ、な・・・」
そんな司馬に逆らうでもなく、一倉は相槌をうった。
暫し、時の流れが止まったようだった。だが、それは決して苦痛ではなく、寧ろ居心地の良い倦怠感を心と身体の両方にもたらしはじめていた。
一倉が再び沈黙を破った。
「あの平賀という男を所轄に―――駆けつけた警官に引き渡してから、オレも救急車に同乗して・・・そこで、初めて君の顔をよく見た」
司馬は黙って、話の続きを待った。
「驚いたよ。君が、その・・・オレの知っている人間によく似てたんでね。他人の空似とは思ったが、それにしても本当にそっくりでな―――で、気になった」
一倉の眼差しが自分の横顔に注がれているのを気配で感じて、何故か司馬は顔が上げられなくなっていた。そんな司馬の心情を知ってか知らずか、隣の男はただ紫煙を吐き続けていた。
「似てるって・・・誰と?」
司馬の発した言葉に、今度は一倉が慌てたようだった。
「あなたとどんな関係にある人と、僕が、似てるんですか?」
別にどうでもいいことの筈だが、自分が誰に似ているのかと訊いた途端、一倉が瞬時戸惑ったのが手に取るように判って、司馬の好奇心が疼きだしていた。
「関係か・・・そんなに深い知り合いじゃ、ないんだが―――強いて言えば、恋敵、かな」
元々告白するつもりだったのか、それとも司馬が今日初めて自分に興味を示し、差し向けた質問に答えてやろうという義務感からか、一倉はさらりと言ってのけた。
「恋敵??」
思わず司馬は訊き返していた。一倉は、まるで他人事のように淡々と話を続けた。
「想い人の恋人だから、やはり恋敵ってことになるんじゃないのかな」
司馬は押し黙ってしまった。
(フツー、逆じゃないか? 想い人に似てるってんならともかく恋敵の方に・・・だったら、助ける気、失せるだろ)
混乱し始めた頭を整理しようと、司馬は一際深く息を吸い込んだ。肺の中がほろ苦い空気で満たされていくのを直截に感じ、なぜか気持ちが軋んだ。
警察官という職業柄、義務だから致し方なく助けたというのなら、納得もする。だが、恋敵なんかに似ていたら、いくら他人と判っていても、二度とその顔を見たくないと思う人間の方が大多数であろう。それに一倉ほどの役職からすれば、事情聴取の立ち会いも写真の確認も、何人かいるに違いない部下の一人へ代行させられる程度の事案に思われた。
にも拘わらず、今日は自分をわざわざ見舞いにまで来ている隣の男の心理が理解出来ない司馬は、不思議そうな視線を一倉へ向けた。
「ああ―――そういう表情なんか、本当によく似てるな」
別に嫌そうではなく、寧ろ面白がるみたいに言われて、司馬はどうしたらいいのか判らなくなってしまった。
「そんなに、そっくりなのか? ソイツと・・・俺と」
独り言のつもりで呟いた小さな疑問は、しかし、一倉の耳にもしっかり届いていた。
「そう、瓜二つってやつだ。尤も、アイツの方がややふっくらしてるな―――お前、痩せ過ぎだ」
「ウルセえな」
思わず同年齢の人間にきくような口調で言い返してしまった司馬は内心焦ったが、自分を見ている一倉の瞳にひどく心配そうな色を認めて、さらに狼狽することになった。
「怪我してるとはいえ、もう少し太った方がいいぞ」
司馬にひたと据えられた視線はとても優しく、病室で自分が目を覚ました時に一番最初に見たあの時の顔と全く同じだった。
「・・・大きな、お世話だ」
不貞腐れたような物言いに自分でも気恥ずかしさを隠せず、相変わらずこちらを見つめている柔らかい瞳から、司馬はとうとう目を逸らした。
「おう、少しは元気、出てきたな―――安心した」
一倉は司馬の頭をポンポンと軽く叩き、満足そうに頷いた。
その大きな手から伝わってくる暖かさは、遠い日の懐かしい感触を司馬に思い起こさせた。その後も、時々心地よい沈黙を挟みながら一倉と司馬はとりとめのない話を屋上で続けた。
思いつくままにポツポツと会話を重ね、触れられたくない話題にさしかかると互いに無視した。尤も、はっきりとそうしたのは司馬の方だけで、一倉は巧妙に科白を転がしつつ、常にその局面を難なく泳ぎきっていたのだが。
一体どれくらい、話していたのか―――気がつくと屋上には自分達の他に誰もいなくなって、西の空を太陽の光がオレンジ色から朱色へのグラデーションに染め抜いていた。
「そろそろ、戻るか?」
一倉から切り出されるまで、時刻のことをすっかり頭から追い出していた自分に気がついて、司馬は少々驚いていた。
元々、担当医や看護婦としか言葉を交わさない入院生活である。あり余っている時間は、多忙だったあの頃、中々手をつけることの出来なかった医学書の読破に充てている。それなりに充実し、満足している毎日の筈だった。だが今日、突然ふらりと見舞いにやってきた一倉との他愛無い会話は、司馬に不思議な安らぎを感じさせていた。
一つには、一倉が相手を詰問するようなことをせず、ひたすら無駄でしかない会話を重ね続けたことに依り、司馬の警戒心が少しく緩んだからだった。都合の悪い問いを前にして口下手な自分が押し黙ってしまっても、それに対して急かしたりせず、隣で煙草を燻らしながら、ただ相手の存在をそのまま受け止めているかのような配慮が、かえって司馬をリラックスさせる結果となっていた。
黙って隣にいるだけなのにも拘わらず、こんなにも気を遣わないで済んだ存在は、司馬にしてみても初めて遭うような気がした。
一倉は揃えて置いてあった松葉杖を司馬に手渡しながら、訊いた。
「なあ、下の名前―――何ていうんだ?」
いきなり何を言い出すかと思えば、名前を尋ねられて、司馬は目を瞬かせた。
「―――江太郎」
「こうたろう? ええと―――どんな字だ・・・?」
司馬は自分の名前を漢字でどう書くか、一倉に教えた。
「フーン・・・いい名前じゃないか」
「何、トボケたこと、言ってんだよ? 俺の名前なんて、とっくに知ってる筈だろ? 事情聴取にも立ち会ってんだから、さ」
相手が何を言いたいのか判らず、司馬は思ったことをそのまま口に出した。
既に数時間を共に過ごした二人の間でかわされる言葉使いは、よそよそしい敬語や慇懃な丁寧語に彩られることはなく、いつの間にかごく慣れ親しんだもの同士のそれへと変わっていた。
「まあ、いいじゃないか。お前から直接、聞いてみたかったんだよ」
「アンタも、ヘンな奴だな」
司馬は溜息を吐いた。そんな自分の様子を可笑しそうに見ている一倉の顔を見ても不快にならないどころか、むしろ安堵してしまうことに合点がいかないものの、それを上手く理屈で説明することは、今の司馬には到底出来そうになかった。
病室まで司馬を送り届けると、一倉は置きっぱなしにしてあったアタッシュケースを取り上げて、出ていった。
別れ際に、
「じゃあな。ちゃんと食って、少しは太れよ」
とだけ言って帰っていった後ろ姿を見送りながら、司馬はまた一倉が自分の見舞いに来るのではないかという、根拠の無い予感を抱いた。そして、それが己の自意識過剰な思い込みでなかったことは、割とすぐに判明したのである。湾岸署の一会議室に拠点を移して、管内に於ける黒田の足取りを本格的に洗い出し始めた一倉達は、昼夜共に忙殺された生活を送っていた。連日の聞き込みと裏付けと張り込みに終始する諜報活動は、長期化するにつれて、再び倦怠とマンネリと苛立ちを殆どの捜査員の内に蘇らせつつあった。
一倉自身も目新しい発見の得られない現実に、やり場の無い怒りを抑え込むのがいいところであり、それを部下達に気取られないようにと心を砕く毎日が続いていた。
そして、己の堪忍袋の限界が近づくと一倉は決まって入院中の司馬を訪ねた。
大部屋に移ってからも、相変わらず他人と積極的に交わろうとしない司馬だったが、この多忙な警察官僚は自分勝手なスケジュールの許に病院にやってくると、患者側の都合へは一切耳を貸さず、あの手この手で司馬を宥めすかして屋上まで引っ張り出し、そこで煙草を燻らした。
長閑すぎる時間を一頻り共有した後、「また来る」と言い残して帰っていく背中に「もう、来んなよな」と悪態をつくのが習いになっても、助けてもらったという負い目の所為からか、再びやって来る見舞客を無下にあしらうのが今の司馬には難しく、結局、一倉の訪問を拒めずに受け入れさせられつつあった。
そして一倉が己を見舞った回数が片手を超えた頃、司馬はいつの間にかそれに慣れ始めている自分に気がついた。表向きは毎回嫌そうな顔をしてみせても、だんだん、突然やってくる一倉の存在をごく自然な日常の一部として認めるようになったのである。
晴れた日は屋上へ出て、雨の日は待合室の片隅に腰を落ち着けて―――二人の間で交わされる会話の九割までが無駄話であり、どうでもいいことの集大成だった。一倉が主に質問し、司馬はその中で自分が答えたいものだけに言葉を返した。
一倉が訊ねる内容は実に多岐に渡っていて、最初は「全く、精神分裂のケがあるのかと思ったぜ」とまで司馬に言わせたが、それにはちょっとした訳があった。種々雑多で似たような問いかけを何回にも分けて細かく繰り返すことにより、一倉は司馬が対人用に築いている精神的な防御壁の中に分け入り、内側で息を潜めている本当の姿に触れようとしていたのだった。
様々なデータから司馬の過去を洗い出した一倉には、どうしても引っかかることがあった。それが東都医科大の研究室にいたころの司馬と中川・現天真楼病院外科部長の関係だった。
当時の中川研究室をよく知っている人間からも証言を取ったが、話が二人のことに及ぶと皆一様に口を閉ざす傾向が認められ、一倉はその度に首を傾げることになった。
果たして、過去、二人の間に何があったのだろうか―――集められるだけ集めた情報を次々と篩いにかけながら、残った断片一つ一つを丁寧に嵌め込んでいってもどうしても埋まらないその空白に、重要な鍵が隠されているような気がしてならなかった。そして、その自分の勘に従い、一倉は忙しいさなかに無理矢理捻り出した時間を使って、数日前にも或る女性に直接話を聞きにいったのだった。
結果として、やはり彼女の口も堅く大した話を聞くことは出来ずに終わった。
「私にも、ほんとうのところは分からないんです―――何故、司馬が変わってしまったのか・・・」
しかし、その困惑したような口調から、一倉は彼女が真相に近い事実を探り当てているらしいことに気がついた。多分、証拠が無いのだろう。また、それは憶測で話せるほど簡単な事情ではないことをも匂わせていた。
「司馬は、決して周りで言われてるような人じゃ、ないんです」
「患者には冷たく、打算的で金に汚くて平気で嘘もつく―――そういう人物では、ないと?」
「ええ。それらは、端で見ていて判る特徴なだけですから。司馬は、いろいろ苦労をしてきた人です。だから、他人の痛みも判っていた筈だと、私は信じてます」
これはあくまでも自分の想像に過ぎない考えだから口にする訳にはいかないのだと、彼女はそれ以上司馬と中川について語ることを頑なに拒んだが、一つ、貴重な情報を一倉に与えてくれた。
―――嘘、つくときに、ほんの僅かだけ視線を泳がせるんです・・・よく、見ていると判ります。司馬の癖・・・なんです・・・昔から・・・
一倉は天真楼病院勤務の麻酔医で司馬の恋人だった大槻沢子の言葉をしっかり自分の中にしまい込み、それから後、司馬と顔を合わせて話す際には、いつも注意深くその表情を窺うようになった。しかし、当の司馬はそんな経緯を知る由もなく、思い付くままに一倉から浴びせられる質問をかわし、また、答えるのが精一杯だった。連日ではないにせよ、数日おきに湾岸署へ室井が詰めているにもかかわらず、青島は実に面白くない気分を味わっていた。
今日だって、せっかく同じ建物の中にいるってのに、顔も見れないし声も聞けないんだもんな―――
自分の席で苦手な報告書作成に渋々従事しながら、時折廊下の様子を窺う。時刻はそろそろ正午になろうかというところで、運が良ければ昼食を摂りに降りてくる室井の姿が見られるかもしれないからである。
なんか、俺って、ケナゲ・・・
ふかしていたアメリカン・スピリットをアルミの灰皿に押し付けていると、後ろから真下の声が降ってきた。
「せんぱーい、昼、ドコ行きますー?」
緊張感の無い年下の上司に向かって、青島は頭を仰け反らせるようにして答えた。
「そーだな・・・久しぶりに、腹に溜まるモン、食いてーな」
「じゃ、『とん平』にしますか」
室井さん、ちゃんと食べてんだろうか・・・あの人、根詰めると食欲がどっかにいっちゃうから心配なんだよな―――
ついつい思考が、室井の方へと向かってしまう。そんな青島の心中を知ってか知らずか、真下が焦れたように催促した。
「先輩! 早くしないと、ロースかつ定食、売り切れちゃいますよー?」
「わぁーった! 今、行くって」
諦めて席から立ち上がり、真下に続いて部屋を出ようとしたところで、青島はすれ違い様にいきなり凄まじい勢いで腕を掴まれ、驚いて立ち止まった。
「青島くん!」
すみれだった。たった今、外から大急ぎで戻ってきたらしく、透き通るように白い肌がうっすらと上気している。
「一体、なんなの?」
形の良い瞳にくっきりと怒りの炎を宿らせているすみれが、真っ直ぐに青島を見つめると、左手の人差し指で軽く上方を示した。それを受けて、青島は困ったように目を瞬いた。憤怒の矛先が、最上階の会議室に詰めている警察庁の捜査員達に向けられているのは歴然としていた。軽く頭を掻くと、ごく普通の口調でその疑問に答える。
「何―――って、さあー・・・俺だって、詳しいことは知らないけど・・・大分前に課長から、コッチ、通常業務だって言われたじゃない」
「そんなこと、判ってるわよ。でも、青島くんなら、室井さんから何か聞いてるんじゃないの?」
その剣幕に圧されて、心持ち後退ってしまう。(だって、本当に聞いてないんだから、しょうがないじゃんか)という正当な弁明をグッと呑み込み、青島は言葉を選んで続けた。
「調整役で来てるってコトしか、聞いてないって―――マジな話。で・・・それが、何か?」
すみれの目が綺麗に釣り上がった。
「・・・どしたの? 何か、あった?」
おそるそおる訊ねると、間髪入れずに返ってきたのは一分の隙も無い厳しい声だった。
「あんたには関係ない。それより、室井さん、どこ?」
「どこ・・・って、上の会議室にいるんじゃ、ないの? ちょっと、すみれさん? 上、俺達所轄は、立入禁止―――」
青島の声を後ろに聞き流して、すみれはエレベーターホールへと飛び出していった。To Be Continued・・・・・
(1999/7/3)
へ戻る
−第5話に対する言い訳−
作者から一言―――仕事してんのか? 一倉(爆)
警察病院の場合、出られるのかどうか知りませんが、『振り奴』では大事な(?)会話は全て天真楼の屋上で交わされているので、書きたくなってしまいました。一倉が煙草を吸うかどうかについては、多分、室井さんと同じだろうと思いまして。警察入るまでは、吸ってたのではないかなーと。
一倉と沢子先生との科白のやり取りも、実はあの三倍くらいありましたが、悠に一話分の文字数くらいになってしまったので泣く泣く削りました。
最後の方で、すみれさんがかなり怒りまくっていますが、これはチョット八つ当たりかもしれないです。でも、前回スリアミ出したし、やはり湾岸署といえばすみれさんと真下くんには最低でも出てもらわないとね…ということで出演してもらいました。
しかし、真下くん、次の回では科白一つで終わりそうです(爆)