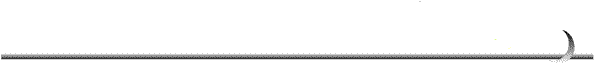百年の孤独 6
(なんなんだよ? あれ・・・)
目の前で爆弾を破裂させ、その身を翻して駆け出していったすみれに置き去りにされた青島は、呆然とその場に立ち尽くしていた。少し前方では真下が、これまた自分に負けず劣らずのあっけにとられた顔をして、エレベーターホールの方を見遣っている。
青島が何気なく振り返ると、おそらくすみれと一緒に外から戻ってきた武がちょうど席に着こうかというところだった。普段は爽やかな好青年という印象が強いその顔をどんよりと曇らせた様は、まるでどこかのお通夜から帰ってきたばかりのような感じを与えていた。青島はそのまま盗犯係の島へ足を運ぶと、元気なく椅子に腰掛けた武に声をかけた。
「あの・・・さ、すみれさん、どーしちゃたの・・・?」
「それがですね・・・」
武は青島の方に向き直ると、神妙な面持ちで事の顛末を話してくれた。
本日午前中、大凪町で起きた二人組の窃盗犯に関するちょっとした騒ぎが、すべての始まりだった。
湾岸署管内では、年明けから一人暮らしの女性ばかりを狙った悪質な窃盗事件が相次いでいた。どうやら二人組で犯行を重ねているらしく金品に限らず下着等にも手をつけており、また、コソ泥にしては手口も込んでいて捜査は難航を窮めたが、盗犯係総勢(といっても三名だが)の地道な努力により漸く被疑者の特定ができて、いよいよ逮捕するまでに漕ぎつけていたのだった。
そして本日午前中、開店直後のパチンコ店から手配書にあった男達に間違いない連中が現れたとの通報が入り、それを受けたすみれと武が現場へ急行した。そして、その場で令状を翳しすんなりと逮捕できる筈だったが―――管内にうじゃうじゃといる警察庁の捜査員が現場に混入したせいで、被疑者にまんまと逃げられてしまったのである。
五ヶ月近く、その男達の逮捕に向けて奔走してきたすみれの怒りは凄まじいもので、現場でも一悶着あったらしいのだが、エリート意識の塊である警察庁の捜査員が自分達の不手際を認める筈が無いだろうということは青島にも容易に想像がついた。
「戻ってくる途中も始終無言で・・・かなり、怒ってましたから・・・」
困惑したような表情で武が青島に訴えた。
「しかたないですよって言ったんですが・・・あんなに怖い恩田さんの顔、初めて見ました―――」
怒り心頭に達したすみれが室井に抗議しようと息巻いて署に帰ってきたのは、もはや火を見るより明らかだった。だが、現在の室井の立場ではすみれに手を貸してやれることは殆ど無いだろうこともまた、青島には判っていた。尤もすみれにしたところで、怒りに任せて感情をぶつけた後、せいぜい自己嫌悪に陥るのが関の山であろう。
刑事部屋の出入り口まで戻ると、青島はエレベーターホールの方へと身体を向け、一歩踏み出した。後ろから真下が、
「先輩! メシは? 行かないんですか?」
と非難めいた声を発したが、青島は心持ち振り向くと、「悪い、ちょっと―――」と左手を顔の前に上げて詫び、早足で歩き出した。
怒りにうち震えた小柄な後ろ姿を追いかけて来た青島が最上階の会議室の前まで来ると、丁度廊下の片隅で、室井を捕まえたすみれが激しく詰め寄っているところだった。
「どういうことなんですか」
まだ青島の姿に気づいていない二人はそのまま張り詰めた空気の中で一歩も引かず、正面から対峙していた。
室井がその激した感情に呑み込まれまいとして、殊更に穏やかな声ですみれを宥めようとした。
「君達所轄に迷惑をかけるつもりでは無かった、と思う。こちらの捜査員も極めて重要な人物を追っていて、偶々、そちらの邪魔をしてしまったんだろう」
「当たり前でしょ?! 悪気があってたまるもんですか」
すみれの瞳が一層大きく見開かれた。
「問題のあった捜査員から今、事情を訊いている。報告書を出させて、署長と刑事課長に―――」
「そんなもん、いらないから―――」
室井の言葉をいきなり遮ると、すみれはきっぱりと言い放った。
「逃した被疑者、あたしに返して!」
青島はまるで自分が怒鳴られたかのようにその場で凍り付いた。
ピリピリと音がしそうな空気の震えが手に取るように伝染してきた。室井の立場もすみれの怒りも今の自分には直に沁み込むほどに受け止めることができた。
青島は二人に気づかれないようにそっと移動し、非常階段の脇へ行くと、防火扉の影にその身を滑り込ませた。
室井とすみれが向かい合っている位置から少しく離れざるをえなかった為、全ての声が聞き取れる訳ではなくなったが、それでも大体の会話内容が把握可能であり、青島の耳を心を容赦無く突き刺し、抉った。
「どうして、こんなことになるの?!」
低い声で突き放す、すみれの口調には激しい憤りが滲み出て、もう手が付けられない状態にまで高まっていた。
「いつだって、勝手にやってきて、ウチの管内、引っ掻き回してばかり!」
対する室井の声が何も聞こえてこないことが、青島の心を苛みはじめる。およそ警察官僚の中で所轄の現実を一番理解している室井にすれば、こんなかたちで責められるのは何よりも辛いだろうということが青島にもよく判る。室井の痛みが自分のもののように感じられて、知らず知らずのうちに身体に両手を廻し、しっかりと掻き抱いていた。
「下で這いつくばってるあたし達が追っている事件のコトなんか、どうでもいいって訳?!」
ここからではよく見えないが、おおかた顔面中に苦渋を張付かせ黙ったまま耐えているに違いない室井に、すみれが尚も追い討ちをかける。
「なんとか、言いなさいよ!!」
出ていって、止めなくちゃ・・・このままじゃ、室井さんもすみれさんも、傷つくばっかだ―――
頭ではそう考えても、二人の間に割り込むタイミングが掴めず、青島は扉の陰で苛々と様子を窺っていた。
「済まない―――今回、私には、指揮権が無いんだ・・・」
室井が一言だけ、悔しそうな声で詫びた。
だが、それで納得するすみれではなかった。
「何、それ―――この前だって、そうだった・・・去年だって、それで痛い目にあったんじゃない」
心底許せないという表情を湛えて、すみれが室井をねめつけた。
「あの時・・・あんた―――青島くん、刺されて、懲りたんじゃなかったの?!」
すみれの一撃に、室井が息を呑んだ。
「チョット、すみれさん!!」
その言葉が耳に飛び込んできた途端、青島は突き動かされるように二人の前へと走り出ていた。会議室の一角にパーテーションで簡単に仕切られただけの打合せコーナーから1係の捜査員二人と共に出てきた一倉は、部屋の中をざっと見回して、室井の姿が無いことに気がついた。
時刻は正午をまわっている。
(先に、昼、食いに行っちまったかな)
それでも、一応近くの捜査員に声をかけた。
「おい、室井参事官は、昼飯か?」
出入口にほど近い席に座っていた彼は急に質問されて面食らったような顔をしたが、少し前の室井の行動を一所懸命思い出そうとした。
「いえ、食事でしたら白板にその旨書いていかれるかと思いますので・・・単に席を外されているだけかと・・・」
なるほど、几帳面な性格の室井だけに余程のことが無い限り、ボードへ何も書かずにいなくなるということは考えられないことだった。
(なら、近くにいるのか。今日こそはあいつに飯を食わせんとな)
昨日、正午近くに飛び込んできた刑事局からの別案件に手間取り、結局タイミングをずらしてしまった室井はとうとう昼食を摂るのを諦めていた。人一倍根が真面目なあの男は、常に目前の仕事を優先させがちである。キャリアともなれば同期といえども一緒に仕事をすることは希であり、決して褒められない室井の癖も一日中行動を共にして初めて一倉が知ったことだった。
(大体、あいつは手を抜くってことを知らんからな。その辺で、くだらないことに煩わされてなければいいが・・・)
答えてくれた捜査員に頷いてから廊下へ出ると、一通り周囲を見回してみる。
次の瞬間、廊下の片隅で室井と青島とすみれの三人が立ち竦んでいる姿が視界に飛び込んできた。そのあたりに漂う剣呑な空気を敏感に感じ取った一倉は、ちょうどいい具合に突き出ている柱の陰に身体を寄せて凭れかかると、黙って事の成り行きを見守ることにした。「ちょっと―――なんで、青島くんがここにいるのよ? お昼、行ったんじゃなかったの?」
姿を現した青島にすみれが少しばかり困惑したような表情を見せた。
「だって、すみれさん、急に飛び出してっちゃうから・・・その、気になって・・・」
すみれに視線を合わせながらも瞬時室井の様子を窺った青島は、清冽な瞳が苦しそうに歪んでいるのを見逃さなかった。
なんとも気まずい沈黙が訪れた。先程すみれが発した一言によって充分険悪になったその場に青島が割り込んだことで、また違った居心地の悪さが生じ、不快指数を増幅させていた。
しかし、この張り詰めた空気を破ったのは闖入者である当の青島だった。
「武君から、聞いた・・・その、今日の、午前中のこと―――」
すみれは無言のまま冴え冴えとした冷たい瞳で青島を見据えた。
「なら、黙ってて!!」
突き刺すような視線が向けられた。取り付く島の無い沈黙が再びあたりに蔓延し始める。たった数十秒の間のことがまるで何十分も時間が経過したように三人の動作を張り付かせた。
青島はすみれの棘のある眼差しからつい目を逸らしそうになる自分を必死で立て直し、息を整えゆっくりと一言一言噛み締めるように話し出した。
「しょうがない、なんて言う気、ないよ。すみれさんの気持ち、判るから・・・でも―――」
室井とすみれが同時に軽く目を見開いた。
二人の視線を受けて、動悸が激しくなるような息苦しさに襲われる。
「だけど―――コトは現実に起きちゃったんだから・・・ここで、揉めててもどうにもならないじゃないか。俺達、支店の苦情は苦情として陳情して、その後はまた最初から犯人を追っかけ直すしか、ないじゃないか」
室井か無念そうに目を瞑る。その姿が何もできず寧ろ所轄に迷惑をかけるだけの立場をどうにも出来ない自身の不甲斐なさを責めているようで、青島には辛かった。
「そんなこと、言ったって―――!!」
凛とした声が空間を容赦なく切り裂いた。だが、その語尾には微かな震えが感じられて、怒りの臨界点に達したことを青島に教えた。
砕け散りそうな感情を必死に押し留めているすみれの正面まで歩み寄ると、軽く肩に手をかけてダメ押しする。
「俺達には、俺達の仕事があるだろ?」
澄んだ瞳は、瞬いた途端、眦に湧き上がりつつある大粒の涙を零しそうである。
「もどろ、すみれさん・・・昼、食いに行こ―――ね?」
こくりと頷いた弱々しいすみれの身体を後ろから支えるようにして非常階段の方へ向き直らせてから、青島は顔を捩り、極めて冷静な口調で室井に告げた。
「湾岸署からは署長と刑事課長連名で書類提出しますから、きちんと処理してください。よろしくお願いします」
「判った。今後このようなことが無いよう―――善処する」
室井の態度にいつもの誠意を確認した青島は軽く頭を下げると、すみれと並んで非常階段を降りて行った。「青島くん・・・どうして・・・」
音も無く隣を歩いていたすみれの囁きが、周囲の壁に反響して跳ね返ってきた。青島は少し歩幅を縮め、意識して移動するスピードを落とした。次に叩きつけられる筈のすみれの感情を黙って待つ。だが、予想に反して彼女は何も言わなかった。
「・・・さーて、何食おっか?」
何事も無かったかのように話し出した青島から数歩遅れて、すみれが立ち止まった。一足先に踊り場へ着地した青島はそこで振り返ると、そのまますみれを見上げた。
「いつから、あそこにいたの・・・?」
青島は俯くと、黙ったまま軽く頭を掻いた。困ったように視線を泳がせるその様子から判断して、かなり前からあの場所で室井と自分との会話を聞いていたのは、間違いないのだろう。
「・・・ありがと」
すみれの発した一言に、青島が顔を上げた。鳶色の瞳が丸く見開かれてこちらを見上げているのを目にして、自分の胸中に何か暖かいものがじわりと拡がった。
「心配してくれたんだ?」
「ん・・・まあね・・・」
ぼそりと青島が答えた。
すみれは深呼吸すると再び階段を降り始め、青島の脇を通過した。まだ強張っているであろう己の顔を見られないようにと、後ろから慌てて追いかけてくる姿の数段先を歩いた。
「あのままだったら、あたし、室井さんに言っちゃいけないことまで言ってた・・・」
狭い非常階段は小さな呟きをも四方の壁で受け止め、幾つものこだまに変換し、その場に還元してきている。
「判ってる―――室井さんにも、多分、どうにも出来ないコトなんだって・・・だけど・・・どうしても、我慢できなくて・・・」
自分に言い聞かせるように言葉を続けるすみれを青島の穏やかな声が遮った。
「もう、いいよ、すみれさん・・・」
柔らかく包み込まれるようなその言い方に、思わずすみれは振り返っていた。
青島は小走りですみれのいる場所まで追いつくと、真剣な表情で対峙した。
「俺だって、すみれさんの立場だったら、きっと室井さんに喰ってかかってるよ・・・でも―――」
室井と同じように真摯な瞳を正面から見据えて、ゆっくりと告げる。
「俺達は俺達に出来る仕事をするしか、無いでしょ?」
すみれが青島に向かって小さく頷いた。それを合図に二人は並んで歩き出した。
「大人だね・・・青島くん・・・」
正面を向いたまま、すみれが話しかける。声に茶化すような風情はさらさら感じられず、青島は真面目な気持ちでそれを受けた。
「別に・・・そんなんじゃないけどさ・・・」
発した声はごく自然な軽やかさを伴って、言葉を紡いでいく。
「室井さん、指揮権無いって、言ってたじゃない? 多分、あの人も詳しいこと、知らされてないんだよ」
すみれは黙って次の科白を待った。
「『なんで、こーなったの? どーしてくれるの?!』って喚くのはカンタンだけど、その間にも被疑者は遠くへ逃げてくし、新しい通報は入ってくるし、さ―――」
今や、すみれも青島が何を言わんとしているのか、朧に理解しつつあった。
「俺達にやれることは、目の前にあるものを一つ一つ、手抜きしないで片付けていくことだ―――俺達にしか出来ない仕事をするっきゃ、無いでしょ?」
どんな時でもへこたれず、前向きな考え方を以って対処にあたり、何事にも最大限の努力を惜しまない同僚の一言は、すみれを元気づけ立ち直らせる力を持っている。それは昨年秋のとある日にもいかんなく発揮され、そのおかげで自分は今この職場に留まっているのだと思うと、先般、迸る激情にかられて取った自分の行動が恥ずかしくなった。
「信じてるんだね・・・室井さんのこと」
「へ?!」
「だって、そういうことでしょ? 室井さんなら所轄のことを考えてくれてるって思ってるから、あの人なら支店が上げた苦情をちゃんと処理してくれるって信じてるから―――あたしのこと、止めにきたんでしょ?」
こんなにも心から信じられる相手を見つけた青島を素直に羨ましいと思った。
「・・・―――俺達の思い、実現するまで頑張ろうって、約束したから・・・さ・・・」
すみれの視線が自分の方に向けられているのを感じて、青島は天井を振り仰いだ。
そう、室井さんが一々説明してくれなくても、正しいことをする為に頑張っているんだってこと、俺はもう疑わない。
だって、信じてるから。あの人は、俺の信じた男だから―――
言葉や態度で確認し合うこともたまには必要だろうが、目に見えない大事なものをしっかり掌中に納めている青島の姿は、室井に揺るぎ無い信頼を寄せている確かな事実を物語っていた。
その青島の横顔を見ながら、すみれは自分も気持ちを切り替えることにした。途端に、お腹の虫が騒ぎ始めていることを気づかされ、いつもと変わらぬリズムが体内に戻ってきていると確信する。
「『とん平』のロースかつ定食!」
隣でいきなり叫ばれて、青島は目を白黒させながら声の主を見返した。
「青島くん、急いで! 売り切れちゃう!!」
「・・・ちょっと、すみれさ〜ん、今からじゃ多分、ダメだと思うんスけど?」
おたおたと腕時計を見遣り現在時刻を確認しつつ、情けない声ながらも一応、訴えてみた。
「そんなの、行ってみなきゃ、分かんないでしょ? ホラ、早く!」
振り向き様ににっこり笑ったすみれの表情は、いつもの快活さを取り戻していた。一歩先に走り出したその後姿に漸く安堵した青島も、弾みをつけると勢いよく階段を駆け下りた。To Be Continued・・・・・
(1999/7/24)
へ戻る
−第6話に対する言い訳−
すいません…イチシバ話なのに、すっかり湾岸署オンリーの回になってしまいました。よくも悪くもすみれさんの所為です、これは。
すみれさんは秋SPの時に裏切られたので(室井を)信じるのを止めてたんだけど、THE MOVIEで刺された青島とその時の室井の行動を間近に見て、青島に免じてもう少し刑事をやっていこうかな&室井のこともまた(少しだけ)信じてみようかな…と思っています。だけど、一種の不可抗力で被疑者を逃すことになり、今回、調整役が室井だったせいで甘えが出てしまう―――それを青島に止められて、また前向きになるという感じでしょうか。彼女は心のどこかで室井のことを仲間の末席(笑)に加えていると、私は思っているので。だからもし、(調整役が)新城さんだったら、わざわざ突っかかりには行きません、ウチのすみれさん。3話脱稿時にブーイングメル(笑)をくださった新城ファンの皆様、この話を作るにあたって、私が新城さんを出さなかった理由の一つはここにあります。
ところで、当初予定していた話と既に大分違った展開になってしまい、書いてる人間が今、一番おろおろしています(泣き言) この次に一倉と司馬が顔を合わせるところまでが、本来の予定箇所でした。丸々3/4話分、次の回にズレ込んでしまったので、ちょっと7話の構成を考え直します。
あああ、なんでこんなことになってしまったんでしょお……