 関富士子のエッセイ・小話など
関富士子のエッセイ・小話など 「関富士子のエッセイ」 もくじへ
「関富士子のエッセイ」 もくじへ
月一回東京都目黒区は緑が丘のコミセンに、詩の好きな連中が十人ばかり集まる。メンバーは、ヤリタミサコ、田村奈津子、豊田俊博、水根たみ、佐藤詠子、藤富保男氏ほか。詩を読んだり批評をしたり、日常を離れた至福のひとときである。拙詩集「蚤の心臓」の半分はこの会から生まれた。ときには藤富保男氏の出題による文章が宿題になる。文章を書くのはあまり好きではない。詩を書くようには興奮しないのである。年に一度小さな文集「COLOUR」にまとめる。そこに掲載したものやしなかったものなどをいくつか集めた。
(題「名前」)
植物の名前
一年ほど前からデジタルカメラで花を撮っている。もう千枚ぐらいになるだろうか。初めのころに撮った写真を見ると、あまりにピンぼけで恥ずかしい。花のおしべやめしべ、小さい柔らかい刺や繊毛がくっきり撮れるとうれしくなる。
画像をトリミングして名前と撮影した日を付けて、インターネットに開設しているHPにアップする。花の好きな人が訪ねてくれて、いっしょに楽しんでくれればいいな。名前を間違えてはたいへん。植物図鑑はもちろん、インターネットでも検索して調べていると、楽しくて時のたつのを忘れる。
こんなことを始めてようやく、今まであまりに花の種類も名前もろくに知らないですごしてきたのに気づいた。
春の田んぼを歩くと、小さく可憐な花が咲き乱れている。その日畔のあちこちに目立ったのは、輝くような黄色の五弁花である。緑がかったしべが内側に反っている。花びらが落ちたあとの金平糖のような緑の実。太い茎に、三つの裂け目が大きく入った葉。調べてみるとキンポウゲ科の「キツネノボタン」だった。とたんに宮沢賢治の童話を思い出す。「どんぐりと山猫」、あるいは「土神と狐」に登場する狐は、チョッキを着込んで胸を張っている。そのチョッキに縦一列光り輝く金色のボタンはこんなふうであるか。よく図鑑を読むと、「キツネノボタン」は「狐の牡丹」と書くらしい。切れこみの深い葉が牡丹の葉に似ているからという。
「キツネノボタン」によく似た花に、同じキンポウゲ科の「ウマノアシガタ」がある。葉が馬の脚の形に似ているからというが、やはり三つに切れこんでいて馬の脚形とも思えない。これは「鳥の脚形」と間違えて名付けられたといわれる。間違えていてもわざわざ訂正しないから、ちょっと変な名前は他にもたくさんある。植物の名前は、こんないいかげんなところもなんとなく面白いのである。
「COLOUR」6掲載 2000.6.179)
(題「勘違い」)
赤い自転車
ある日いつものように自転車に乗っておつかいに出かけた。郵便局で用事を済ませてまた自転車に乗った。何かぼんやり考え事をしていたかもしれない。後ろから女のかん高い声が響いてきた。振り返ると、中年の女が手を振っている。見知らぬ人だったのですぐ向き直って自転車のスピードを上げた。するとその声は金切り声になってなにか呼んでいる。また振り返ると、女はスカートを翻し縮れた髪を振り乱して、いっそうかん高く叫びながらすごい勢いで走ってくる。必死の形相である。女は何と「ドロボウ、ドロボウ」と言っているのだ。(えっ、泥棒?)
通りの店の人が何人かそれを眺め、さらにわたしのほうを見て怪訝な顔をしている。わたしはようやく自転車を止めた。わたしから女まで二十メートルぐらいあるだろうか。女はなおも「ドロボウ」と叫ぶ。そこでふと乗っている自転車を見て驚いた。ハンドルの高さや赤いフレームの色、とてもよく似ているけれど、それはなんとわたしのものではなかった。サドルの座りごこち、ペダルの踏みぐあい、確かに違う。
わたしは呆然としてなすすべもなく、女がわたしに向かって走って来るのを見ていた。女はようやく追いついて、息を切らしてわたしを罵った。
「あんた、なにすんのよっ、わたしの自転車よ!」
「はい‥‥気がつかなくて‥‥ごめんなさい」
「わかんなかったの? あんなに呼んでんのにい?」
わたしは自転車を引いて道をとって返した。郵便局までとぼとぼと歩いた。女は呆れたのか疲れたのか、なにも言わずにいっしょに歩いた。郵便局の前にわたしの赤い自転車が置かれていた。横に並んでいたよく似た自転車を自分のと勘違いしたらしい。よく見ればメーカーだって違うし、わたしのほうが古そうだしだいいち名前が書いてある。
そこでようやく女に自転車を返して、ふかぶかと頭を下げて許してもらった。自分の自転車に乗ってみたら、やはり乗り心地がよかった。
(1999.6.19提出 "rain tree"no.15<雨の木の下で>に掲載2000.2.25)
(題「遠い近い」)
他人の日記
インターネットのホームページを散策していると、開設者の日録をよく目にする。時間軸でどんな記事を掲載したかが記録されてあるので、そこを見ればまだ読んでいない記事がどれかすぐわかるようになっている。ところが、その日録が往々にして個人的な日記風になっしまっていることが多い。記録だけでなく、忙しくて更新が遅れたという弁解から始まって、梅を見に出かけたとかで梅の花の写真が載っていたりする。これが曲者である。
印刷物の詩誌などにも日記風のエッセイをよく見るが、紙テキストだとページ数が限られていてそう好きなだけ書くわけにはいかない。ところがインターネットはスペースに制限がないから、一度書いてしまうと堰を切ったようにとりとめもなくなってしまう。世の中には自分のことを書くのが飯より好きな連中が多いのを知った。趣味の話から日ごろの喜怒哀楽、人づきあいのあれこれが詳細につづられていることもあって、ホームページの本来の掲載ものよりこちらのほうに力が入っていたりする。さらに個人的な悩みをめんめんとしたため、どんなに親しい人にも言わないようなあからさまな感情さえ公開してとめどがない。
こんな日録を読みたくもないのについ読んでいると、この人がどうも他人のような気がしない。まるで親友でもあるかのように、いっしょに一喜一憂している自分が気味悪い。相手がたとえアメリカに住んでいようと、この気分は変わらない。おとなりの奥さんなどめったに顔も合わせないのに、遠い他人へのこの奇妙な親近感はどういうわけだろう。
書くことと他者に向かって発表することの大いなる距離を、インターネットはいともたやすく乗り越えてしまった。書き手は、慣れてくるとそれをいつも見知らぬ他人が読んでいるという状態を忘れてしまう。インターネットのこの近さは見せかけのものであり、親しみは偽りにすぎないということを、読み手も書き手も忘れてはならないだろう。
(1999.3.20提出)
(題「一本」)
一本
「本」は細長いもの、棒状のものを数えるのに使う言葉だが、もともと「植物」という意味があるから、草や木を一本、二本と数える。木の繊維の束である本、これも昔は一本、二本と言ったらしい。
鉛筆はもちろん一本、二本、三本である。
クイズを一つ。一ダース入りの鉛筆のケースがあります。一本ずつ取って使いました。鉛筆は「ナンボン」残っているでしょう。うーむ、わからない。答えは三本だということだ。一本から十二本までの数字のうち、「本」を「ボン」と読むのは、「サンボン」だけだからだって。
電話は糸電話のように細長いイメージがあるから、草木同様一本と数えてもよい。留守電に伝言が三本入っている、などとも使う。しかし電話のない昔も、手紙を一本出しておく、という言い方をした。
ゆうべはビデオを二本見た、と言うが、これはビデオテープが細長いからだろうか。しかし、蛍光灯は円形のサークル灯でも一本、二本と数える。
一本がものを数える言葉である以上、あとに必ず二本、三本…という数が控えている。ただ一本だけで事足りるというものはあまりないようだ。
ご飯を食べる箸は、やはり二本でセットにして一膳である。一本ずつ両手に持ってお皿をたたいたり、里芋を一本箸で突き刺したりすると叱られる。
これが靴下になると、どんなに細長くても一本とは言わない。二本なければどうしても不足だから、「あれ、片方ないよ」ということになって、抽斗をがさごそ探すはめになる。上がつながっているストッキングも一足である。
おやつの取り合いで、一本勝負だ、と宣言してじゃんけんをしても、負けるとあきらめきれずに、三本勝負にしようと言いたくなるのは人情である。
それでは皆さん、一本じめをお願いします、と言われながら、うっかり三本、ぽんぽんぽんと打ってしまい、じろりとにらまれたことだってある。
(1998.12.19提出 「COLOUR」5掲載 1999.6.19)
(題「机の上にあるもの」)
机の上にあるもの
ほとんど一日じゅう机に向かっている。机の上は電話や事務用品や書類など殺風景なものばかり。フリーで書籍の編集を請け負っているので、ここは通常仕事場として機能する。
長いことリビングの片隅に机を置いていたのだが、この家に越して北側の六畳を仕事場に確保した。今は机のほかにOA機器や棚などで実に狭い。ロッカーは本に占領されて、服が部屋にはみ出している。雨が続くと頭の上には洗濯物がびっしり吊るされる。床には犬が寝そべっている。
夕方までは机に向かって、宅配便や速達郵便の集配時刻に合わせて仕事を仕上げている。暇なら本も読めるし、ちょっと余裕があれば手紙を何本か書いて、五時までに近くのポストに歩いて出かける。外出するのはこの時ぐらいで、家族以外のだれにも会わずに一日が過ぎることが多い。夜の数時間はパソコンをいじっている。
ときどき、机の上の本立てからノートを取り出す。子供たちが昔使ったノートのうちの一冊だ。今あるのは、表紙に4年2組と息子の名前。「ロボットはだれが作ったか」というタイトルで二ページほどの作文が書かれている。
「・・・本でしらべてみると、ロボットって言ばをつけたのは、チャペックという人らしい。あとロボットをつくった人は、エジソンじゃなくてフレミングという人らしい。・・・」
先生の赤ペンの花丸もついているが、あきっぽい彼らしくほかは真っ白である。
この国語のノート、十ミリ四方の方眼になっていて、メモをとるときにとても使いやすい。原稿用紙ほど大げさでなく、縦書きで右から左に書いていけるし、横書きもできる。今はわたしの気ままな言葉遊びのためのノートだが、日記風になったり、いつのまにか詩らしきものを書いていたりする。
わたしはこの机の前でひがな一日あきることがない。
(1998.9.26提出)
(題「胼胝」)
シンデレラのゆううつ
足の裏から魚の目や胼胝が消えて何年になるか。今のわたしの足の裏はすべすべですこぶる健康だ。
二十代は足を痛めつける毎日だった。ぴったり合った快適な靴というのを見つけることができない。新しい靴をはけば必ず数日は靴擦れだ。いつも小さな魚の目が数個、治ってはまたできる。かかとの外側も内側も胼胝である。親指の爪が肉にささって腫れ上がるときもあった。三十分もコンクリートを歩くと足が痛くなって、帰宅すると足全体がむくんでいた。そうヒールが高くもない、普通に街で売られていた靴がどれもこれもそんな状態だった。
わたしだけではない。ちょっと大きい足の人はちょうどよいサイズがなく、小さめの靴で我慢していた。ひどい人は親指が付け根から大きく内側に曲がって、足全体が変形している。外反母趾というやつだ。高く細いヒールでさっそうと歩いていた彼女の足は、ストッキングを脱ぐと見るも無残だった。
のちに会社勤めから解放されて、ふだんはくのはもっぱらスニーカーになった。自転車をこぐのにも、子供を追いかけるときも都合がよい。数年後、足の魚の目、胼胝のたぐいがすっかり消えた。早くそうすればよかった。スーツに運動靴をはいて何がいけないことがあろう。ガラスの靴で王子様と踊ったシンデレラの足は、血まみれだったという笑えないパロディがある。なぜわたしたちはあんなにつらい思いを我慢しているのか。あれは中国の纏足を思わせる拷問だと言いたくなる。
女性用の靴は形そのものが、人間の足を入れて歩くようにはできていない。見た目もきれいで足も痛めない靴が発明されたという話は聞かない。今ではわたしは大声で言うことができる。はいて痛くなる靴は明らかな欠陥商品である。直ちに回収しなさい。
でも、ふだんすっぴんの顔にお化粧をしてさて出かけようという日、わたしは押し入れからいそいそととっておきの細いヒールを取り出すのである。
(1998.5.16提出)
(題「爪」)
爪
今見るとあとかたもないのだが、昔猫とよく遊んで、手の甲にいつも無数のひっかき傷を作っていた。特に子猫は手加減を知らないから、ちょっと手を出すとたちまちじゃれついてきて、細い小さな爪でばりばりとひっかく。傷は深くはないが血がにじんでひりひりする。
親はばいきんが入ると心配するし、そんな手じゃお嫁にゆけないよと忠告してくれる大人もいたが、いっこうに平気で、ちょっとなめたぐらいでまた猫にちょっかいを出す。かさぶたができたうえから新しい傷が増えているという調子である。
現在は犬を飼っているが、この雌犬がときどき猿のマウンティングに似た行動をとる。椅子に座っている人間の足にいきなり抱き着いてきて、前脚で抱え込み、股をせわしなくこすり付けるのである。初めは驚いて発情したかと思ったが、あまり関係はないらしい。それでも人間の都合で避妊手術をしてしまっていたから、かわいそうに思って気の済むまでさせてやった。
ところが、これがたいへん痛い。人の足をしっかり押さえて爪を立てるので、スカートのときなど、ふくらはぎにひっかき傷がたくさんつく。しばらく我慢したが、犬の爪の傷は猫より深くて大きい。ストッキングをはいても大きな爪のあとが見えるのには閉口した。
あんまり人がよすぎると思って、ジーンズをはいているときに限ることにした。すると、ジーンズを見るたびにやってきてマウンティングを始める。生地がごわごわして具合がいいらしい。
かくいうわたしも、女の子どうしでけんかをすると、相手の顔をむちゃくちゃにひっかきあったものだ。「ヤマネコ」と呼ばれていたみっちゃんはどうしているだろう。
もちろん今は、爪はできるだけきれいに摘んで、色など塗っておくのである。(1998.3.21提出)
(題「憂鬱」)
芽生える
ある日、K氏の頭に憂鬱の種が芽を出した。それに気づいた時、彼は朝の通勤電車を降り、駅の階段を勢いよく駆け上がっていたのだが、不意に立ち止まって、妙にうそ寒いぼんのくぼをそっと撫でたのである。
生えたばかりの芽は、あいまいな黒い不安感といった風情で、ときどきK氏の後頭部で揺れるのだった。しかし彼は、人間存在の根源的な不可思議にさいなまれるような青くさい年代をとうに過ぎていたから、この弱々しげな若葉を、抜けるばかりの頭髪ほどにも気にしていなかったのである。
ところが、憂鬱の芽は、日に日に成長して双葉をそろえた。毎日使う専用の湯飲みにわけもない嫌悪をいだいたり、コンピューターの画面を見ただけで疲労を感じたりした。そうかと思うと焦燥感に追われて街角を歩き回った。
時間を忘れるほど集中して企画を立てているさなかに、突然分厚い雲のような無力感がK氏の頭上にのしかかるのである。あるときは、口角泡を飛ばして議論する席で、突然相手を説得すべきことばを失って立ちつくした。
そのころにはもう、憂鬱のひげ根が、白くもやもやと、スキャンで見る神経繊維のようにK氏の頭全体をおおっていたのである。
さまようように電車を乗り継ぎ、疲れ果てて家にたどり着く。家の窓には明かりも見えずしんとしている。玄関口にに座ると、犬のアレクサンダーがすり寄ってきた。空腹なのかクンクン鳴いている。その頭を撫でると、カリフラワーのような形と手ざわりのものに触れた。これは何だろう。
K氏はそっと自分の後頭部に手をやった。そっくり同じように、ひんやりと盛り上がってざらつくものがあった。そこには愁わしい憂鬱の花が、ひっそりと咲いていたのである。
(文集「COLOUR」4 1998.5.31より)
 「予定」「富士錦と呼ばれたころ」「ベルを抱える娘たち」へ
「予定」「富士錦と呼ばれたころ」「ベルを抱える娘たち」へ
 「関富士子のエッセイ」 もくじへ
「関富士子のエッセイ」 もくじへ
(題「予定」)
予定
雨上がりの光る土手に、小さな黒い手帳が落ちている。拾い上げると少しも濡れていない。だれかが今落としたばかり。あたりを見回すが、昼下がりの川べの散歩道にはだれもいない。裏表紙を開くと、持ち主の名前も書いていない。
さて、困った。近くに交番はないし、どうしたものか。私は手帳を持てあまして、そばの桜の木の、薄紅色にふくらんだつぼみを見上げた。そのままページをぱらぱらさせて、任意に開いたあたりに目を落とした。
*10月21日 燕家送別会 真鴨氏歓迎会
半年も先の予定が書いてある。ずいぶん気の早い人だ。しかも、他人の歓送迎会である。ちょっとほかのページを開いてみる。
*5月23日 レガッタ観戦
なるほど。毎年初夏になると、この川で大学対抗のボート競技が開催される。ビールを飲みながらこれを観戦するのが、私もいつも楽しみなのだ。してみると、手帳の持ち主は近所の人に違いない。
*7月4日 シロヒトリ学院前期生羽化
*7月10日 5:00am 燕家飛行練習開始
おや、これはどういう予定だろう。
*9月7日 たいふうん注意
*10月15日 冬芽完成 落葉OK
*11月22日 外套着用・19束分 就寝
私は妙な気分になって、手帳の日付を前へめくっていった。今日は、三月二十日である。
*6月26日 さくらんぼうや着地
*6月14日 新芽誕生
*4月26日 2:00pm 植樹祭 イトヤナギ
*4月13日 燕夫妻来日
*3月20日 1:30pm 開花
私は、そっと腕時計をのぞいてから、桜の枝を見上げた。ちらほらとかわいらしい花が咲いているではないか。例年より二週間も早い開花日だった。
(文集「COLOUR」3 1997.5.31より)もんだい:この手帳の持ち主は誰?
(題「怪我」)
富士錦とよばれたころ
子供のころは始終けがをした。ほとんどいつもひざ小僧がすりむけて、赤チンをたっぷり塗りたくられていた。腕の脱臼はくせになるほどだった。
虚弱児なのに気ばかり強くて、男の子と毎日すもうをとった。子供が集まるとまず取っ組み合いである。幼児から中学生まで一緒くたに遊んだ。わたしは富士錦というしこ名だった。手加減をしてくれたか、五回に一回ぐらいは勝てた。
妹が三人いたので、お姫さまごっこもよくやったが、おもしろいのはやはり、すもうやちゃんばらである。そのへんの棒切れを拾うとすぐ始まる。待てー、ねずみ小僧じろきちーと呼ばれたら、ぱっと木に登る。柿の木から落ちて気絶したこともある。
まだ若かった叔父にせがんで、腕を持って振り回してもらって遊んだが、これで骨折した。責任を感じた叔父におぶわれ、ねんねこにくるまれて、真冬の夜道をバイクで町の接骨院に走った。当時叔父は柔道を習っていたが、骨折が治った日の帰りがけ、道場に連れて行かれた。ここを転がってみろと言われ、広い畳をごろごろ転がった覚えがある。
鎖骨にひびが入ったこともある。学校のブランコで思いきり振ってから飛び降りて遊んでいた。腕を地面に着いた拍子に胸と首の間あたりに鈍い痛みが走った。母が留守だったのか、祖父が自転車をこいで駆けつけた。厳しい祖父だったので、痛みより、その自転車の後ろに乗るのが怖かった。
小学三年生のある日、男の子と遊ぶのをやめた。
女の子がそんな遊びをするものではない。
それまでもよく言われていたが、まるで聞こえなかった。いつものちゃんばらをしていたのだが、その時なぜか突然、大人のその言葉が胸に響いた。一瞬、棒切れを持って立つ自分の姿が、脇から眺めるように見えて、その棒切れを捨てた。
今から思えば、わたしの子供時代はその時終わったのである。
(「COLOUR」2 1996.6.30より)
(題「ベル」)
ベルを抱える娘たち
ベルといえば呼び鈴である。白いつるつるした半球形の磁器の中央に、赤いボタンがついている。押すと、ピンポンではなくビーと鳴る。
田舎町の表通りは砂利道で、道に面したたばこ屋のガラス窓はほこりだらけ。その脇の柱に付いていた。店番が見えないとそのベルを押す。しばらくすると、奥の部屋から、おばあさんがやっこらと現れる。今はほとんど見かけないが、六〇年代までのものだろうか。
ベルというとその形の呼び鈴を思い出すのは、もう一つわけがある。
そのころ、つまり六〇年代の終わりに、私は女子高校を卒業して上京した。安保闘争のただなかで街は騒然としていた。同じ高校の友人二人とよくアパートに集まっては、夜を徹して語り合った。親にも干渉されずに、食べ物やお酒を持ち寄り、自由に時を過ごすのは、今から思えばたわいないが、すてきな解放感があった。
そんなとき、三人で銭湯に行って、セツコがすばらしいバストの持ち主なのを知ったのだ。横から見ると、それこそベルのような美しい半円を描いている。ほかの二人は「うーん、きれい」とため息をついた。
彼女は三人の中ではただひとり恋人がいた。彼は二部に籍を置く苦学生で、あまり会えないらしかった。たまにセツコの部屋を訪れて、首尾よく彼女のバストに対面すると、彼は人差し指で乳首を押して「ビーッ、今晩は、入っていいですか」と言うのだそうである。私たちは、うらやましさに呆然として笑いころげたものだ。それからセツコをベルちゃんと呼んでからかった。
やがて、三人は新しい街の生活に慣れていった。ベルちゃん以外の二人も無事に恋人ができた。三人が語り明かすことも少なくなった。娘たちのそれぞれの人生が始まったのである。
(「COLOUR」1 1995.6.30より)
 「フジトミ詩とヤスオ絵の怪しい関係1 舌と否」へ
「フジトミ詩とヤスオ絵の怪しい関係1 舌と否」へ
 「関富士子のエッセイ」 もくじへ
「関富士子のエッセイ」 もくじへ
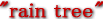 もくじ
もくじ 詩人たち
詩人たち 最新号
最新号 BackNumber
BackNumber 閑月忙日
閑月忙日 リンク
リンク 詩集など
詩集など 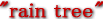 もくじ
もくじ 詩人たち
詩人たち 最新号
最新号 BackNumber
BackNumber 閑月忙日
閑月忙日 リンク
リンク 詩集など
詩集など  関富士子のエッセイ・小話など
関富士子のエッセイ・小話など 「関富士子のエッセイ」 もくじへ
「関富士子のエッセイ」 もくじへ 「関富士子のエッセイ」 もくじへ
「関富士子のエッセイ」 もくじへ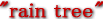 もくじ
もくじ 詩人たち
詩人たち 最新号
最新号 BackNumber
BackNumber 閑月忙日
閑月忙日 リンク
リンク 詩集など
詩集など  「関富士子のエッセイ」 もくじへ
「関富士子のエッセイ」 もくじへ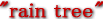 もくじ
もくじ 詩人たち
詩人たち 最新号
最新号 BackNumber
BackNumber 閑月忙日
閑月忙日 リンク
リンク 詩集など
詩集など