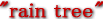 もくじ
もくじ 詩人たち
詩人たち 最新号
最新号 Back Number
Back Number 閑月忙日
閑月忙日 リンク
リンク 詩集など
詩集など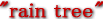 もくじ もくじ 詩人たち 詩人たち 最新号 最新号 Back Number Back Number | ふろく 閑月忙日 閑月忙日 リンク リンク 詩集など 詩集など |
拒絶 藤富保男 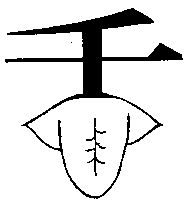 石になったから喋らない
石になったから喋らない喋らないから笑わない 笑わないから目が動かない 手をふりあげたままである 残念にも 舌を引込めるのを忘れた (「Bo'r」2号1995年) |
拒否 藤富保男 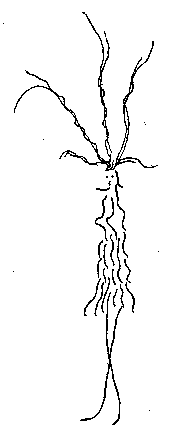 静かにしてくれ
静かにしてくれわめき散らすな なぜ 一斉に歯ぎしりするのだ 蝉よ いきなり音を立てるな 夜の空の奥をのぞかせてくれ なぜ そんなに見栄を張るのだ 花火よ 来ないでくれ ぼくのまわりで ひとり言を言うな なぜ だまって体にさわるのだ 蚊よ (詩集『やぶにらみ』より1992年思潮社刊) 身の毛 |
 詩人藤富保男の紹介
詩人藤富保男の紹介 「フジトミ詩とヤスオ絵の怪しい関係2 孤独のポエジー」へ
「フジトミ詩とヤスオ絵の怪しい関係2 孤独のポエジー」へ *COLOUR の会提出作品へ
*COLOUR の会提出作品へ 「関富士子のエッセイ」 もくじへ
「関富士子のエッセイ」 もくじへ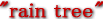 もくじ もくじ 詩人たち 詩人たち 最新号 最新号 Back Number Back Number | ふろく 閑月忙日 閑月忙日 リンク リンク 詩集など 詩集など |