|
<はじめに> 同じ標準MIDI(GM)データを演奏しても,音源によっては,聞こえ方が全く違うこともしばしばです。ここでは,ベロシティー(その音の大きさを示すパラメータで,1-127の値を指定できる,以下 vel. と表す)の値と実際の音の大きさの関係,また,それが音源の種類によってどう違うか,を調査してみました。 なお,ここでは音の種類を示す「プログラムチェンジ(以下p.c.と略する)」の値を,0-127の値を取るものとして扱います。 <今回調べた音色グループ>
音源の設定の条件はすべての音源について, + (各種リセット[GS,XG,GM]) + (ボリューム 127) + (プログラムチェンジ [音の種類に対応したそれぞれの値]) + (パン 127[めいっぱい右]) + (デジタル効果[リバーブ,コーラスなど]なし) としました。 また,ベロシティーを変化させたときの音量の変化を調べるため, + (ゲートタイム:Tg(音の種類による)) + (空き時間:Tbl1(音の種類による)) + (コントロールチェンジ[c.c.]120-値-0) <オールサウンドオフ> + (空き時間:Tbl2(音の種類による)) の「命令」を,ベロシティーを変化させながら繰り返したものをMIDI音源で発音させ,その音を数値データとして取り込みました。ただし,MU90B では「オールサウンドオフ」が利かないことがたびたびありました。(ここで測定したベロシティーの値:vel.= 1,5,10,15,……,115,120,125,127)  なお音源本体のボリュームは,音源本体ごとに常に一定(最大)にしました。また「ノートナンバー69」の音は右図に相当し,440 Hz の周波数です。 発音された音の波形のデータは,各音源のラインアウト端子のR(右)からの出力に 47 kΩ の抵抗をつなげたときの抵抗の両端の電圧をアナログ/デジタル(A/D)変換器を通してノートパソコンに取り込むことによって得ました。( A/D変換器とノートパソコンは,研究室(1)と同じものです。ただし,A/D変換器のサンプリング周波数は 16.6…kHz。) <結果> まず,各ベロシティーに対する音の大きさをどういうものの数値で表すか,というのが問題になりますが,ここでは簡略のため,音の波形グラフの振れ幅(最大と最小との差)の1/2の電圧値を「振幅」とし,GZ-50M以外ではそれを使うことにしました。(音の波形グラフのようすは,研究室(2)などを参照) 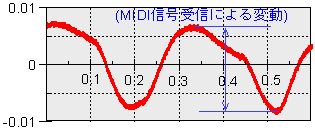 GZ-50Mでは,上記の「振幅」に若干の修正を加えました。右図は,ピアノ[p.c.0]でベロシティーの値が1のものの波形データを示したものです。ここでは,縦軸は電圧[V],横軸はグラフ上での相対時刻[秒],を表しています。この図のような「変動」は,どのベロシティーの値でも起こっているので,これは,MIDI信号を受信した時に発生すると思われます。また,この「変動」はそのときごとに,形や大きさが多少変化します。このため,GZ-50Mでは「振幅」を修正するために,以下の手順に従いました。 GZ-50Mでは,上記の「振幅」に若干の修正を加えました。右図は,ピアノ[p.c.0]でベロシティーの値が1のものの波形データを示したものです。ここでは,縦軸は電圧[V],横軸はグラフ上での相対時刻[秒],を表しています。この図のような「変動」は,どのベロシティーの値でも起こっているので,これは,MIDI信号を受信した時に発生すると思われます。また,この「変動」はそのときごとに,形や大きさが多少変化します。このため,GZ-50Mでは「振幅」を修正するために,以下の手順に従いました。
実際に耳が感じるのは「エネルギー」だから,単位時間に耳が感じる「エネルギー」I は,単一周波数成分のみでは, と考えられます。ただし,^2は2乗,∝は比例,V は音源の出力電圧,R は負荷抵抗を表します。したがって,音の周波数成分が同じであるとき,近似的に, と考えられます。この両辺の対数を取って整理すると, したがって,「振幅」の対数で考えれば,それは,実際に聞こえる大きさを考えることになります。 上のことは,あくまでも「荒っぽい」近似です。なぜなら,同じ振幅でも周波数によって「耳の感度」は違いますし,同じ音の高さ(ノートナンバー)でも,ベロシティーの値によって,音源から発生する音の音質が変化(周波数成分が変化)することがあるからです。 とは言っても,大まかな傾向は十分に分かると思います。 具体的な,音の種類[p.c.]ごとの結果を,次の別ページに記載します。なお,各[p.c.]共通の説明については,ピアノ[0]にのみ書かれてありますので,必ず ピアノ[0] を先にお読み下さい。(( )内はページの内容のサイズ)
(上記の結果をより実用的にまとめたグラフ集は,こちらへどうぞ。) なお,音の種類[p.c.]による違いの考察は,別の機会に行う予定です。 |