| |
秋の剪定について
剪定の具体的な時期は8月25日〜9月5日前後です(関東標準)北では早めに、南では遅くなります。
秋の剪定は、冬とは目的が違い、開花時期を調節することが主な目的です。これによって、冬の最中に開かない蕾を残さないようにする。或いは時期を揃えることで、出来るだけ薔薇の成長に良い気温の時期に蕾を成長させ、大きな美しい花をたくさん咲かせるといった効果が期待できます。もちろん必ずやらなければならないものではありません。
幾つかの区分について大まかな方法を述べます。
開花期を揃えるためには今現在蕾のもの、成長途中の枝をも切り落とす必要があります。
HT・FLの場合
先ず全体を見て、他の枝に比べて細い枝を根元から切り取ります。その後混み合った枝、或いは交叉した枝を間引きます。交叉枝は光が当たりにくいので良い花が望めないでしょう、混み合った枝も同じです。残った主要枝は本葉(複葉という小さい葉が5枚ついている葉)を枝全体で5枚以上残すような位置の芽の上で切ります、または3枚葉を残さないような位置で切ります。重要なのは、葉を出来るだけ残すようにすることです。葉が無いと良い花を咲かせることが出来ません、上記の方法は基本ですのでこれに縛られないでください。
イングリッシュローズの場合
イングリッシュローズもHT・FLと同じ剪定方法で良いのですが、シュラブローズに分類されているのでHT・FLの方法では難しい品種もあります。横に広がる樹形の品種や半つる性の品種は大まかに枝を間引いてから適当な長さで切り詰める方法でも構いません。縦に伸びる樹形の品種、ブッシュタイプの品種はHT・FLの方法で構いません。
オールドローズの場合
オールドローズはほとんどが一季咲きなので秋の剪定をする意味がありません。四季咲きのティーローズ、ポートランドローズはHT・FLと同じ剪定方法が使えます、ハイブリット・パーペチュアルは剪定はしないほうが良いと思います、むしろ蔓薔薇として育てた方が良いでしょう。返り咲きの度合いは品種によって違います。
蔓薔薇の場合
四季咲き性の強い半つる性の品種、ランブラー系は、咲き終わった枝を切り取り、適当な芽の上で剪定します。四季咲き性の弱い品種(LCL)、ランブラー系は剪定はしません、力強いシュートが伸びていると思いますが、それが次年度の春に良い花を咲かせる開花枝になりますので、出来るだけ真っ直ぐに伸ばします、途中で曲がるとそこから新しい枝が数本伸びてきてしまいますので支柱を立てて、真っ直ぐ固定します、途中で折れてしまってもまた先端の芽の上で切り戻しておけば芽を伸ばしてきます、この際数本の枝が伸びて来る場合がありますが、出来るだけ一本に絞って他の芽は欠きとってください。
ミニバラの場合
樹形が大きめの品種にはHT・FLの方法が使えます、普通のミニバラは適当に枝を切り詰めるだけで構いません。
葉が無くなって殆ど丸坊主になってしまった場合
剪定しません、このような場合は剪定しても株を弱めるだけなので薄めの液肥を与えて新芽が出てくるのを待ちます。
さらに株から強い芽を出させるために先ず全体を見て、残っている葉の上で枝を切ります。その後紐を用意して、枝の先端に結わえつけ、枝を横に倒すようにして固定します。固定する場所は地面に杭を打つか、鉢植えの場合は鉢に固定するか同じく杭を打ちます。
っまたは簡便に枝の途中で折り曲げる方法もあります。切り取るのではなく折り曲げるのです、硬い枝の場合は反発して戻ってしまうこともあるので曲がったままで固定する必要があります。
何故こんなことをするかというと、薔薇に限らず、植物の芽には頂芽優性(ちょうがゆうせい)と言う性質があり、高い位置にある芽から成長が始まる事を言います、そして薔薇の芽は、枝の下に付いている芽ほど強い枝を出す性質があります。つまり剪定によってただでさえ少ない葉を落とすと更に樹勢が弱るので、剪定を行わず、葉の残っている上の方の芽ではなく、下の方の強い芽を伸ばすと言う樹勢が弱るのを防ぐ方法なのです。この方法の利点は成長期であればいつでも使えることです。しかしミニバラは大型の品種なら可能ですが普通のものにはこの方法は小さすぎて現実的ではありません。枝を少し切り詰めて再生を待つしかありません。
秋の剪定で重要なのは、葉を出来るだけ残すようにすることです。葉が無いと良い花を咲かせることが出来ません。
夏場の潅水(水やり)について
バラにとっては最適な生育に必要な温度帯は15℃〜25℃です。ですが30℃を越す高温な日が続くとバラにとっては疲労の原因になります、そこで生育を助けるためにはこまめな水やりが必要です。晴れが続けば鉢の場合は、特に乾燥しがちになるので毎日、一回或いは二回の潅水が必要になります。出来得る限り先端部がしおれる事のないよう心掛けましょう。
また、鉢周りの地面に打ち水をして地温を下げると効果的です。このような高温乾燥時はハダニが発生しやすい環境ですので水遣り時に葉裏にも水をかけてあげましょう、すぐ乾くので病気の心配はないでしょう。
病気について
薔薇は他の植物に比べて病気の被害が大きく、枯死に至ることもあります。しかし、かといって薬剤で完全に防げるかと言うとそうではありません。あくまで人間がすることですから、小手先で何とかしようと思っても自然の巨大な力の前では無力です。良い例が耐性菌です、薬剤の散布を続けていると病原菌がその薬剤に対して耐える力、耐性をつけてしまい効かなくなります。そして更に強い薬剤を使いつづける内に、どんな薬でも効かない多剤耐性菌が生まれてしまうのです。院内感染で話題となったMRSAも多剤耐性菌です。
このように、薬剤は万能ではありませんので過信して使いすぎることは危険と言えます。
ポイントとしては薔薇に抵抗力をつけさせることが必要です、最近注目されている木酢液は、20倍くらいに薄めて薔薇に散布する事で薔薇に活力を与えます。また土壌に散布することで有効微生物を増やして、癌腫病の発生を抑える事が出来ます。
詳しくはGAMIさんの農薬嫌いの薔薇作りのページがとても参考になりますのでご覧ください
次は薔薇の冬の選定のついてと一年を通した作業一覧表です>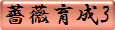 |







