| トップ | お知らせ | 会 報 | 会館 | あゆみ | パーラー | サ ロ ン |
ギャラリー | リ ン ク |
| 会報 |
| トップ | お知らせ | 会 報 | 会館 | あゆみ | パーラー | サ ロ ン |
ギャラリー | リ ン ク |
| 会報 |
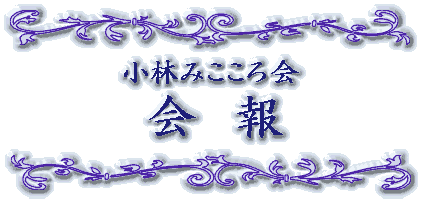
| 御挨拶 | 小林みこころ会会長 | 31回生 | 楠 喜美子 |
| 聖心会創立200周年を迎えて | 小林聖心女子学院校長 | シスター | 山 下 まち子 |
| 聖心会は今 | 聖心会小林修道院院長 | シスター | 景 山 佐和子 |
| 東京支部だより | 東京支部長 | 34回生 | 野上 惠三子 |
| 入会のあいさつ | 第72回生代表幹事 | 72回生 | 尾嵜 由佳 |
| 平成11年度行事報告 |
| マリア・マグダレナ・ソフィア 三宅きみ子先生を偲んで |
先頭へ
|
|||||
| 同窓会館の竣工とともに、役員の選出法が新しくなり、学年の当番制となりました。 その二期目の会長という大役をお引き受け致しまして、任期の半分、約一年が経とうとしております。最初の二年間を担当されました前会長はじめ役員の方々は、新路線で会や会館の運営を始められたことでもあり、色々な面で大変な思いをされたことでしょうと痛感致しました。 就任致しました当初は、31回生の私から48回生の役員まで10年以上の学年のへだたりがあり、自分の部の引継ぎは出来ていても他の部との関連が分からなかったり、意思の疎通がうまくはかれなかったりという事が、ままありましたが、幹事の皆様、同窓生の皆様のご協力のもとで、色々な行事をこなしていくうちに、お互いの理解と信頼が深まり、より良い活動が出来るようになってきたと思います。 今年、西暦2000年は、二十一世紀へ踏み出す第一歩の年であり、私達が敬愛する聖マグダレナ・ソフィアが聖心会を創立されて200年に成るという記念すべき年でもあります。フランス革命後の混乱の中から生まれ、今日まで脈々と続いてきた聖心のスピリットは、まさにAMASC世界大会の今回のテーマ「和解」そのものだと思います。科学の進歩を追い求めて来た二十世紀とは観点を変えて、もっと精神的な面から、相互の理解と信頼を深めなければならない、その為に「聖心の愛を人々に伝える」という創立者の望みを私達が、日々の生活の中で、実践していくことが「和解」なのではないでしょうか。 2002年4月にシドニーで世界大会が開催されます。この「和解」というテーマに沿った勉強会も開かれております。直接参加されなくとも、心の片隅に留めておかれて、実践していただければ、新世紀の未来は明るいものになるのではないかと思います。 昨年6月に聖心会創立200年祭記念行事として、小林みこころ会館で、パネルディスカッションやコンサートを開催いたしました。大勢の同窓生がご参加くださり、口々に、会館で催し物が出来ることを喜んで下さいました。念願の同窓会館の運営も、私達の重要な仕事の一つです。 色々な講座、奉仕活動など、多方面に亘って使用して頂いておりますが、クラス会や個人的な集まりなどにももっとご利用頂ければと思っています。又、ホームページも充実してきておりますので、一度ご覧下さりご意見などございましたら係りまでお寄せ下さい。 開かれた同窓会、開かれた会館を目指して、残る一年皆様のご協力を仰ぎつつ、役員一同励んで参ります。よろしくお願い申し上げます。 |
|||||
先頭へ
|
|||||
| 今年西暦2000年は聖心会創立200年記念の年です。全世界の聖心会の修道院や聖心学院は勿論、会員が関わる様々な活動の場で、意義深い記念の行事やお祝いが催されることでしょう。日本では、11月22日に東京カテドラルで、修道会と学校が一緒に200年記念感謝ミサを行います。東京以外の地にある姉妹校からも代表者が出席し、聖心は一つの家庭であるという強い絆を確かめ合いながら、喜びを共に分かちあうことになるでしょう。 姉妹校では、2000年度の学校教育目標として「漕ぎ出そう」という共通の目標を設定しました。創立者聖マグダレナ・ソフィア・バラが抱かれた教育の理想をより探く学び、聖心の生徒として新しい二十一世紀に向けて、いかに槽ぎ出していくべきかを共に考える年にしたいと願ってのことです。2000年を記念して、姉妹校合同の行事や、各校独自の計画もあります。小林聖心では、高校生徒会が今年の学院祭のスローガンとして「こぎだせ」を揚げ、早速準備を始めました。 「漕ぎ出そう」という言葉には、聖心会の200年の歴史が集約されているような気がします。1800年11月21日、フランスのパリで誕生した小さな会は、翌年アミアンで寄宿学校を始めましたが、その後急速にヨー口ッパ各地に広がっていきました。やがて、ヨー口ッパ大陸から出て海を越える時が来た侍、シスター達は文字通り漕ぎ出すことになりました。1818年の、フランスのボルドー港からアメリカ・ニューオリンズ迄のフィリピン・デュシェーン一行の船旅や、1907年12月3日から1908年1月1日迄のオーストラリア・シド二ーから日本の横浜港への四人のシスター達の旅は、私達に馴染み探い「漕ぎ出そう」の例です。これに類似する話は、各国の聖心学院の創立の歴史に必ず登場するものでしょう。実際に海に漕ぎ出すのではなくても、新しい修道院や学校の創立には、未知の国に神様の愛を伝えようとするシスター達の強い情熱と、どのような逆境にもひるまない勇気がありました。彼女達は様々な姿をした「海」に向けて喜んで漕ぎ出したのです。その結果が2000年現在、43国に存在する聖心会といえます。 「漕ぎ出そう」という姿勢は又、聖心学院で育った卒業生達の生き方の中にも深く入り込んでいるといえます。この200年間、世界各国の聖心女子学院を巣立っていった数多くの卒業生達が、その人生において様々な形で「漕ぎ出そう」と努カしてきたことは確かです。 他者の幸せのために何か自分達に出来ることをするようにと教えられた人達は、そのために自分の小さな世界から出て、他者の世界に漕ぎ出していくべきであると知って実践しています。私は今迄、多くの卒業生達が、実に様々な形で、様々な分野で活躍しておられるのを見聞きしてきました。自分達に出来る社会貢献の場を、時間をかけて見つけけ、その人らしい生き方の中に、充実感を味わっておられる卒業生達に会う度に、聖心学院での学びが充分に生かされているのを頼もしく思います。創立者が願われた愛の人としての生き方の根底には、「漕ぎ出そう」という前向きで、未知の世界を恐れない、心の強さが必要ですが、卒業生の中にこの芯の強さと実行力を備えた人達が多いことを創立者は、喜んで下さっていることでしょう。 今春、小林聖心女子学院高等学校から第72回生119名が巣立っていきました。生徒会活動助のテーマとして、「気付き〜そして実践へ」、学院祭スローガン「和〜かけ橋となれ」、クリスマス・ウィッシングのテーマ「愛の使者〜伝えよう希望の光を」を選び学校生活の充実を図ってきた72回生です。彼女達には二十世紀が残した山積ずる課題に収り組み、明るく希望に満ちたた新しい世紀を築いていく使命があります。それぞれの進学先で真摯に学び、やがて社父において活躍する場を得ていくことでしょう。卒業式の式辞の中で、私は彼女達に「聖心の子供達を通して世界に神のみ心の力が花開くように」という創立者の言葉を贈りました。聖マグダレナ・ソフィアは、フランス革命後の混沌とした社会を立て直すために、最も必要であった女子教育に一生を献げ尽くされましたが、彼女の生徒達への願い、聖心学院の教育のめざすものが、よく表現されているこの言葉が私は大好きです。この言葉を心に刻み、二十一世紀の世界をいかに人間がより人間らしく、幸せに生きる世界にしていくのかを彼女達が真剣に考え、創立者から託された使命を果たしていってほしいと心から願います。 彼女達もいつか、「漕ぎ出そう」という心の促しを感じる時がくるでしょう。自分達が必要とされる場へ、自分達を必要とする人々の所へ、愛と勇気をもって漕ぎ出していくことになるでしょう。同窓会の先輩の方達と共に、小林聖心の卒業生として、物惜しみせず、他者のために尽くす人生を歩んでいってほしいと思います。そのような卒業生達は、現在、小林聖心女子学院の教育に従事する教職員は、勿諭、在校生にとっても心強い支えであり、新しい世紀を始める聖心会の将来にとっても希望の拠り所となるものです。これからの時代は、今迄以上に私達聖心学院に関係する人達皆が、心を合わせて共に協力しあうことが必要になってくることでしょう。聖心会創立200年の年にあたり、今迄同窓会の皆様が、聖心会そして小林聖心女子学院にお寄せ下さいました温かいお心を心から感謝申し上げますと共に、新しい世紀に向けて、皆様と共に力強く漕ぎ出していきたいと願っております。 |
|||||
先頭へ
聖削立者、マザー・バラの聖心への愛と宣教の情熱は、ヨーロッパをはじめ、北米、南米へと広がり、1865年5月25円、マザー・バラが帰天された時には、聖心会の学院は89、会員数は3539名にもなっていました。その後も、聖心会は発展を続け、1960年代には、7千名を越す会員が、全世界の各地で宣教に携わっていたのでず。20000年を迎えた今、聖心会は、四十三ヶ国に3600名の会員が働いています。 200年を記念して、聖心会は色々な企画を準備しています。その一つに、出版物の刊行があります。先日、全世界の会員に「聖心会会員は今」という冊子が配布されました。1965年、第二ヴァチカン公会議の後、聖心会は、 禁域に留まっているだけでなく、人々の中へ出て行くことが、神のお望み、教会の望みであることを知りました。学校教育を大切にしながらも、「教育」の意味をずっと広げ、貧しい人々、飢え、不正に苦しむ人々、愛を求めている人々と共に生き、人間としての尊厳に生きることを助けるため、外へ出て行き始めたのです。 この冊子を見まずと、この二十年間に、聖心会員が、学校という枠にとどまらず、多くの人々の中に入っていき、関わっている様子を知ることができます。キりストがこの世で見られた、そして手をさしのべられたであろうすべての人々のところに、会員が存在しています。私の目に止まった、ウガンダで働く一人の日本人シスターの言葉を紹介させていただきまず。 「私はホスピスで、また家庭での介護のプログラムで働いています。私は多くの苦しんでいる人々に付き添って彼らの苦しみを少しでも軽くしてあげられることを嬉しく思っています・・・(以下略)」 「私たちは、教会によって遭わされています。それは、イエズスの聖心の愛を伝えるためです。・・・」(1987年会憲NO.10) この200年の間に、沢山の会員が、この目的のために一生を自国で又宣教国で献げました。勿論、学校教育の中でも、生徒たちは、この精神で教育を受け、世界の人々に目を向けることを学んでいます。また、卒業した後も、播かれた種が芽を出し成長していくのを見ることは喜びです。 卒業生の方々も、色々な立場にありながら、国際的、社会的、又草の根の活動を通して、この精神で「宣教」活動を続けておられます。会員が高齢化し、数の減少を見るのは少し淋しい気もしますが、会員と共に、そして会員の先を歩んでおられる卒業生の方々、又これから歩むであろう在校生の力に希望を見出します。 いつも、「あなた方と共にいる」といわれた主イエス・キリストのお導きを信頼して歩み続けていく限り、聖創立者のお望みも生き続けることでしょう。 |
||||||||||
先頭へ
昨年4月、支部長としての仕事始めに当たり、考えましたのは、先ず如何にして東京支部各回幹事の方々と早く親しく意志疎通を図り、確かな情報連絡を密にするか、ということでした。小林のような会館が支部にあるわけでもありませんので、とり急ぎ「小林みこころ会東京支部つうしん」(5月21日付一号)なる通信を発行致しまして、役員八名は6月3日、ホテルオークラにての総会で150名ご出席のもと、承認を受けました。通信はその後9月7日付2号、本年1月14日付3号と続き、目下3月17日付4号を作成中です。 この1年間、会長代理としてJASH理事会に出席致しました。偶々、私はその前2年間をバラ会東京支部長として参加しておりましたので、連続3年になるのですが、JASH主導の種々の交流、奉仕の場でお蔭様で大変貴重な学習と実践をさせていただきました。 小林の一人一人が、日本中、世界中の聖心の一員として祈られ、求められているという実感。広い心で深く考え、しなやかに行動する喜び。聖心女子大学同窓会のイベントである宮代祭への参加出店もその一つでした。当日は、役員・幹事だけでなく、支部長・副支部長の同期として特に34回生の方々が多数ご協力下さいました。又、台湾からの夏季体験合宿学生への物心両面への支援なども多く、感じ入りました。 昨年末のある日、クリスマスカードをお届けに修院へ伺い、シスターにお手渡し致しました。 その際、個人的に私の抽い句集を添えさせていただきましたが、思えばその修院の一室で、故シスター福川が幼児教育に赴任されていた九州本渡市時代からの句友の方と、小さくも清しい勉強会を持っておられ、そこへ私をいれてくださったのが始まりで出来た本だったのです。では謹んで福川元校長様のの春の壱っくを福川元校長様の春の一句をご紹介させて頂きます。 沈下の井の赤らみで日はうるむ 福山よ志 さて、2000年3月14日は、JASH主催の型聖心会創立(二百年祭一東京)です。小林の先輩方が、まさに聖心スピリットをもって献身的にご活躍で、本当に頭が下がります。当会は感謝ミサのお手伝いを担当させて頂きまず。 3月17日は、新旧の役員・幹事会議を宮代会館で行い、その後、大学の春休み中だけ参観できることになった、「パレス」と呼ばれる和館内部を、シスター河本のご案内を請うて見学致します。3回生の方々をはじめ、90余名のご出席予定です。 なお、次期支部総会は、6月14日、東京全日空ホテルにて開催されます。(2000年2月末日日記) |
||||||||
先頭へ
|
|||||
今にも雪が降りだしそうな冬空の下、二2月19日私達72回生は多くの方々に見守られながら、六年間あるいは十二年間過ごした学び舎から卒業いたしました。 高校生活の締めくくりとしての卒業週間を迎えても、まだはっきりと卒業を実感ずることができなかった私達も、ついにこの日を迎え、今さらながらもうこの学校に生徒として通い、皆で集まることもないのだということに、何とも言えない寂しさを、そして同時に、学校は社会の中で私達を守ってくれる存在だっただけに、今までの生活の基盤からの別れに大きな不安を感じました。卒業式で、保護者代表の方から「卒業に対する英語のCommencementの意味はは新たなはじまり」というお言葉をいただきましたが、正にこの日、私達は小林みこころ会の新一年生を歩みはじめました。このことが、たとえ遠く離れ、歩む道は別々でも、私達は聖心という一つの家族なのだということをより一層認識させてくれました。 この度、小林みこころ会に入会させていただくにあたり、私達72回生一人一人が、小林みこころ会の会員であるという自覚を持って活動していきたいと思っております。いたらない点も多いと思いますが、よろしくご指導お願い申し上げまず。 |
|||||
先頭へ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
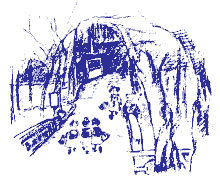
| 会報 |
| トップ | お知らせ | 会 報 | 会館 | あゆみ | パーラー | サ ロ ン |
ギャラリー | リ ン ク |
