
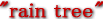 vol.10
vol.10
<雨の木の下で 10>
母の怒り(1999.3.4) 小池 昌代
馬事公苑で馬を見ながら、何の脈絡も関係もなく、突然、母の怒りをふたつ思い出した。
それは、深いところから、棒のように、ぬっと出てきた記憶であった。私自身がそれを記憶していたのも、おもしろかった。母は覚えていないかもしれない。私たちがそれについて話すことはないだろう。奥行きのある怒りだと思うが、表面的には、ただ、感情的という印象が残るからだ。私は、そのことで母を少しも恨んだりしていない。ただ、私にとっては、複雑で不思議な感触が残り、いま、反芻してみると、母が、私のなかにある、ある種の「悪」に気づいていたのではないか、と考えさせられる。
ひとつは、私が学生のころのこと。洗ってほしたパンティについて。それは、レースを使った、かなりきわどいデザインだった(ような気がする)。私は、あるとき、きゅうにそんなパンツがほしくなり、買っただけのことなのだが、母にはものすごくみだらに見えたようだ。怒りはパンティというよりも、パンティが差し出した、ある気配に向けられた。母は自分の想像力に苦しんだのかもしれない。私は母に言えない人とつきあっていた。若いころ私は、気持ちがいいので、どうせ見えないからとパンツをはかずに町を歩いたことがある。日本人には着物を着るとき下穿きをぬぐという習慣があるのだから、別におかしなことではない。しかし性をめぐって、自分のなかに混乱したものがあるのを自覚した。しかしその源は母からきているような気がするのだ。
もうひとつは、私が詩を書きはじめたころのこと。ある日、「これ、あなたが書いたの?きちがい、おそろしい。くるってる」と、私にあるメモをさしだした。それには、
「犬の舌枯野に垂れて真赤なり」
という俳句が書きつけられてあった。
これは野見山朱鳥の句である。初めてその句を読んで、その迫力に、思わず書きとめておいたのだ。しかし、母のつめより方は、言い訳も聞かぬ断定だった。確かにおそろしい一句である。そう思いながら、罵倒することで、この句を無視できなかった母は、まちがっていない、俳句がわかるなと思った。母のまちがいは、私の書くものに、この句のような深さが到底ないことに、気がつかなかったことである。私は母に、何度かくるっていると言われたが、本当にくるっているのではないかと思うこともあるのだ。仕事をなくしてしまったというのに、大変な費用をかけて自費で詩集を出そうと思うなんて、確かにある尺度から見れば、くるっている以外の何物でもない。
馬事公苑に来て、母の怒りを思い出すうち、母の命をつかんだような気がした。母は年をとったので、私については、とうにあきらめ、怒りをむけることはなくなった。もっと若い頃の母には、生命過剰のような野蛮さがあって、それは私に向けられるとき、鞭となったり、過保護となって現われた。
母は若いころから、ベートーベンが好きだった。私は最近、ベートーベンの弦楽四重奏を骨身にしみるように聞いたばかりだ。なんだかんだといっても、この作曲家はやはり、苦しみにある人間の友達であるような気がする。母は、たくさん苦しみながら生きてきた人である。
母を母として持ったことは、私の苦しみとなったこともあったが、母にとっては、私のような娘を持ったこともまた、苦しみであった。お互いを選んだわけではないので、この苦しみには、不思議な様相がある。
言葉のない世界(1999.2.25) 小池昌代
帽子をかぶった二人の女が、カフェのなかで、テーブルをはさんで座っている絵を見たことがある。エドワード・ホッパーというアメリカの画家が描いたものだ。この絵について小説家のアップダイクは、「まるで二人が互いに聴きあっているように見える」と書いている。とても奇妙な言い方だ。普通、会話というものは、一方が話し、一方が聞き、これが交互に繰り返されたりする。同時に互いが聴きあってしまっては、会話は成立しないだろう。しかし「聴きあう」という表現ほど、この絵の女たちに相応しい言い方もない。この不思議な対面は、まるで、互いを静かに消しあうようでもあるのだ。こうした「存在の相殺」が、絵を見ているあいだじゅう、絵のなかで行われていて、描かれているのは、女たちというよりも、透明な「関係性」なのではないかと思われてくる。
そんなとき、テレビでたまたま、モーツアルトのバイオリンとビオラのための協奏曲を聞くことがあった。バイオリンは堀米ゆず子、ビオラは今井信子。偶然だが、これもやっぱり二人の女が、視線を一度もあわせることのないまま互いの身体を聴きあい、奏でていた、モーツアルト。そのしぐさと気配は、あの絵の女たちにとてもよく似ていた。
言葉というものを操って、私たちは他者と関係したつもりでいるけれど、本当は、あの女たちのように、互いを少しも知らないで、この世に寄る辺なく点在しているだけではないのか。そうして見ると、この絵の二人は、最も純粋な「関係」の縮図として、私たちの前に、静かに立ち現われる。
聴きあう彼女らに、話題はない。それは彼女たち自身がまさに「話題」である証拠ではないか。誰にとっての話題か?カミにとっての?
人と話をしていて、話題がとぎれることがある。その瞬間のまの悪さが、私は実はとても好きだ。話すことなど、もう何もない。――その虚空のなかに身を置くと、ないことのなかに、やがてゆっくりと充ちてくるものがある。話題を探すのではない。私たちという存在が、こうしていつも、遠くからやってくるものに、手繰り寄せられ、探されるのだ。
さあ、話しをしよう。
 <雨の木の下で>痴漢を許さない(関富士子)へ
<雨の木の下で>痴漢を許さない(関富士子)へ
 <詩を読む>藤富保男詩集「客と規約」を読む(桐田真輔)へ
<詩を読む>藤富保男詩集「客と規約」を読む(桐田真輔)へ
 <詩りとり詩>みみずのせぼね(関富士子+木村信子)へ
<詩りとり詩>みみずのせぼね(関富士子+木村信子)へ
 詩人たち
詩人たち 最新号
最新号 BackNumber
BackNumber vol.10
vol.10 閑月忙日
閑月忙日 リンク
リンク 詩集など
詩集など  詩人たち
詩人たち 最新号
最新号 BackNumber
BackNumber vol.10
vol.10 閑月忙日
閑月忙日 リンク
リンク 詩集など
詩集など 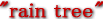 vol.10
vol.10 <雨の木の下で>痴漢を許さない(関富士子)へ
<雨の木の下で>痴漢を許さない(関富士子)へ <詩を読む>藤富保男詩集「客と規約」を読む(桐田真輔)へ
<詩を読む>藤富保男詩集「客と規約」を読む(桐田真輔)へ <詩りとり詩>みみずのせぼね(関富士子+木村信子)へ
<詩りとり詩>みみずのせぼね(関富士子+木村信子)へ 詩人たち
詩人たち 最新号
最新号 BackNumber
BackNumber vol.10
vol.10 閑月忙日
閑月忙日 リンク
リンク 詩集など
詩集など