 詩人たち 詩人たち 最新号 最新号 BackNumber BackNumber vol.10 vol.10 | ふろく 閑月忙日 閑月忙日 リンク リンク 詩集など 詩集など |
 詩人たち 詩人たち 最新号 最新号 BackNumber BackNumber vol.10 vol.10 | ふろく 閑月忙日 閑月忙日 リンク リンク 詩集など 詩集など |
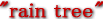 vol.10
vol.10<詩を読む>
関 富士子
小池昌代の生まれたての詩
"rain tree"がめでたくvol.10になった。遊びに来てくださった皆さん、ありがとうございます。
詩のサイトを開いて満1年になったときも、訪問者の数が5000を超えたときも、サイトの管理とパソコンのメンテナンスに追われて感慨にふける余裕もなかった。vol.10といっても、詩人たちの中には何十号という詩誌を何年にもわたって発行し続けている方たちがたくさんいる。わたしなどはほんの駆け出し。ほんとうにたいへんな時期はまだまだこれからという気もする。
二か月ごとの発行のたびに、自分の好きな詩人で書いてくれそうな方に原稿を依頼して、新作をいただいた。稿料もないので気が引けたが、皆さん快く受けてくださった。 原稿が送られるたびにわくわくして、その作品をしげしげと読む。力のある詩はエネルギーがこちらに伝わってくる。詩りとり詩じゃないけれど、差し出された言葉をしっかり受け止めて、なんとか自分の言葉で返したい。締め切りになっても書けずにいるときなど藁にもすがる思いである。ありがたくそのエネルギーを浴びるべく目を閉じる。そうやって二か月ずつをクリヤーしてきた。
特に今回の小池昌代の仕事ぶりには圧倒された。ほとんど毎週のように新しい作品を書いてくれた。できたばかりのほやほやの詩を真っ先に読むことができる喜び。詩誌を編集する者の特権だ。
毎週というがこれは実は大変なことである。詩は文章に比べて短いものだし、書ける人はさらさらとかんたんに書けるのだろうと思われがちだがとんでもない。詩は文章のように、できごとや論理を追っていけばよいものではない。つねに自分は詩を書くのだという強い意欲と相当な集中力が要求される。寝ても覚めても詩のことを考えている状態である。
小池昌代の詩は、どれも平易な表現でありながら、詩で書かれた哲学のような趣がある。ありふれた風景が詩人によって子細に観察される。ささやかな日常がすくいあげられ、誠実に思索されていく。よけいな言葉はないのに、思考の過程が読者にも手に取るようにわかる。それらが、詩人の言葉によってわたしたちに確かに伝えられた時、生活や風景の断片は、世界をかたちづくるのに欠くことのできない存在として再び姿を現す。それは「神」のいる風景といってもいいのだろうか。鮮やかというほかはない手腕である。
しかし、小池昌代の詩にわたしが胸を衝かれるのはそのことではない。風景が世界を体現するのを目のあたりにするのとひきかえに、見ている「わたし」はその場から消えてしまうのだ。消滅していく「わたし」のかすかな悲鳴が聞こえる作品もある。なんと痛ましいことだろう。圧倒的な存在、けっして傷つかない世界を見てしまった「わたし」という個人の運命とでもいうのか。
それでは詩人はどうかというと、「わたし」の姿が消えていくのを悲しみながら、一方ではその運命に満足しているかのようだ。それが見るということ、書くということなのだろうか。風景と言葉とのあいだで、詩人は「触媒」として機能する。言葉で何ものかを伝えることを自分の仕事と決めた人の、潔い姿勢である。
小池昌代の詩が言葉そのものを語るときには、「わたし」はもっと幸せそうに見える。自分にやってくる言葉をうやうやしい仕種で迎え、それが表わすものを真摯にひもとく。その敬虔な姿に打たれる。長い間たくさんの意味に纏いつかれ、手垢にまみれてしまっていた言葉は、この詩人によってさっぱりと生まれ変わり、かつて聞いたことがないような真新しい響きと確かな意味を獲得するのである。このとき言葉もどんなにか幸福だろう。
桐田 真輔
藤富保男詩集『客と規約』を読むKIKIHOUSE
ここに複数の連からなる行分け詩の作品があるとする。まず、その作品に使用されている漢字を全部取り除いてみる! するとそこに意味不明のひらがなだけが残るはずだ。このスポンジ状態の言葉の集積の中から、さらに13文字だけ残すが、その際、各連から最低一文字以上は選ぶ、というルールで、文字の順序はそのままに、最初の作品に関連した意味ある語句をつくる、ということをやってみる。うむしかし、誰がそんなことを考えつくだろうか。『客と規約』はそういう試みをしているとても風変わりな詩集だ。久々にこちらの詩についての既成観念がぐらりとさせられるような楽しさを味わえた。
黒い艶光りする服を着た見知らぬ女が勝手に玄関から上がり込んで、「まあお元気で」などとおざなりな挨拶を口にしたあとはこちらの問いにもろくに答えず座り込み、そのうち冷蔵庫をあけてジュースなどのみはじめた。ついつい「お前は誰だ」と詰問すると、女はさっと鳥かごの中に忍び込んでカラスになってしまった。そんな夢のような、とぼけた味わいのある「客」という詩が、この詩集の巻頭に置かれている。
詩集全体は6編の詩からなるのだが、この巻頭の詩「客」が、都合5回の、前述したような様々な変身をとげることになる。どんなルールでそれがなされたかはゲームのルールブックのような「規約」という解説が付されている。たとえば漢字をぬいて、残ったひらがなから13文字を選択して成った作品(「はてなの巻」)。また、ひらがなを全部抜いて、残った漢字から13文字を選んで成った作品(「足軽の巻」)。きわめつけは、漢字をすべて抜き、ひらがなも濁音だけ残して除いたうえで、濁音のあった箇所に濁点だけ26文字分を表示した「足跡の巻」という作品だろう。それは、もはや無意味な痕跡、しかし白いページの上で見ると、星座や、鳥の飛跡を思わせるようなきれいな痕跡を表すのみとなっている。
作者がどんな考えでこういう試みをされたのか分からない。むしろ、どうしたらこういう風なことを思いつけるのか知りたい位だが、その柔軟な着想やレイアウトも含めて、詩集としてすぐれた出来映えだと思う。「客」という7連、38行の詩を構成する文字のなかから、奇想天外な「規約」を介してうまれでた13文字の作品。それは詩「客」の原型をとどめてはいないが、作者のユーモラスな意想と言葉のセンスによって、家にあがりこんだ女がカラスに変身する、という幻想的でとぼけた詩の味わいを、ほのかに伝える仕上がりになっている。
「あ ら に ら み あ って は て な に な って」(「はてなの巻」全文)
「笑 女 足軽 丸 眼 王 蛇 化 光 衣 妖 声 飛」(「足軽の巻」全文)
こうして余白やレイアウトを無視して文字だけ引用すると、詩集を手にして感じる、巻頭の「客」という詩の内容と緊密に繋がった「ほのかな味わい」は、まず伝わらないと思うが、こうした作品は巻頭の「客」と、巻末におかれた「客帰るー文字隠れの巻」(「客帰る」(「客」の連を逆に構成された、内容的には続編というべき作品)から13文字だけを抜いた作品)にはさみこまれることで、とても調和がとれている。いわば一冊の書物全体が「規約」で連結されたひとつの作品というしかない感じだ。
作品「客」についていえば、私事だが、私は九官鳥と暮らしているので、鳥かごの中から声をかけられながら炬燵でこの詩を読んでいて、なんとも愉快な空想に浸れるものがあった。ただカラスの入れる鳥かごだと相当大きそうだが、詩の中の主人は、なぜそんな大きな鳥かごを前もって用意してあったのだろうか。あやしい。。。
藤富保男詩集『客と規約』\2000E(1999年1月26日第一刷発行・書肆山田)
ミステリィ詩集
変装の麗人。黒の衣装。点々とした足跡。……これは誰もが思い付かなかった20世紀の推理詩だ……(河原比和)
7つの連。13文字を残す。13の倍の26。そしてまた13文字。この暗号めいたルールで、各詩が組み立てられている。
ご注文は書肆山田へ
 <雨の木の下で>母の怒り/言葉のない世界(小池昌代)へ
<雨の木の下で>母の怒り/言葉のない世界(小池昌代)へ <詩>馬喰という名の土地で(小池昌代)へ
<詩>馬喰という名の土地で(小池昌代)へ
 <詩りとり詩>みみずのせぼね(関富士子+木村信子)へ
<詩りとり詩>みみずのせぼね(関富士子+木村信子)へ 詩人たち 詩人たち 最新号 最新号 BackNumber BackNumber vol.10 vol.10 | ふろく 閑月忙日 閑月忙日 リンク リンク 詩集など 詩集など |