 詩人たち 詩人たち 最新号 最新号 BackNumber BackNumber vol.11 vol.11 | ふろく 閑月忙日 閑月忙日 リンク リンク 詩集など 詩集など |
 詩人たち 詩人たち 最新号 最新号 BackNumber BackNumber vol.11 vol.11 | ふろく 閑月忙日 閑月忙日 リンク リンク 詩集など 詩集など |
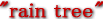 vol.11
vol.11駿河昌樹のエッセイ |
南太平洋の紺碧の青空 (1999.6.10)
フォリオ版のモンテーニュから二十ページほどコピーをとる必要があって、ちかくのコンビニエンスに行った。作業自体は簡単だが、いちいちページを繰ってガラスの上に置きなおさねばならず、時間がかかる。
途中、高校生らしい女の子が来て、わきに立った。
「コピー?」
と聞くと、ええ、というので、
「まだ十分以上かかるかもしれないよ。あなたのほうはどれくらいの量があるの?」
英語のテキストを出し、ぱらぱらと繰って、八ページだという。それなら、さきにやってもらったほうがはやい。しばらく場をゆずった。やりかたがわからないというので、設定してやり、ついでに、ほとんどわたくしがコピーサービスをしてやるかたちで、女の子のコピーはすぐに終わった。
「どうも、ありがとうございました」
すてきな笑顔をくれて、店を出ていった。
ふたたびモンテーニュのコピーに取りかかって気づいたが、英語のテキストのコピーといっしょに、一枚、『エセー』の中の「食人種たちについて」のコピーを持っていかれてしまっていた。女の子がうっかりそんな文書を持っていってしまったことが、すこしおもしろかった。彼女がコピーの「食人種たちについて」を読むことはあるまい。が、そんなふうに、偶然、フランス語のモンテーニュが彼女の勉強机にたどり着き、わずかのあいだでも場所を占めてしまうのを思うと、偶然というもののおもしろさに触れるようで、気分がよかった。
そのあとすぐに、六十代後半かそれ以上と見える、しかし矍鑠たる男性がきて、わきに立った。袋を持ち、コピー機のほうを向いて逡巡なく立っているのを見れば、どういう用事でそこにいるのかはすぐにわかる。
「コピーですか?」
と聞くと、うなずくので、
「まだ十五分ぐらいかかるかもしれません。」
と告げた。どのくらい時間がかかるかを知っていれば、雑誌のコーナーで時間をつぶすこともできる。終わったら、呼んでもらうということにしておけば、待つ側の気分はかなりよくなるはずだ。そう思って、だいたいの時間を告げたのだった。
ところが、この男性の返してきた言葉に驚かされた。
「なんで十五分もかかるんだね? だいたい、どういう計算基準で十五分というのが出てくるんだ?」
「どういう計算基準って・・・・・、概算ですよ。コピーにかかる時間の計算に、だいたい、基準を持ち出すこともないでしょう?」
とっさに答えたものの、せっかく親切心から、そのくらいかかるから心づもりしてくださいと告げてやったのに、と、すこし苛立った。怒るのも大人げないし、だいたい、このひとの性格や口調の問題かもしれないから、と考えて、
「ま、とにかく、ちょっと時間がかかります。終わったら、あなたのことを呼びますから、雑誌のところにいっていらしてもいいし・・・・・・」
そういうと、このひとは、また、とんでもない応えを返してきた。
「ここで待っていてはいけないというのかね? ここにいるのはわたしの自由なんだから。邪魔だといいたいのかね?」
唖然とした。「なんでこんなやつが生きているんだ!」という『カラマゾフの兄弟』のある章名が脳裏に浮かんだほどだった。正面からこの男性を見て、しかたなく言った。
「あなたがそこで待っていてよいとか、いけないとか、そういうことじゃありませんよ。ひとがコピーするのを待っているのは退屈でしょうから、もしよろしければ、わざわざそこに立ち続けてなくても、わたしが終わったら、あなたを呼ぶ。そう決めておけばいいでしょう、ということです。」
「そんなことはわたしの自由だ。待っていても、待っていなくても、自由じゃないか。わたしはここにいるつもりなんだから、それでいいじゃないか。」
「それならそれでいいんですが、手持ち無沙汰じゃないですか。そこに十五分もいたら退屈でしょう? だから、あなたの順番はわたしがちゃんと確保しておくから、よろしければ、と言っているんです。」
「いいんだ。べつにほかに用事もないから、ここで待ってる。」
「そうですか、それなら─────」
それなら、ご勝手に、と言いたかったけれど、まあ、それを言うのはよそうと思って、コピーの作業に戻ることにした。
しかし、コピーを続けながら、心中の不快はおさまるどころか、激しくなった。もともと喧嘩ずきで、ことに年長者と理屈を戦わせるのを最大の娯楽としているわたくしが、こういう好機を逃していいはずがない。気まずい雰囲気、とげとげしい空気、たがいの理論が支離滅裂になり、表面的な紳士づらやかっこつけが剥がれ落ちていく状況に居合わせるのが、三度の飯より好きなのだ。
コピーを終えて、紙や本をしまいながら、
「十五分はかかりませんでしたね。」
と、笑みをつくっていった。このひとのほうはニコリともせず、うなずくだけである。
「それにしても、あなたの狷介さにはおそれいった。」と続けると、
「どういうことか、わからんね。」と、このひとは外を見る。
「いいですか。わたしがあなたに、かかる時間をいい、もしよかったら、そこを離れてもいいといったのは、純粋に親切心からなんです。それをあなたは、あなたの自由うんぬんなどという話に持っていった。あなたの自由が侵害されるといった方向に勝手に入っていって、そういうあなたの誤解からすこしも出ないで、自己防御ばかりしていた。」
「なにがいいたいのか、まったくわからんね。」
「狷介、頑迷固陋。公共精神の欠如。社会的コミュニケーションへの配慮のなさ。それがあなたがたの世代の特徴だな。あなたがたが日本をダメにしたんだ。すこしは反省したまえ!」
初対面にしてはかなり急上昇の物言いだが、こちらはコピーも終わったし、いそぎの用事もないしで、ここでひとつ、喧嘩の回数を稼ごうという気持ちになったのだった。
「わたしは、わたしの自由だってことを言っただけなのに、どうしてそんな失敬なことを言われなきゃならんのか、わからんね。とにかく、わたしはそんな議論をしている暇はない。あなたのほうが失礼なことを言うから、それに応えただけだ。」
やりとりをしながら、わたくしはこのひとにコピー機をゆずり、このひとも本を出して作業をはじめた。本は厚手のしっかりした二冊で、背表紙には『実習民法』とある。
それを見て、わたくしは俄然うれしくなって、いっそうの議論欲が出てきた。むかしから、法学系のひとびとの論理の異常さや偏りには関心があって、かれらの論理の根幹を壊すというのは、いかなる娯楽にもまさる至上の快楽なのだから。もっとも、このひとを相手に、そこまでするつもりはなかったのだが。
「あなたのコピーしている本は法学のだけれども、その本が理解できるくらいなら、わたしのいいたいことはわかるでしょう。もしわからないのならば、あなたがそんなものを読むのはムダだというほかないし、法学があなたの専門なら、日本の法学のレベルも知れたものだということになるし、あるいは、あなたがたの世代の愚かしさをまじまじと見つめる好機にたまたま居合わせたということかもしれないけれど、とにかく、詫びのひとつも言うのがスジだよ、え?」
相手はもくもくとコピーに励みながら、「わたしは、自分がどこで待っていようが自由だと言っただけなのに、これをこんなふうに吹っかけられちゃ、困る。失敬だ。・・・・・こんな言いあいをするなんて。」
「言いあいじゃないよ。ただの話しあい。オハナシ。こんな程度の話を、言いあいなどと呼ぶほど、現代日本の対話の現状は貧困なんですかね?」
こんな調子で、十五分ほどねちねちといじめ続けたのち、
「まあ、とにかく、反省したまえ。反省。あなたがたがこんな日本をつくったんだ。この国をこんなふうにしてしまったんだ。あなたと話して、きょうはいよいよ確信したね。このまま、やすらかに老後をむかえて退場しようと思っているのかもしれないが、そうはいかない。オトシマエをつけてもらわなきゃ。じっくりと反省しなさいよ。」
なにか言い返したら、まだまだやるつもりだったが、押し黙ってしまったので、わたくしは店を出ることにした。
日本のある種の小説では、こういう場合、主人公のこころに一抹のむなしさが兆した、といったオチをつける習慣がある。が、わたくしの場合、はるかにバロックしているから、ただもう、南太平洋の紺碧の青空、といったさっぱりした気持ちなのだった。これからも、生意気な年長者にはバンバンやったるでえ、と決意をあらたにした次第である。
言い忘れたが、話の途中、この六十代後半以上の矍鑠男は、いまの日本のどこにも問題はない、と言い切っていた。昨今の日本のドタバタのなかで、どこにも問題はないとサッパリ言い捨てるアイロニカルな精神は、じつはわたくしの好むところである。バンバンと打ちのめしてやるべき生意気な年長者を、けっして嫌ってもいなければ、軽蔑もしていないわたくしの、高度にうつくしく屈折したバロック精神を、読者はよくよく、ご自身の偏狭さをさらに歪めながら、理解していただきたいものと思う。
すてきなキスのしかた 1999.6.10
郊外に仕事に出た帰り、つかれきって、長距離列車に乗り込んで発車を待っていた。
わかい男女がドアのところで話している。
男は列車に乗っていて、女はホームに立っている。
わたしはすこし離れて腰かけていたので、かれらの話の内容までは聞こえない。楽しそうな女の顔がよくみえた。ときどき声が高くなる。笑う。
発車ベルが鳴ると、すてきな光景になった。顔がちかづいて、ふたりはキスをした。女の頬のやや赤らんだかがやきが、光景を清潔なものにした。
それから、男がなにをいったのか、女は笑みをいっぱいに浮かべて、顔全体が、いっそう生き生きとかがやくようだった。
別れ際のキスのあとで、こんなにあかるく微笑んで、すてきだと思った。
ドアが閉まり、手をふりあって、ふたりは、ふたりのきょうを終えた。
駅でも街でも、キスをしたり抱きあったりしている男女を見るようになってひさしいが、見ていて、すてきだなと思う光景はすくない。見せものではないといわれれば、それももっともだと思うもの の、人目に触れる場所でそういう行為におよぶのだから、やはり、当人たちにそれなりの演技を期待したいという気はする。あんなふうにキスができたらすてきだろうな、という思いをひとに抱かせる のは、たぶん、恋人たちの義務というべきものではないだろうか。すてきなキスのすがたが、街をどれだけ美しくするか、ヨーロッパを旅したひとなら、だれでもわかるはずだろう。
おおげさな言い方をあえてするけれども、むかし、生涯の愛を傾けたといってもいいひとがいて、じつはそのひとのために一生分の愛を使いきってしまい、いまでは、わが内なるヴィーナスは、から からのミイラになってしまっているのだけれど、そのひとが生まれ育ったアルザスにわざわざ訪ねていったことがあって、なんとも煮え切らぬ一夜を語り明かしたものだった。
わたしにもむこうにも、やむにやまれぬといってよい事情があって、これからふたりで将来どうするか、じゅうぶんに話せないまま、別れねばならなかった。わたしの非社会的な感性では、どこで 生きるにも苦労を背負い込むだろうし、都会ぎらいの彼女は、パリにも東京にも住む気はないと言うし、いま彼女を精神的に支えてくれている年上の男のプロポーズを、感謝の気持ちから受け入れるべ きかもしれないなどとも言うし、くわえて、あなたは遠すぎるのだもの、と言うし、そう簡単には結論の出せない状態だった。
翌朝はやく、わたしはパリに戻るために、彼女は仕事にむかうために、いっしょにアパルトマンを出る。ストラスブールの冬の早朝は寒くて、舗道に立って見つめあいながら、息がミルクのように白 くなるのを見ていた。笑顔で別れようと努めていたのに、彼女の顔がみるみるうちに崩れて、大きな目いっぱいに涙がたまって、つぎつぎ流れ落ちる。お別れのキスも、かるくすまそうとしていたの に、こころにふかく陥没ができるほど、ながくなった。
あのとき、わたしと彼女のすがたはどうだったのだろうと、ときどき思う。そういう感傷的な回想のときがあっていいのだとも思う。やがて彼女は、例の年上の男と結婚して子供を生むことになる が、わたしと彼女との連絡は途絶えなかった。夫となったブリュノも、いまではわたしの友だちになったし、彼の家系が代々暮らしてきたブルターニュの田舎で、かれらふたりは、毎年わたしを迎えて くれる。
ブリュノの家の敷地には、森があり、沼があり、草原がある。沼のまわりをゆっくり歩くと、三十分ほどはかかる。夏にはそこで翡翠が魚をとり、白鳥がゆっくりと泳ぎ、散策のゆくてを兎が駆けぬ ける。
かれらの家にいったときは、いつも小さなふたりの娘をつれて、彼女と散歩に出る。沼をまわり、森をぬけて、遠くまで見晴らせる草原に沿って歩きながら、おたがいの生活に最近どんなことがあっ たかを話すのだ。まるで、ひさしぶりに帰ってきた父のように娘たちを抱いて、鳥の声を聞き、風にふかれながら、ぽつぽつと話す。
「こうやって、こんなすてきなところにいて、この子たちも生まれて、やっぱりこれが、きみにはいちばんよかったね」
そんなことを、ある夕暮れ、言ったことがあった。
はにかんだ笑みを浮かべながら、むかしとちがう、あかるい涙を幾粒か、彼女は落とした。
その涙の意味もあかるさもわかる、と言おうとして、けれども、思えばあまりに当然のことなので、言わなかった。
以前にも、なにかそんなことを言って、こう返された。
「あなたにわからなくて、だれがわかってくれるっていうの?」
日本のこころ 1999.6.5
ひさしぶりに国立劇場で勧進帳を見た。
富樫が関の通行を許可したあと、義経が弁慶の機知に感謝し、労 う。ことばはむしろ少なめで、主従のこころとこころの間で伝えら れ、受けとめられるものが舞台を領するその場面で、斜め前の婦人 が何度も涙を拭いていた。眼鏡をはずしては拭い、掛けてはまたは ずして、拭う。劇は劇場という場に発生するのでなどなく、観客の こころのなかにだけ発生する。劇場という空間だけを拡大してなさ れる演劇論が、立論はしやすくとも、どんなに空疎か、個々人のこ ころという、だんじて一様に扱えない真の舞台をずいぶんと薄っぺ らに見て、芸術論や芸術鑑賞の心理を説くことが、どれほど多くの ものを損なうか。そんなことを考えて、その婦人のハンカチの動き を見た。
おかげで、多少、気は散ってしまい、涙が込みあげるなどという ことはなかった。
それでもよかった。勧進帳は何度も見たし、そのつど役者たち 個々の味に接したし、目頭を熱くするような情動を今回持つに到ら なかったからといって、脳裏をめぐる過去のさまざまな舞台を同時 にこころのなかに見ることは、やはり楽しかったのである。
帰りの道すがら、婦人の涙を拭う姿はこころに消えず、勧進帳の あの場面で涙するのは、どういうことだろうなどと、愚かといえば ずいぶん愚かな疑問を持った。むろん、こころが動いたから泣くに きまっているのだし、なにでこころが動くかは、ひとにより、経験 によるだろう。培われてきたこころのありかたや、琴線の張り様に よるのだ。わかりきったことだ。だが、こんな答えがほしくて抱い た疑問ではなかった。あの婦人はなぜ泣いたのかという、この疑問 自体のほうが、よほど答えの体を成しているではないか。答えとい うのは、真相のほうをたしかに向いている思いのことをいうので あって、ことば巧みに、分析的に説明することとは違う。正しいと 見えるものが間違うのは、こうした思いの向きの、微妙な、あるい はあからさまなずれがあるからだ。
なぜ泣いたのだろうと、ずいぶんぼんやり考えながら、五月のす こし蒸し暑い午後の繁華街を抜けた。パチンコ屋ののぼりを眺め、 焼き鳥屋の店員の白い帽子を眺め、髪の毛を染めてサングラスを長 髪に乗せ、女の子の品定めに興じる若者たちのあいだを抜けなが ら、わたくしたちは、わたくしたち日本人は、どんな考えを持ち、 どんな個人的な信仰を持ち、教養を持ち、好みを持とうとも、けっ きょく皆、死ねば日本のこの空気に戻っていくのだと考えた。若い 頃なら苛立ったに違いないこの考えに、不思議にこころは平静だっ た。勧進帳を見て涙を流すこころも、勧進帳に流れ込んでああいう かたちに作品化されたこころも、劇場に坐ってちょっと退屈なよう な、半分いつも眠いような気持ちになる、その根底にあるこころ も、皆、この日本の空気を故郷としている。それを認めたところか らしか、わたくしたちの生活ははじまりえないのに、頭はたびあるごとに、 それから逃れようとしている。いや、逃れるのが正しいことである かのように教えられ、慣らされてきて、そうして、それが進歩でで もあるかのように考えている・・・・・
あの婦人が、個人的な経験の疼きから涙したなどと考えるのは、 わたくしたちが馴染まされてきた近代の愚かな思考法にすぎまい。 涙を流すべき場面があり、そこで正確にあの婦人は反応したまでだ と思いやる感受性を、わたくしたちがはなはだしく欠いてしまった までのことなのだろう。泣いていたのは、日本のこころというもの ではないか。ああいうところで、あのように泣くというのが日本と いうものだったのではないか。過去のものでなどなく、廃れようも ない、考えようによっては、絶望的なまでに不変の心身のかたち。
日本のこころは変わらず、変わりようもないのに、それをとらえ る理知が、杓子定規の外来物のままになっている。その杓子定規が 世の中につっかえたままになっている。この定規にも、これで測ら れた世の中にも、果てまで厭きたわたくしのようなものには、あの 婦人の涙する姿は新鮮だったのだが、思い返すと、国立劇場の建物 はどうにも杓子定規に見えていたようだった。帰りがけに見たパチ ンコ屋や焼き鳥屋は、杓子定規からはずれていた。通俗の、場合に よっては、俗悪ともいえるそんな光景が、不易の日本のこころに、 たしかに通じていると感じられてならなかったのだが、これはわた くしの間違いなのかどうか、わからない。
虚構について 1999.4.29
人間というものは、お互いに騙し騙されるのでない限り、ながく世間には生きられまいよ。そんなふうに、ラ・ロシュフーコーさんが十七世紀に言っている。
ごく若い頃なら、この箴言の正確さにこころで頷きつつも、希望を確保したいがために生意気に否定などしてみたかもしれない。が、歳を重ねるにつれ、希望とか、誠実さとか、友情とか、相互理解とか、そんな言葉はどれも、じぶんの意識の森のかなた、メルヘンの領域にまで遠ざかり、こんな箴言の真実がじわっと沁みてくるばかりになった。だが、そうはなったものの、こんどはまた、希望のためでなしに、この箴言を言動をもって否定しようとするこころが強くなってきた。よき人間関係という虚構のため、といったらいいだろうか。人間は真実になど立脚してはならず、友情も、誠実さも、相互理解も、たえず創作し続けねばならぬものであって、ほかに人間らしさの基盤などというものはない。そんなことが、ようやくわかってきたのだと言ったらいいか。
本性上、健康的に虚構のものであるはずの人間関係と、それを糸として編まれる社会という織物を、あくまで創作する、し続ける、という認識が、世界のどの地域でも希薄化している。そんな気がする。それも、数百年も昔から。あるいは、数千年も昔から。 真実こそ敵、と言ったら、狂人とでも思われるだろうか。まあ、言う必要もないのだが、この数千年の真実ブームの人類のなかで、真実よりは虚構の道を、いやまして、勝手に選ばせてもらっていこう、と考える。いつの時代、どこにあっても、虚構はつねに、幸福のためにわざわざ捏造されてきた。世間に背いてでも、わたくしはひとり幸福を選ぶ。からだや生活はともかく、たましいまで人類と心中させるわけにはいかないよ、と言い続けたい。
<机上にいてもらいたい>1999.5.17
机の上に、しだいに無駄なもの、有用でないものが増えていく。 ふと気づくと、ルルドで買ったマリア様、目をぐるぐる廻したよう な顔の、インドの金属製の目まわし鳥の香炉、アフリカのソープス トーンのお皿や宝石箱、ベイベリーのポプリ、プーさんの絵柄の ディズニー時計、大きなアメジストの塊、ドラえもんの陶製の貯金 箱、京都やインドのお香や香台、ラヴェンダーのアロマセラピーの 蝋燭、サンダルウッドやムスクやストロベリーのインセンスマッチ などが、勝手にじぶんたちの領土を獲得してしまっている。ピー ターラビットの卓上カレンダーは、いちおう有用のうちだから、 しょうがないか。このあいだ、火曜朝7時半のテレビ東京の『キ ティズパラダイス』を偶然見た時など、はじめてキティーちゃんの かわいさに開眼してしまい、なんでもいいからグッズを買いたく なって、とっても危険だった。妖精の小さな人形なんかもほしい ・・・・・と、きりがない。いいトシして、いちおうオトコなのに、趣 味というわけでもないのに、なんか、あぶないぞ、これは。
辞書も好きで、内容というより、装丁や組み方に惹かれてよく買 うのだけど、最近のヒットは『プチ・ロワイヤル仏和辞典』と 『ニュー・サンライズ英和辞典』。どちらも基本語の説明がわかり やすく、懇切丁寧でいい辞書だし、他の上級の辞書とともによく使 う。でも、このふたつが気に入って、いつも机上にある理由は、な により装丁がステキだということ。ともに旺文社だけど、このあい だ、じっくりとふたつを眺めていて、両方とも、服部一成さんとい うひとと、ライトパブリシティというところの装丁・デザインで作 られているということに気づいた。仏和のほうは、かるーいアール デコ調、英和のほうは白地にパステルブルーの文字。まるで、ヨッ トの帆に海が文字となってくっついたよう。ちゃんとした有用が、 有用さを脱ぎさっているようで、やっぱり、机上にいてもらいた い。
<、・・・・・・・・、問いはじめていた。>1999.5.15
東京郊外の、田畑と丘と森のほかにはなにもない土地で生まれた ことが、だんだんとじぶんの核になりつつあった・・・・・・
五月の連休、そこを両親とはじめて再訪してみると、むかしの面 影は残るものの、小奇麗なモデル地区となっていた。まあ、きれい になっちゃって、ねえ、・・・・・・と、母は言いやまなかった。
駅を出ると、ただもう、見渡すかぎりの田畑、草っぱら、森、林・ ・・・・・・ それだけのさびしい郊外に、豊かでない夫婦がたま たま住んで、風呂もなく、テレビもなく、たいした家具もない借家 で、生まれたばかりの病弱な子を育てていた。たしかにそんなこと が、この地であった、いまはすっかり消滅したその家、家をかこむ 風景、そこから、じぶんは、来た、?、・・・・・・・・・
そう思いながら、かつて家があったというところ、いまはグレー の現代風のマンションの建つ地に、立っていた。
じぶんの記憶に残る風景の、あの、貧しさ、さびしさ、を思い出 し、両親の語る当時の町並みを想像し、・・・・・・・そうして、 そこからこそ、わたしは来たのか?、と、「来た」という断言では なしに、嘆声のような、問いのような言葉をこころに響かせ・・・ ・・・・ すでに記憶と想像のむこう、風景の貧しさ、さびしさ の、その豊かさに触れられて、溢れるようだった。「来た」?、そ れとも、「居た」、のだったか? ずっと居た、のですか、と、わ たしに、問いはじめていた。ずっと居た、わたし、だった、です か、・・・・・・・・、問いはじめていた。
<レット・イット・ビー> 1999.5.16
レット・イット・ビーをひさしぶりに聴いている。日になんども 繰り返して。家で、リピートに設定して、聴き続ける。外で、MDで やはりリピートにして、聴き続ける。
そんなふうにして同じようにこの曲を聴いていたのは中学生の頃 で、ながい内蔵疾患が奇跡的に癒えた直後だった。六年も続いた病 のために、ぼくは育ち盛りの時代を育たずに過ごした。運動と塩分 摂取の禁止の六年間を、文字通り、ただ「暮らし」、「過ごし」、一 生、二度と走ることはできないという思いを心の底まで染みさせ て、成長していく友人たちを、時代を、見ていた。一生がじぶんの 傍らを通り過ぎていく、そう思って、いまさらなんの期待すら持た なくなっていた夏のある日、ふいに完治を宣言される・・・・・
ぼくだけの「戦後」の曲。余生のはじまりの曲。「すべてなすが ままに」という歌詞を繰りかえし聴いていたあの頃の心を その響 きを聴くように、いま、聴く。なんども聴く。毎週毎週の血管注射 や採血検査の終わり、日々、山のようだった投薬の終わり、病院の 待合室でのあれらの長い長い待ち時間の終わり、関節の腫れ、浮 腫、蕁麻疹、度重なる精密検査の終わり。六年も幽閉されて、突 然、生きろ、と、ふつうのひとのように生きろ、追いついて行け、 と言われたようで、なんの指針もないまま、歳相応の筋肉もない足 で、よろよろと駈け出し始めていた・・・・・・
あの頃のぼくの、駈け出しはじめた道の先を、いま、生きているのだろうか。「戦後」は もう終わったのか? 運命への復讐なんてこと、もう思ってないだ ろ? 心だって、癒えたのだろ?
・・・・・そんな言葉を響かせなが ら、MDをポケットに入れて歩く。電車に乗り、降り、また、乗り、 足だけが、どこまでも行く。<雨の木の下で>巣立ち(関富士子)へ
<詩を読む>川本真知子詩集「勾配のきつい坂」を読む(桐田真輔)へ
もくじ
詩人たち
最新号
BackNumber
vol.11
ふろく 閑月忙日
リンク
詩集など