 詩人たち
詩人たち 最新号
最新号 Back Number
Back Number vol.5
vol.5 閑月忙日
閑月忙日 リンク
リンク 詩集など
詩集など  詩人たち 詩人たち 最新号 最新号 Back Number Back Number vol.5 vol.5 | ふろく 閑月忙日 閑月忙日 リンク リンク 詩集など 詩集など |
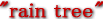 vol.5
vol.5<詩を読む7>藤富保男詩集『文字の正しい迷い方』を読む
つむじまがり
関 富士子
『文字の正しい迷い方』は、漢字を行に折り込んだ折り漢字詩集ともいえる。冒頭の「各々方(おのおのがた)」では作者みずから、
あなた方みなさんと親切に案内してくれる。しかしこの迷路はどこへ案内されるかわからない。
こちらの方へおいで下さい
あら あの方々という具合である。
方々さまよって
仕方なく
檻の中に一方的に入って行くみたい
「鬼」の中にすむ角のはえた「私」という人間(「ム」)、「風」の形定まらない抽象性(「クロードの風格」)、「片」のかわいそうな不恰好さ(「片思い」)、「音」の愉快な多義性(「人は音に囲まれて生きている」)など、漢字の意味や形、その音や訓を考察しながら、イメージをひろげて詩行に仕立てていく。
ときには漢字の姿かたちに詩人は異議を唱える。
犬の耳と言うのだから、思わずわが家の犬の耳を引っ張りたくなる。しかしこの考えは、漢字の本来の成り立ちに戻れば実にまっとうである。漢字はもともと象形から生まれたのだから。
犬という字の点である
左と右に点を打つべきなのだ(「いぬ」)
「つむじ概説」はこんな詩人の自画像に近い。
人をおそれずともかく読者は、詩の行の中に漢字が巧妙に折り込まれているのを、テクニックとして楽しみ、そこに独自の漢字論が展開されているのに驚くだろう。
神をおそれず
猿をおそれず
パンツも
名刺もおそれず
ただただ
まちがいなく
つむじが正しく曲がっている
ところで、この折り漢字の作業は、書くほうにとってはどんな意味をもつのだろうか。
頭が濡れた蒲団のように重い書けないというのは詩人の日常である。書かなければよいのだが、詩人だからそうもいかない。
詩の一行が出てこないから
頭が重いのである(「一行」)
仕方がないのですると、こうなる。
机を離れて
シガレットを一本すおう と思う
通りすがる勤め人の一行がこんな行も生まれる。
くさい動物を眺めるように
一瞥を放つ
見上げるとこの詩の場合、詩の一行は折り込まれる文字に触発されて生まれる。行の生成はその文字に全面的に委ねられる。おのれを無にして、煙草でも吸って、その文字から喚起される行をただ待つのだ。
蒲団会社 御一行様と表示してあった
濡れたバスが
綿ゴミを巻き上げて通って行く
そのとき、言葉遊びが本来もつ無名性が、作者の存在をさっぱりと消していくだろう。文字に呼ばれてどんな詩行が現れるかはだれにもわからない。この生成の過程を目のあたりにすることは、詩を書こうとする者にとってじつに興味深い。
藤富保男の場合、立ち現れた行とその詩の全体の姿は、辛辣な笑いに満ちたまさしくこの詩人だけのものである。
考えてみれば、詩を書く者は多かれ少なかれ同じ体験をするのではないか。たった一つ書きつけた言葉が、次の行を呼び、連へつらなり、詩の全体を形作ることがある。書き手はただ導かれるように、現れる言葉をひたすら書き留める。もちろん、こんな幸福はそうたびたびはない。しかし、そのたった一滴のインクのしたたりを求めて、今夜もペンを持つのである。
詩を書くことは、まず第一に、感情も体験も思想も、さらに詩という既成概念をもなきものにして、我が身を言葉に委ねることなのかもしれない。藤富保男の方法は、この言葉の喚起力と詩の成立との関係を自覚し、明確なスタイルとして採用したものといえるだろう。
ところで、今号の "rain tree" の present for you「おんがえし」は、詩集の中の「ケガ」のこんな詩行がヒントになっている。
と
か
げとかげ
と
がけ
かな文字で書いても
けが
をする思いだ

 <詩を読む6>「花丸」のごほうび(森原智子「花丸」を読む)(関富士子)へ
<詩を読む6>「花丸」のごほうび(森原智子「花丸」を読む)(関富士子)へ <詩>「先生が」(関富士子)へ
<詩>「先生が」(関富士子)へ present for you 「おんがえし」五音で遊ぶ(関富士子ほか)へ
present for you 「おんがえし」五音で遊ぶ(関富士子ほか)へ
 詩人たち 詩人たち 最新号 最新号 Back Number Back Number vol.5 vol.5 | ふろく 閑月忙日 閑月忙日 リンク リンク 詩集など 詩集など |
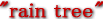 vol.5
vol.5花丸 (森原智子『スローダンス』1996年思潮社刊より) |

 <雨の木の下で5>「鳩を拾う」「gui詩gui詩(ギシギシ)」「言葉遊びの作者」「羽化・産卵」(関富士子)「フジトミィ」(宮野一世)へ
<雨の木の下で5>「鳩を拾う」「gui詩gui詩(ギシギシ)」「言葉遊びの作者」「羽化・産卵」(関富士子)「フジトミィ」(宮野一世)へ <詩を読む7>「つむじまがり」(関富士子)へ
<詩を読む7>「つむじまがり」(関富士子)へ present for you 「おんがえし」五音で遊ぶ(関富士子ほか)へ
present for you 「おんがえし」五音で遊ぶ(関富士子ほか)へ 詩人たち 詩人たち 最新号 最新号 Back Number Back Number vol.5 vol.5 | ふろく 閑月忙日 閑月忙日 リンク リンク 詩集など 詩集など |