 詩人たち
詩人たち 最新号
最新号 Back Number
Back Number vol.5
vol.5 閑月忙日
閑月忙日 リンク
リンク 詩集など
詩集など  詩人たち 詩人たち 最新号 最新号 Back Number Back Number vol.5 vol.5 | ふろく 閑月忙日 閑月忙日 リンク リンク 詩集など 詩集など |
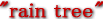 vol.5
vol.5<雨の木の下で5>
鳩を拾う 関富士子 (1998.6.11)
6月1日(月)
真夏のように気温が上がった更衣の日、コンクリートの道路の真ん中に動かない鳩を見つけた。 車はつぎつぎに鳩を見つけると徐行しながらよけて走り去る。全く飛び立とうとしないので、仕方なく車の切れ目を見はからって近づき、そっと両手で抱えるがなすがままだ。
ドバトである。見ると背中に羽根を毟り取られてつつかれたようなまだ新しい傷。左の目はとうにつぶれて灰色である。全体に弱りきっている。
クリーニング店への帰り道で、おおきな空の紙袋を持っていたので、それに入れて自転車で家まで連れ帰る。マンションのベランダは、犬のチャコや
チョウの幼虫や、高一の息子のカメの大きな水槽で満員だが、一部を囲って
鳩の居場所を作ってやった。
意識もうろうとしているらしく、チャコが匂いをかいでも鼻面で触っても動かない。水の入ったコップをくちばしにつけてやると、チャコが飲めというように一声吠えた。するとびくりと驚いて見えるほうの目を開き、くちばしを水に突っ込み、小さな水滴を飛ばして飲みはじめた。これで安心。あるいは、生きられかもしれない。クラッカーを砕いてやる。お湯にといたものをくちばしにあてがうが少ししか飲まない。
夕方、帰ってきた息子が傷を見て、病院に連れて行こうという。鳩が点滴してもらってチューブにつながれて喜ぶと思う? 鳩だって死ぬときは静かに死にたいでしょう、と言うと沈黙。
6月2日(火)
朝見ると濃い緑色の粘液状の糞をいっぱいしている。それもあちこちにしているので、夜のうちに多少動いているようだ。今日はくちばしに水をつけてやっても飲もうとしないで、嫌そうに首を上に反らすばかり。ごはんをつぶした流動食も受け付けない。昼間はほとんど動かず、ときどきからだがぐらぐらしている。見える方の目もじっと閉じたままである。息子に持たせてくちばしをこじあけようとするが、ちょっとあばれるだけで手を放してしまう。
6月3日(水)
水や流動食をくちばしにもっていっても首を振るばかり。しつこくやっていたら、突然身動きして180度向きをかえ、こちらに尾羽根を向けてしまった。断固たる態度にびっくり。そんなに嫌なら無理強いはしないでおこう。ここ数日の命かもしれない。
子供のころ、弱ったスズメを拾ってきたものの、水も餌もいっさい受け付けず死なせてしまったことがある。とても悲しかった。野生の鳥は人間の食べ物を食べないのだときかされた。子供たちが小さいころ、羽根も生えていないあかはだかのヒヨドリのひなを拾ってきたことがあるが次の日には死んでしまった。
しかし、娘が小学生のころ、子供たちがカワラヒワを拾って学校の教室で飼っていたことがあるが、あれはとても元気だった。休みの日は交代で家に持ち帰り、わが家でも夏休みの数日預かった。結局、野生の鳥は自然に生きるのが幸せ、と先生に説かれて、子供たちが見守る中、籠から放してやったときいた。ドバトは本来伝書鳩が野生化したものだし、雑食性だから何とかなりそうな気もする。
6月4日(木)
やはり水も食べ物も受け付けない。ご飯はつぶさず椀に入れて置いてある。しかし、もうろうとしていた意識は回復したらしく、ときどき動き回っている。首を回して背中の傷のあたりをくちばしで点検している。羽づくろいをするようになって、白い小さな羽根があたりに散らばっている。それを見た娘は「羽根を抜いているよ。鳩の恩返しだ」と叫ぶが、何のことやら。
しかし夕方見ると、今までなんとか立っていたのに、脚を折って座り込んでいる。立つ力もなくなったのか。
6月5日(金)
今朝見ると、ご飯の入った椀がひっくり返ってご飯粒が少し減っているような気がする。人の見ていないうちにこっそり食べたかもしれない。羽づくろいもしている。背中の傷は赤みが消えて、黒いかさぶたになった。自然の治癒力はすごい。これに頼るしかない。
それにしても不思議なのは、見えない方の目を常にこちらがわに向けている。見える方の目は壁の方を向いている。チャコが興味津々で柵に鼻面をつっこんで羽根に触れてみたりする。
6月6日(土)
昨日の残りのご飯粒が椀の周りに散らばっている。パンのかけらを置いてやるとつついた形跡がある。食べられるようになったのだ。糞も普通の白っぽいものに変わっている。動きが活発になり、羽根をばさばさ広げるときもある。餌のお椀や水のコップがひっくり返っているのは、その縁にとまろうとするかららしい。声をかけると首をかしげる。鳩は強い!
6月7日(日)
鳩がさかんに羽根を広げてばたつくので、娘が柵を取り払ってやる。娘の話ではダッシュして飛ぼうとしたという。わたしが見たときは疲れたらしくじっとしている。柵に戻し、少し広くして羽ばたけるようにしてやる。
息子が鳩の餌を買ってくる。コーンやいろんな木の実がたくさん混じっていて、炒って食べたらおいしそうだ。でも弱った鳩がこんな固いものを食べられるだろうか。ご飯粒の脇に並べて置いてやるが食べない。
夕方、チャコの散歩のときに息子がミミズを3びき取ってくる。夫はミミズは食べないだろうと言うがとりあえずやってみる。太いものはにょろにょろ動くので、チャコが興奮して吠える。鳩は見向きもしない。
6月8日(月)
鳩が来て一週間になる。朝見ると鳩の餌もご飯粒も減っていない。ミミズの容器は空っぽになっているので食べたかと思ったが、掃除のときに遁走してひからびているのを二匹見つけた。あと一匹はどこへ?
今日は昨日の元気がまるでない。一か所にじっとして動かない。糞も薄く白く真ん中が濃い緑色のを少しだけ。ほとんど食べていないのだからしかたがない。息子が、おい、どうしたんだ、と頭や背をなでてやるが動かない。
6月9日(火)
朝息子がベランダに出てあっと小さく叫ぶ。おい、大丈夫か、だめだ、死んじゃってるよ。
ついにその日が来たかと思いつつベランダへ。鳩が柵の間に首を差し出すようにして横たわっている。そっと首を引き入れてやるとすっかり冷たい。寿命かな、と息子。うん、寿命だね、あとでお墓をつくってあげるから、と言ってそのまま中に入る。息子は黙々と食事をして学校へ。
チャコが柵に鼻を突っ込んでしきりにクンクン鳴くので、死んだ鳩を持ち上げて嗅がせてやる。チャコはくちばしから脚の爪の先まで鳴きながら嗅いで点検している。死んじゃったの、と言ってきかせるが言わなくても犬はわかるだろう。
子供たちが保育園のころ使っていた古いランチョンマットに包んで、裏の植え込みの下に埋める。ビヨウヤナギの黄色い五弁の花が満開だ。おしべとめしべが髪飾りのように美しい花だ。
たくさんの小動物の死を見たが、死はいつも悲しい。こんなときは、新しく生まれるたくさんの命も見てきたことを思ってせめてもの慰めとする。
もくじ
詩人たち
最新号
Back Number
vol.5
ふろく 閑月忙日
リンク
詩集など
gui詩gui詩(ギシギシ)
詩誌「gui」(ギ)Poetry Reading のお知らせ 関富士子(1998.5.28)
guiの若手、古株取り混ぜて、にぎやかにやります。奥成達をはじめ、詩集「夜の水」を出した銀座マリーンの詩人ママ山口真理子、「横浜←→上海」で横浜詩人会賞受賞の徳弘康代、バロウズの翻訳で名だたる飯田隆昭、「葉山日記」の吉田仁、インターネットでおなじみ、Books bar 4-kamaの四釜裕子、京都から
「文屋」の萩原健次郎もやってくる。
日時 6月27日(土)午後7時から9時ぐらい
場所 'howl' the bar 3F La Boite Noire 渋谷区神宮前2-3-26 tel.03-5771-5577
JR千駄ヶ谷駅 徒歩10分 あるいは 地下鉄銀座線外苑前下車徒歩10分
外苑西通りをまっすぐ歩いて行くと、信号のそばの小さなビル。1Fにアレン・ギンズバーグにちなんだ'howl'というバーがあります。そのわきの螺旋階段を上って3Fの小さなスペースがLa Boite Noire です。
オーナーの藤本さんのご厚意で入場無料。ただし、大変狭い。
8畳ほどの壁際に15人ほど座れるベンチ。真ん中の床のシートにつめて座って15人。これ以上はどうしても入れません。
ただ、一階のバーにも音声は流れていて、お酒を飲みながら聴くことはできます。夏なら歩道のベンチで涼みながらというのも楽しそう。
というわけで、皆さん、どうぞおいでください。わたしはなぜか前回の Booby Trap の会に引き続き、関わることになりました。前回はお客の気分で行きましたが、今回は事務雑用を一手に引き受けました。
それでは、回文を一つ。
出た、詩の朗読。倉庫に元々入るの義理が。雨上がりguiの類は友、共に高速道路の下で
でたしのろうどくそうこにもともとはいるのぎりがあめあがりぎのるいはともともにこうそくどうろのしたで
<雨の木の下で5>「言葉遊びの作者」「羽化・産卵」(関富士子)「フジトミィ」(宮野一世)へ
<詩を読む6>「花丸」のごほうび(森原智子「花丸」を読む)(関富士子)へ
present for you 「おんがえし」五音で遊ぶ(関富士子ほか)へ
もくじ
詩人たち
最新号
Back Number
vol.5
ふろく 閑月忙日
リンク
詩集など
言葉遊びの作者(1998.5.21) 関富士子
言葉遊びは、ルールさえ決めてしまえば、同じスタイルでだれにでもできるところがよい。俳句や短歌の素人芸に似ている。本家はいちおうルールを作った人ということになるだろうが、おもしろければ遠慮なく遊んでしまえばいい。少々ルールから外れてもいっこうにかまわない。
スタイルを優先するということは、作る人間の存在は二の次ということだ。言葉は記号として単純化され、非常に乾いたモノそのものになる。定型に盛られた短歌はその器から情をふんだんにあふれさせるが、言葉遊びは逆に、いくら情を過剰にしても、どこか乾いてくる。器にヒビが入っているのだ。
ただ、どちらかというと、ルールはやはり自分で考えるほうがおもしろい。ルールが、まれに、表現しようとする者の切実な動機によって、必然的な形になって発見されることがある。その形は一回限りのスタイルとして言葉に詩という名称を与え、さらに、言葉の陰に消えたはずの作者を獲得するのだ。
ところで、"rain tree" vol.5<詩>「いいたい」(関富士子)は、次の詩を本歌としている。
いえないことは いえない*田代俊基
いいたくないことは いわない
いってならないことは いってはならない
いいしれず いいたい
いわくは いいがたい
いうにも いわれない
いわれなく いたい
いえなく くえない
いやされず いえない
いうほどには いうにことかき
いわずとも いいつのれば
いえるものなら いうまでもない「ア・フロワ」より「はだしのゲンに捧げる」)
田代俊基(たしろ としき)「東京上機嫌」ヘジャンプ
もくじ
詩人たち
最新号
Back Number
vol.5
ふろく 閑月忙日
リンク
詩集など
羽化・産卵 関富士子(1998.4.30)
4月8日に今年初めて羽化したチョウを見つけた。ベランダ用のサンダルの中にいて娘がうっかりふみそうになったが助かった。フリージアの花にとまらせてから、ベランダのあちこちを調べると、もういくつかのさなぎが空っぽだった。そのあと数日は続けてチョウが飛んでいくのを見た。
去年の秋さなぎになったナミアゲハが次々に羽化しているのだが、なにしろベランダは周りがコンクリートだから、壁にさなぎを掛けることになる。羽化したものはふつうさなぎのぬけがらにとまって羽を乾かすが、うっかり落ちるとまだ体が柔らかいためにはいあがれない。朝のうちに発見して、植木の枝にとまらせてやらないと、死んでしまうことになる。うちのベランダには犬も住んでいるので、これに発見されるといいおもちゃにされる。一冬を無事に過ごしてようやく羽化しても多事多難である。
さなぎのあいだも災難は多い。犬の毛が気になるので毎朝ベランダに掃除機を掛けるが、うっかり吸い込んでしまうことがある。雨風にはたいへん強いさなぎの糸も、不自然な力が加わると弱くて、切れてさかさまになっているものもある。
ちょっとおいたダンボールの箱にとりついてさなぎになるものもいて、冬じゅう片づけることができない。アルミサッシの外側にある狭い窪みは、ちょうどさなぎが収まる幅で具合がいいらしく安全でもあり、十個ほど縦に並んでいる。さなぎ団地と呼んでいたが、ここはほぼ全員が羽化した。
なかなか羽化が始まらないものもいて、そっと押してみるとこなごなに砕けてしまった。とうに死んでしまっていたのだ。掃除機のホースの先の部分でさなぎになったクロアゲハは、ナミアゲハより一回り大きく、立派な角が二本あって、おもちゃのロボット怪獣みたいで、いつもほれぼれと眺めているが、いっこうに羽化しない。
やれやれと思っていたら、このごろはグレープフルーツの植木に卵を産みにやってくる。ほとんどは羽化したと同じナミアゲハで、うちで産まれたものがどこかで交尾をしてまたもどってきたかと思うとうれしい。きのうはすばらしく立派なクロアゲハが黒い羽のかげに真っ赤な模様をちらちらさせて、幾度も産卵していた。うちのはまだか。
チョウはなぜ自分の食草がわかるのだろう。アゲハたちはあちこち飛び回って、葉に触れてみたりして慎重に点検し、グレープフルーツの葉だけに産卵するのだ。いっしょに生えているフリージアの細長い葉っぱにも一度お尻をつけたりしていたが、だいたいは間違えることはない。
今年もおおいそがしの青虫飼育が始まるのである。
フジトミィ 宮野一世(1998.4.30)
藤富保男との出会いは、十代の終わりごろ、たしか角川文庫の『全集・戦後の詩 第五巻』で読んだのが最初だったと思う。まず作品の前に置かれた藤富保男のプロフィールに、「以前からサッカーの選手だった。現在は関東蹴球協会に所属して、レフェリーvol.5もやっているとあって、へえっと思ったのを今でもはっきり覚えている。この全集によって現代詩の全体を大まかに俯瞰することができ多くの詩人を知ることができたが、藤富保男には、そのプロフィールだけで何か他の詩人とは違うものを予感したかも知れない。
詩を読んでみると、目が点になった。あるいは薮睨み、いや寄り目か。解説で大岡信が「藤富保男の詩を、この全集に収録された他の詩人たちと読みくらべてみれば、この詩人と「ことば」との関係がいかに独特なものであるか、一目瞭然であろう。彼は言葉に脱臼を起こさせる名人だ」と書いているように、まったく他の詩人たちにはない独自のものをぼくは受け取った。「言葉に脱臼を起こさせる」とは、読むものの言葉感覚を脱臼させることだ。
ぼくはみごとに脱臼した。もちろん痛快な脱臼。とにかくそれは新鮮な喜びだった。そして、「ほんとう」という詩の( )や、「一杯」という詩の 、
そうして
夕方がゆっくり { }
のようにあたりをつつむ と
など括弧を巧妙に使った表現に影響されてたとえば、
きょうぼくはすることがなくて
悩むことに忙しい
┌───┐
日程表は│ │
└───┘
という詩行を書き、そのころ入ったばかりの大学の文芸部のガリ版刷りの部誌に発表して、上級生から「部の歴史でたぶん詩にそんな四角を使ったのはきみが初めてだよ」とか「詩を嘗めてはいかん」などという言葉をもらって、勝手に得意になっていた。
でも元来単純な抒情詩人にすぎないぼくは書き手として─→フジトミィではなかった。心の奥に{フジトミィ}であった。そしてそれは時々「人間砂時計」のような詩になって孵る。うまく孵しているかどうかは、さてわからない。
*
ところで前号("rain tree" vol.4)の「グラグラと黒い墓」で紹介した『グラグラ』、あれはあくまでも『偽書百撰』という本に載っている「偽書」なのであって、実際には存在しない書物です。編者の「股区傴蛆世」は「こく嘘よ」或は「全く嘘よ」ということでしょう。
 <雨の木の下で5>「鳩を拾う」「gui詩gui詩」(関富士子)へ
<雨の木の下で5>「鳩を拾う」「gui詩gui詩」(関富士子)へ present for you 「おんがえし」五音で遊ぶ(関富士子ほか)へ
present for you 「おんがえし」五音で遊ぶ(関富士子ほか)へ 詩人たち 詩人たち 最新号 最新号 Back Number Back Number vol.5 vol.5 | ふろく 閑月忙日 閑月忙日 リンク リンク 詩集など 詩集など |