
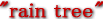 vol.9
vol.9
<雨の木の下で 9>
蜜柑を食べながら思うこと(1999.1.2) 関富士子
あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、正月というのはやはりよいものである。暮れの狂騒が過ぎて炬燵でぼんやり蜜柑を食べたりしていると、ほっとしてこれまでを振り返り、何か新しい抱負などを考えてみようかという気分になる。もっとも正月といっても日付が変わっただけで中身はあまり変わっていないのだが。
インターネットにホームページを持ち、詩の個人誌の発行を始めたこの一年半は、わたしにとってはとても重要な日々だった。それまで他者に向かって積極的に発信するという努力をしなかった。書いたものは所属している同人誌に載せてもらって満足していて、読まれることにあまり興味をもたなかった。詩は人のものを読むことも自分で書くことも、ただわたし自身のためにのみ大切なものだった。
詩は飢えた子供にたいして無力であるとはよく言うことだが、少なくともわたしにとっては無力ではない。心も体も癒し、人間の魂を救うものである。
家庭があって、仕事を持っていて、健康で、なんの不足もなかろうに、なぜ詩など書くのだ、詩は不幸な人のためにあるのだ、とある人から言われたことがある。たしかに今のわたしは幸福であるということができる。しかし、幸福、あるいは不幸とはいったい何だろうか。
一人の人間として社会の中で生きようとするとき、わたしという個人はその社会との軋轢を避けることができない。親との葛藤からに始まって、このことは幼いころからことあるごとに感じてきたことだ。小学生のとき集団の中で居場所を失い、死にたいと思いつづけた時期があったが、本を読むことでその苦しみから救われた。そのころから詩を書き始めた。それ以来自殺したいと考えたことはまったくない。
しかし、仕事を持って経済的に自立しようと思えば社会組織との摩擦に悲鳴をあげることになる。それは男と女という一対一の関係でも凝縮した形で現れる。社会的な存在であろうとする自分と、そこからはみ出してしまう自分がともにひどく苦しむのである。そんなとき、わたしは自分をなんとか取り戻すためにすがるように詩を書いた。
人の親になり、母として子供を育てることは喜びであったが、育児が社会的な役割の一つとしてあるかぎり、わたし自身の内面的な欲求を殺さなければならなかった。仕事をせずに育児に専念していたのはほんの5年間ほどだったが、詩を読むことも書くこともできず、その最後の時期は、ほかのだれも気づいてはいなかったが、わたしはほとんどビョーキになりかけていた。
あるきっかけがあって、子供を保育園に預けて仕事を再開し、すっかり失われていたような言葉をようやくかき集めて詩のようなものを書いてみた。そのとき目の前に垂れた幾重ものカーテンが一枚だけ開いたような、かつてない喜びを感じたのである。病が癒える時、薄紙を剥ぐようにという言い方があるが、そのカーテンのようなものは、詩を一つ書くごとに開かれていった。
わたしは今たしかに幸福だが、もし詩を書いていなかったらこの一日一日を生き延びることはできない。これはわたしだけではなく、詩を書く人が多かれ少なかれ実感していることではないだろうか。詩は書かれただけで存在価値があると考えるのはそのためである。それが作品としてどうかというような評価はまったく別の次元にある。
しかし、それではなぜ詩なのだろう。書くだけでいいのなら日記でもよいではないか。不平不満を思う存分ぶつけるだけで済むなら、また日々の生活の機微を記すだけなら、もちろん日記で十分だ。しかし詩でなくてははならなかった。しかも読むだけでは十分ではなく、自らペンを持って書き始めなければならなかった。
日記ではなく詩という形式を選んだ以上、それはいつかは他者に向かって差し出されるだろうことを前提とした作品にほかならない。ただの心情吐露をいったいだれが読むだろう。わたしの自意識など他人にとってはたかが知れている。普遍性と客観性をもち、読者の目の前になにか新しい世界を作り出すような希望のあるものでありたい。
そう考えながら、まだ見ぬ読者を前にして言葉をさがしているとき、わたしはわたしと社会との違和感がやわらかく融けていくのを感じる。わたしの場合、外的世界は一人の男の姿で現れることが多い。その男と和解することは、あるがままの自分が社会に受け入れられることでもある。そしていつかはともに新しい世界に進んでいきたいとせつに願う。
このことは、人の詩を読むときにも言えることだ。わたしに差し出された詩を読むとき、わたしは読者として最高の喜びを味わいたい。つまり、自分はもう書かなくてもいい、ここに自分が書こうとしたことがすでに書かれている、と思えるような詩に巡り合いたいのだ。
インターネットに詩のサイトをもつということは、わたしにとっては、詩という形式を選んだ時に前提となった読者という存在が、明らかになるかもしれない場所を得たということである。たがいに読者に相まみえたい、とほんとうに願うとき、あれほど相容れなかった世界は、わたしを大きな力で受け入れるだろう。
などと考えていると、もうぬくぬくとした炬燵から出て、いつのまにかパソコンの前に座り、もどかしくキーを叩き始めているのである。
詩にまごまごしている理由(1998.12.24) 桐田真輔
「言葉には2種類がある。「自分の言葉」と「他人の言葉」だ。これは結局、「人間には2種類ある、”自分”と”他人”だ」というのと、ほとんど同じだ。」(橋本治『ぼくらの東京物語』)
人間は自分専用の幼児語の習得から始まって、家族で流通する自分たち語、家族の外で流通する共通語(この違いは方言と標準語の違いを考えるとよいです)、というようにだんだん段階的に言葉をマスターしていくのだが、その間で、家族で流通するはずの自分たち語を学ぶ経験が、家庭へのテレビの浸透のせいで、とても希薄になっていて、そこをすっとばして、今や「家族の外で流通している言葉=特殊な自己専用語」だけの世界になってしまっている。という、とても重要な指摘を、橋本治は、『ぼくらの東京物語』という本の中で、しているのだが、そのことをすこし。
詩を読むというのは、人の言葉を自分(たち)の言葉のように取り込むということで、詩を書くというのは、自分の言葉(自己専用語)を、自分(たち)の言葉として表現すること。そして、もしかすると詩の究極の無理な願いというのは、自分の言葉と人の言葉がスムーズに通い合うこと。
つまり詩は自分(たち)の言葉と他人(たち)の言葉の世界の越境体験という性格をもっていて、たとえば、大人といえば親や近所の人や先生しかしらなかった子供が、詩を読むことで大人(他人)の内面世界をダイレクトに知る(ダイレクトに知る、というところがみそで、たとえば北村太郎は「詩は直撃力です」と言った)。体験したことのない深い恋愛感情なども知る。なんだか知ってるような気分になって、自分だけ大人の仲間入りをした気がして、そういう語彙をつかって詩を書きはじめる。こういうことには、体験の先取りという意味ももっていて、読んだ詩の意味が経験的にわかるのは先のことかもしれないけれど、言葉の経験としてみれば、すごく得難い貴重な体験です。また自分の言葉の世界と他人の言葉の世界(共通語の世界)の間の違和感に悩んで、詩(人前で言えば「世界を凍らせる」言葉)を書きはじめるということもある。
でも、こういうことはすこし怪しくなってきた。というより、とても見えにくくなってきた。なぜかといえば、最初にもどるのですが、基本的に家庭の中で、自分たちの言葉を覚えたり鍛えたりする経験が希薄になって、いごこちのいいテレビの世界「家族の外で流通している言葉=特殊な自己専用語」に一挙になじんで成長した世代が時代を担うようになってきたから。それが詩を読む体験、詩を書く体験にも影響を与えないわけがない。これは全然倫理的な問題ではないけれど、詩の理解ということも、これまでのようでは、結構、的をはずすってこともありそうな気がします。
「お母さんはつまんないことをグチャグチャ言うけど、お母さんの言うことが通用するのはこの狭い家の中だけで、この家の外はみんなテレビの言葉が流通しているんだから、お母さんの言うことなんか通用しないよ」(同前)
 <雨の木の下で>群ようこ「尾崎翠」を読む(桐田真輔)へ
<雨の木の下で>群ようこ「尾崎翠」を読む(桐田真輔)へ
 <詩>詩りとり詩(関富士子・北原伊久美・桐田真輔)へ
<詩>詩りとり詩(関富士子・北原伊久美・桐田真輔)へ
 詩人たち
詩人たち 最新号
最新号 BackNumber
BackNumber vol.9
vol.9 閑月忙日
閑月忙日 リンク
リンク 詩集など
詩集など  詩人たち
詩人たち 最新号
最新号 BackNumber
BackNumber vol.9
vol.9 閑月忙日
閑月忙日 リンク
リンク 詩集など
詩集など 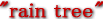 vol.9
vol.9 <雨の木の下で>群ようこ「尾崎翠」を読む(桐田真輔)へ
<雨の木の下で>群ようこ「尾崎翠」を読む(桐田真輔)へ <詩>詩りとり詩(関富士子・北原伊久美・桐田真輔)へ
<詩>詩りとり詩(関富士子・北原伊久美・桐田真輔)へ 詩人たち
詩人たち 最新号
最新号 BackNumber
BackNumber vol.9
vol.9 閑月忙日
閑月忙日 リンク
リンク 詩集など
詩集など