
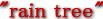 vol.16
vol.16
詩集「黄金週間」には、33編の詩が収録されている。それぞれの作品は二十行足らずの比較的短いものが多く、ページをひらくと視野に1編がぴったりと収まる(例外は2編だけ)。いろんな理由があってのことだろうと思うが、こういうレイアウトには、意外な効果がある。短歌や俳句を読むような感じで、スムースに視線をいきつもどりつできるので、変な言い方だが、どこか安心して作品を味読できるのだ。詩の内容も、そういう気分で、じっくり読むスタイルにマッチしている。何度も読みかえすことで、繊細で映像的な、確かな比喩の姿がしっとりとなじんでくる。
「髪を洗う黄金週間
薄い衣服が誘うように
くちを あけている」 (「黄金週間」部分)
「遠い鉄塔から鉄塔へ
はげしいものが流れる
めらめらと景色に穴をあける
くろあげは」 (「六月の影」部分)
「交配の罪が八重咲きの花のように
水にひろがり」 (「蘭鋳」部分)
「昼の星のように
噴水の一片のように
燐光の輝かしい混乱が
六月の静謐に融けてゆく」(「紋白蝶」部分)
「満開は
やわらかい雪崩になって
鈴のように青空を振り続ける」(「祝福」部分)
詩集の背景になっている季節は、春から秋にかけて。まず風景に出会う視線がある。この風景が実景として作者の眼前にあったものか、想像的に構成されたものかどうかは、わからない。ただその風景のなかで生じている変化に、作者の注意はうながされてゆき、そこにひとつの喩をとらえる。というよりも、注意をうながされたことを表す記述が、すでにして、心のイメージの表白であることのように詩はつくられている。
風景のなかの変化。それを象徴するのが、前半の作品に多く登場する「蝶」の姿だ。作品の表題も含めて、この詩集には蝶を示す語彙が頻出する(青筋揚羽、くろあげは、黒揚羽、紋白蝶、たては蝶、黄蝶、アゲハモドキ、春蝶、迷蝶、薄羽揚羽)。
これらの蝶たちは、ただイメージのさわりのように点景として登場する場合もあるが、ときには象徴的な意味を与えられている。その意味合いをいえば、心に、ひそか
に性的な情意を喚起するようなイメージの形象化として、といっていいかもしれない。
これは実は「蝶」という象徴に限らない。この詩集全体から受け取ることができるのは、作者が詩の情景に訪れる変化を、注意をこめて定着するときに、言葉にまとわせている成熟したエロスのイメージだ。だがそれをテーマとしてのエロスと呼んでいいのかどうか、ためらわせるものがある。そう呼ぶには情感が端正に流れすぎている感じを抱くからだ。
このことをうまくいえないのだが、作者はエロスの表白というテーマよりも、その表現構成に「明晰であること」(「薄羽揚羽」)自体に心を傾けているのではないだろうか。そういう意味では、「槍」と投げる「私」の関係を描いた「槍投げ」という、難解だが魅力的な散文詩を、作者の詩法として読みとりたい誘惑にかられもしたのだった。そこには、「明晰であること」を、書かれる言葉の側からとらえたような、不思議な表現の達成がある。
放れつづける力が晴天をくぼませ、その迅さを
投げるわたしの心がはるかに追い越してゆく。
槍は小さく渦巻きながら、厚い大地に突きささ
る。深々と、心を廃墟にして。白い踏切線のむ
こうに残されたわたしの肉体が、まだ揺れ止ま
ない力の翳りを見つめている。風が見分けられ
る。精魂こめて投擲するたび、わたしは、自分
がほんとうは何処から来て、何処へ帰ってゆく
のか、疾うに、知っているような気がする。
(「「槍投げ」全編)
古内美也子『黄金週間』(発行2000年3月20日・書肆山田)
******************************************
 桐田真輔
桐田真輔  KIKIHOUSE
KIKIHOUSE
******************************************
 <詩を読む>城戸朱理詩集『千の名前』を読む(三井喬子)へ
<詩を読む>城戸朱理詩集『千の名前』を読む(三井喬子)へ
 <詩を読む>山本楡美子詩集『うたつぐみ』を読む(関富士子)へ
<詩を読む>山本楡美子詩集『うたつぐみ』を読む(関富士子)へ