
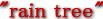 vol.16
vol.16
「今夜のおかず2000年4月」に掲載した文章。まとまりがなくて改稿しようと思っていたがなかなかできない。「白樺の木」についてもっと書きたいのだがとりあえずここまでと弁解しつつです。(関)
山本楡美子詩集『うたつぐみ』 書肆山田
を読む 関 富士子
|
枕もとにおいてくり返し読んでいる。何度読んでも不思議な気持ちに満たされる。謎が残るのだがその謎が気持ちがよくて、また開いてしまう。詩人のそばへ何処からとなく何時となく誰かがやってくるのだ。キッチンで、絵を見ていて、上水路で、大聖堂で。河馬と格闘するヘラクレスだったり、7、8人の「彼女たち」の塊だったり、行事の朝の空砲だったりする。詩人はその全体を受けとめる。描かれているのは彼らの存在のそこはかとない、あるいはくっきりとした気配である。
「ウタツグミ」では、イタリアの思想家グラムシの獄中書簡や、「ナルニア国物語」を書いたイギリスのC.S.ルイスの手紙の言葉を引き、彼らを「父たち」と呼んで、その存在が詩人のそばに現れる様子をこのように書く。
「ただ漠然と押してくる
白い綿雲のように押して
わたしが手で押し返せばとけていく
ひとつの感情のように」
そして詩人が言葉でわたしたち読者に伝えるのは次のような方法によってである。
「こどもであるわたしは
(イギリスにウタツグミという鳥がいるんですって)
と文字にして
もうすでに何度も手紙を書いた」
この詩の場合やってくるのは、「ひとつの感情」のような「漠然と押してくる」ものなのだが、彼らは具体的に詩人に影響を与えた人物である。その影響を人に「文字にして」伝えようとするとき、最終的にわたしたちは、普遍的な「ウタツグミ」という存在を伝えることにならざるをえないし、それがもっとも良い方法だ。
しかし、詩人のそばに現れるのは、このような具体的な人物ばかりではない。それらはときにはとらえどころがない抽象的な存在として現れる。
「おいでよ 生まれつきの夢
わたしたちが飛ばす塵や埃」(「どこからともしれない」)
詩人はいったい何を感知し、何を呼び寄せ、誰と会話をしているのか。親密な口調だが、大半は会話ともいえないような低いささやき声である。
彼らはこのように詩人を誘うのだ。
「霊草を摘みにいくんだよ」(「水の村」)
「それでもわたしはあなたの顔から目を離さず
うぶ毛をなびかせて
絶え間なく訪れるあなたを見つづける
砕けては繕いまた砕けるかけがえのないものに思えて」(「訪れる人」)
「信号を待つ人たちのなかに彼女はいた」(「抽象の人」)
そんな霊魂のような「抽象の人」のひとりに、一本の白樺の木がある。それは「倒れるくらいに斜めに」立っている白樺の木だが、このように存在する。
「横向きに生成する白樺
彼女と出会うものだけが
葉に編まれて
息詰まる」
読者であるわたしは息を凝らし、耳を澄まして聴こうとする。あるいは姿を思い描こうとする。そこに誰がいるのかを知ろうとして。出会う者を葉に編みこんで息を詰まらせてしまうくらいの生命力を持つものの存在にはげしく魅了される。
「わたしは緑色の血管に肥厚した皮膚を隠し持っていた
体のなかで鞭が静かに鳴っていた」(「抽象の人」)
そんなわけで、彼らは詩人のそばにやってくるのである。
詩人は白樺の葉に編みこまれることを望んでいる。なぜなら詩人もまたそのような存在だからだ。
「その暗闇と
ただ親しくなりたくて」(「ある暗さ」)
彼らに親しく交わる力を持っているのは、詩人自身の血液が緑色だからだ。しかし、詩人自身は「抽象の人」ではない。いつも、生きる限り、わたしと同様、彼らに魅了されている人の一人だ。その喜びを伝えながら、詩人は悲しげでもある。
「死んでしまったものよ。
死んでいくものよ。
わたしを立ちどまらせて−−」(「真夜中に」)
山本楡美子詩集『うたつぐみ』2000年2月25日刊 ご注文は 書肆山田
書肆山田
 古内美也子詩集『黄金週間』を読む(桐田真輔
)
古内美也子詩集『黄金週間』を読む(桐田真輔
)
 ダイアン・ディ・プリマ「1955年感謝祭のためのリスト」を読む(中上哲夫/関富士子)
ダイアン・ディ・プリマ「1955年感謝祭のためのリスト」を読む(中上哲夫/関富士子)
書肆山田