
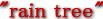 vol.17
vol.17<雨の木の下で>
夢想する日々 2000.8.9 関 富士子
日々を滞りなく過ごすためにくりかえされるたくさんの仕事。床を拭き衣類を洗い火を使って調理をする。電話を受けキーをたたき紙をつぎつぎにめくる。その一連の作業は、何年もの間毎日行われているので、ほとんど何も考えず、無意識のうちに進んでいく。すると、動きを止めたほんの一瞬、自分が今何をしていたのかわからなくなることがある。
そのときわたしはまったく別の想念にとらわれている。どんな想念かと具体的に言うことは難しい。情感のある音楽を聴いているような状態というか。実際には音楽はほとんど聴かない。楽しかった記憶を反芻していたり、漠然とした甘い不安感を抱えたままのこともある。手を確実に動かしながら、わたしの心はいつもうわのそらで、ここではないどこか遠くへ出かけている。
実際の夢の中で詩を書いていて、これは傑作、目覚めたらすぐに書きとめようと考えているのに、朝にはぼんやりしか覚えていないという経験はないだろうか。そのときのように、何かことばが胸から出かかっていることもある。詩が現れるのかと思ってノートを広げてみるが、たいていは何も書けない。
 今日は朝からずっと、胸の中にかすかなイメージが色だけになって漂っていた。全体は淡い青である。下に行くにしたがって青が濃くなる。非常に静かな暗喩に満ちた青。海にでも出かけていたのだろうか。ふとテーブルに夕べ読んだ詩集が置いてあるのを見て、その夢想の源にようやく気づいたのである。
今日は朝からずっと、胸の中にかすかなイメージが色だけになって漂っていた。全体は淡い青である。下に行くにしたがって青が濃くなる。非常に静かな暗喩に満ちた青。海にでも出かけていたのだろうか。ふとテーブルに夕べ読んだ詩集が置いてあるのを見て、その夢想の源にようやく気づいたのである。
エンマは、青が好きだった。
アーケードの店で売っているドレスやリボンの青、あるいは軽四輪馬車の窓に掛かった絹のブラインドの青。愛について語られている本のカバーの青。ダンスの後で、頭の中に残っている音楽の青い色彩。
だか彼女はいちども海を見たことがなかった。
(ジャン・ミシェル・モルポワ『青の物語UNE HISTOIRE DE BLEU』1999年思潮社刊より「愛の最後の知らせ」部分 有働薫訳より)
 <雨の木の下で>一冊の詩集ができるまで(関富士子)へ
<雨の木の下で>一冊の詩集ができるまで(関富士子)へ
 <詩を読む>山本楡美子『うたつぐみ』を読む(桐田真輔)へ
<詩を読む>山本楡美子『うたつぐみ』を読む(桐田真輔)へ
今日は朝からずっと、胸の中にかすかなイメージが色だけになって漂っていた。全体は淡い青である。下に行くにしたがって青が濃くなる。非常に静かな暗喩に満ちた青。海にでも出かけていたのだろうか。ふとテーブルに夕べ読んだ詩集が置いてあるのを見て、その夢想の源にようやく気づいたのである。