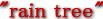 vol.17
vol.17
私たちが日常でであう見慣れた情景、音や形のなかに聴き慣れない音を聞き取り、
見慣れない形を読みとること。おそらくそんな一瞬の感触が心にとどまっていて、詩
を書くことのさわりになっている。その一瞬の体験を物語のようにふくらませて作品
を構成することも、その由来を過去にたどっていって結果的に作品に厚みをもたせた
りすることも可能だ。しかしそうではなくて、その一瞬の体験が物語を構成して完結
する手前で作品を閉じてしまうこと。由来を過去にたどっていって像が鮮明になりは
じめる手前で引き返してくること。そうすると、言葉は謎のようなものとして残る。
その謎は、最初に音や形が聞き慣れず見慣れない形で訪れたそのことの、意味づけら
れない不思議な初源の意味と交感して、どこか収まりのわるい、かゆいところに少し
だけ触れられたような、くすぐったいような魅力的な言葉の世界をつくる。
もうすこし、山本さんの詩の言葉の世界の特徴をいえば、対象や情景のとらえかた
の言葉の感覚の伸びやかさと、人称化への要求ということだろうか。幻が幻として描
かれて少しも病的な感じがしないのは、多くの作品に見て取れる終連のたち際の鮮や
かさや、幻を統御するための情景の人称化ということがよく自覚されているからに思
える。もちろん、この情景の人称化は方法論的に呼び込まれたものではなくて、むし
ろ無意識に聞き慣れない音を聞き、見慣れない形を見ることの自己意識の多重化の根
拠にあたっていて、著者は鏡像のように世界を映しみているのだ。私の感触では、こ
の人称化は95年の「抽象の人」あたりでピークをむかえて、後半に収められている
詩編では、しだいにわたしとあなたの分離という個別性を獲得しはじめていると思う。
この詩集に収録されている作品がおよそ13年の間にわたって書かれたということ、
またそれを書かれた順序そのままで詩集にまとめられているという、けれんみのない
著者の配慮も含め、とてもいい感じで詩とつきあってこられたのだなあと思う。散歩
したり自転車で通り過ぎたりする、家の近所には上水路があり、こんもりした森(井
の頭公園裏?)があり、著者はこの10数年、なんどもなんども(木々に挨拶したり
水音に耳をすましたりしながら)その小道をくぐりぬけたに違いない。家にはよく拭
きこまれたガラス戸があって、いろいろなものが写るし、キッチンでもいろんな音や
声がきこえるし(^^;。。そういう一見平穏な近郊都市生活からこんなに魅力的でおか
しみを含み、時にちょっと怖いような詩編が沢山生まれたということが人ごとながら
喜ばしい。
言葉の伸びやかな前半の詩編がすごく個性的なのだが、ここでは、短い作品「冬の
椅子」を紹介しようと思う。ありふれた椅子の布地のほつれに草むらを見る。その草
むらが大きな幻の草原になって広がっていくイメージの手前で心を鎮めて、瞬時に過
ぎていった幻をそっと慈しんでいるような著者の繊細な感触(詩法)が、読む人に伝
わればいいと思う。
冬の椅子
ダイニング・チェアの布地がほつれて
草むらがのぞいている
その綿毛はどこにつながっているのだろう
もろい陽光が揺れるたびに
一点が銀色に光る
やがて
もうひとつの椅子から
女が立ちあがった
女は草の傷口に両手を当てて
名前のない光を
そっと包んだ
山本楡美子詩集『うたつぐみ』2000年2月25日刊 ご注文は 書肆山田
書肆山田
******************************************
桐田真輔
e-mail:  kiri@air.linkclub.or.jp
kiri@air.linkclub.or.jp
:  http://www.linkclub.or.jp/~kiri
http://www.linkclub.or.jp/~kiri
******************************************
 <雨の木の下で>夢想する日々(関富士子)へ
<雨の木の下で>夢想する日々(関富士子)へ
 <詩を読む>『御庄博実第二詩集』を読む(桐田真輔)へ
<詩を読む>『御庄博実第二詩集』を読む(桐田真輔)へ
書肆山田