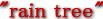 vol.17
vol.17
<詩を読む>
遠くへいかない歌(淵上毛錢を読む) 2000.8.24 布村 浩一
岩本勇からぶあつい淵上毛錢の詩をコピーしたものを渡される前に、自分で淵上毛錢の詩集を探してみた。みつからない。ぼくの住んでいる国立の町の本屋にはなく、隣の立川の大きな本屋でやっとみつけた。淵上毛錢の個人の詩集はなく、中公文庫の「日本の詩歌・近代詩集」というタイトルの六十三人の詩人のうちの一人として、あった。埋もれた詩人なのだ。ぼくもはじめて読む詩人だ。
淵上毛錢というちょっとおかしなペンネームから、いかにも戦前的な、昔の詩人というイメージを持った。しかし立川の本屋で文庫の中の五編の詩を立読みしながら、古くはないと思った。分かりにくくもない。簡潔だった。こういう詩人が昔いたのだと思いながら、税込み九八〇円の文庫本を買った。まずはいい出会いだ。
彼の書いたほとんどの詩は二十行に満たない、短い詩だ。満ち足りた気持ちを歌う詩ではない。しかし暗くはない。ユーモアもある。「簡潔」「やわらかさ」「ゆるやか」「願い」「日常の」という言葉が浮かんでくる。たくさん詩を作った人のようだ。渡された「淵上毛錢全集」(国文社)のコピー紙四〇二ページのうち、年譜が十ページぐらいだから、このぶあついコピーの紙は詩で満ちている。
ちょうど春分の日の、休日、陽射しの入ってくる部屋の中で淵上毛錢の詩を読みつづけた。百編はあるだろう。ぶあついコピー紙の、詩を読みつづけているあいだ、感受のうちの一つの扉で、同じ扉で淵上毛錢の詩と向かい合いつづけたと思う。淵上毛錢の日常とずっとつきあっている気がした。一人の、寂しい歌だと思った。遠くへは行かない言葉。
淵上毛錢は一九一五(大正四)年から一九五〇(昭和二十五)年まで生きた人だ。その時代に生きた人の詩の言葉を身近に感じるのは不思議だとも思う。
彼が死んで五〇年が経っている。一九五〇年までの大正から昭和に入り、それから戦前、戦中、敗戦後とつづく淵上毛錢の生きた社会は、ちょうど二十一世紀を迎えようとしている、二〇〇〇年の今の社会とでは大きな落差があるはずだ。しかし彼の書いた詩がストレートにはいってくるのは何故だろうと考える。
それは淵上毛錢が、日常の、自分の視線の届く範囲を歌ったためだと思う。日常の視線の言葉というのはなかなか古くならないのだ。淵上毛錢は視線のそんなに遠く行かないところで、自分の歌を歌っている。遠くまで行かない視線が、「情景」や、「簡単な思い」を連れて、ぼくたちのところまで届いてきている、と思う。
年譜を読むと一九三五(昭和十)年、二十歳の時から胸を病んでいる。結核ということなんだろうか。あまり動けない生活だったと思う。動かない人。病気のせいもあるだろうが、淵上毛錢という人はそういう遠くへ行かない資質の人だったという気がした。動かない、視線を無限の方には持っていかなかった人。寂しい日常のスケッチを描きつづけた人。簡潔に、やわらかく、願いのようなものを書きつづけた人。数十年という時差があるけれども、そこに淵上毛錢の詩を感じ取れる理由があると思った。
たとえばぼくは行こうと思えば、どこへでも行くことができる。しかし実際のところは生活圏の外に出て行くということがほとんどない。毎日職場に通い、部屋に帰り、また職場へ行く。その間には散歩だけがあるような生活をしている。週一回ぐらいはビデオを借りて楽しんだり、ときどき都心の映画館に行ったりする。そして毎年正月になると岡山の田舎に帰るのが、この東京の町を離れる唯一の時だ。ぼくがどこにも行かないのは、どこへも行く気がないということかもしれない。
遠くへ行こうという気をなくしてしまっている自分を嘆く気持ちがあるわけではない。それが自然のような気がしている。これから何かが変わっていくだろうという予感は絶えず持っているのだが、ぼくの生活圏は狭く、毎日おなじようなことを繰り返している。淵上毛錢とは、遠くへ行かないという視線でつながることができると思った。
最初から詩人のイメージというのは遠くへ行かない人だったわけではない、中学校の小さな図書館でランボーの冒険物語に憧れたこともある。その時、詩人というのは遠くに行く人だった。ここではなく、ちがうところへ絶えず行こうとする人。高校を出るまで、地方の田舎というよりは、古い村落共同体に住んでいたぼくは、そのころ淵上毛錢の詩に出会ったとしても、よく分からなかっただろう、立ち止まることもなく、そのまま通り過ぎてしまったと思う。
ぼくのなかの詩人のイメージの変わり方は、六十年代以降の、この日本の社会が体験した非日常的なものへの、イメージの変わり方でもある。詩を書く人とは、遠くに行く人ではなく、近くで、生活の中で、生活の中のあるへこんだ場所に、一日のある時やってきて、じっとうずくまる人たちのことなのだ。そういうことになった。
世界はもう隅々まで見えているし、遠くへ行ったところで未知のものがあるわけではない。今のぼくたちに人間が美しく見えているとはいえないし、社会の具体的な場で生きつづければ、いい人のままでいられることもできない。
生きようとするなら、人を押し退けなければならない時もある。社会の雑な暮らしの中にまみれて、ときどきそっと自分の中の硬いもの、やわらかいものに触れることができればいいほうなのだ。たまには人間を信じることができて、熱い夜を持つことができるかもしれない。それがせいいっぱいだ。
淵上毛錢の日常的な、視線を遠くに持っていかない詩の言葉が、簡潔な一つの思いの、装飾しない願いのような詩の言葉が今、ぼくの心によく届くと思う。冬と春の境のような、ちょっと暖かい日に、本屋で、さがし回ってやっとみつけた文庫の中の五編の詩を立読みした時から、ぶあついコピー紙の、たくさんの詩を読み終わる時まで、彼の書いた詩を、過去の、遠いものだとは思わなかった。ちょうどいい時に淵上毛錢の詩を読むことができたと思う。
初出誌 「詩学」2000年6月号「淵上毛錢特集」より
 <詩を読む>言語秩序からの解放
栄瞳流フリル言語の生成
(佐藤文明)へ
<詩を読む>言語秩序からの解放
栄瞳流フリル言語の生成
(佐藤文明)へ
 <詩>崖の町(布村浩一)へ
<詩>崖の町(布村浩一)へ
