
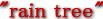 vol.18
vol.18
黒い羊はたくさんいるよ−ヨーコ・オノ、塩見允枝子、白石かずこ、ヤリタミサコ
2000.11.8 ヤリタ ミサコ
高校生のときだった。ヨーコ・オノに手紙を出して、秘書から返事をもらったのは。1970年代北海道夕張炭田の端っこの炭鉱では、世界の女性たちの動きも彼女たちの考えもほとんどわからなかったが、ものごころついたときから「大きくなったらお嫁さんになるの?」という大人からの強制に猛烈に反発していたヤリタミサコにとって、ヨーコ・オノはわが英雄であった。
キュリー夫人も、ナイチンゲールも、もの足りなかった。他に女性の英雄は知らない。市川房枝や平塚明子を知るのはもっとあとだった。
大学生のときには、婦人問題研究会で討論した。私たちはどうして「婦人問題があって、それに対応するコトバがないのか、それこそが問題なのだ」と激烈に怒っていた。婦人に対応するのは、殿方?ちゃんちゃらオカシイ。男性問題が問題だから、女性問題があるんじゃないか!!!
大学1年生の夏休みに「第二の性」を3回読んだ。これこそが私のバイブルであると実感した。
エンゲルス「家族・国家・私有財産の起源」にも心酔した。
大学院ではもちろん、女性学を学んだ。3歳半から実感してきた不平等への不満をぶつけ、正々堂々と男たちを罵倒できるのだ。とっても楽しかった。「男根主義者」というレッテルは、そんなやつのはチョン切ってしまえ、というコトバによるリンチ暴力とほとん同じだった。だが、男と同じテツを踏んではならない。
上野千鶴子や田中美津さんにも夢中になった。が、しかし、私は詩人であった。家事や子育ての分担のためだけに女性学をやっているのではない。自分のなかにさえも、どこかに女性を低く見くびってディスカウントしてしまう価値観が、まったくないとは言えない。男でも女でもなく、世界に1個しかない自分として、自分らしくのびのびと自己表現すること。それが、私の女性学なのだ。
白石かずこは1965年に「男根(penis)―スミコの誕生日のために」を発表した。塩見允枝子は、ニューヨークで1965年から「spatial poem」を運動した。その後30年たってから、ヤリタミサコは、かずこさんとビートし、允枝子さんとフルクサスしている。
1996年に赤坂でヨーコ・オノのコンサートを見た。たくましい筋肉質の腕と、名作「fly」以上に言語と音楽を拒否するコンサートだった。
黒い羊たちは、世の中にたくさん生息している。アタリマエだよね。
YARITA Misako( yarita@mguad.meijigakuin.ac.jp)
yarita@mguad.meijigakuin.ac.jp)
 <雨の木の下で>言葉を織る女たち(関富士子)
<雨の木の下で>言葉を織る女たち(関富士子)
 <詩を読む>若林道枝『パッチワークの声』を読む(三井喬子)
<詩を読む>若林道枝『パッチワークの声』を読む(三井喬子)
yarita@mguad.meijigakuin.ac.jp)