
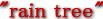 vol.18
vol.18
<雨の木の下で>
悪霊退散 2000.11.1 関富士子
10月28日の西脇順三郎の会の帰り、会場の日本近代文学館から井の頭線の駒場東大前へ向かう途中、塀の上に大きな南瓜が置いてあるお宅があった。あ、ハロウィーン!と思ったが、日本ではこのお祭りについてはクリスマスほどに馴染みがあるわけではなく、わたしにしても、「万聖節」? ふうん、といった程度である。悪霊退散を願ってというが、アメリカで日本人留学生の射殺事件があってから、どうもハロウィーンのアメリカは物騒だといったぐらいの印象しかない。
それはそれとして、ハロウィーンには、子供たちが仮装をして通りを練り歩き、家々の門口でお菓子をもらうという風習を聞くと、そういうことはわたしだってやった覚えがあるという思いにかられて、それにつながっていつも必ず思い出してしまうことというのがあるのだ。
わたしは福島県の福島市に近い小さな町で育ったが、ここにもちょっと似たような冬の行事があった。「コッコドリ」といったっけ。小正月の1月15日の前日14日である。この日は、いろとりどりの小さな餅を棒に差して玄関や神棚に飾る、豊作祈願の「だんごさし」の日でもあって、これが終わると、夕方、近所の子供たちが手に手に布袋を下げて、いさんで集まってくる。時代は、ベビーブーマーの悪童たちが町や村にあふれかえっていた昭和35年(1960年)前後か。幼児から小学校の高学年まで、「コッコッコッコ」と鶏の鳴き声を大声でまねながら近所を練り歩く。仮装はしなかった。
冬の夕方だからすぐ日は暮れてしまう。年長の子供は蝋燭をともした提灯を持っている。みんなと一緒とはいえ、街灯もない田舎の雪道を歩くのは心細い。でも、暗くなって出歩くなどはもってのほかの時代だから、年に一度許される冒険に昂揚している。お化けが出そうな怖さと、お菓子が貰える嬉しさ。田舎の家は街道沿いでも密集していないから、その窓からもれる、ぼんやりした暖かそうな明かりを頼りに行くのである。
門口でわくわくしながら「コッコッコッコ」と呼ばわると、玄関先にはざるに入れたお菓子が用意してあって、家の人がひとりひとりに手渡してくれる。せんべいや飴など、日持ちのする駄菓子や干した柿や芋や蜜柑のたぐいである。だんごさしで余った餅もある。一軒一軒回って自分の家の近くで三々五々別れて、午後7時ぐらいにはみな家に帰るのだ。
福島の母に電話で聞いてみると、この行事は「カセドリ」というのが一般的らしい。辞書を引いたらと言われて「カセドリ」を広辞苑で引いてみると、
「カセドリ」
小正月の夜、鶏の鳴き声などをして各戸を訪れて物を貰う民間習俗。福島県で「カッカドリ」、山形県で「カセイドリ」、岩手県で「カセギドリ」などという。
という説明がある。
ネット検索をしてみると、まだ風習が残っているところがあるようだ。土湯は福島県北部の温泉場。わたしもよく家族と出かけたところである。懐かしいな。リンクしておこう。 土湯の歳時記 かせどり
土湯の歳時記 かせどり
「コッコドリ」はどのぐらいの範囲での呼称だろう。岩手の「カセギドリ」から「稼ぎ鳥」の意味かなというくらいは想像がつく。「稼ぎ」が鶏の鳴き声のコッコッコに重なって「コッコドリ」となったのかもしれない。雪道で足下は危ない。物をもらって歩くなどコジキみたいだ、あるいは不衛生であるという理由で、学校では先生に参加しないようにと言われたように思う。そんなこんなで、わたしの育った町では、昭和40年代には行われなくなったようだ。
わたしのかすかな記憶では、ある家の戸口で「コッコッコ」と声を張り上げると、「うちはなにもねえぞう」と怒鳴る男の人の声を聞いたことがあり、あそこの家はケチだと子供たちと言い合ったものだが、母に聞いてみると、物忌み(喪中)の家では行わない慣わしだから、たまたま喪中だったのだろうということだ。そんな家には行かないようにとあらかじめ言われるのだが、子どもたちは忘れてしまう。水をかけてよこす家もあったとは母の子供のころのコッコドリの思い出だ。
母はさらにいろいろ思い出してくれた。「コッコドリ」の行われる1月14日は、家族に厄年の人(19歳の女性や25歳の男性)がいる家では、厄落としのために天まり(紙風船)や天ばた(凧)を近所に配る風習があったという。今は廃れたが一部では今でも洗剤や饅頭を配る家があるそうだ。ハロウィーンは悪霊退散のお祭りだそうだが、「コッコドリ」も厄落としの意味があったのではないだろうか。
その次の日の1月15日の小正月は女正月ともいって、嫁は女の子だけを連れて里帰りをし、里ではその家の嫁や姑や姉妹など、女性だけが集まってお祝いをしたという。うちは4人姉妹だからみんな連れて里帰りをしたのだろうが、母の里は一時間ほど歩いて山一つ越えた向こうの村で、始終遊びに行っていたし、当時は法事や祭など、さまざまな行事がたくさんあったから、小正月についての特別な記憶はない。
それでも、「コッコドリ」のように子供たちが中心の行事はそうたくさんはないし、親も子供たちも楽しみにしていたのに、どうして廃れてしまったか。よい風習ではないなどという大人がいたのかもしれない。あんたもそんなことを懐かしがる年になったんだね、と母は述懐するのである。
電話を切ってからいろいろ考えた。
「コッコドリ」の行事でどうしても忘れられないことがある。
どういう経緯でか忘れてしまって、母にも聞きそびれたが、わたしの家の裏の木小屋に、一時身寄りのないおばあさんが独りで住んでいたことがある。やがて親戚に引き取られたはずだが、わたしのぼんやりした記憶では、足掛け2年はいたはずである。木小屋は西向きの2階建てではしごが掛かっていた。一階には藁束や農機具などの道具類、じゃがいもなどの保存野菜類が置いてあって、子供はめったに行かないところだった。
わたしの育った家は織物業を営むいわゆる機屋(はたや)で、家に隣接する工場には女工さんたちが大勢働いていたが、それとは別に「糸通し」という内職のような仕事を近所の家に頼んでいた。おばあさんも隙間風の入る粗末な木小屋で、一個だけの裸電球をともし、肩のこる細かい糸通しの仕事をしてひっそりと暮らしていたのだ。普段のおばあさんの暮らしぶりについては、それ以上の記憶がない。
その年の「コッコドリ」の夕方、わたしは母に何度も言われた。裏のおばあさんの木小屋にも必ずみんなで行くように。おばあさんはお菓子をいっぱい買って、みんなが来てくれるのを楽しみに待っているんだから。前年には言われなかったのだから、木小屋におばあさんが住むようになってまもなくのことだろう。
わたしはもちろん、おばあさんのところへ行くつもりだった。でも、家々を回り、袋がお菓子でいっぱいになり、日が暮れてあたりが真っ暗になると、おばあさんの木小屋に行くのが億劫になった。木小屋に行くは、家の裏の工場と、便所や味噌蔵の並んだせまい路地を通って、畑の横の道をとおらなければならない。じめじめしていて臭いし、みんなも行きたがらないだろう。だいいちそんなところに人が住んでいるなんてびっくりするかもしれない。わたしの家は地域の外れにあったから、道のりもいちばん遠いのである。おばあさんの家に行こうとも言い出せないまま、子どもたちは散り散りに別れていく。
家に帰ってくると、母はすぐに、裏のおばあさんのところに行ったかと尋ねる。行かなかったと答えると、今すぐ行きなさい、あんたたちだけでもいいから、と言う。わたしたち四人姉妹はしかたなく、提灯で足下を照らしながら、「コッコッコ」とおばあさんのところへ行った。おばあさんは薄暗い明かりの下で待っていてくれて、わたしたちを見るとにこにこしながら、「よく来た、よく来た」と言って、大きなざるの中からせんべいを一つかみずつ取り出してくれた。
そのときわたしは来てよかったと心底思ったのである。おばあさんの喜ぶ顔を見てとても嬉しかった。妹たちもそう思ったはずだ。でもどうしてだろう。その翌年の「コッコドリ」の晩も、わたしたちはやっぱりおばあさんのところに行かなかったのだ。しかも、母に行ったの?と聞かれて、行ったと嘘をついたのだ。嘘は翌日にはわかって、母に叱られた。おばあさんはずっと待っていたのに、だれも来なくてがっかりしていたよと言われたのだっけ。
そのあとの「コッコドリ」のことは覚えていない。わたしはもう小学校の高学年になっていて、真っ暗な雪道を歩いて、家々の明かりに迎えられる、不安と期待に満ちた胸の高鳴りを感じられなくなったのかもしれない。学校からよくない風習だと言われて、参加するのをやめてしまったのだったか。あるいは、行事そのものが廃止されてしまったのだろうか。
昭和30年代の後半、白黒テレビが我が家にやってきた。町のせまい砂利道にはぐにゃぐにゃのアスファルトがしかれ、臭い自動車が走るようになった。蒸気機関車は真っ黒な煙を吐くディーゼル車に変わった。父は田んぼの真ん中に新しい工場を建て、今までの木製織機を捨てて、鋼鉄の自動織機を入れた。3交代で機械を動かすようになり、夜明けから深夜まで機の音がした。日本の高度成長期が始まったのだ。
女工さんたちは寝不足のまま赤ん坊を背負って機を織った。四人姉妹の長女だから、養子をとって機織りをやれと言われていたが、こんなところにはいられない、いつか家を出ようと思い決めるようになった。わたしは知らなかったが、変化しているのはわたしの心だけではなかった。あの時を境に、日本じゅうの町も村も野山も川も森も、なにもかもが大きく変わってしまった。「コッコドリ」の終わりはその先触れだったのだ。
 <雨の木の下>北村太郎の会/小さくて濃い朗読会駿河昌樹「モウ戻リノキカナイモノ。ソレトトモニ行ケ。行ケ。」の感想
(桐田真輔)
<雨の木の下>北村太郎の会/小さくて濃い朗読会駿河昌樹「モウ戻リノキカナイモノ。ソレトトモニ行ケ。行ケ。」の感想
(桐田真輔)
 <雨の木の下で>言葉を織る女たち(関富士子)
<雨の木の下で>言葉を織る女たち(関富士子)
土湯の歳時記 かせどり