
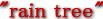 vol.20
vol.20 地上の人に告げて
地上の人に告げて 梅を見に
梅を見に 机と椅子のある庭
机と椅子のある庭
地上の人に告げて
|
|
| 海の湿った舌状気団が長くのびて
|
| 北の窪地に大量の雨を降らせ
|
| あわただしく去った朝
|
| 雲量は目測で「3」だが
|
| 風の水気は残っている
|
| 笑ったドラゴンみたいな巻雲が
|
| 南一万メートルにある
|
| 太陽に乱反射してきらめく
|
| 羽毛あぶらのスペクトル
|
| エッジに氷の粒が透けている
|
| たった今つぐみの群れを
|
| エレキテルが走りぬけた
|
|
|
| 川べの散歩者は発見した
|
| けさ羽化したばかりのトンボのよう
|
| 黄に白を混ぜたやわな機体だ
|
| ななめに水に浮いている
|
| ヘリコプターの風防ガラスに
|
| 僅かなひびわれがあって
|
| 操縦士が倒れている
|
| 気流落下のスピンで目をまわした
|
| でも死んじゃいない
|
| 堰堤の管理小屋にはこんだ
|
| 続きの夢から醒めない
|
| 砂あらしで耳をやられて
|
| 総天気図の気圧の谷をさまよっている
|
|
|
| 森の案内者は語った
|
| 喉を鎮痛して材木は防腐した
|
| クレオソートがあたりに満ちている
|
| 焼けたイヌブナのタールのにおいだ
|
| 廃ダムの魚道にカケスたちが避難した
|
| きこえるか
|
| 業腹そうに鳴いている
|
| きのうの雨が火を収めた
|
| キャンプは水に漬かったがしかたがない
|
| 炎は都市の方角から来て
|
| 鳥の群れを川に追いこむ
|
| 東の都市はヒートアップして
|
| 放熱は鎮める方法がない
|
| 乾いた風がはこんでくるのだ
|
|
|
| 爪の先で葯にしがみついたまま
|
| 一ぴきのカナブンが客死した
|
| 有毒きんぽうげの野原で
|
| 我知らずバタカップはゆれる
|
| みっつに裂けた葉紋スタンプが
|
| 鉛筆用の画板にひろげられ
|
| 観察者のルーペに縁どられている
|
|
|
| 人力で地上三百メートルまで
|
| 櫓を組んで延びたビルの
|
| 強化ガラスにスネタカヒコの右脚が映る
|
| 尾根から半島の岬まで左脚をかけている
|
| 弾けた積雲の一列が北北西にあって
|
| やや欠けた昼の月をめざす
|
| 過ぎていくキャラバン
|
| かすんだ都市をまたぎこして
|
| スネ高の男は行ってしまう
|
| 光が散乱して目が痛む
|
| 輝くテレスコープの画像に
|
| 羅針はふるえて止まらない
|
| どんな気象も観測者の上に顕れる |
「gui」2001.夏掲載より
 <詩>梅を見に(関富士子)
<詩>梅を見に(関富士子)
 <ことばのあやとり>かかとに羽もつ六人の勇者が(関富士子)
<ことばのあやとり>かかとに羽もつ六人の勇者が(関富士子)
梅を見に
|
|
| 杉林を登っていく
|
| 雪の残る北側の中腹に氷池がある
|
| 午前中に氷を切り出す
|
| 着くともう昼過ぎで
|
| 尾根の南側の日溜りに
|
| 二人の男が弁当を広げている
|
| あたりに材木が積まれていて
|
| 氷は見あたらない
|
| 池はどこですか
|
| 一人が日陰のほうを指さす
|
| もう一人が言う 氷はないよ
|
| それきり黙っている
|
| 池には行かずに日溜りで
|
| 男たちが材木を切り出すのを見ている
|
|
|
| 紅梅、白梅、蝋梅
|
| 案内図にしたがって
|
| 右手に紅梅、左手に白梅が咲く小道を行く
|
| 山の頂きは蝋梅の林だ
|
| いちめん黄色にぼやけている
|
| 人々は木の下に座って
|
| 町はずれに光る川を眺めている
|
| その向こうに
|
| 台形に切り取られた岩山があって
|
| 発破が響く
|
| 山のてっぺんが吹き飛ばされて
|
| 石灰岩のかけらが降ってくる
|
|
|
| ケーブルカーは三十分おきに来る
|
| 町へ下りる人でぎゅうづめだ
|
| メンドリを抱いた女が窓際に座っている
|
| ケーブルがぐらぐら揺れるので
|
| 人々は小さな叫び声をあげる
|
| メンドリは喉をくうくう鳴らす
|
| メンドリの尻の下
|
| 女の膝の上に
|
| 卵の籠がある
|
| 女はこらえきれないように顔をしかめている
|
|
|
| 駅に向かう道に沿って
|
| 豆屋と佃煮屋と石屋があって
|
| 豆屋で甘納豆を
|
| 佃煮屋で椎茸の甘辛煮を買う
|
| 石屋では
|
| 蛇紋石や柘榴石や
|
| ヒトデやアンモナイトや
|
| アマゾンの巨大な魚の化石があったが
|
| 蝋石を買う
|
紙版「rain tree」no.20 2001.5.25より
 <詩>机と椅子のある庭(関富士子)
<詩>机と椅子のある庭(関富士子)
 <詩>地上の人に告げて(関富士子)
<詩>地上の人に告げて(関富士子)
机と椅子のある庭
| ファインダーをのぞいているときは気づか
|
| なかった。全体は翳っているヤブコウジの西
|
| 側だけ光があたって、艶を含んだ赤い実の一
|
| つにピントを合わせるのに気を取られていた。
|
| 焼きあがった写真を見ると、くっきり浮い
|
| た一粒の実のかげから、奥へ進むように小道
|
| が続いていて、行きどまりの空き地に何かが
|
| 置いてある。小学校で使ったような小さな木
|
| の机と椅子。
|
| 辺りは庭木が茂って雨ざらしなのに、ぼや
|
| けているせいか、数十年前の小学校の教室か
|
| ら運ばれて、たった今、そこへ置かれたばか
|
| りのようだ。
|
| 椅子は、横木の二本ついた低い背もたれと、
|
| 四角なみじかい四本の脚の造りで、そこに座
|
| っていた少年のことをたしかに覚えている。
|
| 窮屈なお下がりの学生服の両肩が緊張して
|
| いて、まっすぐに伸びたきゃしゃな背中の上
|
| に、バリカンで刈り上げた細長いぼんのくぼ
|
| の二本の筋だけ太く張っている。その首筋全
|
| 体が紅潮していて、彼が激しい感情にじっと
|
| 耐えていることがわかる。
|
| 教室ではいつもだれかが突然わけもなく侮
|
| 辱された。それが自分ではなかったことに安
|
| 堵しながら、わたしたちはいっせいにうなだ
|
| れてそのときが過ぎるのを待っていた。どの
|
| 机の下でも、急速に伸びてしまった足がねじ
|
| れて折れ曲がっていた。
|
| 少年もいつだって口ごたえをせず、どんな
|
| 言葉も思いつかないというように俯いている
|
| のに、なぜか抑えようもなく首の付け根まで
|
| 一気に赤らんでしまう。すると、いらだって
|
| 震える細い指示棒が、いつも彼の肩に振り下
|
| ろされるのだ。
|
| 写真にぼんやり見えている古びた机と椅子
|
| には、もうだれも座っていない。彼はいった
|
| いいつ、立ち上がってわたしたちに背を向け
|
| たまま教室を出ていったのだろう。
|
| いいえ、わたしはうなだれた目をそっと上
|
| げてそれを見たように思う。学生服の袖から
|
| ぶかっこうに突き出した長い腕を伸ばして、
|
| 椅子の背もたれをつかみ、脚をはめこむよう
|
| に机にきっちりと収めて、彼は大またに出て
|
| いった。そして、机と椅子をその庭に置き去
|
りにしたのだ。
|
小池昌代個人詩誌「音響家族」no.15 2000.11.15発行より  執筆者紹介(せきふじこ) 掲載一覧
執筆者紹介(せきふじこ) 掲載一覧
 <詩>挨拶詩3「日永」「順番」――関富士子へ(中上哲夫)(縦組み縦スクロールのみ)へ
<詩>挨拶詩3「日永」「順番」――関富士子へ(中上哲夫)(縦組み縦スクロールのみ)へ
 <詩>梅を見に(関富士子)
<詩>梅を見に(関富士子) <詩>地上の人に告げて(関富士子)
<詩>地上の人に告げて(関富士子)