| 僩僢僾 | 偍抦傜偣 | 夛丂曬 | 夛娰 | 偁備傒 | 僷乕儔乕 | 傒偙偙傠媢 |
僊儍儔儕乕 | 儕 儞 僋 |
|
|
夛曬 |
| 僩僢僾 | 偍抦傜偣 | 夛丂曬 | 夛娰 | 偁備傒 | 僷乕儔乕 | 傒偙偙傠媢 |
僊儍儔儕乕 | 儕 儞 僋 |
|
|
夛曬 |
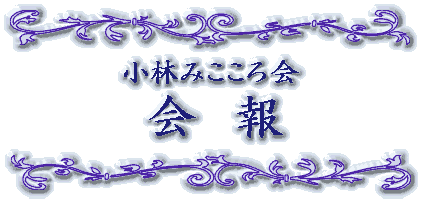
| 屼垾嶢 | 彫椦傒偙偙傠夛夛挿 | 35夞惗 | 栰懞丂庻巕 | ||||
| 僀儞僪偱偺弌夛偄 | 彫椦惞怱彈巕妛堾峑挿 | 僔僗僞乕 | 塅栰丂嶰湪巕 | ||||
| 乽巕嫙偺棦乿僾儘僕僃僋僩偺偛曬崘 | 37夞惗 | 憫曐丂嫟巕 | 憫曐丂嫟巕 | ||||
| 搶嫗巟晹偩傛傝 | 搶嫗巟晹挿 | 39夞惗 | 桍堜丂榓宐 | ||||
| 擖夛偺偁偄偝偮 | 戞77夞惗戙昞姴帠 | 77夞惗 | 嫶杮丂旤撧巕 | ||||
| 暯惉侾5擭搙峴帠曬崘 |
愭摢傊
|
|||||
| 丂 儘僓儕僆僸儖偺憗弔偼婩傝偺応偵憡墳偟偔惷鎹側暤埻婥偵曪傑傟偰嫃傝傑偡丅奆條偵偼擛壗偍夁偛偟偱偄傜偭偟傖偄傑偡偐丠 丂屼堿條傪帩偪傑偟偰峆椺偺奺峴帠傕懾傝柍偔嵪傑偣丄擟婜擇擭偺屼栶傕梋偡強悢儢寧偽偐傝偲側傝傑偟偨丅偙偺娫姴帠條傪巒傔夛堳偺奆條偺屼嫤椡偺傕偲偵戝夁側偔夁偛偡帠偑弌棃傑偟偨丅栶堳堦摨丄怱偐傜姶幱偲嫟偵屼楃怽偟忋偘傑偡丅 丂偝偰丄嶐擭棃庢傝慻傫偱嶲傝傑偟偨姌働嶈乽偙偳傕偺棦乿傊偺帒嬥墖彆偺僾儘僕僃僋僩偼偙偺擇寧枛丄栚昗妟傪挻偊傞忩嵿傪屼婑晬捀偒丄嶰寧巐擔丄戙昞偺憫曐嫟巕偝傫偵偍搉偟偡傞帠偑弌棃傑偟偨丅偙偙偵奆條偵岤偔屼楃怽偟忋偘傑偡丅枖丄彫椦偺曽偩偗偱柍偔奺惞怱偺摨憢夛偺曽乆偵傕怺偔屼棟夝捀偒屼嫤椡壓偝偄傑偟偨丅偙傟偼丄乽惞怱偼堦偮偺壠懓偱偁傞乿偲屼嫵偊捀偒傑偟偨儅僓乕僗偺惛恄偑柆乆偲堷偒宲偑傟丄幚傪寢傇帠傪幚姶偟婐偟偔丄枖懖嬈惗偲偟偰屩傜偟偔懚偠偰嫃傝傑偡丅 丂塣塩偵墬偒傑偟偰挿擭偺寽埬帠崁偱偛偞偄傑偟偨夛曬憲晅偼崱夞傛傝捈愙奆條偺偍庤尦偵屼撏偗偡傞帠偲側傝傑偟偨丅姴帠條偵偼崱枠戝曄屼晧扴傪偍偐偗抳偟傑偟偨偑丄壗偲偐幚巤偺塣傃偲側傝傑偟偨帠丄屼曬崘怽偟忋偘傑偡丅 丂暉巸偺暘栰偱偼丄嶐崱懕敪偡傞嵭奞傗愴壭偵傛傞梫墖彆偺惡偼堷偒傕愗傜偢丄恀潟偵庴偗巭傔弌棃傞尷傝偺巟墖傪懕偗傞巔惃偱嫃傝傑偡丅 丂夛寁偱偼夛堳悢偺憹壛偲嫟偵塣塩偺崌棟壔丄僗儕儉壔偵椡傪擖傟廩幚偟偨夛偺塣塩宍懺偺婎慴傪屌傔丄奆條偵擺摼偟偰捀偒暘傝堈偄夛寁曬崘傪栚巜偟庢傝慻傒傑偟偨丅 丂夛娰傕島嵗傗曭巇妶摦偵屼棙梡捀偒丄弴挷偵壱摦偟偰嫃傝傑偡丅崱堦憌僋儔僗夛傗僇儖僠儍乕妶摦偵屼巊梡捀偒丄夛堳摨巑偺岎棳偺応偲偟偰妝偟傫偱捀偒偨偄偲巚偭偰嫃傝傑偡丅 丂棃擭2006擭偼丄僯儏乕僆乕儕儞僘偱AMASC丂乮悽奅惞怱摨憢夛乯丂戝夛偑奐偐傟傑偡丅扅崱JASH丂乮擔杮惞怱摨憢夛乯丂偺栶堳偺曽払偑搉暷偺堊偺弨旛傪恑傔偰偄傜偭偟傖偄傑偡丅惀旕丄奆條偵傕惞怱僼傽儈儕乕偺堦堳偲偟偰惞怱偺敪揥偺堊偵傕屼嶲壛捀偒岎棳傪怺傔偰捀偒偨偄偲巚偭偰嫃傝傑偡丅彫椦僗僞僨傿僌儖乕僾偱偼AMASC戝夛偺僥乕儅丂噣奆偲庤傪崌傢偣悽奅傪峫偊傛偆亶丂偵揧偭偰曌嫮夛傪帩偨傟偰嫃傝傑偡偺偱丄惀旕戝惃偺曽偺屼嶲壛傪屼懸偪偟偰嫃傝傑偡丅丂 慡偰偺恖偑怱偐傜婅偄傑偟偨暯榓側擇廫堦悽婭偑柧偗悢擭偑宱偪傑偟偨丅巚偄偲偼棤暊偵丄師乆婲偒傞憟偄傗娐嫬墭愼摍偺栤戣偵恖椶偺斱彫偝傪斀徣偝偣傜傟傞偙偺崰偱偛偞偄傑偡丅巹払偑捀偒傑偟偨惞怱偺嫵堢偼峑壧偵鎼傢傟偰嫃傝傑偡噣暯榓偺堊偵恠偣偐偟亶丂偺堦尵偵恠偒丄偦傟傪幚慔偡傞憢岥偑摨憢夛偺栚揑偲擣幆偟偰嫃傝傑偡丅偙偺巚偄傪庴偗丄偙偺搙師悽戙偺僼儗僢僔儏偱僄僱儖僊僢僔儏側曽払偑屼栶傪堷偒宲偄偱壓偝偄傑偡丅偳偆偧曣峑偦偟偰丄彫椦傒偙偙傠夛偵巹払偑捀偒傑偟偨壏偐側屼巟墖傪崱堦憌帓傝傑偡條偵屼婅抳偟傑偡丅丂 嵟屻偵側傝傑偟偨偑丄僔僗僞乕塅栰峑挿條傪巒傔妛堾偺奆條丄奺惞怱摨憢夛偺曽乆偵捀懻抳偟傑偟偨屼岤媌偵懳偟怱傛傝屼楃怽偟忋偘傑偡丅偦偟偰彫椦傒偙偙傠夛偺塿乆偺屼敪揥傪屼婩傝抳偟偰偍傝傑偡丅桳擄偆偛偞偄傑偟偨丅 |
|||||
愭摢傊
|
|||||
| 丂 崱擭傕崅峑3擭惗122柤偑丄條乆側巚偄傪嫻偵偙偺妛幧傪憙棫偭偰偄偒傑偟偨丅怳傝曉偭偰傒傞偲丄偙偺惗搆偨偪偑夁偛偟偰偒偨崅峑偺嶰擭娫偼丄擇廫堦悽婭偵擖傝悽奅偱傕擔杮偱傕戝偒側曄壔傪懱尡偟偨嶰擭娫偱偁偭偨偲尵偊傞偱偟傚偆丅怴偟偄悽婭偙偦乽嫟惗偺悽婭乿丂偵偲丄恖乆偺戝偒側婜懸偺撪偵巒傔傜傟偨擇廫堦悽婭丅偟偐偟丄9.11偺弌棃帠埲棃丄悽奅偱偼嫲晐偲憺埆偺楢嵔偵傛傞愴憟偲僥儘偺僌儘乕僶儖壔偑恑傒丄堘偄傗棫応傪挻偊偰嫟偵偁傞偙偲偺擄偟偝傪栚偺摉偨傝偵偣偞傞傪摼側偄枅擔偑懕偄偰偄傑偡丅擔杮偱偼丄恖偲恖偲偺丄偁傞偄偼帺暘帺恎偲偺娭傢傝擻椡偑掅壓偟丄柦傊偺姶惈偑撦偔側偭偰偄傞偙偲傪徹柧偡傞偐偺傛偆側條乆側斶偟偄弌棃帠偑屻傪愨偪傑偣傫丅傑偨丄抧媴偺曄摦婜偑偒偨偺偱偟傚偆偐丅師偐傜師傊偲悽奅奺抧偱婲偙傞帺慠嵭奞丅偦偺拞偵偼丄恖娫偑帺傜彽偄偨抧媴壏抔壔偵婲場偡傞嵭奞傕尒傜傟傑偡丅偙偆偟偨崿柪偺搙崌偄傪怺傔傞悽奅偵怴偨偵堦曕傪摜傒弌偟偨崅峑嶰擭惗偵偼丄偙偺妛堾偱妛傫偱偒偨傕偺傪戝愗偵偟丄恄偐傜梌偊傜傟偨偐偗偑偊偺側偄堦偮堦偮偺柦偺懜偝傪幚姶偟側偑傜丄恖偲恖丄柦偲柦傪宷偖壗傜偐偺栶妱傪壥偨偡恖偲偟偰堢偭偰傎偟偄偲丄婅傢偢偵偼偄傜傟傑偣傫丅 丂嶐擭枛偺廫擇寧偐傜怴擭堦寧偵偐偗偰丄僀儞僪偺儉儞僶僀偱丄傾僕傾丒僆乕僗僩儔儕傾惞怱妛堾峑挿夛偵嶲壛偡傞婡夛傪偄偨偩偒傑偟偨丅偙傟偼丄俀侽侽俀擭偵僔僪僯乕偱奐嵜偝傟偨戞俀夞惞怱峑挿夛偺榖偟崌偄傪庴偗偰幚尰偟偨傕偺偱悽奅偵峀偑傞惞怱妛堾傪嶰偮偺抧堟丂乮儓乕儘僢僷乛傾僼儕僇丄撿乛杒傾儊儕僇丄傾僕傾乛僆僙傾僯傾乯丂偵暘偗丄偦傟偧傟偺抧堟偱峴傢傟傞梊掕偵側偭偰偄偨傕偺偱偡丅崱夞偺僀儞僪朘栤偼丄巹偵偲偭偰怓乆側揰偵偍偄偰堄枴怺偄傕偺偲側傝傑偟偨偑丄嵟傕怱偵巆傞擇偮偺偙偲偵偮偄偰偍榖偟偟偨偄偲巚偄傑偡丅 堦偮栚偼丄僀儞僪偺懡條惈偵怗傟偰懡偔偺偙偲傪峫偊偝偣傜傟偨偙偲偱偡丅儉儞僶僀懾嵼拞丄僾儘僌儔儉偺堦娐偲偟偰僸儞僘乕嫵丄僀僗儔乕儉嫵丄僔-僋嫵丄偦偟偰暓嫵偺帥堾傪朘傟傞婡夛偵宐傑傟傑偟偨丅巹払傪壏偐偔寎偊偰偔偩偝偭偨懡偔偺曽乆偲偺弌夛偄偼丄尰戙偲偐偔懳棫傪惗傒弌偡尨場偲峫偊傜傟丄帪偵偼嫍棧傪抲偄偰尒傜傟偑偪側乽廆嫵乿偲偄偆傕偺偑丄懳榖偲岎傢傝偺梫偲側偮偰偄傞偲偄偆偙偲偺慺惏傜偟偝傪嫵偊偰偔傟傑偟偨丅憡庤傪搢偦偆偲偟偰懳棫偺峔憐偺拞偵惗偒傞偐丄傑偨偼屳偄偺堘偄傪擣傔崌偄嫟惗偟傛偆偲偡傞偺偐偼丄寢嬊堦恖傂偲傝偺慖戰偵偐偐偭偰偄傞偺偩偲偄偆偙偲傪丄嫮偔姶偠偝偣傜傟傑偟偨丅乽僀儞僪暥壔偺懡條惈乨偦偺娫偄偐偗傞傕偺乿偲偄偆戣偱島墘偟偰偔偩偝偭偨僀僄僘僗夛偺恄晝條偺尵梩偑崱傕嫮偔怱偵嬁偄偰偒傑偡丅乽懡條惈偼丄悽奅偺尰幚偱偁傞丅乧暥壔偺憡堘傪懜廳偟丄憡庤偺棫応偵棫偭偰丄傕偺傪尒傞偙偲丅偦偺偨傔偵偼丄偍屳偄偵堘偆偙偲傪擣傔崌偊傞恖傪堢偰傞嫵堢丄懳榖偑偱偒傞恖傪堢偰傞嫵堢偑媮傔傜傟偰偄傞丅乿偙傟偼丄暥壔偺堘偄偽偐傝偱側偔丄巹払偺擔忢惗妶偵傕摉偰偼傑傞偙偲偱偟傚偆丅忣曬媄弍偺敪揥偵敽偆僌儘乕僶儕僛乕僔儑儞偼丄悽奅偺恖乆傪弖帪偵宷偖偙偲傪壜擻偵偟偨堦曽丄悽奅偺暥壔傪夋堦壔偵岦偐傢偣丄摨偠偱偁傞偙偲傪埫栙偺撪偵嫮梫偟偰偒傑偡丅傑偨丄嫞憟尨棟偱傕偺偛偲偑摦偄偰偄偔尰忬偵偁偭偰偼丄傛傝曋棙偱傛傝懍偔偲偄偆壙抣偑桪愭偝傟丄恖偑偦偺恖帺恎偱偁傞偲偄偆偙偲偑丄擄偟偔側偮偰偒偰偄傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅 丂傕偆堦偮怱偵巆傞偙偲偼丄僀儞僪偺惞怱偺懖嬈惗偲偺弌夛偄偱偡丅僜僼傿傾戝妛偺摨憢夛偼丄僀儞僪偺條乆側懞偵偍偄偰帺傜偺庤偱丂"Water Harvesting Program"偲偄偆婇夋傪幚巤偟偰偄傑偡丅偙偺妶摦偼丄堦擔拞悈塣傃偲偄偆恏偄楯摥偵廬帠偟側偗傟偽側傜側偄彈惈偨偪傪媬偆偨傔偵巒傔傜傟偨傕偺偱丄嫄戝側悈憛傪愝抲偟丄悈傪挋偊傞偨傔偺僟儉寶愝傪嶌傞摍偺妶摦傪懕偗偰偒偨寢壥丄尰嵼偱偼34偺懞偑悈偺壎宐偵偁偢偐傞傛偆偵側傝傑偟偨丅傑偨峹奜偵偍偗傞悈偺栤戣偺怺崗偝傪傕偭偲巕嫙払偵揱偊偰偄偐側偗傟偽側傜側偄偲偄偆偙偲偱丄搒巗晹偺彫丒拞妛峑摍偱偼嫵堢僾儘僌儔儉傕幚慔偟偰偄傑偡丅摨憢夛偺妶摦曬崘傪暦偒側偑傜丄條乆側栤戣偵捈柺偡傞僀儞僪偺幮夛偺拞偱丄偙偺傛偆側懖嬈惗傪堢傫偩惞怱偺嫵堢傪棅傕偟偔姶偠傞偲嫟偵丄偦偺擔巜偡強偺堄媊傪夵傔偰擣幆偝偣傜傟傑偟偨丅 丂僯儏乕僗偵帹傪孹偗傞搙偵丄悽奅偼偙傟偐傜偳偆側偮偰偄偔偺偩傠偆偐偲丄婥帩偪傕捑傒偑偪偵側傞偙偲偺懡偄崱擔偙偺崰偱偡丅偟偐偟丄廆嫵偺堘偄傪挻偊偨嫟惗傪栚巜偟妶摦偟偰偄傞恖乆丄帺暘偑妛傫偩偙偲傪妶偐偟偰昻偟偄恖乆偺偨傔偵嬶懱揑側曽朄偱妶摦偟偰偄傞懖嬈惗丄僀儞僪懾嵼拞偵弌夛偭偨偙偆偟偨恖乆偼丄戝偒側桬婥偲婓朷傪巹偵梌偊偰偔傟傑偟偨丅偦偟偰丄巹払偼擔乆帺暘偺惗偒曽偺慖戰傪媮傔傜傟偰偄傞偺偩偲偄偆巚偄偑丄崱傕巹偺拞偱嬁偒懕偗偰偄傑偡丅 丂My丂optimism丂rests丂on丂my丂belief丂in丂the丂infinite possibilities of the丂individual丂to丂develop丂丂non亅violence丏The丂more丂you丂develop丂it in your own being丆the more infectious it becomes till it overwhelms your surroundings and by and by might oversweep the world丏乮M丏K丆Gandhi乯 |
|||||
愭摢傊
|
||||||||||
愭摢傊
|
||||||||
愭摢傊
|
|||||
| 丂丂 丂塉忋偑傝偺嬻偵峀偑傞慛傗偐側擑偵尒憲傜傟丄巹払77夞惗偼2寧19擔懖嬈偟傑偟偨丅 丂巹払偼拞妛惗偺崰偐傜條乆側峴帠傪捠偟偰乽抍寢乿丂偺慺惏傜偟偝傪妛傃丄惵偺妛擭偲偟偰椡傪敪婗偟偰偒傑偟偨丅偟偐偟傂偨偡傜撍偭憱偭偰偨偩彑偮偙偲傪捛偄媮傔偨偨傔偵丄妛擭偑忋偑傞偵偮傟巚偆傛偆偵寢壥傪弌偣側偔側傝丄偦傟傪婡偵偦傟偧傟偑帺屓傗妛擭傪尒偮傔捈偡傛偆偵側傝傑偟偨丅偦偟偰巹払偼丄怳傝曉傞偙偲偺戝愗偝丄帺暘払傛傝傕廃傝傪桪愭偟丄懠妛擭偵偲偭偰傕婥帩偪偺椙偄嬻娫傪嶌傞偙偲丄傑偨抍懱偺拞偵偍偄偰傕堦恖傂偲傝偺屄惈傪懜廳偡傞偙偲偺廳梫偝側偳丄朰傟偐偗偰偄偨懡偔偺偙偲偵婥晅偒丄崅嶰偱偼偦傟傜傪幚慔偵妶偐偟側偑傜壗帠偵傕惛堦攖庢傝慻傫偩寢壥丄惵偺妛擭傜偟偄椙偄傕偺傪巆偡偙偲偑偱偒傑偟偨丅丂 巹払偑偙傟偩偗慺惏傜偟偄巚偄弌傪戲嶳嶌傟偨偺偼丄僔僗僞乕丒愭惗曽傪偼偠傔偲偡傞懡偔偺曽乆偑巟偊偰壓偝偭偨偍堿偩偲怱偐傜姶幱偟偰偄傑偡丅壎巘傗拠娫偲嫟偵徫偄丄嫟偵椳傪棳偟偨擔乆偼丄巹払偺偐偗偑偊偺側偄嵿嶻偱偡丅偙傟偐傜偼惞怱偱偺宱尡傪妶偐偟丄惓偟偄敾抐椡傪帩偪丄恑傫偱恖偺堊偵恠偔偡偙偲偺偱偒傞尗柧側彈惈偵側傟傞傛偆搘傔偰偄偒偨偄偲巚偄傑偡丅丂 偙偺搙丄彫椦傒偙偙傠夛偵擖夛偝偣偰捀偔偵偁偨傝丄夛堳偺堦恖偲偟偰愑擟傪帩偭偰妶摦偵嶲壛偟偰偄偒偨偄偲峫偊偰偍傝傑偡丅傑偩傑偩枹弉偱偡偑丄偛巜摫媂偟偔偍婅偄抳偟傑偡丅 |
|||||
愭摢傊
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
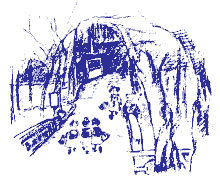
|
|
夛曬 |
| 僩僢僾 | 偍抦傜偣 | 夛丂曬 | 夛娰 | 偁備傒 | 僷乕儔乕 | 傒偙偙傠媢 |
僊儍儔儕乕 | 儕 儞 僋 |
