 詩人たち
詩人たち 最新号
最新号 Back Number
Back Number vol.4
vol.4 閑月忙日
閑月忙日 リンク
リンク 詩集など
詩集など  詩人たち 詩人たち 最新号 最新号 Back Number Back Number vol.4 vol.4 | ふろく 閑月忙日 閑月忙日 リンク リンク 詩集など 詩集など |

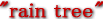 vol.4
vol.4<雨の木の下で 4>
Lucent Blue-Monday の夜 (1998年4月9日)
雨が断続的に降る春の夜、青山まで出かけた。前日まであれほど美しく咲いていた桜が、雨に打たれて無残に散るのをいたましく見た。朗読会のタイトルはその晩の気分にぴったりで、会場までの人通りの少ないキラー通りとやらは、たどりつくのを断念させるかと思われるほど長かった。
バーの三階の狭いスペースに、Booby Trap の連中が待っていてくれたのでほっとした。この詩誌が中心の初めて朗読会である。長く寄稿しているが、彼らと会う機会はあまりない。吉田裕さんや駿河昌樹さん、倉田良成さん、布村浩一さんとは初対面だった。みなとてもふつうの落ち着いた男たちで、詩人として派手ではないが、それぞれ個性的な作品を長く書き続けている。
朗読もどこか遠慮がちである。音楽もないし、声を張り上げるでもない。非常に狭いので客はすぐ目の前にいる。構成や段取りがあるのでもなく、清水鱗造さんと駿河昌樹さん、長尾高弘さんがなんとなく交代に読む。このさりげなさは主宰の清水さんの持ち味のようだ。終わると「それでは、関さん」と、何の打ち合わせもなく呼ばれるが、すぐそばのマイクと椅子に移動するだけなので、あまり緊張しない。
結局わたしと森原智子さんも朗読した。森原さんは生まれて初めての朗読。読まないと言っていた彼女をごく自然にマイクの前に座らせたのは、彼らのさりげなさのおかげである。
プロデューサーの青木栄瞳さんはいつもの雰囲気。
詩は読者が読んで楽しめるものであればそれで十分なのだが、なにかの機会にそれを書いた詩人を見たり、声を聴いたりすると、やはりよかったと思う。次に詩を読むときにその姿や声を頭に思い浮かべることになる。すると何だか新しくわかったことがあるような気がする。
朗読をきくことの良さはそれぐらいであろう。
自分が読む立場になってみると、事態は違ってくる。しっかり伝えたいので、発音をはっきりと、リズムを意識して読もうとする。マイクに声が乗っているかどうか、読んでいる最中も気になる。緊張すると福島なまりが出てどうにもならなくなるので、それが恥かしい。あまり積極的に朗読する気になれない。
でも、その晩の朗読は自分ではうまくいったような気がする。集中して自分の詩に入り込んでいけて、その詩を書いたときの切実な思いで胸がいっぱいになった。声にあふれるものがあって、一瞬だがだれかに届くかもしれないとさえ思えた。
聴きにきてくれた方々に楽しんでもらえたらそれでよいのだが、わたしの少ない経験では、観客の思いをしっかりととらえることはできなかった。この辺りをもう少し考えなければならない。
*興味のある方は、朗読会の様子や朗読のビデオを、長尾高弘さんサイトlongtail でご覧ください。BoobyTrap朗読会報告

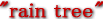 vol.4
vol.4<雨の木の下で 4>
消息 (1998年4月2日) 関富士子
新国道から見た千貫森
写真をたくさん並べたのは、スキャナー付きのプリンターを買ったのがうれしいからだが、ここに写っているのは、福島県のとある田舎道である。
先日、三年ぶりに故郷の川俣町に帰ったのだが、春の彼岸の墓参りの途中の道すがら、その風景がありありと数十年前の記憶を蘇らせるのに、狼狽に近い驚きがあった。
墓地は今は廃校になった小学校の裏山にあるので、墓参りの道はおのずからかつての二キロほどの通学路を行くことになる。バスが、登校する子供たちに砂利や水溜まりの水を弾き飛ばして走っていたのだが、それに平行して新しく広い国道ができたので、今は裏道になっている。ここを散歩するのは帰省のたびの楽しみだった。
ここには、子供のわたしが毎日見ていた風景が、その当時のままに残っている。ほこりまみれのガラス戸や白茶けた板塀のたたずまい、門口の梅や無花果の木。駄菓子屋、酒屋、金物屋のさびれた店先。その壁に打ち付けられたブリキの看板のさび具合。空き家が目立つのは、奥にきれいな文化住宅を建てて移り住み、道路に面した古い家屋を取り壊しもせず放ってあるからだ。
今は舗装された幅4メートルほどの田舎道だが、人っ子一人通らない。みな車で広い道路を行くのである。楯和気神社の参道の薄暗い並木、すがれた垣根、金松寺へ続くくねくね道。まだ土起こしも始まらない吹きさらしの田んぼ。その向こうに見える千貫森と女神山、さらに奥に真っ白な吾妻連峰。森閑とした梅満開の昼下がり。わたしはカメラをぶらさげて、呆然とこの道を二往復もしてしまった。
ところで、下の写真のあばら家は、その中でも特に当時そのままの印象である。家の向こうに見えるのは風向計付きの新しい火の見櫓のようだが、むかしはハンショウ(半鐘)といって、火事が起こるとこの鐘がジャンジャン打ち鳴らされたのである。
通学時、この辺りまで来ると、松川駅発川俣駅午前八時着の蒸気機関車が、大きな汽笛を鳴らしてカーブを曲り、重たく強く、けもののように太い息を吐きながらやってくる。川俣産の織物を運ぶために敷設された線路が、ディーゼル車に変わってからも、昭和40年代まで道を50メートルほど隔てて平行に走っていた。
平和な田園風景だが、風景と心象は一致しない。小学校の高学年時、わたしは長い間いじめに遭っていて、毎朝学校へ行くのがつらくてならなかった。子供はみなそうだが、景色などに興味はなかった。この家は数十年前もぼろ家に見えたが、今は住む人もなく道路脇の傾斜にあいかわらず傾いて建っている。剥げ落ちた壁、柱の歪み、破れたガラス戸にビニールが貼り付けられている。波打つ瓦屋根、傾斜の下の半地下は農機具置き場にでもなっているのか。がらんどうである。眺めているうち、この家に当時住んでいた、わたしと同級の二人の少年のことが少しずつ思い出されてきた。
同じ家を反対側から撮ってみた。この家は三世帯ほどが住む長屋だった。広い土地がある田舎でも貧富の差は激しく、三男、四男坊の家族、余所者、出戻りなど、土地も家もない人は、小さな貸し家に子だくさんでひしめきあい、農家の小作か、主産業だった機織り工場に勤めて生計を立てていた。
子供の数が圧倒的に多い時代に、悪がきぞろいの同級生の中で、二人は比較的おとなしいほうだった。T君は、ずんぐりむっくりの固太り、肌がどんぐりのように黒光りした男の子で、とてもまじめ。ふざけた冗談が通じなかった印象がある。
もう一人の少年S君は対照的に色白のハンサムだが、ひどく内気で無口だった。わたしはこの子がちょっと好きで、低学年のころは教室でよくなんだかんだと話しかけたのだが、彼は一言も口をきかず、困惑しきったふうでしかめつらをするのだった。家からはちょっと離れているし、一緒に遊んだことはなく、この二人の仲が良かったのかどうかも記憶にない。
中学まで一緒だったが、クラスも違って二人に強い印象はない。二人とも成績もスポーツも取りたてて目立つほうではなかった 。卒業してからほとんど会うこともなく数十年が過ぎた。T君はその後刻苦勉励、教師になって、5年ほど前、40代そこそこで町の小学校の校長に就任した。これはたいへんな出世である。聞けば彼の二人の弟も教師だそうだ。
その前年にわたしの詩集が賞を受けて、町の新聞に大きく出たので、「T君とふうちゃん(わたしのこと)を祝う会」というのを開いてくれた。もちろんわたしはおまけである。そのときT君はわたしに向かって、「おお、ふうちゃんの顔はつやつやして、手入れがいいない。エステにでも行ってんだべえ。」と叫んだ。彼は今ではどじょうすくいでもカラオケでも何でもオッケーだそうである。そのときS君の消息をききそこねたのはちょっと残念である。
その祝う会のさらに数年前、東京近辺に住む同級生たちに呼びかけてクラス会を開いたことがあった。名簿を頼りに、越谷に住んでいるらしいS君に電話をしたのである。彼はわたしと同じ大学に入ったと聞いていたが、連絡を取り合うこともなく、広いキャンパスで出会うこともなかった。たまのクラス会にも彼は出席しなかった。独身で弟と二人で暮らしているらしい。電話には弟が出たので取り次いでもらうと、しばらく待たされたあと、兄は電話に出たくないと言っています、とつよい福島なまりで言うのである。これには少なからずショックだった。彼は、そんなにわたしのことを嫌いだったか。それとも、未だに相変わらず、小学生のころの、内気で無口なS君のままなのだろうか。
鶴沢小学校の100人ほどの同級生のうち、4割は中学を出てすぐ働いている。貧しさから抜け出して一旗揚げるには、金の卵として都会に出るのがいちばんだった時代だ。知っている限り、四年制の大学まで進学したのは、わたしとT、Sの両君ぐらいである。勉強はよくできても進学せず地道に働き、好不況の波をまともにかぶりながら、それなりに満足して暮らしている友人はたくさんいる。家も財産もない人間にとって、高等教育を受けることは貧しさを克服する大きな手段にせよ、やはりかなりの負担だったのだ。
わたしは機織り工場の四人娘の長女で、家業を継ぐのが嫌さに、親とけんかも同然に東京に出てきたのだが、学費は送ってもらった。T君は、高校からめざめて刻苦勉励、教師になってからも硬軟の処世術を身につけ、単身赴任のアパートで寝ずに勉強して校長の試験を突破し、出世を果たしたのだ。
それを思うと、同様に貧しかったS君のことが気に懸かる。子供時代、生きるのがつらかったのはわたしばかりではないだろう。T君にもS君にもそれなりの鬱屈があったに違いない。わたしたちはそれに耐えて大人になった。けれども、やはりあのころの子供の心を痛々しく思い返さずにはいられない。ただ沈黙していたS君の目に、あの風景はかつてどのように見えていたのだったか。彼はもう故郷に帰らないつもりなのだろうか。わたしではなくてもだれか今自分を語れる相手がいるだろうか。幼い日々を過ごしたあの家は、彼にとっては、今どのように見えるのだろうか。
 <雨の木の下で4>「恩知らず」「清水哲男の猫背」(関富士子)へ
<雨の木の下で4>「恩知らず」「清水哲男の猫背」(関富士子)へ <詩を読む>「グラグラと黒い墓」(宮野一世)へ
<詩を読む>「グラグラと黒い墓」(宮野一世)へ
 「たけやぶやけた」回文をひろげる(関富士子ほか)へ
「たけやぶやけた」回文をひろげる(関富士子ほか)へ 詩人たち 詩人たち 最新号 最新号 Back Number Back Number vol.4 vol.4 | ふろく 閑月忙日 閑月忙日 リンク リンク 詩集など 詩集など |

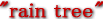 vol.4
vol.4恩知らず (1998年3月19日) 関富士子
渋澤孝輔が亡くなった。とてもさびしい。わたしなりのお別れをきちんと言うべきなのだが、どう書いたらよいのかまだわからない。
学生のころ、『漆あるいは水晶狂い』にあこがれ、大学の大教室で、彼のランボーの書籍講読を受けていた。一方で「ユリイカ」の投稿少女でもあったのだが、ある日お茶の水の喫茶店マロニエで、当時ユリイカの編集者の小野好恵さんに会い、これから二か月の間に詩を書きまくれと言い渡された。その中の一編を本欄に掲載するという。そこへ偶然渋澤先生が現れたのである。さっそく小野さんがわたしを紹介してくれたのだった。
別れ際、原稿を持ってきて見せなさいと言ったのを真に受けて、授業のあと、書きなぐりに近い原稿を彼の教卓にせっせと運んだ。その言葉を胸を高鳴らせて聞いた。ある日、活字じゃないといいのか悪いのかわからないな、と一言。ユリイカの新鋭としてデビューしたものの、あとの原稿はボツになり続けていた。活字にする手だてなどなく、原稿を運ぶのをやめてしまった。しかしその後も、詩誌「駿台詩人」の仲間とディスコに繰り出し、不思議なリズムで踊る詩人を何度か見ている。
卒業後、書きたい気持ちを捨てきれず手紙を書いた。すぐに詩誌「オルフェ」に紹介してくれた。同人会のあと、足が速くて行き方知れずになってしまう詩人にくっついて新宿の街を歩いた。第一詩集に長い書評を書いていただいたが、ちゃんとお礼を言ったのだったか。
四半世紀も前の話である。その後人生の諸事に追われて詩が書けずに、挨拶もせずにいったん遠ざかった。十年後にふらりと舞い戻ったら黙って受け入れてくれた。オルフェの主宰藤原定の詩碑の除幕式の晩、敦賀の宿で語り明かした。わたしの第二詩集が晩翠賞を受けたばかりで喜んでくれたようだが、言葉は厳しかった。いい気になるなと言われたのを覚えている。第三詩集のお祝いにと連れていってもらった鰻屋では、彼のちょっとした言葉に傷ついて涙が止まらず、鰻をろくに食べられなかった。
ここ数年、わたしは独り立ちしたつもりで、会えば憎まれ口をたたいていた。それを先生も楽しんでくれていたと思う。新しい詩集が出るたびに贈ってくださったのに、ついに、生前一行の渋澤孝輔論も書けなかった。思えば不義理、わがままの数々、甘えていたのだ。こんなに早く別れが来るとは思わなかった。悔やみきれない。先生、ごめんなさい。
二年前の夏、『行き方知れず抄』に書かれた甲斐大泉の庵で、物悲しいタンゴに合わせて、夜っぴて歌いながら独り床を踏み鳴らして踊っていた。物狂いの詩人渋澤孝輔を悼む。
清水哲男の猫背 (1998年2月26日) 関富士子
猫本と呼ばれるネコをネタにした本は数々あるらしいが、わたしはほとんど読まない。ネコとマゴの自慢話にろくなものはないからだ。これは詩人清水哲男の持論でもあるらしいが、そういう彼が「ネコとマゴの詩にロクなものはない」とぶつくさ言いながら書いたのが、『詩に踏まれた猫』(出窓社刊)である。おびただしく書かれた猫詩から、「世紀末のごみの日」に捨てられないでかろうじで残ったという二十数篇は、萩原朔太郎から藤富保男まで。これに猫を主人公にした小説や、インターネットサイト「増殖する俳句歳時記」で紹介した俳句を加えて、文学に登場する猫を論じたものである。
この猫本の特長は、「猫背」の詩人清水哲男ができるだけ猫の立場で書こうとしていること。これが案外難しい。動物ものというのは直ちに擬人化されて、人間を論じるのと結局同じということになるのがほとんどだが、それを自らにかたく戒めているふうだ。詩を読むときも、論じるときも、主人公猫に共感するときも、飼い主を批判するときも、謙虚に猫に寄り添う。ときどき人間の男の目が現れることもあるが、すぐに思い直すところが好ましい。
これがけっこう新鮮な切り口になっていて、猫になりかわって古今の猫文学を読んでみると、漱石の猫などはどうもひどい扱いなのがわかる。「猫的には」おもしろくないらしい。ところが長谷川四郎の詩「猫の歌」はよほど気に入ったらしく二度も登場する。これらを読むと、詩は猫を比較的よく遇しているではないか。というより、詩というジャンルは、猫だのなんだのというらちもないこだわりを書くのに適しているとでもいおうか。
わたしは猫の詩を一篇しか書いたことがないが、それ(「猫を被る」i/ii詩集『蚤の心臓』所収)がこのアンソロジーに載っているのでうれしい。おまけに清水哲男は作者のわたしを「良い人」といっている。わたしは詩人Y・F氏にかつて「悪役」の折り紙をつけられた者である。つまり、人間にとって悪役は猫にとっては良い人というわけだ。
『詩に踏まれた猫』(出窓社刊・1500円 ご注文は書店か、武蔵野市吉祥寺南町1-18-7-303 Tel:0422-72-8752 Fax:0422-72-8754 e-mail:dmd1@parkcity.ne.jp
 <雨の木の下で4>「笑うお皿」(田村奈津子)「近況」(宮野一世)へ
<雨の木の下で4>「笑うお皿」(田村奈津子)「近況」(宮野一世)へ <雨の木の下で4>「Lucent Blue Monday の夜」「消息」(関富士子)へ
<雨の木の下で4>「Lucent Blue Monday の夜」「消息」(関富士子)へ 「たけやぶやけた」回文をひろげる(関富士子ほか)へ
「たけやぶやけた」回文をひろげる(関富士子ほか)へ 詩人たち 詩人たち 最新号 最新号 Back Number Back Number vol.4 vol.4 | ふろく 閑月忙日 閑月忙日 リンク リンク 詩集など 詩集など |
vol.4
<雨の木の下で 4>
笑うお皿 (1998年2月26日) 田村奈津子
澤田痴陶人(ちとうじん)の展覧会を見た。昨年大英博物館で初の日本人陶芸家として個展が開催されたのだという。
彼の陶磁器の絵付けを初めて観た日、私の身体は大喜びだった。先住民のアートに触れたときのようにユーモラスで原初的な力が溢れてきたかと思うと、昔から知っているはずの東洋の模様が生き返るように跳ねていて懐かしかった。鬼や天女、茄子や瓢箪、龍や蛙が伊万里の色でお皿からはみ出しそうに踊っていた。ずらっと陳列された作品に囲まれて「日本もまだまだオモシロイ」と、詩の隠れ家を捜し当てたような気になった。
「ゆきとどけば/つまらなく/かけてこそ/また」。ぜひ一度ご覧になることをお薦めする。
近況 (1998年2月26日) 宮野一世
1月、北村太郎の詩集・全集未収録詩篇を見つけた。ライトヴァース風の7篇。そのうち折句詩(アクロスティック)が1篇。
ぼく自身は、まだ折句詩を2、3篇しか書いたことがないし、これからもあまり書くつもりはない。折句詩集を夢見たこともあったが、『新聞紙とトマト』(前ページ「グラグラと黒い墓」)の存在を知って、諦めた。とてもかなわないと思ったからだ。もし今後ぼくの詩に折句が見つかったとしても、おそらくそれは神様の力による偶然の産物である。
これも1月のことだが、本を書かないか、とぼくに或る出版社から声がかかった。どうなるかまだ雲をつかむような状態。
そんなこんなで詩が書けない。去年詩を読み過ぎたのかも知れない。暗い毎日をおくっている。関さんの活動を刺激にしたい。
 <雨の木の下で4>「恩知らず」「清水哲男の猫背」(関富士子)へ
<雨の木の下で4>「恩知らず」「清水哲男の猫背」(関富士子)へ 「たけやぶやけた」回文をひろげる(関富士子ほか)へ
「たけやぶやけた」回文をひろげる(関富士子ほか)へ 詩人たち 詩人たち 最新号 最新号 Back Number Back Number vol.4 vol.4 | ふろく 閑月忙日 閑月忙日 リンク リンク 詩集など 詩集など |