| <詩を読む10> 詩集『石 KAMEHЬ』(オシップ・マンデリシュターム作/早川眞理訳) |
関 富士子
 翻訳者であること、翻訳するとは、どんな行為なのだろう。オシップ・マンデリシュタームの詩集『石』を読むうちに、ふとわたしは思った。その行為はまず第一に、作品の最初の、最も良い読者たろうとすることなのかもしれない。くりかえし翻訳されている著名な作品だとしても、最良の読者になることは可能である。翻訳者の栄光とは、そのようなささやかな喜びのなかにあるのではないか。
翻訳者であること、翻訳するとは、どんな行為なのだろう。オシップ・マンデリシュタームの詩集『石』を読むうちに、ふとわたしは思った。その行為はまず第一に、作品の最初の、最も良い読者たろうとすることなのかもしれない。くりかえし翻訳されている著名な作品だとしても、最良の読者になることは可能である。翻訳者の栄光とは、そのようなささやかな喜びのなかにあるのではないか。
詩と翻訳者との幸福な出会い。詩集『石』はこのようにしてわたしのもとへ届けられた。
25
どうして心はこんなに歌いたく
そして愛する名はこんなにも少なく、
ふと捉えるリズムは――ただの偶然、
ふいに吹き寄せる北風にすぎないのか?
北風は埃の雲を吹きあげて、
原稿箋の葉をざわめかせ
それきりもどってこないか――あるいは
もどってきてもすっかり様変わりしている。
おお オルペウスの広やかな風よ、
おまえは海のかなたへ吹き去ってしまう、
そして、創造されていない世界を愛おしみつつ、
ぼくは不要な「わたし」を忘れていた。
おもちゃのような茂みをさまよいながら
ぼくは瑠璃色の洞窟をみつけた……
ぼくは実在の人間なのだろうか、
死はほんとうにやってくるのだろうか? 1911年
詩集のあとにていねいに付けられた訳注によると、この詩の最終2行が、スターリン獄の死刑囚雑居房の壁に刻まれていたという。
訳者の早川眞理さんは、20年以上も前にこの詩集に出会い「たちまち魅せられてしまった」というが、その気持ちがよくわかる。詩集のタイトルの「石」は「言葉」の喩として使われているらしい。詩人のピュアな心は、「生」という「創造されていない世界」へ向き合い、言葉の深い魅惑と、表現することへのはかりしれない不安に揺れている。
わたしはマンデリシュタームをほとんど知らない。解説では、彼は1891年にユダヤ系家庭に生まれ、主に帝政ロシアのペテルブルグで育っている。『石』は20代で出した第一詩集である。初めのほうの硬質なシンボリズムをへて、中ほどから詩はより現実世界にかかわるものに変わっていく。
49 (部分)
塔の上では女怪獣(キマイラ)たちの言い争い――
このなかでいちばん醜いのは誰?
朝になると冴えない伝道者が
天幕へ人びとを呼び込んでいた。
市場では犬どもが騒ぎまわり、
両替屋の錠前ががちゃついている。
誰もが永遠から掠めとる、
けれども永遠は――海の砂のよう、
こんないかにも辛辣な目で、風景や人物を生き生きと描写した詩もわたしには好ましい。
マンデリシュタームは、スターリンを風刺した詩で逮捕され、流刑地生活ののち、ラーゲリで死去。47歳。
訳者の早川眞理さんは、小出眞理の名で詩集『異邦、そして懐郷』(書肆山田)を持つ詩人でもある。この詩集は、1985年にモスクワやレニングラードに滞在し、マンデリシュタームの生前ゆかりの人々を訪ねたときのことがモチーフになっているようだ。「マンデリシタームの迷宮、究めがたい森」に魅せられつづけている早川眞理さんの仕事に敬意を表する。
詩集『石 KAMEHЬ』オシップ・マンデリシュターム作/早川眞理訳 1998年6月30日刊 ¥1800E ご注文は群像社 千代田区猿楽町2- 3- 1〒101-0064 TEL.03-3291-6153 振替00140-8-95943
詩誌「貝の火」8掲載
| <詩を読む9> 木下夕爾児童詩集『ひばりのす』を読む |
関 富士子
 装丁を見てほしい。ベージュの地にマロン色のかこみ。同じ色の丸っこいタイトルの字体。ひとひらの葉。ページを開くと大き目の活字が字間を半角ほど空けて並んでいる。
装丁を見てほしい。ベージュの地にマロン色のかこみ。同じ色の丸っこいタイトルの字体。ひとひらの葉。ページを開くと大き目の活字が字間を半角ほど空けて並んでいる。
心をこめて本を造る人の愛が伝わってくるようではないか。
懐かしい「ひばりのす」をはじめ、見開き2ページで終わる短い詩が21篇。どれも幼かった自分のこころがそのままそこにあるような、郷愁を誘うものばかり。
しかし、ここに描かれているのは郷愁ばかりではない。
詩集全体に流れているのは、たった独りで森閑とした世界に向き合っている子どもの、生への根源的な不安である。
しずかな晩
それからどうなるのか わからない
わるものに さらわれた おひめさまは
うまにのって さがしにでかけた おうじさまは
お話のとちゅうで
おとうさんが でかけたので
ふたりがうまくあえるか どうか
とおくに
うっすらと
野やきの火のみえる
しずかな晩だ
思いがけなかったのは、詩篇の最後に収められた「メルヘン・ながれの歌」という散文。もとはエッセイ集に収められていたものらしいが、詩がいくつか挿入された童話のような散文詩のようなすてきな文章である。
厳酷の夏よ
麦のように稲のように
私を刈り取るものは誰?
私を植え育てるものは誰?
太陽とそれから
あの閉ざされることのない大きな眼のために
絶えず白い雲たちを押しのけているものは?
この本を企画・編集したのは渡部俊慧さん。詩誌「オルフェ」に拠り、詩人たちの俳句のグループ「余白句会」のメンバーだったが、ある日姿を消して何年か。「現代詩手帖」で井川博年さんに「行方不明」などと書かれて心配している方もいるかとおもうが、こうしてめだたないがいい仕事をしている。酒は相変わらずのようだ。どうか酒を減らして詩を書いてほしい。
木下夕爾 (1914 −1965) 詩人・俳人。広島県生まれ。
堀口大学に認められる。詩集「田舎の食卓」「生まれた家」「児童詩集」「笛を吹くひと」など。没後刊行された「定本木下夕爾詩集」により第18回読売文学賞受賞。
また、久保田万太郎に認められ、俳誌「春燈」に加わる。句集「南風抄」「遠雷」など。
同郷の井伏鱒二との交流は終生続いた。
木下夕爾児童詩集『ひばりのす』1429円+税 B6判67ページ ハードカバー
ご注文は 光書房 東京都板橋区4-30-6 〒173-0004
tel. 03- 3961- 5057 fax. 03- 3961- 4140
振替00110- 1- 17547
愛の成就に立ち合う
関富士子
詩集『海に沿う街』を読み終えたときの気持ちをなんといったらよいか。
人が切望しながらひどく得がたく思えるものが、ここにひっそりと生まれ、はぐくまれているのをまのあたりにした驚き、羨望、感嘆、喜び。
倉田良成の最新詩集「海に沿う街」は、前2冊に惜しげもなくきらめいていた詩的言語が極力抑えられ、一見平易な恋愛詩篇のようだが、実はなまなかに得られない新しい世界をかちえているように思われる。
彼は1970年代に二冊の詩集を上梓しているらしいが、その後沈黙し、90年代に入って旺盛な詩作を再開した。この7年の間に4冊の詩集を出している。わたしが読んだのはそのうちの近作3冊だが、この詩人の獲得している極上の言葉に、いつも詩を読む愉楽を味わってきた。
「(未来からの光のおとずれに/かすかに戦慄して)」(「忘れ水」)
「おおきな叫びの時間のうちに森はある/しかしこの世では/それは深い沈黙とともに聴き取られる」(「猫曲がり町で」『金の枝のあいだから』1994年私家版より)
世界は、彼の眼に触れたとき、あらゆる事物が苦さと剥落をともなったまま、この世のものとも思えずきらめきはじめる。
「夕ぐれ、世界は巨きな花の痕跡となる」(「青空のほかにはなにもない」)
「濡れた光彩が映す精緻な夏の市街図」(「いつもここからが発端である」)
「わたしたちが生きているあいだは墜ちづつける鳥のさけび」(「夕映え」『ゼノン、あなたは正しい』2000円1995年 昧爽社刊より)
昧爽社刊より)
崩壊寸前の街の残酷なまでの輝き。まるで天使が中空からこの世を見るように、世界を眺め渡す硬質の視線。このように「世界」を俯瞰する天使が、一人の女性に出会ってようやく地上に降り立ち、羽根を折りたたんだというとまるでなにかの映画のようだが。
いやいやそうではなく、40年以上も別々の人生を歩いてきたごく平凡な男女が、ある時出会い愛し合うのだ。
表題作の「 海に沿う街」はこんなふうである。
八重洲口へむかうタクシーのなかで、きみは何を言ったのか
頭が変なジェルソミーナにひどいことをして捨てたザンパノは
年老いて、彼女が死んだ海べりの街の砂浜で悔恨にくれて泣いたが
彼があやめた天使のように軽薄な綱渡り師の哄笑とともに
それでも人生は祝祭だった
タクシーのなかで、きみはきみの知らない謎を私にかけたのか
夜の横浜駅で甘栗売りから甘栗を買う
焼け石からたちのぼる熱のむこうで男はなんだかゆらめいて
やいばのように清冽な大河口都市の殷賑をまぼろしに見せる
ティエンチン、大蒜と麺麭の芳香がする街衢を草鞋の男が行く
この世は夢と、風が語り木が鳴り、きみの身体の無比なロゴスが示した
きのうと同じように海へ出かけていって、ある日帰らなくなる夫や恋人を
永遠に待ちつづける黒い服の女たちの声で歌うアマリアは
床を踏み、腕をよじらせ、恍惚のなかにふと恋しい亡人の声音をひびかせる
そこで陸が尽きるところ、青い川の流れる果てに涙の匂いのする繁華な街がある
鰯と葡萄酒でいつもの食事を取るきみと私に、このヨコハマが
思い出せない夢のように、かすかな痛みとしてよみがえることがあるのだろうか
八重洲口まで行くタクシーのなかで、私の膝のうえに手を置き
楽譜に書き込むようにきみは私の肋骨にひとつの音符を深く刺した
巌のような雲の間から射す冬のはげしい夕映えに耐えながら
それでも人生は歓びである
夜にむかって流れ下るわれわれの小さな船のなかで、きみはたしかにこう言った
「次のときも、わたしのなかに生まれ変わって」
よけいな解説は不要なのだが、わたしなりの読みでこの詩をたどってみる。
男と女が古い映画を見た帰りだろうか。悲しい物語の余韻を味わいながら、ふと女がつぶやいたひとことを、「私」は謎の言葉のようにいぶかしむ。そのひとことは、夜の街の雑踏のなかで甘栗を買うときも耳に残っている。
都市のにぎわい、豊かな猥雑にもかかわらず、ここでの「世界」はまぼろしのようにはかなく「私」の眼に映る。男と女は、時を漂泊する船に同乗した客人である。そのつかのまを、いにしえの「草鞋の男」が時を超えて往還する。
「私」はようやく、死が二人を分かつときの、女の深い悲しみ、嘆きに思い至る。言葉が、恋歌の「ひとつの音符」のように「私」の肋骨の間を縫い、胸を「深く刺した」のである。「次のときも、わたしのなかに生まれ変わって」。
「この世は夢」でありながら、それでもなお、人が永遠を望むとき、世界は悲哀に満ちてあまりに短い。いつか「思い出せない夢」のように、このひとときがまぼろしになるのを「私」は知っている。それでもなお、世界はかけがえなくいとおしく、「人生は歓び」と気づくのである。
このとき「私」をとりまく「世界」は大きく変革している。しかも読者は、その変革の過程に立ち合い、「世界」への愛が成就する希有な光景を、つぶさに見ることができる。一篇の詩の、夕方から夜へと移る現実の時間に、永遠と一瞬、過去と未来がふかぶかと交錯する。詩人のすばらしい力量である。こうしてみると、詩とはまるで、一瞬にしてすべての時を生きることができるもののようではないか。
(詩集『海に沿う街』倉田良成著2000円+税・1998年 ミッドナイト・プレス刊)
ミッドナイト・プレス刊)
 詩人たち
詩人たち 最新号
最新号 BackNumber
BackNumber vol.6
vol.6 閑月忙日
閑月忙日 リンク
リンク 詩集など
詩集など  詩人たち
詩人たち 最新号
最新号 BackNumber
BackNumber vol.6
vol.6 閑月忙日
閑月忙日 リンク
リンク 詩集など
詩集など 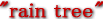 vol.6
vol.6翻訳者であること、翻訳するとは、どんな行為なのだろう。オシップ・マンデリシュタームの詩集『石』を読むうちに、ふとわたしは思った。その行為はまず第一に、作品の最初の、最も良い読者たろうとすることなのかもしれない。くりかえし翻訳されている著名な作品だとしても、最良の読者になることは可能である。翻訳者の栄光とは、そのようなささやかな喜びのなかにあるのではないか。
装丁を見てほしい。ベージュの地にマロン色のかこみ。同じ色の丸っこいタイトルの字体。ひとひらの葉。ページを開くと大き目の活字が字間を半角ほど空けて並んでいる。
昧爽社刊より)
ミッドナイト・プレス刊)
 <雨の木の下で>「4羽のひな」(関富士子)「天気のあとで」(樋口俊実)「片思い」(関富士子)へ
<雨の木の下で>「4羽のひな」(関富士子)「天気のあとで」(樋口俊実)「片思い」(関富士子)へ <詩>「墓地へ」(関富士子)へ
<詩>「墓地へ」(関富士子)へ これなあに?1・2(関富士子・桐田真輔)へ
これなあに?1・2(関富士子・桐田真輔)へ 詩人たち
詩人たち 最新号
最新号 BackNumber
BackNumber vol.6
vol.6 閑月忙日
閑月忙日 リンク
リンク 詩集など
詩集など