 詩人たち
詩人たち 最新号
最新号 BackNumber
BackNumber vol.6
vol.6 閑月忙日
閑月忙日 リンク
リンク 詩集など
詩集など  詩人たち 詩人たち 最新号 最新号 BackNumber BackNumber vol.6 vol.6 | ふろく 閑月忙日 閑月忙日 リンク リンク 詩集など 詩集など |
 "gui詩gui詩"もくじ
"gui詩gui詩"もくじ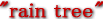 vol.6 「gui詩gui詩」 Poetry Reading
vol.6 「gui詩gui詩」 Poetry Reading
 「Books Bar 4-kama」に掲載されている「傾向」という詩。ルリユールの話も詳しく本の写真や図入りで説明がある。ぜひジャンプして楽しんでほしい。
「Books Bar 4-kama」に掲載されている「傾向」という詩。ルリユールの話も詳しく本の写真や図入りで説明がある。ぜひジャンプして楽しんでほしい。四釜 裕子
ルリユール(装丁)の話
・・・・古臭いなあと思うかもしれませんけれど、パッセ・カルトンという手法は、そもそも歴史のあるもので、わたしはジャリがすごく好きなんですけど、本読んでもまったくわかんないんですけれども、皆さんもどうですか、わかんないけどもなんか好きってありますよね。
それで、この本は別格なんですが、パッセ・カルトンというのは本が開かないんですよ。何が違うかというと、パビヨンという手法(栃折久美子氏考案のかがり方)はここにこう溝があるからべろっと開くんですが、パッセ・カルトンはきちきちに作りますから溝がないんですよ。ということは開かないんですよ。唾付けたくないし、花切れは丹念に編んでるからここに指をかけたくないし。
じゃあ、あたしは何のためにこれを作ったのかわかんないんですよ。パッセ・カルトンてわりとそういうものなんで、だからフェチですね、一種のね。そうは言いたくないんですけど。
いちばん違うのは何かといいますと、かがり方が違うんです。ここに若干線が見えますね。かがるときに縦に麻糸を付けるんですね。この麻糸が残っているんですけれど、この麻糸を表紙の厚い型紙のなかに埋め込んでしまうんです。
ふつうの本ですと、表紙は見返しで留めるんですけど、パッセ・カルトンだと、この革と、埋め込んでますので、それで留めてる。あと内側の革で留めてる。だから見返しっていうのはつながっていないんですね。あまり開きたくないんですけど、見ていただきたいんですが、こういうふうに革が張ってあるから見返しをつながなくてもいいんですね。
パッセ・カルトンで一番言いたいことは、ここをいっしょうけんめい丹念につないでるから壊れないよということで。でも、開かないし、触りたくないし、花切れはもう何十回と編み直してるわけです。 シルクの糸で編んでますから。ということはこれ大切に取っておきたいなというのがあるんです。
実はこの本はタイトル入ってませんし、これは函に入れるつもりですがそれはまだできていませんし、今日は間に合わなくって、今日はこういう形になってしまいました。
パッセ・カルトンはそういうふうにちょっとフェチ入ってますけど、大好きな人が一生懸命造ってます。
あんまり時間かかっちゃうのも何だなと思うんですけど、わりと面白いんじゃないでしょうか。 この紙なんかもわたし自分で作ったんですね。マーブルですけど、いくらでもできます。マーブルは簡単な溶剤ができてますから、十回くらいやり直せば自分の思い通りにできますし。
これも一応ジャリですし、渦巻を入れようかなと思ったんですけど、できなかったんでこういうふうになっちゃたんですが、いろんな紙を作るシステムもできてますから、もしみなさん本の大好きな方だと思いますので、もし作りたい方がいらっしゃいましたら、どうでしょうか。
 詩「傾向」へ 「Books Bar 4-kama」
詩「傾向」へ 「Books Bar 4-kama」 「傾向」の朗読 四釜裕子
「傾向」の朗読 四釜裕子 飯田隆昭/ W.バロウズ「デッド・ロード」
飯田隆昭/ W.バロウズ「デッド・ロード」 南川優子「注射器」ほか2編
南川優子「注射器」ほか2編 "gui詩gui詩"もくじ
"gui詩gui詩"もくじ "rain tree" バックナンバーvol.6もくじへ
"rain tree" バックナンバーvol.6もくじへ "rain tree" 表紙へ
"rain tree" 表紙へ "rain tree"最新号もくじへ
"rain tree"最新号もくじへ ふろくへ
ふろくへ