 "gui詩gui詩"もくじ
"gui詩gui詩"もくじ

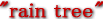 vol.6 gui詩gui詩 Poetry Reading
vol.6 gui詩gui詩 Poetry Reading
 奥成達「帽子の海」へ
奥成達「帽子の海」へ
 「ね、森原さん」 ―「gui」20周年のための回顧譚― その2 奥成達 へ
「ね、森原さん」 ―「gui」20周年のための回顧譚― その2 奥成達 へ
「ね、森原さん」 ―「gui」20周年のための回顧譚― その1
奥成 達
初出 現代詩手帖1998年5月号 わが仲間たち/4
 (gui例会1993.7.10怪しげな人物もいるがやくざではない。前の方から、藤富保男・飯田隆昭・関富士子・国峰照子・奥成達・金子晴子・金子礼子・岡崎英生・吉田仁・森原智子・安藤一男・小野悠子・川辺元・田村祐介・高橋肇・奥成繁・上久保正敏)
(gui例会1993.7.10怪しげな人物もいるがやくざではない。前の方から、藤富保男・飯田隆昭・関富士子・国峰照子・奥成達・金子晴子・金子礼子・岡崎英生・吉田仁・森原智子・安藤一男・小野悠子・川辺元・田村祐介・高橋肇・奥成繁・上久保正敏)
僕は相当古くから資生堂のPR誌「花椿」の愛読者で、いまでもほぼ毎月欠かさず読んでいる。
最近(やや大型版になってから)特に愛読しているのは、後藤繁雄さんという1954年大阪生まれのエディターによる「当世藝問答」というシリーズの対談頁だ。
なにしろその対談の様子が、よくいえば鋭いヒラメキにあふれ、悪くいうと(ぼくは少しも悪いと思ったことはないが)独断、即興の口から出まかせを、斟酌いっさいなしに(ラージヒルのジャンプのように)喋り合っている。そのスポーツ感覚、セッション感覚がいつも痛快なのである。つまり、体中の五感をそのままに、一度たりとも”文学”に翻訳して黴くさく喋り合ったりはしない。そのスピード感がいつもとても爽快なのである。
たとえばいま手元にある最新号(三月号)の対談のお相手は大竹伸朗さんで、試しにその最後の締め括りのところだけでも、せめてここで少し読んでみて下さい。
大竹 (前略)とにかく、「こんな絵あるわけないよな」っていう絵が描きたい。誰が見てもこれは絵じゃない、こんな絵で成立つわけがないっていう絵を描いてみたい。作品とかつくってると、あくまで個人の世界だから共感しなくでもいいんだよ、っていうふうに閉じてしまいがちでしょ。それはイヤなんだ。地方で展覧会をやる時は、その美術館の近所に住んでいるおじさんやおばさんが、「あ、馬だ」とか「女だ」とか指さして言葉で言えた方がいいと思うから、そういう作品にしようと思う。
例えば、宇和島のタクシーの運転手なんかは、ピカソなんて名前は知っているけど、どう知っているかと言うと、「わけのわからない絵」として認識してるんだ。それって正直だよね。現代アートって、そういうのがあまりにもなさすぎる。
後藤 「わからない絵」っていうわかられ方っていいと思う。
大竹 作品つくるにしても、哲学なり宇宙観みたいな高尚なところから出てくるんじゃなくて、タクシーの運転手と言い合いになって、「コノヤロー」みたいな気分で車降りて、それでダーッっとつくったりするものじゃなきゃね(笑)。
特にこの最後の“(笑)”で終る(乱暴な)感じがすごくいいのだ。たとえば「現代詩手帖」の中の対談で“(笑)”が出てくる対談にはなかなかお目にかかれないけれど、“詩”の話をしている時に笑うって、そんなに普段あり得ないことなのだろうか。
その点だけなら「gui」の例会では、みんなとにかくよく笑います。必ずしも“詩”の話ばっかりではないにしろ、guiの同人たちは会話のユーモアをまず最優先している人々が多いから、とはとりあえず言ってもいいかもしれない。
だからこの後藤さんと大竹さんの対話の仕方に特別に親近感をもってしまったのかもしれない。ぼくも密かに大竹さんを見習って「こんな詩あるわけないよな」という詩を、ぜひ書いてみたいものだな、と、すかさず思ってしまうのである。
といっても、というようなことは、あくまでぼく個人の密かな抱負なのであって、決して「gui」の同人みんながそう思っていること、というわけではけっしてない。“詩”に対する考え方はもちろん各人各様でよく、だからこそ面白いのだから。
 (森原智子と奥成達1993.11.13)
(森原智子と奥成達1993.11.13)
と、こんなことをわざわざ付け加えるのは、うっかりこういう事を書くと、たいていまず同人の森原智子さんから、すぐさま猛烈なクレームの電話がかかってくるので、話がえらく面倒臭くなってしまうのが困るからだ。
他の同人誌もそうなのかどうかはわからないが、それにしても森原さんはこういうことに特にチェックのうるさい頑固同人なのである。
全てにこんな調子だから「gui」が“わが仲間たち”だなんて気楽な同志感覚は、まったくといっていいほどない。
それにしてもせっかくの20周年なのであえて昔話を書くことにする。
初めてその森原さんにお目にかかったのは、ぼくが20代後半で(いまぼくは55歳です)、森原さんの故郷・秋田へ鍵谷幸信、藤富保男両氏のお供で出かけたときだった。いまから30年ぐらいは以前のことになる。
そして、森原さんはまだこのころはやさしい(詩作品のことではなくて、人柄のこと)詩人で、ご主人の故・船木仁さんもご一緒にきりたんぽの鍋を仲良くつついて食べた。ぼくにとってはあのころの森原さんのほうが、はるかにいまよりも和気あいあいとしていて、ずっと近しい仲間のようであった。
藤富保男さんと初めてお会いしたのはさらにはるか前で、まだぼくは15歳の少年だった。北川冬彦の主宰する「時間」の集まりで、四ッ谷須賀町明石」という古めかしく、見るからに木賃宿の座敷の一室であった。
 (京都万福寺の前でシガレットを吸う藤富保男と奥成達1997.3.22gui京都例会)
(京都万福寺の前でシガレットを吸う藤富保男と奥成達1997.3.22gui京都例会)
北川先生の提唱されるネオ・リアリズムという詩学のもとに参集した「時間」の錚々たるお歴々と一緒に、いま考えれば29歳の藤富さんと、15歳のぼくが同席していたのだから、ひとの出会いの初めというのは、こうやってあらためてふり返ると想像を絶して面白いことが多い。
このネオ・リアリズム詩運動についていまぼくは説明する気も、またそのスペースもないが、ともかくこうやって書いているだけで猛烈に懐かしくなるのは事実である。
かつての〇〇主義、〇〇イズムはすっかり地に落ちてしまっていま元気がないが、ぼくはこの15歳を機にその後“運動”(文学運動とか、芸術運動とか、政治運動というような)名のつく組織に参加したことは一度もない。
強いていえば、全日本冷し中華愛好会(略し全冷中)神奈川委員会・逗子支部長・バビロニア派だったことと、「温泉主義ストーンズ」という温泉クラブの事務局をしていたことがあるが、これは言ってみればどちらもパロディで、文学運動でも芸術運動でも、まして政治運動でもけっしてない。
 (川辺元1997.夏)
(川辺元1997.夏)
ぼくは北園克衛主宰の「VOU」にいたこともあるから、モダニズム、そしてモダニストと呼ばれるような人々にずっといまでも親近感をもってはいるが、だからといって「gui」がモダニズムの同人雑誌であるはずもない。
昨年の本誌(現代詩手帖)12月号に「今や日本のモダニズムの総本山とも言うべき「gui」と紹介されていたが、これはお気持ちはうれしいが大いなる誤解である。
これはもうちょっとゆっくり誌面を読んでくださり、もうちょっと同人の顔ぶれをながめなおしてくれれば一々説明の要もないことだ。一目瞭然である。それにいくらなんでもモダニズムに“総本山”はないでしょう。
ぼくはいま「gui」に、たまたま北園克衛の戦時中のエッセイを読むことで連載をつづけているから、そのせいだといわれるなら、この連載の前はずっと“ドラッグ”がテーマだった。こちらはおかげで「ドラッグに関する正しい読み方」(大村書店)という一冊の本になった。
 (高橋肇と國峰照子1993.11.13)
(高橋肇と國峰照子1993.11.13)
だからぼくはずっと旗をふることも、大手をふることも一度もなく、ただただノンポリといわれつづけてきたし、自分でも素直にそれを甘んじて認めつづけてきた。いまからペン・クラブや現代詩人協会というような団体に入るつもりも、第一誘われたこともない。(昔、小中陽太郎さんにペン・クラブに一回だけ誘われたことがあったかもしれない)
これは、こちらがそうした組織を否定している、というように大袈裟にとられてしまうと困るのだが、ようするになんとなく外野から見ていると人間関係が面倒臭そうにしかどうしても見えてこないのだ。
「gui」だって“集団”だし、確かに組織をつくっているじゃないか、といわれれば返答のしようもない。それにはっきりいってやはりかなり面倒臭い。
“サロン”というのは、あまりいい意味で使われることはないが、正にそのいい意味ではけっしてない“クラブ”“サロン”に「gui」はよく似ているかもしれない。
 (徳弘康代1997.夏)
(徳弘康代1997.夏)
なぜなら最初からそれほどしっかりした考えがお互いにあって始めたわけでもなく、まあ言ってみれば、物を書く、描く、造るという、どちらかといえば、普段孤独な作業をつづけているひとりひとりの、定期的寄り合いの会という雰囲気も強いからだ。
このコラムのシリーズは「わが仲間たち」というサブがついているらしいが、前にも少し述べたようにうるさい大先輩がけっこう多いし、ぼくが一まとめに括れる顔ぶれでもない。職業も立場も年齢も、あまりに違いすぎているのである。よくいえば顔ぶれの幅がやたらに広いのだ。
じゃあ話がぜんぜん噛み合っていないのかというと、けっしてそうでもなく、年に三回けっこう高額の同人費を払い、同じく年3回例会というお酒を飲む会を、同人の山口真理子さんの酒場「マリーン」で、こういう時だけはいやに几帳面にこれまで一回も休むことなく開いている。そしていつも盛況である。
 (山口真理子1998.夏)
(山口真理子1998.夏)
およそ毎回5、6時間はひたすら飲みつづけていることになるこの会で、どんな話をみんながしているのかを報告すれば、実はとてもわかりやすいのかもしれないが、(森原さんのこともあるし)これは公開を憚る。しかし、さっきの話のつづきではないが、みんなゲラゲラとよく笑うことは確かである。だから、どうなのだといわれてしまうとまた困るけど。
それからその夜の出席者の顔ぶれの組み合わせによって、おそろしく話は変わり、妙に生真面目になってみたり、泥酔者がやたらにあふれたり、日々、千差万別に変化する。誌面の上でもまったく同じで、同人の新入、退会によってその都度著しく変化していくのがわかる。
つまりなんだかんだといっても、何等かの形で、バラバラはバラバラなりに、メンバーがメンバーたちによって互いに大きな影響を確実に受けあってはいるのである。
 (墨象家小野悠子1998.夏)
(墨象家小野悠子1998.夏)
しかし、それは特別意図的にそうなっているわけでは、けっしてないのだ。
もともとメンバーが無思想で“思想”もなにもない人たちというわけではないのであって、ようするに思想がとても見えにくい(見えにくくしている)人たちが多いということなのかもしれない。
あるいは生き方やモラルについて語るよりも、この会にいる間ぐらいはせめて想像力の世界を最優先しようと考えられているからかもしれないし、カテゴライズされた一つの物事(イデオロギー)ですべてを見ることをしない、それが当然のように複数のカテゴライズを隠しもった人々の、ささやかなパーティ(宴会)好きの団体のようにも思える。
 「ね、森原さん」 ―「gui」20周年のための回顧譚― その2 奥成達 へ
「ね、森原さん」 ―「gui」20周年のための回顧譚― その2 奥成達 へ
 ヤリタミサコ「gui詩gui詩レポート」
ヤリタミサコ「gui詩gui詩レポート」
 "gui詩gui詩"もくじ
"gui詩gui詩"もくじ
 "rain tree" バックナンバーvol.6もくじへ
"rain tree" バックナンバーvol.6もくじへ "rain tree" 表紙へ
"rain tree" 表紙へ "rain tree"最新号もくじへ
"rain tree"最新号もくじへ ふろくへ
ふろくへ
 詩人たち
詩人たち 最新号
最新号 BackNumber
BackNumber vol.6
vol.6 閑月忙日
閑月忙日 リンク
リンク 詩集など
詩集など  詩人たち
詩人たち 最新号
最新号 BackNumber
BackNumber vol.6
vol.6 閑月忙日
閑月忙日 リンク
リンク 詩集など
詩集など  "gui詩gui詩"もくじ
"gui詩gui詩"もくじ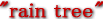 vol.6 gui詩gui詩 Poetry Reading
vol.6 gui詩gui詩 Poetry Reading 奥成達「帽子の海」へ
奥成達「帽子の海」へ 「ね、森原さん」 ―「gui」20周年のための回顧譚― その2 奥成達 へ
「ね、森原さん」 ―「gui」20周年のための回顧譚― その2 奥成達 へ (gui例会1993.7.10怪しげな人物もいるがやくざではない。前の方から、藤富保男・飯田隆昭・関富士子・国峰照子・奥成達・金子晴子・金子礼子・岡崎英生・吉田仁・森原智子・安藤一男・小野悠子・川辺元・田村祐介・高橋肇・奥成繁・上久保正敏)
(gui例会1993.7.10怪しげな人物もいるがやくざではない。前の方から、藤富保男・飯田隆昭・関富士子・国峰照子・奥成達・金子晴子・金子礼子・岡崎英生・吉田仁・森原智子・安藤一男・小野悠子・川辺元・田村祐介・高橋肇・奥成繁・上久保正敏) (森原智子と奥成達1993.11.13)
(森原智子と奥成達1993.11.13) (京都万福寺の前でシガレットを吸う藤富保男と奥成達1997.3.22gui京都例会)
(京都万福寺の前でシガレットを吸う藤富保男と奥成達1997.3.22gui京都例会) (川辺元1997.夏)
(川辺元1997.夏) (高橋肇と國峰照子1993.11.13)
(高橋肇と國峰照子1993.11.13) (徳弘康代1997.夏)
(徳弘康代1997.夏) (山口真理子1998.夏)
(山口真理子1998.夏) (墨象家小野悠子1998.夏)
(墨象家小野悠子1998.夏) 「ね、森原さん」 ―「gui」20周年のための回顧譚― その2 奥成達 へ
「ね、森原さん」 ―「gui」20周年のための回顧譚― その2 奥成達 へ ヤリタミサコ「gui詩gui詩レポート」
ヤリタミサコ「gui詩gui詩レポート」
 "gui詩gui詩"もくじ
"gui詩gui詩"もくじ "rain tree" バックナンバーvol.6もくじへ
"rain tree" バックナンバーvol.6もくじへ "rain tree" 表紙へ
"rain tree" 表紙へ "rain tree"最新号もくじへ
"rain tree"最新号もくじへ ふろくへ
ふろくへ