 "gui詩gui詩"もくじ
"gui詩gui詩"もくじ

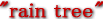 vol.6 gui詩gui詩 Poetry Reading
vol.6 gui詩gui詩 Poetry Reading
 「ね、森原さん」 ―「gui」20周年のための回顧譚― その1 奥成達へ
「ね、森原さん」 ―「gui」20周年のための回顧譚― その1 奥成達へ
 奥成達「帽子の海」へ
奥成達「帽子の海」へ
「ね、森原さん」 ―「gui」20周年のための回顧譚― その2
奥成 達
初出 現代詩手帖1998年5月号 わが仲間たち/4
 (高橋肇1997.夏)
(高橋肇1997.夏)
「gui」には主宰者というものは特別いないが、事務局というボランティアがあり、原稿集めからゲラの校正、集会などの連絡事務、会費の徴収、雑誌の荷造り、発送(いま部数は800部)の一切をやらされる。これは、いま現在(53号)は、ぼくと高橋肇さん、関富士子さんの三人で担当している。
その高橋肇さんと初めてお会いしたのは、1960年代の終りごろ。当時ぼくは劇画家の上村一夫のシナリオを書いていた(岡崎英生さんもそうだった)ので、「ヤング・コミック」編集部上村一夫担当の高橋さんとして顔を合わせた。もちろんこの時お互いに“詩”の話なんか一言もしたわけではなく、それがいまになって互いに「gui」の同人なのだから面白い。
それがどこの酒場だったのかまでははっきり覚えていないが、多分六本木のいつものスナックのはずで、まだ無名時代の阿久悠さんを上村一夫に紹介されたのもこのお店だった。
 (関富士子1998.夏)
(関富士子1998.夏)
いま「gui」にスミ一色のヌード画を描いている岡村昭和さんは、その上村一夫の大親友としてかつて紹介された人である。
酒場といえば、「gui」にかぎらず、ぼくがあらためて知る知人、友人は、ほとんどといってもいいほど酒場で知り合った飲み仲間で、いま「gui」の読者人気ナンバーワンの「葉山日記」を連載している吉田仁さんと出会ったのも銀座の「やまな」という店でだ。
小中陽太郎さんとのファースト・コンタクトは、同じ「ヤング・コミック」執筆者同士ということで六本木の焼き鳥屋であった。NHKを例の件でクビになったばかりだったと思うが、この焼き鳥屋の勘定は小中さんにすっかりご馳走になったはずである。
 (京都丸太町赤垣屋で品書きを見る遠藤瓔子(右)と大阪の井上典子1997.3.22gui京都例会)
(京都丸太町赤垣屋で品書きを見る遠藤瓔子(右)と大阪の井上典子1997.3.22gui京都例会)
遠藤瓔子さんは1970年代初め、青山に合った「ロブロイ」という酒場の文字通りおっかないママだった方だ。いま作家になっておられる安部譲二さんとご夫婦だったころで、それはド迫力のある店だった。
「ロブロイ」のハウスピアニストは渋谷毅、そこでピアニスト修業中で弾いていたのが現・矢野顕子さんである。とにかくヤッちゃんをはじめ、見るからに危険人物がたまる店だったが、ぼくは深夜になって行き場がなくなると、山下洋輔トリオや三上寛と泥酔してよくたどりついた、いつもその日の終点となる店であった。
その遠藤さんが「gui」に入ったのは、1993年、39号からなのだから、お会いしてからおよそ20年後の久しぶりの再会ということになる。
こうやって一人ずつ同人の紹介をしていったらキリがないが、もっと古い再会で「gui」に入ることになったのが飯田隆昭さんである。
 (飯田隆昭1994.夏)
(飯田隆昭1994.夏)
飯田さんとお会いしたのは1961年に日比谷の三井ビルホールで開いた「新人類学会総会」というイヴェントの時で、ぼくは十八歳だった。吉増剛造さん、岡田隆彦さんに初めてお会いしたのもこの日の夜のことだ。
ついでにこのパーティは、藤富さんをはじめとして、諏訪優、清水俊彦、鍵谷幸信、白石かずこ、片桐ユズルさん等、たくさんの詩人たちによる「詩とジャズ」の会であった。これは日本初の詩とジャズの会ではなかったのかとぼくは密かに自負しているのだが、もちろん本当のことはわからない。
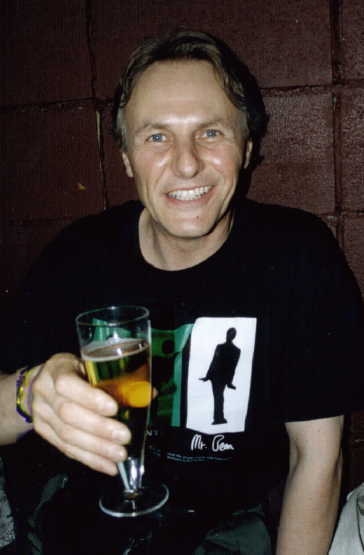 (JOHN SOLT 1998.夏)
(JOHN SOLT 1998.夏)
つまり飯田さんともお会いした時から数えてみればもう40年近いお付き合いをしてきたことになってしまっている。飯田さんとはディックやバロウズやドラッグのことなど、諸々のことで趣味がかなり一致しているので(それに酩酊派同士であるし)、安心して“仲間”と呼ばせていただける数少ない同人の一人なのかもしれない。
白石かずこさんの紹介で初めてお会いしたジョン・ソルトさんも、「gui」に入ってからでももう10年以上になるはず。あらためてふり返ってみると結構みんな古いお付き合いばかりになってしまっているのだ。
「gui」の創刊号は1979年4月1日(エイプリル・フールの日)だから、来年で20周年になる。酒場だったら常連客が花束を抱え次々に祝ってくれるはずだが、さて同人誌の場合はどうしたらいいのだろう。
長ければそれでいいわけじゃないし、いつのまにか高齢化もかなりすすんでいるし、そうそういいことづくめばかりではない。しかも、古くからいる同人はそうでも、新しく入ってこられた方のほうがむしろ最近は多いのだし、そうそう同窓会のようにこうやって昔話ばかりして、感傷の涙にくれるような雰囲気になってしまってもいけないのだろう。
3年あまりも同人費を未納のまま平気な顔でやめたF.Kのような詩人があったり、つづけたくても会費が払えず仕方なくやめる人がいたり、同人誌ならではの悲喜こもごもはきっとどこの同人誌にでもあることなのだろうが、20年たったからそれでもうすっかり安泰というわけにならないのは、これも酒場経営とまったく同じである。
特にいまはインターネットの時代、コンピュータネットワークの時代といわれている時に、グーテンベルク以来の活字印刷文化にいやおうなくこだわり、(というより、パソコンをいじれないからであるが)、出版をつづけているのだから、「gui」(に限らないが)の継続は、無意識にこういうある種のノスタルジーを持ちつづけている人々によって、かろうじて成立してきているような気がしてこないでもない。
 (京都宇治黄檗山万福寺内の普茶料理に喜ぶ吉田仁と萩原健次郎1997.3.22gui京都例会)
(京都宇治黄檗山万福寺内の普茶料理に喜ぶ吉田仁と萩原健次郎1997.3.22gui京都例会)
今年の1月に岡山の秋山基夫さんが、「gui」に連載中の吉田仁さんの私生活日記「葉山日記」を、「ユートピア文学としての“葉山日記”」として顕彰してくださり、400字詰め70枚余という大論文(「あおぞら」1998・2号)には、とてもひと事とは思えないほど感動させられた。
つまりこの吉田さんのすべてにわたるノンポリぶりは、吉田さんだけに限ってのこととはとても思えないのだ。どこか「gui」のポリシーを代表している“ポリシーの無さ”の一つのように考えられないこともないからである。
無党派層といえば確かに無党派層としか他にいいようがないが、そういう明確な政治的立場も、将来の展望もまったくない(それでぜんぜん平気な)というスタンスは、ユートピアというより、かつて慣れ親しんできた、いまと比べたらひどく悦楽的マイペース生活の記憶に対する、たかがおじさんのエゴイスティックなノスタルジーでしかないのではないか、と思ったりもするからである。
 (南川優子1997.夏)
(南川優子1997.夏)
しかしこれを自宅の引き出しにしまっておいたりせずに、「gui」に年三回、400字詰め40枚の日記として連載、発表されたとき、それは吉田さんの個人的なノスタルジー日記という状態から手を離れて、これこそみんなで大切にして守りたいかけがえのない日記へと、いつのまにか大きく変貌していたのである。
どんなものでも(いや失礼!)、きちんと活字にして発表するということは、やはり凄いことなのだと、こういう時にこそあらためて思わされ、成程とビックリさせられる。秋山基夫さんは、だから「葉山日記」を“文学”だと、わざわざ力説し、愛情いっぱいに書いて下さったのだろう。
「gui」がたまにどこかの誌上に紹介されることがあると、たいてい“詩誌”と説明されるけど、すでにご存知の方はすぐわかるようにけっしていわゆる“詩”だけが連載されている同人誌ではない。写真も画もイラストもあり、小説も評論も翻訳も日記もある。
 (奥成繁と四釜裕子1998.春)
(奥成繁と四釜裕子1998.春)
たとえば小中陽太郎、奥成繁、岡崎英生、藤瀬恭子、遠藤瓔子といった同人は、ジャンルとしては普通“小説”あるいは“散文”という区分けに入るはずのものになるのだろう(それも、いわゆる“純文学”でもけっしてない)。
つまりここでぼくがこんな区分けをわざわざ説明してみせるみでもなく、同人誌というのはめいめいが勝手に抱いている“文学”や“アート”というものを、それぞれ自分勝手に、しかし締切り厳守はきちんと守って発表していくという原則があるだけなのだ。締切りを守れなければ、次号にまわり、会費を払えなければやめるしかない。同人誌に他に条件はないのである。
最近号(1997・52号)に飯田隆昭さんが翻訳されたアメリカの新鋭女性作家、ポピー・Z・ブライトの小説「甘美な死体」は、「そこに詩がある」(冨上芳秀)と、特に絶賛されていたくらいだから、本当は詩、散文と、ことさらぼくがここでわざわざ区別して書くことでも実はなかったのかもしれない。“詩”の内部、外部という言い方をうっかりするとこれまた結構面倒臭い話になってしまいそうだが、「gui」をあえて“詩誌”ということにすると、どちらかといえばいわゆる“詩”(というカテゴリー)の外に立つ“詩愛好者”がかなり多いのかなとぼくは思う。(森原さん、これもあくまでぼく個人の意見ですから、けっして電話はいりません。これまた念のため)
 (1997.3.22gui京都例会京都丸太町赤垣屋にて。藤富保男・関富士子・吉田仁・大園由美子・高橋肇・萩原健次郎・井上典子・遠藤瓔子。撮影は奥成達)
(1997.3.22gui京都例会京都丸太町赤垣屋にて。藤富保男・関富士子・吉田仁・大園由美子・高橋肇・萩原健次郎・井上典子・遠藤瓔子。撮影は奥成達)
だからあえて「gui」に新しさ(珍しさ)というものがあったとすれば、それはこれまでの“詩”の正統的(というのがなんだかよくわかってはいないけど)歴史の蓄積の上にだけ立っている新しさ(珍しさ)ではない、ということなのではないだろうか。
もともと詩本来は、どんなやり方でも、どんな書き方でもいいし、まったく自由で構わないものだったんじゃないか。とはいっても、ただ無茶苦茶に書いたらそれで“詩”になるのかというと、そういうわけでもない。
しかし、そういう、いってみれば実験(と、お稽古)をしてみたくてウズウズしている人たちにとっては、こうした半公的な「gui」のような遊園地はとても便利な運動場にきっとなってきたのではないだろうか。
ディズニーランドや日比谷公園ではとても面白くなく、草ぼうぼうの空地ではゲームがかぎられすぎるし、「gui」が一番遊びやすいグラウンドとしてみんなでワイワイ楽しんでいたら、いつのまにか20年もたっていた、とまあ、そんなところじゃないですか、ね、森原さん。
 「ね、森原さん」 ―「gui」20周年のための回顧譚― その1 奥成達 へ
「ね、森原さん」 ―「gui」20周年のための回顧譚― その1 奥成達 へ
 奥成達「帽子の海」へ
奥成達「帽子の海」へ
 "gui詩gui詩"最新号もくじ
"gui詩gui詩"最新号もくじ
 "rain tree" バックナンバーvol.6もくじへ
"rain tree" バックナンバーvol.6もくじへ "rain tree" 表紙へ
"rain tree" 表紙へ "rain tree"もくじへ
"rain tree"もくじへ ふろくへ
ふろくへ
 詩人たち
詩人たち 最新号
最新号 BackNumber
BackNumber vol.6
vol.6 閑月忙日
閑月忙日 リンク
リンク 詩集など
詩集など  詩人たち
詩人たち 最新号
最新号 BackNumber
BackNumber vol.6
vol.6 閑月忙日
閑月忙日 リンク
リンク 詩集など
詩集など  "gui詩gui詩"もくじ
"gui詩gui詩"もくじ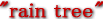 vol.6 gui詩gui詩 Poetry Reading
vol.6 gui詩gui詩 Poetry Reading 「ね、森原さん」 ―「gui」20周年のための回顧譚― その1 奥成達へ
「ね、森原さん」 ―「gui」20周年のための回顧譚― その1 奥成達へ 奥成達「帽子の海」へ
奥成達「帽子の海」へ (高橋肇1997.夏)
(高橋肇1997.夏) (関富士子1998.夏)
(関富士子1998.夏) (京都丸太町赤垣屋で品書きを見る遠藤瓔子(右)と大阪の井上典子1997.3.22gui京都例会)
(京都丸太町赤垣屋で品書きを見る遠藤瓔子(右)と大阪の井上典子1997.3.22gui京都例会) (飯田隆昭1994.夏)
(飯田隆昭1994.夏)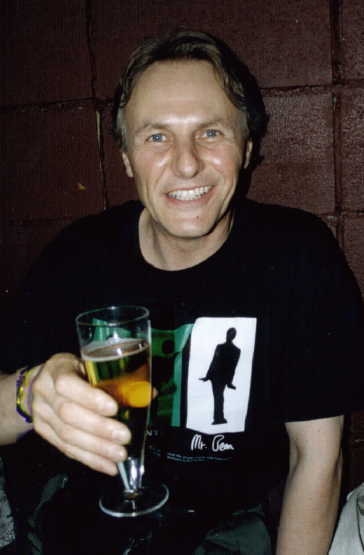 (JOHN SOLT 1998.夏)
(JOHN SOLT 1998.夏) (京都宇治黄檗山万福寺内の普茶料理に喜ぶ吉田仁と萩原健次郎1997.3.22gui京都例会)
(京都宇治黄檗山万福寺内の普茶料理に喜ぶ吉田仁と萩原健次郎1997.3.22gui京都例会) (南川優子1997.夏)
(南川優子1997.夏) (奥成繁と四釜裕子1998.春)
(奥成繁と四釜裕子1998.春) (1997.3.22gui京都例会京都丸太町赤垣屋にて。藤富保男・関富士子・吉田仁・大園由美子・高橋肇・萩原健次郎・井上典子・遠藤瓔子。撮影は奥成達)
(1997.3.22gui京都例会京都丸太町赤垣屋にて。藤富保男・関富士子・吉田仁・大園由美子・高橋肇・萩原健次郎・井上典子・遠藤瓔子。撮影は奥成達) 「ね、森原さん」 ―「gui」20周年のための回顧譚― その1 奥成達 へ
「ね、森原さん」 ―「gui」20周年のための回顧譚― その1 奥成達 へ 奥成達「帽子の海」へ
奥成達「帽子の海」へ
 "gui詩gui詩"最新号もくじ
"gui詩gui詩"最新号もくじ "rain tree" バックナンバーvol.6もくじへ
"rain tree" バックナンバーvol.6もくじへ "rain tree" 表紙へ
"rain tree" 表紙へ "rain tree"もくじへ
"rain tree"もくじへ ふろくへ
ふろくへ