 詩人たち
詩人たち 最新号
最新号 BackNumber
BackNumber vol.7
vol.7 閑月忙日
閑月忙日 リンク
リンク 詩集など
詩集など  詩人たち 詩人たち 最新号 最新号 BackNumber BackNumber vol.7 vol.7 | ふろく 閑月忙日 閑月忙日 リンク リンク 詩集など 詩集など |
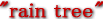 vol.7
vol.7
|
|
 <詩を読む11>長尾高弘詩集「縁起でもない」を読む(関富士子)へ
<詩を読む11>長尾高弘詩集「縁起でもない」を読む(関富士子)へ <詩>「岸辺にて」(関富士子)へ
<詩>「岸辺にて」(関富士子)へ <詩>「これなあに?2-6」(関富士子ほか)へ
<詩>「これなあに?2-6」(関富士子ほか)へ 詩人たち 詩人たち 最新号 最新号 BackNumber BackNumber vol.7 vol.7 | ふろく 閑月忙日 閑月忙日 リンク リンク 詩集など 詩集など |
<詩を読む11>長尾高弘詩集『縁起でもない』を読む
関 富士子
タイトルどおり、縁起でもない話が次々に出てくる。コーヒーをいれるたびに死んだ男のことを思い出させられるとか、会社にたどりつくまでに何度もけつまずくとか、今日死ぬという天啓があって、ぐしゃっと潰れた自分の顔まで目に浮かぶとか、都庁の前でポカンと口をあけたまま銅像にされてしまうとか、カメムシに家を占領されるとか、身体からはぐれて迷子になるとか、人間のときの記憶を持ったまま犬として生活するとか、蓑虫みたいに宙吊りで生きるとか、男らしくなるのに苦労する人生とか、電車の中で痰をひっかけられそうになるとか、朝出がけに歯が欠けるとか・・・。
同情しつつ笑いがこみあげるのを抑えられないおもしろさ。まったく日常生活とは果てしない冒険である。ひたすら眠いだけの小心なひとりの男。彼のごく平凡に始まる一日は、ちょっとしたつまずきをきっかけに奇妙な想念を呼びこんで、思わぬ方向へ転がっていく。男は右往左往、七転八倒、立ち往生。とまどい、困惑、怒りのやり場もない。自問自答をくりかえし、ときには「私は何者だろうか」と首をかしげるのである。
そこへ登場するのが男の一人息子、ナオキくん。ナオキくんのすることなすこと話すこと、率直かつ、明快、生きることの示唆に満ちて、当惑している男を人間社会のこんがらかった災難から救い出す。ナオキくんこそ「何者」だろう。
人の親として子どもを育てていると、成長していく年齢に応じて、その年代の自分のことをわれ知らずまざまざと思い出すことがある。子どものころ感じていたこと、考えていたことがすっきり整理されて見えてくるのだ。わたし自身、子どもを持つまで思いもよらなかったことだが、もう一度子ども時代をなぞりかえし、生き直しているような希有な体験をするのである。
人は一生自分が何者かわからないで生きるのだろうが、その人生にいやおうなくかかわってくる他者が、そのことについてなんらかのことを教えてくれる。もちろん我が子でなくてもよいのだが、心の内側だけをのぞきこんで途方にくれるより、身近な家族や友人などの目に映る自分を知るほうが、よほどわかりやすいことがある。
その具体的な手段として、『縁起でもない』の小話風のスタイルは成功しているように思える。作者はちゃんと存在するが終始受け身に徹している。現代の寓話とも読めるが、寓話のように完結せず、さらに日常に寄り添いながら、ひとつひとつに疑問符が付けられている。言葉の枝葉を刈り込んでいないから、詩を読んでいるような気がしない。リズムや呼吸、思考の道筋はあきらかに作者固有のものである。テクニックを弄せず、過剰な比喩をいましめ、普段用の言葉をシンプルに使い、人間というものを読者にありのままに伝えることを心がけている。現代詩の肥大しきった表現にうんざりしている人にも、詩などあまり読んだことのない人にも、共感をもって受け入れられるだろう。
(Longtail)長尾高弘『縁起でもない』の紹介/BoobyTrapで一部の詩が読めます。2200円+税1998年8月15日刊 ご注文は
書肆山田
 <雨の木の下で7>むかし、解放という言葉があった(倉田良成)雨の木のしずく(関富士子)へ
<雨の木の下で7>むかし、解放という言葉があった(倉田良成)雨の木のしずく(関富士子)へ <詩を読む12>「生きるまなざし」(田中清光詩集を読む)(関富士子)へ
<詩を読む12>「生きるまなざし」(田中清光詩集を読む)(関富士子)へ <詩>「これなあに?2-6」(関富士子ほか)へ
<詩>「これなあに?2-6」(関富士子ほか)へ 詩人たち 詩人たち 最新号 最新号 BackNumber BackNumber vol.7 vol.7 | ふろく 閑月忙日 閑月忙日 リンク リンク 詩集など 詩集など |