
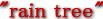 vol.12
vol.12
<詩を読む>
 詩と時間(2)−北村太郎を中心に(河津聖恵)へ
詩と時間(2)−北村太郎を中心に(河津聖恵)へ
時間とはなんだろう。そんなことを考える素地もないのに、安直に、そんな問いかけをしてしまう。そしておそらくそのように問いかけることは、生きている今このときという時間を逸脱してしまうことにしかならないのに、なにか、最近の自分にからまってくるさまざまな問題が、結局はその問いかけへ収斂してしまうような気がする。たとえば、このままでいいのかという自分の生のありかたへの疑い、あるいはリアルには親の老いや知人の思いがけない死、そしてもっと抽象的にはなぜ生きているのかとかなぜ生き物が存在するのかという誰にでもある通奏低音的な問題。それらはつきつめれば時間とはなにかという最もシンプルな問題へと結局はたどりつくにちがいない。もちろん個々の問題は具体的に対処していかなければならないが、その対処のあり方を根本的にささえるものは、時間というものへの決然とした態度─しかも諦め以上にどこか信頼や希望?をふくんで─ではないかと思うのだ。
ところで、詩というものも「時間芸術」のひとつである。しかも、短歌や俳句といった伝統詩型が、定型という空間的な安定性をあらかじめ与えられているのに対し、詩にはそれが生ずる空間は与件としては全くないといっていい。あるいはもしかしたら、それが発生する場所は空間を越えて世界そのものであり、世界は詩の一行が始まるまでは存在しないという言い方さえあながち極論にはきこえない。すると世界とはなにかという問題がでてくるが、ここでは世界は時間そのものだとしたい。たとえばアンリ・ベルクソンという哲学者は時間をそのように全的なものとして考えていた。空間はむしろわたしたちの知覚が有用性の観点で、つまりはなにかを有用なものとして利用しようとするときに出現する世界の静止であり、知性が分析し、目盛りをつけうる、知性の都合にあわせてあるものにすぎないのだが、時間はそのようなものではない。それはたえまなく現在から過去におちこんでつねに増大するために、均質とはほど遠く、分析もできないし目盛りもつけられない知
性を越えたものである。そしてそれがそうしたものであるのは、時間が私たちの意識の流れであり、あるいは意識の流れをもふくみこんだ宇宙の意識そのものものでもあるからだと。『物質と記憶』『創造的進化』といった難解な書物のどこまでを理解できたかわからないが、そうした、ある意味で正統な哲学からすれば異端な哲学者の考え方、いやむしろ直観の仕方にこそ、私はひどく魅了されてしまう。
私たち自身の意識が時間なのだとすれば、私たちは時間についてかたりきることは決してできない。哲学においてさえ結局は、いかに私たちが時間をかたることができないかを示すことができるにすぎない。そうだとしても、時間をかたりたいという衝動は、古代から存在したのだ。たとえばヘラクレイトスの時代から、あるいは万葉の時代から。また、時間をかたりたいという衝動は、根本的には時間に逆らいたいという衝動だったかもしれない。ベルクソンによれば、生命とは物理的な時間と反対の運動を行うもの(だからエネルギーの要るもの)のことであるが、哲学や文芸は時間そのものに魅せられながら時間に抗する、生命のなかの生命だといってもいいのではないか。そして「時間芸術」
のなかでも、定型や、小説にみられる舞台や背景といった空間性、あるいは音による素材性からもっともとおいところにある詩というものは、もっとも時間に近くありうるジャンルであると考えてもいいのではないか。日常の言葉が、世界を空間的に分割する「観念」であるとすれば、詩はそれを時間の流れへ戻すのであると。もちろんそうすると一般的に無時間的なものと感じられるポエジーというものも、実は本来は時間的なものということになるだろう。
たとえば戦後世代の詩は「戦後詩」という名を冠せられている。「戦後俳句」や「戦後音楽」とはあまりいわないのに、詩はそのように時間的なメルクマールによって形容される。「戦後文学」とはいうけれど、その場合どうしても力点は「戦後」にあるように思える。だが「戦後詩」というときは、力点はやはり「詩」にあるようにきこえる。うまくいえないが、「戦後詩」という呼び名が内包するものは、「詩」が「戦後」にのみこまれ無化されてゆく、という方向ではなく、むしろ「戦後」という時間が「詩」という時間のなかへ、むしろその時間をより本質的なものにするようにして濾過されてきたという過程だといっては的外れだろうか。もちろんそんな言い方をすれば、「戦後詩」が結局は「非歴史」的なものだということになってしまうかもしれない。しかし歴史とはいったいなんだろう。
たとえば今このときは歴史だろうか。そういう感じはあまりしない。歴史という言葉のニュアンスには戦争というものの存在がどうしても関わってくると思う。戦争がないところに、あるいは戦争の実質的な影響がないところに歴史はあるのだろうか。たとえば「〈歴史〉は、たんに個体化し、現働化した身体(事物)の状態から成り立つのではなく、言葉、記号、意味がもたらすものと身体(事物)の状態との調和も融合もしない複雑な結合から生じている」(前田英樹『映画=イマージュの秘蹟』)といった考え方に私はうなずく。けれどここでいわれている「事物」と「言葉」の「調和も融合もしない複雑な結合」は、なぜ「調和も融合もしない」のか。それは、「言葉」は「出来事」や「事物」をかたりたくて生じるが、「言葉」にすぎないために決してかたりきることはできないからだ。そして戦争とは、最もかたらなくてはいけないと急かされながら(それは人事ではあるのだから)、けれどけっしてかたることができない「出来事」(それはもしかしたら運命かもしれないから)ではないだろうか。だから、歴史の核にはつねに戦争があり、言説になりきれない傷として記憶されつづけるのだろう。そのような考え方からすれば、戦後の過程とは、実は歴史の不在の進行の謂となる。そこで歴史はメディアによって言説化され、言葉と「調和と融合もして」あらわれてきてしまう。あるいは歴史からは時間が個人へ脱落してくる、といってもいいのではないか。けれどそれが歴史から濾過されてきたばかりの時間であれば、まだ生や死についてリアルな陰翳をおびているにちがいない。「戦後詩」において、もしかたられているのが時間であるとするなら、そこではまだ時間がそうした陰翳を帯びていたからだろう。もちろん一方で、身近なリアルな時間の方ではなく、失われた歴史の空の方をあえて見上げつづけるという、歴史の「遺言執行人」として生きつづけることも可能だった。しかし他方、歴史から脱落してくる時間のリアリティを凝視しつづける道もあった。あるいはむしろ後者こそ、戦後をより深く現在へとむすびつける方途だったのではないか。
「戦後詩」において時間のリアリティを凝視しつづけた詩人、といえば、誰しも思い浮かべるのは、北村太郎ではないだろうか。今その全仕事をあらためて読むと、やはりその高すぎる技量と深すぎる素養に、やはりこんな詩人は二度と出ないだろうと思うしかないが、その稀有な仕事を稀有なものとする最も大きな要因は、やはり時間へのその特異な関わり方であると思う。どの作品を読んでも、言葉を書いてゆくそのただなかにおいて時間そのもののリアリティを作者自身が感じていることがわかる。時間についての深い洞察が明言されている場合も多いが、そうでない場合にも、書いてゆくという時間あるいは生きているという時間のリアリティが、作者には苦いものだったかもしれないが読むこちらにとっては、まるでエロスのように迫ってくる。つまり、北村太郎の詩は多くの詩のように空間的には読めない。主題はなんなのか、とか、作者の位置はどこにあるのか、とか、ベルクソンのいうところの空間的=功利的な読みができない。もちろん空間的な配置に作者は精緻な意図をはたらかせている。けれどそれはまた、時間のリアリティをより効果的に滲みださせるためなのだ。
私が初めて北村太郎の詩に触れたのは、あの「朝の鏡」でだった。どこかに引用されていたものを読んだのだが、これを読む誰しもそうだろうが、冒頭からいきなり自分の知覚に深い亀裂が走るのを感じた。その有名な三行を引用してみる。
朝の水が一滴、ほそい剃刀の
刃のうえに光って、落ちる──それが
一生というものか。不思議だ。
こう引用しても「不思議だ」といいたいのは、やはりこちらの方である気がする。こんな短い単純な三行を読む間に、なぜ目の前にどこともつかない薄暗い朝の洗面所が脳裏に浮かび、そしてまたいきなり間近に剃刀が浮かび水滴がかすかに光ってはらっと落ちるのか、わからない。だが謎は謎のままに、今あらためてこの三行を時間との関わりで考えてみると、やはり北村の特異な時間感覚が浮かび上がってくる。こ
こでは、「一生」という時間が一滴の「朝の水」が「刃のうえに光って、落ちる」その物質的な運動によってたとえられている。それは、一見なにごともないたとえのように思える。「一生」を「一滴の水」にたとえるのは、抽象的なものを具体的なものにたとえるという比喩の一般的な遠近法の範囲に収まりえるだろう。けれどまた、この「水」は目の前の刃の上を、ちらっと光りながら動いて消えた、現実の時間そ
のものなのだ。「一生」というものはたしかに不思議なものかもしれない。だがそれは今目の前にはない。むしろ一つの観念としてはわたしたちの脳裏に安定しているものだ。それに対し、眼前を光ってよぎった水滴こそは、リアルな時間を創りだし、時間の不思議さを垣間みせる。つまり「不思議だ」といわれているものは、「一生」の方ではなく、実は「水滴」の方ではないか。むしろ眼前の時間の不思議さをたとえ
るために、「一生」というもうひとつの時間の「観念」が呼び起こされたのではないか。もしそうだとするとここには比喩の逆遠近法があると考えられる。リアルな時間の不思議さを、抽象的な時間にたとえ安定させる、という構造が。いや、安定ではない。そのように逆転的な比喩によっては、読む者の遠近法も逆になり、「比喩」の方向感覚は混乱してしまう。そしてリアルな時間は抽象的な時間にたとえられきる
ことなどなく(それは過剰すぎるから)、それらは「刃のうえ」のようなきわどい感覚の上で一瞬つりあうだけである。「刃のうえに光って、落ちる──それが一生というものか」──そこでわたしたちは「あっ」と思うだけである。
そしてたとえばそのように朝の水が刃が伝い落ちる「眼前の時間」は、あるとき「持続性」と呼ばれている。
僕はもし人間が作り出した言葉のうちで最も下らない言葉をあげろ、といわれたら、躊躇なく時間をあげたい。持続性という言葉のうちには、当然時間という観念が含まれているにちがいないと人は考えるかも知れないが、僕はむしろ、時間と反抗しあっているものを感じ、そしてそういうものだと信じている。精神、ある個人のうちにある 自意識、その持続性と時間とはいったいどんな関係があるのだろうか。おそらく全く別のものだ。持続性と主体とは決して分離して考えられるものではないが時間と主 体性は実にはっきりと異ったものとして考えうるのだ。いわば主体の外側に、まるで関係なく時間とい うものがある。まるで関係がないというのは、それが何であって構わぬということだ。あるいはそれは神であるかも知れない。そして奇妙なことに、それは空間であってもすこしもおかしくないのだ。 (「空白はあったか」『孤独への誘い』)
ここで「持続性」といわれているものは「時間と反抗しあっているもの」「ある個人のうちにある自意識」であり、他方「時間」とは「主体の外側」にあり、「主体」とは無関係に「神」や「空間」でもありうるものである。この「持続性」対「時間」という対立は、おそらくベルクソンからのものだ。パスカルにも通暁し、また小林秀雄に関して否定的ながら言及している北村太郎は、ベルクソンをも読みこなしていた
にちがいない。先に述べたようにベルクソンもまた「時間」を「意識の流れ」としてとらえ、それを北村同様「持続」とも呼んでいる。それに対して、時計をみて「十分たったな」というような、計量化あるいは空間化された「時間」を対立させている。後者は科学的あるいは分析的に世界を解釈しようとするときに使われる「有用」な「時間」であり、北村太郎がここで「時間」とシンプルに呼ぶものだ。そしてベル
クソンはそうした「時間」の「有用性」こそがわたしたちの「世界」の流れを止めて切り刻むものであるといい、北村太郎も「いかに多くの人間がこの有害な毒のために無数の誤謬のうちに己れの思想を歪曲して死んでいったか! いかに時間という観念が詭弁を正当化するに与って力あったか! 僕はその害毒の果てるところを知らない。そして実に奇怪至極なことに、人間が主体的に持続性を有しているにも拘らず、
自己を欺いたり、他人の眼を眩ますときに限って、時間をまるで最強の味方のように引っぱり出してくるのだ」(同上)と同様に怒りをあらわにしているのだ。たとえば、「人生」という時間の観念もそのような「時間」のひとつではないか。「戦後」や「近代」といった「時間」もまた。もちろん、一切そのように名付けてはいけないということではない。北村太郎もまた散文ではそのような言葉を使って語ってはい
るのだから。けれど問題は、「持続性」とは無関係に「時間」を「まるで最強の味方のように引っぱり出してくる」ことなのだ。つまり「戦後」だ「近代」だのと、よく切れる「時間観念」で「持続性」を切り刻んでよしとし、我が身の「持続」を振り返らない「歪曲」と「誤謬」に気づかないことだ。「朝の水」を「一生」にたとえるという先の比喩の逆転も、「持続性」を「時間」に故意にたとえることによって、
むしろたとえきれないという緊張した印象を与える効果がもくろまれていると思う。「朝の水」のリアルな「持続性」は「一生」という「時間」の「刃」にとらえきれず、つまりわたしたちの「時間観念」にとらえられず、はらっと光って落ちるのである。
しかし、「持続」や「持続性」という硬質な言葉を詩のなかで使えば、それもまた「観念」になってしまう危険がある。だからなのだろう、北村太郎の詩作品では、「持続性」も、「空間」あるいは「神」である「時間」(「主体の外側」にある「時間」)もひとしく「時間」「時」という同じ言葉で表されている。そして後者の意味で使われている場合は、「計量化できる時間」という人間の配下にある「空間」的
な時間である場合よりは、「神」や「必然」といった「運命」的な時間である場合の方がはるかに多い。いやほとんどそうであろう。そしてそれは、批評ではない詩というものが自然とかけたバイアスだといっていいかもしれない。たとえば、「不滅の/時はおそろしくない。コンクリート・ミキサーのように、突然/わきを通りぬけてゆくが、ただ/それだけのことである」(「ある墓碑銘」『北村太郎詩集』)「静か
な寝息の猫をながめて時を消すか/いやちがうぞ/時がわたくしを消す」(「memento mori」『眠りの祈り』)「ときどきわたくしの耳に時間のおそろしいとどろきが聞こえてきて/目のまえの会社の内部が急速に遠ざかり気づくとわたくしはデスクに坐っている/そんな経験を何十回していまだわたくしは労働して倦まない/むかしギリシア神話にこったのはきっと時間がおそろしかったのだな」(「十六行と六十行」『眠りの祈り』)といった「時間」あるいは「時」は、そうした「運命」的な時間である。また、そうした「運命」的な時間は、先述したように詩というものが自然にかけるバイアスの方向にあるものであり、(「詩は永遠である」といったいいかたをわたしたちは自然としてしまうものだ)もちろんこれだけでは北村太郎の特異な「時間」感覚をいいきることはできない。「朝の鏡」で見たように、北村太郎の魅惑の本質は、「持続性」とみずからよんだ「意識の流れ」としての「時間」の方にあるだろう。たとえば、
ミルクを温めるのはむずかしい
青いガスの火にかけて
ほんのすこしのあいだ新聞を読んだり
考えごとをしていたりすると
たちまち吹きこぼれてしまう
そのときのぼくの狼狽と舌打ちには
いつも
「時間を見たぞ」
「時間に見られてしまったな」
という感覚がまざっている
(「冬の時計」『ピアノ線の夢』)
この「時間を見たぞ」「時間に見られてしまったな」というところの「時間」は、誰しも経験したことがある、沸騰したミルクが鍋のなかで次第に膨れてきて吹きこぼれてしまうまでの時間、正確にはそれを見ている「ぼく」の同様に膨らんでゆく「意識の流れ」そのものである。このミルクの沸騰するまでの「時間」という「持続性」は、やはりベルクソンを思い起こさせる。たとえば次のようなくだり。
一杯の砂糖水をこしらえようとする場合、とにもかくにも砂糖が溶けるのを待たねばならない。この小さ な事実の教えるところは大きい。けだし、私が待たねばならぬ時間はもはやあの数学的な、すなわち物質界 の全歴史がかりに空間内に一挙にくり拡げられたばあいにもやはりぴったりそれに当てがわれるような時間 ではない。それは私の待ちどおしさに、すなわち私に固有な、勝手に伸ばしも縮めもできない持続の一齣に合致する。これはもはや考えられたものではない、生きられたものである。もはや関係ではなく、絶対にか かわるものだ。それはこういうことに他ならぬのではないか。一杯の水、砂糖、砂糖が水に溶ける過程はおそらく抽象物であろう。それらは私の感覚と知性がある全体のなかに切りとったもので、そしてこの全体は たぶん意識なみの進展のしかたをするものなのであろう。
(『創造的進化』真方敬道訳・岩波文庫版)
この「砂糖が水に溶ける過程」と北村の「ミルク」の沸騰過程は、「持続」あるいは「持続性」の謂である。前者は「待ちどおしさ」に、後者は「狼狽」に関わるという違いはあるのだが、「もはや考えられたものではな」く、「生きられたものである」という点で深く一致している。ところで「もはや関係ではなく、絶対にかかわるもの」というベルクソンの時間観は、まぎれもなく神的な傾向をもつものである。「砂糖が水に溶ける過程」は確かに私の「意識の流れ」であり、「私に固有な、勝手に伸ばしも縮めもできない持続の一齣」であるのだが、それはむしろ「私の感覚と知性がある全体のなかに切りとったもの」つまり、私を越えた「全体」(=神的なもの)の「抽象物」だというのである。あるいはこの「砂糖が水に溶ける過程」は、「意識なみの進展」をしている、私をも含みながら私を越えて流れている大きな神的な時間の一部なのであり、私はその「抽象物」として今白濁してゆく溶けた砂糖水の動きをみているのである。この「抽象物」という言葉には、「全体」を結局は知覚できないという否定的な意味と、それこそはわずかながらも「全体」を予感し、「全体」の一部を知覚するとば口となるものだという、肯定的な意味がこめられているだろう。そして「抽象物」とはまた「知覚されたもの」であり、「知覚」そのものだといってもいいだろう。そうしたベルクソンの観点からすると、北村の「ミルクの沸騰過程」の知覚もまた、そうした二重のものであるとわかる。まず、「時間を見たぞ」はミルクの沸騰過程という「持続性」を知覚したということである。これは沸騰過程という時間を「ぼく」の知覚が全体から抽象したということである。だが「時間に見られてしまったぞ」では、「見る」ことが沸騰過程で「狼狽」とともに弛緩してゆき、泡立つミルクのうごめきのなかから「全体」(=神的なもの)の方がこちらを見始めたのである。
なにかを「見る」ことがなにかが背後に秘めた「全体」的なものに「見られる」ことになること──けれどそれは「見ること」を「全体」に奪われることではない。北村太郎の世界にも「ここ」から「全体」への「出口」などない。そこではただ「私」と「全体」が知覚においてせめぎあうだけだ。だが「私」と「全体」がせめぎあえる知覚そのものを、言葉という非知覚的なものにおいて表現しうることは、しかも時間という本質的なものを通じて実現することは、もしかしたら詩という「時間芸術」が、実は潜在的にたえず欲望していることではないだろうか。
詩について書こうとするとき、あるいは詩を書こうとするとき、多くは時間というものは意識されないと思う。むしろあらかじめ詩という「空白」あるいは「空間」があり、そこに言葉が発生するように思う。けれど世界は時間であり、詩が実はもっとも時間的なジャンルであるということに思い至れば、どんな作品からもまざまざとその本来的な欲望、時間をかたりたいという欲望がみえてくるにちがいない。そして今回とりあげた北村太郎の作品では、そうした欲望はあまりにも意識化され、そのためあまりにも静かな狂気のようなものになっている。紙幅は尽きたが、次回もまた北村を中心に、「詩と時間」というテーマで考えられたらと思う。
(「pfui!」16号1999.7.20)
 <詩を読む>駅名のような自然(河津聖恵)
<詩を読む>駅名のような自然(河津聖恵)
 (縦組み縦スクロール表示1)<詩>駿河昌樹の詩へ
(縦組み縦スクロール表示1)<詩>駿河昌樹の詩へ (縦組み縦スクロール表示2)へ
(縦組み縦スクロール表示2)へ
詩と時間(2)−北村太郎を中心に(河津聖恵)へ
<詩を読む>駅名のような自然(河津聖恵)
(縦組み縦スクロール表示1)<詩>駿河昌樹の詩へ
(縦組み縦スクロール表示2)へ
もくじ
詩人たち
最新号
BackNumber
vol.12
閑月忙日
リンク
詩集など