
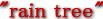 vol.15
vol.15<雨の木の下で>
7 これからは自分の場所で 2000.3.16  金井雄二
金井雄二
前回のエッセイは、今の自分の仕事に対する気持ちを正直に書いてみた。2回目のエッセイと少しかさなるところがあったかもしれないが、この気持ちはどうしても言っておかなければならないことだとおもい、書かずにはいられなかった。というわけで「雨の木の下で」のんびりしている間に、そろそろ外も晴れてきたようだ。今回でこの場所をおいとますることになった。
関富士子さんの「rain tree」にお招きにあずかり、ずいぶんゆっくり過ごしてしまった。好き勝手なことを書いて送れば載せてくれるので、つい好意に甘えてしまったのだ。短かったような長かったような、不思議な時間だった。でも、ぼくなりになんとか書いてきたので、それなりの充実感はある。
文章も詩もその出来が大切なわけだが、良いものを書くためにはやはりそれなりの量を読み、そして書かなければならないと思う。おおいに駄作を書こう! と声を大にして言いたい。どこのどいつもつまらない詩ばかり書いていて、世の中駄作で溢れかえっている。しかしその中に、ほんのひとつふたつ、どこかに面白い詩があるはずだ。書き手は自分のベストをいつも尽くせばそれでいい。山と積まれた駄作の中に、自分の信じることのできる作品がひとつあれば、それでいいじゃないか。もし、その詩さえ駄作であると言われても、それはそれでいいのだ。自分が信じれるものが一篇でも書ければ。
さて、当初の「rain tree」の予定では、前期、後期と分けてぼくの拾遺詩集をつくり、「アメリカ現代詩101人集」の詩をできるかぎり載せて紹介しようとした。しかし、さすがに諸般の事情で思うがままにはならなかった。
これからは自分の場所「独合点」で書くことにしようと思う。「独合点」はホームページ版と冊子体とふたつ出していく予定だ。よろしかったら、お付き合いください。
「rain tree」に書かせてもらって、なんとなく感じたことを今日は書いてみた。こんなことを感じることができたのも、つまるところ関さんのおかげだ。
心から感謝の意を表して、ぼくの「rain tree」を終了したい。
関富士子さんどうもありがとう。そして、いろいろご意見等下さった方々、どうもありがとう。
2000年3月 金井雄二
(金井雄二さんのホームぺージ 「独合点」ができました。今すぐジャンプしてご覧くださいね。金井さん、3ヶ月間、ほんとうにありがとう。金井さんのがんばりにいつも励まされました。関)
「独合点」ができました。今すぐジャンプしてご覧くださいね。金井さん、3ヶ月間、ほんとうにありがとう。金井さんのがんばりにいつも励まされました。関)
6 司書と詩 2000.3.1 金井雄二
ぼくは図書館で働いているが、「司書」という仕事と「詩を書く」ということはどうしても結びつきがないように思っていた。もちろん図書館では本を扱っていて、ぼくらは詩なんか書いていて、共通項はいくらでもあるじゃないかと思われそうだが、実際働いていると、図書館と詩は結びつかなかった。
それが、である。去年いろいろな人の話を聞く機会がありひとつの経験をしてからは、少しばかり意識が変わってきた。
ぼくが図書館でかかわっているのは児童奉仕という分野で、つまりお子様たちに本を手渡すことが仕事なのだ。それにはさまざまな仕事があって、本の受け入れや棚の整理などもさることながら、お子様に本を読んであげる、というのがけっこう重要な仕事だ。図書館というところは結局は物語のおもしろみを伝えて行く、という使命があり、まずそうやって本と親しむことができれば、あとはその応用なのだ。図書館にくれば本がある、本というものは、知識の源なのだ、という考えかたができれば、物事を書物で調べるという発想はすぐに出てくる。
さて、本を読んであげるなんて簡単じゃないか、と思っている人がいたら、一回、子どもの前で簡単な絵本でいいから読んでもらいたいものだ。これがどうして、難しい。持ち方から始まってページの開き方、自分の身体の位置、声の大きさ、どれひとつとってもなかなか完璧にはできないものだ。絵本や紙芝居ならまだしも、究極的なものにストーリーテリングがある。これはすばなしと呼ばれるもので、テキストを見ることはできないし、自分が物語りの語り部となるのだ。
ぼくは、ストーリーテリングだけは出来ない、と確信に近いようなものがあった。しかし去年、はからずも覚えなければならない事態になってしまった。頑張って、完璧に一篇覚えたはずなのだが、いざ本番、たった一言間違えたために、物語の後半、一気に崩れてしまった。
言葉の神秘というか、本当に複雑さを感じたのはそのときだったと思う。言葉がどこからでてきて、どのように声になっていくのか、ぼくは本当に考えた。結論なんてでないのだが、ひとつだけわかったことがある。
簡単だが、それは「伝える」という意思だ。言葉にそれがないと声にならない。ぼくが必死に一篇覚えて語ったものは、「間違わずにやろう」と思っていて、言葉の上っ面をなでているだけだった。伝えようとは思っていなかった。相手に伝えようという気持ちがあれば、ぼくは何もあせる必要がなかったのだ。
子どもたちにお話を伝えよう。真底、そのように思って話せば、言葉はきっとでてくる。
ぼくはそのことに気づいたのだ。
じゃ、詩はどうなのだろう。言葉を扱うかぎり、ほとんどそれは同じことではないのか。ぼくは仕事のなかでそれを教わった。自分にとってこれはすごい収穫だった。
図書館で働くということは、人に本を手渡して行くということなのだ。つまりぼくは子どもたちに物語を伝えて行くことを使命にしなければならない。詩だって伝えることが究極の使命なのだ。図書館と詩は意外なところで手を結んだような気がした。
5 2000年を迎えて 2000.2.17  金井雄二
金井雄二
2000年だの、ミレニアムだの言って今年は騒いでいるようだが、なんだかわびしいと感じているのはぼくだけであろうか?
12月が過ぎれば1月が来るのはあたりまえであって何の不思議もないことだ。1999年が終れば2000年がくるのに決っている。何も大騒ぎすることはない。もちろん区切りがよかったり、千年に一度きりだと言えば、それはそれで記念すべき年ではあるのだろうが、何も皆が皆、そろって騒ぎたてることもない。いろんなところで聞こえてくるミレニアムの声には、なんだか商魂のたくましさとそれにのせられている人々のノーテンキさが目について、ぼくにはやるせない。
以前、職場で一緒に働いている嘱託の方と話をしていて、その人はしみじみとした顔をして「この年になって、毎日毎日がとっても大切になってきたよ」と言っていた。この方は六十を過ぎたばかりで、まだまだ現役だ。毎日が大切になってきたということは、それ以前はあまり考えもしないでノホホンと生きてきたということなのだろうか? そこらへんをやんわりと尋ねてみると、すべてが楽しく過ごせればそれで良かった、他は何も考えなかった、ということらしい。それが、今は少し違う。つまり、時間の経過がいとおしくてならないという。一時間、一分、一秒を大切にしたいという。そして、今のうち何かをしておきたいんだが、と言っている。今この人には、ミレニアムなんて関係ないのだ。
今ぼくの生活はというと、とてもめまぐるしい。ちょっと疲れている。しかし、それはそれで、毎日を大切に生きているのかもしれない。2000年だからミレニアムだから何かをしよう、なんてことは具の骨頂だ。世間の風潮にながされず、一秒を大切にするという生き方がいい。ぼくも、あらためて毎日を大切に生きるということに終始したい。
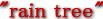 no.15 2000.2.25 掲載
no.15 2000.2.25 掲載
4 スポーツについて 1999.1.20 金井 雄二
小学生の頃、「相撲」というスポーツが退屈でしようがなかった。僕の祖父が、これがまた「相撲」の大ファンで、相撲の時期になると我が家に居候し、テレビのチャンネルを独占するのが常だったのだ。小学生だった僕は相撲を見るのが苦痛だった。まず、仕切りが長く、その割りには勝負があっけなくついてしまうこともあり、第一スマートな格闘技でなかったからなのだ。しかし僕は、真剣に膝を乗り出すように見ている祖父の顔を眺めながら、思ったものだ。「相撲」というスポーツもどこかに面白いところがあるのに違いない、と。そこで、僕は相撲の楽しさを探すことにした。
まずは好きな力士を何名か作ること。これはシコナがおもしろかったり、顔が好みだったり、小兵力士だったりしたところから選び出す。そして、決り技をおぼえること。これは圧倒的に寄りきりが多いのだが、ときにはカワズガケとか、コマタスクイとか、ウチムソウとかおかしな技があるのでおもしろい。自分の好きな力士が、どんな有利なカイナの組み方をすると勝てるとか、でかい腹をどんなふうに利用して相撲を取るのかなどと考えるのである。そんなふうに自分なりの楽しみかたを積極的に見つけて行くうちに、あんなに退屈だった相撲が楽しくなりだした。嫌でたまらなかった仕切りさえも、気力が満ちてくるまでの顔の表情をとらえるのが楽しくなった。そして、その間に力士同士がどのような組み手になるのか、などということを専門家のように考えてみるまでにもなった。
相撲の話から別なスポーツに移る。最近ではあまり聞くことはなくなったが、一時期、卓球が「暗くて、ダサイ」スポーツなどと言われていたのを耳にしたことがある。誰がそんなことを言ったのかよくわからないが、まったくそれはおおきな間違いである。
去年の暮れ、たまたまテレビをつけたら「全日本卓球選手権」の「男子シングルス決勝」が始まるところであった。別に見ようとしたわけでもなかったのだが、おもわず見入ってしまった。息もつかせぬ熱戦に手に汗を握ったのだ。(なんと言い古された言葉!)。かたや「全日本卓球選手権」3連覇を狙う偉関晴光選手と毎回決勝で涙をのんで、4回めの決勝で悲願の初優勝を狙っている渋谷浩選手との戦い。
5セットマッチで3セット先取した方が優勝だ。結果は2−1と先取されて後がない渋谷選手が、大逆転で偉関選手を破り涙の優勝だった。何が面白かったのかというと、そのスピーディーな動きとリズムがまずひとつ。サーブからはじまって、カット、スマッシュと人間技とは思えないくらいの動きだった。そして、もうひとつは両選手の心理だ。第1セットの後半、あと2ポイントでこのセットをとれるという偉関選手。しかし、偉関選手はここからが少しおかしくなってしまった。ほんのちょっとした心の隙であろうか、なんと7ポイント連続で、渋谷選手にポイントを奪われ、第1セットを落としたのである。実力では偉関選手の方が上なのであろうか、2、3セットは偉関選手がとったが、その後はまたまたリズムをくずし、逆転負けをくらった。
渋谷選手は終始がまんの卓球だった。「がまんの卓球」という言葉があるかどうかはしらないが、相手のスマッシュを何度も受け止め、(これが見事!)偉関選手のミスを誘い出しているかのようだった。
卓球の面白みはこんなところにあったのか、と思われるほど、僕には白熱した試合ぶりだったように思えた。試合後の渋谷選手のインタビューで「これでやっと父に追いつけた」(というような内容だったと思う。渋谷選手のお父さんも全日本選手権の優勝者)と言ったさわやかさがとても印象的だった。
相撲、卓球以外でも、スポーツを見るのはすごく好きだ。僕は今、息子と一緒に剣道をやっているが、もう、辛いのでやめることにする。僕はスポーツをやるとそこから抜けられなくなってしまうので、困るのだ。つまり、スポーツは奥が深い、ということ。どんなスポーツも奥が深くおもしろい。だからまじめにやればやるほど、精神的にも辛い。やっぱり見ているだけの方がいい。自分で体を動かすのは、自転車か、ウォーキングに徹し、それも楽しみだけのためにやりたいと思っている。
今のスポーツをめぐる報道は非常に差があるように思えてならない。わたしはもっといろいろなスポーツを見て楽しみたい。その素晴らしさをこの目で見たい。できれば、ライブがいいけどね。なかなかそうもいかないし。テレビで映し出してくれるとありがたいなあと常々思っているのだ。野球と卓球の放映時間を考えてみればいい。感動の質も、やっている人たちの真剣さの質もたいして変わりはないのに、どうしたものだろう、この格差。不公平きわまりない。高校野球もすばらしいが、何も予選からテレビでやることもない。それより、高校のハンドボール(これもおもしろいよ)や、弓道なんてものもみたい、と思う。確かに視聴率は低いかもしれないけど、甲子園を全試合放送するなら、同じ高校生のやっている他のスポーツにも光をあててやってもいいと思う。新聞の報道も同じだ。
少しグチっぽくなってしまった。そこで、結論めいてはいるのだが、なんでも楽しさを発見することがわれわれには必要だ。スポーツを今日はとりあげたが、存続するもののすべては何かしらの意義があるのだから、それはそれで、どこかに面白さが存在するのだ。長く続いているものならなおさらなのだ。「古典を読もう」とはよく聞かれる言葉だが、長く続いているからには、人の心を打つなにものかがある。そう、それを見つけ出そう!
もちろん、クラーイ、つまらない、と言われている「詩」も面白いところはいくらもあるのです。みなさん、「いい詩」を見つけましょう。そして「いい詩」があったら教えてください。それではまた。
3 詩のはじまりについて 高校時代を中心に 1999.1.13 金井 雄二
エッセイのテーマを何にしようと考えながら、やはり詩のことを書こうと思った。なぜそう思ったのかはわからないが、詩のことを書かなければ、自分が成立しないようにも思ったからである。
わたしは自分が詩を書く人間だとは思っていなかった。むしろ正反対で、技術者になろうとしていたのだ。中学から高校にはいるときは真剣にそう考えて、工業高校に進学した。今振り返ってみるとあさはかだったとしかいいようがない。工業高校イコール技術者という訳であろうはずがなく、そのギャップに苦しんだ。わたしと工業高校との相性はよくなかったのである。それは散々だった。理数系中心の勉強もさることながら、回りの人間とウマが合わなかった。つまり、私立にいけなかった者、公立の普通科に行けなかった者が集まる場所、と言ったら言い過ぎかもしれないが、リーゼントでタバコをスパスパの環境はわたしにはあまりいい場所ではなかった。もちろん普通の高校生もいるのだが、どういうわけだか毎日バイクとオンナの話しかせず、わたしは仲間に入れなかった。そんな話はしたくなかったのだ。たぶんわたしは変な奴だったはずだ。
そんな高校生活のある一日、それは突然やって来たのだったが、「もし明日死んだら、ぼくは今まで何をしてきたと言えるだろう」と考えてしまったのだ。ぼくはその日から、日記を書き始めた。日記は記録であり告白であった。自分はまず、その日1日何をしたか、どんなことを考えたかを記した。嘘は書かず、真実だけを思い返した。好きな歌の歌詞や、気にいった人の言葉なんかも書き写したりした。小説の一節をわけもわからず書いたりした。そんな中に、自分は自分だけの言葉を書いてみたくなった。言葉は皆で共有しているものであるが、そうではない、ボクだけの言葉がどこかにあるような気がした。たぶんわたしの詩はそこから出てきたと思う。
今現在、同世代の伊藤芳博、岩木誠一郎らと同人雑誌「59」(「ゴクウ」と読みます)をやっている。第2号で音楽と詩をテーマにエッセイを書いたのだけれど、生まれ育った環境は違うのに、やっぱりどこかに共通なものを感じることしきりだった。わたしたちは音楽の洪水の中で、耳から詩を読んでいたようにも思う。わたしはそんな中で、自然に音楽に興味を持ち、というより、ギターでジャンジャカ弾いて歌うのが好きで、冴えないフォーク・シンガーになりさがっていたようだった。
それというのも、(また高校時代の話にもどるのだが)高校時代の音楽の先生が非常に面白い人で、音楽の授業にレコードを聞かせてくれたのだ。それもクラシックではなく、井上陽水の「氷の世界」だった。このリズムはいいの、歌詞が素晴らしいのと解説したり、これはギターで弾けるとかいって、熱心に話してくれたのだった。その先生はつまり、「ギターのコード(和音)を覚えて、弦を鳴らせれば、君達だって、歌がつくれんだぞ」とリーゼント頭のヤニ臭い高校生に本気で言っていたように記憶している。だからといってそれがすべての引き金ではないだろうが、今になって、そのことが自分で創作するということに目覚めた第1歩なのではなかったか、と思うのだ。感化されやすいわたしは多分「氷の世界」に参り、陽水にはまりこみ、拓郎を拝むという、フォーク・ソングオタクになっていった。
自分で歌がつくれる! 確かにこんなに魅力的な世界はなかった。ヘタクソなギターで、スリーコードだけで、信じられないくらいヘタクソな歌をつくった。で恥ずかしげもなく、それをオリジナルと称して、大学生の頃は人前で歌っていた。さすがに今そんなことをしようとは思わないが、当時わたしは真剣だった。もちろん、歌詞は自分で書く。どうすれば、カッコよくなるか、どこでどんなふうに繰り返すか、人が聞いてくれるか、ということを考えながら。
歌と歌詞はわたしを救ってくれたし、自分を外に表すことによって、自分のアイディンティテイを保ってきたように思う。今死にたくはないが、もし今死んでも悔いは残らないと本気で思っていた。すべて日記が創作ノートのような形をとっていたと思う。
その後の音楽とわたしとの係わり合いは「59」第2号のエッセイに書いた。(ご覧になりたいかたは、ご連絡を。)わたしの中の「詩」はそんな生活が母体となって、メロディが離れて歌詞が生き残り、詩だけを書いていこうと考えたのかもしれない。ただ、自分がいつ本当に現代詩を意識したかがあまりよくつかめない。フォーク・ソングの中で、山之口獏や、谷川俊太郎や、吉野弘を知ったことは確かで、そこから感化されたのかもしれないけど。でもそれはいつのことでもいい。働くようになって、わたしは真剣に詩を読み始めた。そして、それが、今のわたしに続いている。もちろん日記も続いている。内容はずいぶんと変わったが、最初に書いたように「記録」するということは怠っていない。
高校時代、技術者になろうなんて希望はどこへやら、フォーク・ソングを片っ端から聞き、明日死んでもいいように今何をすべきか考え、三島由紀夫の文庫本を片手にもって、悩んでいた姿は今自分で思い返すだけでもコッケイだ。そんなことをしていたからか、女の子に持てるわけもなく、マスタベーションの毎日。軟式野球部で汗かいて、本を読んでギターを弾くという、なんとも変な子供だったと思う。
わたしの高校生活は暗いものだったけど、自分にとって生きていくとはどんなことか、ということを真剣に考えた時期であった。その「考えている毎日」は今詩を書いている原点だとも思うし、その期間がなければ、わたしは詩を書かなかったような気がするのだ、暗いわたしの青春もまんざらでもなかったのだな、と振り返って思う。
そうやって自分のことを書けるようになったわたしは、たぶん年をとったのだろう。いいや、まだまだ若いもんにゃ、まけんぞ! なんて。ああ、自分のことばかりの自意識過剰な文章になってしまった。ごめんなさい!
さあ、これから詩を書くぞ!
2 詩を書くことの、あるひとつの意義として 2000.1.6 金井雄二
1999年もいろいろな事があった。なんといっても東海村の臨界事故は現代のずさんさを目の当たりにしたような感じだ。おこるはずのないとされていた事故だが、死者まで出すようなことになってしまった。原子力発電は本当に必要なのか? という問いをもう一度なげかけたい。しかし、原発はもう後に引けない状態になってしまっている。安全に稼動するには、ということを国はもっと真剣に、(もちろんわれわれも)常に考えていかねばならないだろう。
しかし、今回は原発のことを書こうと思ったのではない。去年の痛ましい出来事の中でも、悲惨を極めていたのが、幼児虐待とそれに付随する事件だろう。過去にもあったはずなのだが、今年はそれがとくに目立った。大人が子どもに対してひどい仕打ちをする、そういうことを想像しただけでも、ぼくは耐え切れない気持ちになる。ブコウスキーの短編小説に幼児をレイプするものがあったが、読んでいて気持ち悪くなった。ああいうのはいやだ! それからトリイ・ヘイデンの「シーラという子」を筆頭に続く、一連のノンフィクションはどうにもやりきれない。大人はむかし子どもだったのに、それをすっかり忘れている。
1989年子どもの権利条約が成立し、1990年9月に発効した。これは、端的に言うなら、子どもたちにもちゃんとした人権があり、それを大人が勝手に犯してはならないということと、子ども自身も発言することができるんだよ、ということだ。
あまりに当たり前すぎることのようだが、今のご時世にはこれがわかっていない親、大人がたくさんいる。だから痛ましい事件がおこるのだ。ここでの子どもは一応18歳未満のことを言っているわけだが、自分より地位的、体力的に弱い立場にいる者にたいして、傲慢に振る舞いつづけ、その弱者の立場をいいことに、心の中を土足で踏みにじっている人がいるのである。子どものときにつけられた、精神的な傷は絶対に消えないということをもっと考えるべきだ。それに、大人になりきれない精神的に未熟な大人。そんな人間が勝手に親になってしまうから、自分の子どもを放棄してしまう結果になるのだ。原因はそれだけじゃないだろうけど、それだけでも十分悲しい状況だ。
わたしは公立図書館に勤めている。そして、今児童のサービスを担当しているのだが、発達段階にある子どもたちにたいして、何を手渡すのが一番いいのか、何を手渡さなければならないのか、を常に考えている。「何を」という言葉を使ったのには意味がある。当然図書館なのだから、その「何を」は「本」であると思うだろう。しかし、図書館は本だけを手渡すところではないからである。ビデオやCD? それもだが、それだけでもない。つまり、わたしたち図書館員は、文化を伝えていくという大切な使命があるのだ。いや、図書館員だけの問題じゃなくて、わたしたち「大人」と呼ばれている人は、子どもに対して文化を継承していくという大切な役割があることを忘れちゃいけない、と本気で思っている。大きなことばかりを言っているが、つまりは、「感動を伝える」あるいは、「感動を渡すことをする」ということを言いたいのだ。
「本」は文字で書かれていて、文字は言葉からなっている。言葉は人間が発明? した最高の伝達媒体であり、それらを駆使して、わたしたちは生きている。伝えることは本能であり、喜びだ。喜びを伝えあう。苦しみも伝えあう。悲しみも伝えあう。そうすることによって人々は生きていくことができる。われわれ大人は、生きていくために不可欠なものを子どもたちに伝え続けなければならない使命がある。「本」はそれら人々の声の結晶だ。しっかりとした声は子どもたちに感動を呼び起こすだろう。
詩を書く行為はすべてここにもつながる。
子どもということを念頭において書いたが、わたしが詩を書くということの一つの意義がここにもあるのだ。
1 何かができそう−「rain tree」参加にあたって一言 1999.12.30 金井 雄二
関さんのおすすめにしたがって、三月の末まで「rain tree」にお世話になります。まずお声がかかったとき、この場所をおかりして何かができそうだという予感でいっぱいになりました。というのも、自分の作品が毎週何篇でも載せられ、それは新作旧作を問わないというのですから。もちろん紙版の「rain tree」を出すにあたって新作を書くことも約束しています。掲示期間は三ヶ月間もの長い間です。更新は全部で12回。まとまって何かをするにはいい機会かもしれません。そして、期間終了後もバックナンバーで読めるというのはありがたいことです。
そう、何かができそう、です。何かが…。では何をしようかな?「rain tree」に掲載されるものとして、まず、「詩」があります。そして、「詩を読む」と題しての「詩評」です。そしてこの「雨の木の下で」の「自由エッセイ」です。これから三月の末まで、関さんのホームページに汚点を残さぬようにするため、自分なりに少し構成を考えてみました。第1回目の「雨の木の下で」では、わたしなりの道しるべをみてもらいたいと思っています。
<詩>の欄では…
わたしは今までに詩集を二冊出していますが、その二冊を合わせても40篇ぐらいの量しかありません。しかし、今までやってきた、同人誌、個人誌の発表分、未発表のものなどを合わせると200篇は越しているはずです。もちろん駄作ばかりですし、読むにたえないものもあるでしょう。でも、自分にとっては、出来の悪い子供たちもかわいいものです。なんとかその子たちにも日の目を見せてあげたいといつも思っていました。今回、<詩>の欄においては、最初の6週間を第1詩集「動きはじめた小さな窓から」の拾遺集として、そして後半の6週間を第2詩集「外野席」の拾遺集として集めてみようと思っています。もちろん、その中に随時新作をまじえて、今と昔を比べてみようとも思っています。最低でも毎週3篇ぐらいは、皆さんが読んだこともない作品が載ることになるわけです。なるべく初期の作品から順次掲載していくつもりなので、笑えるものもあると思います。ご期待ください。
<詩を読む>の欄では…
この欄は詩評の場所です。既発表の作品でもかまわないということなのですが、それではあまりおもしろくもないと思いました。わたしは今、岐阜の伊藤芳博さん、札幌の岩木誠一郎さんと三人で「59」(「ゴクウ」と読みます)という同人雑誌をやっています。わたしたち三人は1959年生まれということで集い、世代というものをとらえて詩を考えていこうとしています。そして、もうひとつ考えていることは、詩を読むという行為です。しかし「59」は年3回ぐらいの発行頻度なので、自由な連作詩評はなかなかできそうもありません。そこで、わたしは「rain tree」の中でこれをやったらどうかと考えました。毎週というのは少々厳しいとは思いますが、ちょっぴりスリリングだと思います。
「アメリカ現代詩101人集」思潮社刊、を端から読み進めて、その時点でのわたしの寸評なり感想なりを書きこんでいきます。
どうなることやら皆目見当もつきませんが、詩を読むことの実践をしてみたいのです。息切れしないことを願って、いざ出発です。
<雨の木の下で>の欄では…
「雨の木の下で」という場所は「自由エッセイ」です。テーマが自由というのは書きやすいようでいてそうではないかもしれません。そこでわたしも考えました。<雨の木の下で>の欄ではいろいろなわたしを見てもらおうと思います。音楽、映画、小説、童話、少年詩、絵本、図書館、ストリーテリングのことetc…ほんの少し考えただけでもこれだけでてくるのですから何かかけるでしょう。何でも屋の金井を楽しんでください。
今最高に頑張っている詩人、関富士子さんのホームページにこのような形で掲載していただけるのは、やっぱりチャンスなのではないかと感じています。やるだけやったほうが悔いが残らないし、それでダメでも頑張った事実が自分にあればそれでいいと思っています。関さん、どうもありがとうございます。
これを契機に、インターネットデビューとし、さらに自分のホームページも開ければ最高の結果だと言えます。
読者の皆さん、三ヶ月の間、どうぞよろしくお願いいたします。
 「かない ゆうじ」執筆者紹介
「かない ゆうじ」執筆者紹介
 <雨の木の下で>ポストマン/詩の交流ってなあに(第1回埼玉詩の交流会報告)(関富士子・阿蘇豊)
<雨の木の下で>ポストマン/詩の交流ってなあに(第1回埼玉詩の交流会報告)(関富士子・阿蘇豊)
 <詩を読む>詩と時間(北村太郎を中心に)2 (河津聖恵) へ
<詩を読む>詩と時間(北村太郎を中心に)2 (河津聖恵) へ
金井雄二
「独合点」ができました。今すぐジャンプしてご覧くださいね。金井さん、3ヶ月間、ほんとうにありがとう。金井さんのがんばりにいつも励まされました。関)
金井雄二
no.15 2000.2.25 掲載
「かない ゆうじ」執筆者紹介