
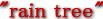 表紙へ
表紙へ
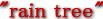 最新号もくじへ
最新号もくじへ
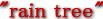 表紙へ
表紙へ バックナンバーvol.16もくじへ
バックナンバーvol.16もくじへ ふろくへ
ふろくへ
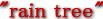 vol.16
vol.16 「みついたかこ」執筆者紹介
「みついたかこ」執筆者紹介
「歴史の風土」(1)かまど (2) 食卓 (3)浜辺の祀り (4)人生とは (5)ギンガム格子 (6)レモン
歴史の風土
(1) かまど
|
二つ。 |
| ならんだ火床の かまどの痕跡 |
| 楕円形の。 |
| 晴天の渇きが露出させる |
| (遠い)異国 |
| 光は理不尽な客である |
| と 旧い本はいった。 |
|
| クリークには舟影も途絶えたまま。 |
| 丘の上の |
| 白い家の、 |
| 窓辺にひるがえる |
| ギンガム格子のカーテンの、 |
| 晴天の、 |
| ものうい若い妻 |
| 冷たい水を飲む |
| 三度も飲む。 |
| 苦しいからまた飲む |
| ときにはうすい砂糖水を。 |
| レモンをすこし滴らせて。 |
| かすかな油分がひろがる |
| その |
| 輪。 |
|
| 消えて行く記憶は |
| 苦い香りがすることもある。 |
| 調査隊はかまどの痕跡を発掘したが |
| 焦げた臭いは見つけられなかった。 |
| 丘の上の白い家の |
| ギンガム格子は青く、 |
| 若い妻は |
| レモンをたらした |
| うすい砂糖水が好き。 |
(2) 食卓
| 定住していたとは思えないと、白髪の講師 |
| はいった。水汲みや食器に用いられたであろ |
| う陶器の、いかなる破片も出土しなかった。 |
| 貝殻の堆積、魚の骨。それでも陶片は見つか |
| らなかった。 |
|
| かまどの痕跡において、火床が二つである |
| 理由を推測すれば、調理時に同時に二つの鍋 |
| を使用する生活が浮かびあがってくる。それ |
| は、シチューとフライが食卓に並びうる豊か |
| な暮し、ということだろう。わたしは、学生 |
| アパートの狭いキッチンを思い出した。お茶 |
| とチャーハンの優先順位は、ちょっとした問 |
| 題なのだった。 |
|
| 貴人や海賊の天幕があってさ、とスープで |
| 汚れた顎ひげまで類想した。 |
| 夫はつまらなさそうに視線を泳がせた。つ |
| まらないのはわたしの方なのに、どうしてそ |
| んな目をするのよ。シチューだけで何が悪い |
| の。わたしだって忙しかった…わけではない |
| ので、もっとつまらなかった。 |
| そうよ、お肉と野菜を別なお皿に盛れば、 |
| 二品になるわ。…シチューはつらい。煮込ん |
| だせいではないのだから。 |
|
| 煮込んだせいではないのだが、うんざりす |
| るアブラ臭さ。窓のカーテンが揺れている。 |
| 明日も同じような一日になる、そうなのね。 |
| やっぱり、そうなのね。 |
| 明るい青空と、長い長い午後。待っている |
| だけの、ずうっと待っているだけの、わたし |
| の吐き気。 |
| 静かで、清潔な、わたしたちの家。 |
 <詩>「歴史の風土(3)浜辺の祀り」(三井喬子)へ
<詩>「歴史の風土(3)浜辺の祀り」(三井喬子)へ
 <詩>四月の茄子(三井喬子)へ
<詩>四月の茄子(三井喬子)へ
 <詩>モクセイの木(関富士子)へ
<詩>モクセイの木(関富士子)へ
(3) 浜辺の祀り
| 今はもうないよ。嗄れ声の男がそういった。 |
| 今はもうないよ。いつだったかここは改装され |
| て、石も砂もみんな均してしまった。だから、 |
| 有るといえば有って無いといえば無い。人生と |
| はそういうものさ。といった。 |
|
| 波の音が猛々しい夏の終わりの浜辺で、少年 |
| がいなくなった。探しに探したが、足跡もなく |
| 衣服の切れ端もなく、命終わるとはこのような |
| ことかと、みんなで黒い服を着て歌を歌った。 |
| 安らかにお眠り下さい、…とはいえなかった。 |
|
| 嗄れ声の男がいう人生とは、遠い異国に拉致 |
| されて、つくりかえられる記憶のようなものだ |
| ろうか。地下室で浄化される液体のようなもの |
| だろうか。納得したとは言い難く別れて、黒い |
| 服を脱いだ。 |
| ほんとうに無くなってしまったのだろうか、 |
| 「それ」と、「あれ」。 |
| 無くなるのだろうか、「これ」。 |
|
| 波が運んでいたものは、おなじメゾソプラノ |
| の声、だった。あの声は、もう帰る身体がない |
| から眠れないのだ。眠りは在ることの一つの |
| 様態だと、わたしは思う。在らぬ身体が、ど |
| うして眠れるというのだろうか。 |
| 在らぬ、そう、在らぬ傷痍には、いかなる |
| 治癒も望めないのだ。と、痛みつつあるもの |
| に不意に紛れ込む、小さな物語。 |
| あなたは痛くないか。あなたは、痛くない |
| のか。 |
『イミタチオ』 第34号掲載 金沢近代文芸研究会 平成12年1月31日発行
 <詩>「歴史の風土(4)人生とは」へ
<詩>「歴史の風土(4)人生とは」へ <詩>「歴史の風土(2)食卓」へ
<詩>「歴史の風土(2)食卓」へ
(4) 人生とは
| 人生とはそういうものさ。と嗄れ声の男は |
| いった。そして、それほど分かったふうでも |
| なく、煙草をくちゃくちゃにして立ち上がっ |
| た。 |
|
| 人生とはそんなふうなものか。黄砂が風景 |
| をセピア色にしたその日、もういい、と思っ |
| た。切開された腹が人体解剖図のとおりだっ |
| たかどうか、わたし自身には分からないが、 |
| それでもそれは、秘密に属することではなく |
| なった。光は、理不尽にも、内部を明らめた |
| のだ。もうどうでもいいと思って、調書に署 |
| 名した。 |
|
| 人生とはそんなものよ。と、友達だった女 |
| にいった。精一杯の皮肉は通じず、彼女は傷 |
| の具合をルーペで調べるのだった。 |
| そんなものだとわたしは思う。遠景はかす |
| んでしまって、太陽はもはや生命のない円盤 |
| だ。イメージは生命を生起させるだろうか。 |
| 明日になれば、太陽は再び輝くだろうか。 |
|
| 欲しけりゃあげるわよ。と友達だった女は |
| いって、西の空にはしごをかけた。苦もなく |
| 日輪をはずすと、ぽいと投げてよこした。卑 |
| 屈さに胸を高鳴らせながら、急いで手を出し |
| た。傷口が、ぱっかり開いて、世界は真っ赤 |
| になった。ああ、夕焼けだ…、嗄れ声の男の |
| すった煙草が、人生を焦げ臭くさせている。 |
 <詩>「歴史の風土(5)ギンガム格子」へ
<詩>「歴史の風土(5)ギンガム格子」へ <詩>「歴史の風土(3)浜辺の祀り」へ
<詩>「歴史の風土(3)浜辺の祀り」へ
(5)ギンガム格子
| 青 鳥 青 花 青 蝶 青 春 青 |
|
淡 青 冷 青 湿 青 弱 青 寂 |
|
青 夢 青 恋 青 望 青 真 青 |
|
失 青 悲 青 憂 青 鬱 青 黴 |
|
青 希 青 信 青 友 青 和 青 |
|
変 青 性 青 罪 青 怯 青 冥 |
|
青 空 青 海 青 知 青 癒 青 |
|
藻 青 魔 青 死 青 喪 青 闇 |
|
青 愛 青 円 青 聖 青 鐘 青 |
 <詩>「歴史の風土(6)レモン」へ
<詩>「歴史の風土(6)レモン」へ <詩>「歴史の風土(4)人生とは」へ
<詩>「歴史の風土(4)人生とは」へ
(6) レモン
| わたしの「死」は |
| ほんとうに わたしのものだろうか |
| わたしが死ぬことが |
| だれかも死ぬことになる |
| そんなことも ある |
| と わたしは思う |
|
| わたしの身体の奥深く |
| 喜びや悲しみや怒りを わたしと |
| 時間や広がりや厚みを わたしと |
| 共有している あなたの |
| その「死」は |
| あなただけのものであろうか |
| わたしに含まれる あなた |
| 未来という あなた |
| 過去がわたしの一部分であるように |
| あなたもわたしの一部分である |
| レモンレモン レモン |
| 受胎の光は 未分のわたしたちを引き裂いて |
| わたしたちがわたしたちである日々から |
| 記憶を食らい |
| 意味を抹消し |
| あなたがわたしたちであることを失わしめる |
|
| クリークの水面は |
| 半ばは暗く 半ばは輝いている |
| 船着場には鳥たちがざわめき |
| ああ 誰も彼もが帰る時刻だ |
| カーテンを揺らし |
| さわやかに往くものよ |
| 歴史の風土は |
| ときに吐き気をもよおすにおいがする |
| さようなら という声すらなかったが |
| 若い妻は |
| レモンが好き |
 <詩>「一枚のレコード」(豊田俊博遺稿詩集『彗星』より)へ
<詩>「一枚のレコード」(豊田俊博遺稿詩集『彗星』より)へ
 <詩>「歴史の風土(5)ギンガム格子」へ
<詩>「歴史の風土(5)ギンガム格子」へ
<詩>「歴史の風土(3)浜辺の祀り」(三井喬子)へ
<詩>四月の茄子(三井喬子)へ
<詩>モクセイの木(関富士子)へ
<詩>「歴史の風土(4)人生とは」へ
<詩>「歴史の風土(2)食卓」へ
<詩>「歴史の風土(5)ギンガム格子」へ
<詩>「歴史の風土(3)浜辺の祀り」へ
<詩>「歴史の風土(6)レモン」へ
<詩>「歴史の風土(4)人生とは」へ