
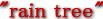 vol.18
vol.18
「そんなふうに生きている」 布村浩一の詩を読む
須永 紀子
|
布村さんの詩を初めて読んだのは、1992年『ジライヤ』の9号誌上だった。「ぼくのお城」と「お茶の水駅」。大らかな、どこか少年っぽさのある作品で、若い人にちがいないと思ったのだが、1952年生まれだというので驚いた。詩もご本人も、青年らしいナイーブなところをたくさん持っていて、実年齢よりもずっと若くみえる。
第1詩集である『布村浩一詩集』(1992年・私家版)には、生まれ育った土地での疎外感や孤独が色濃く出ている。嘆きや憎悪は抑えられ、どの作品も見開きにおさまる長さ。スタイルはすでに決まっていて、「口数の少ない詩」というような作風はこの頃からのものだということがわかる。
2冊目の詩集『ぼくのお城』(1995年・昧爽社)は、都会での生活が基盤になっていて、詩の世界はぐっと広がっている。ことばの運びがあまりにも自然なので、なかなか気づかないかもしれないが、うまい詩人だと思う。生の気持をそのまま出しているようにみえるけれども、読む者に不快感をまったく感じさせない。ものを書くという行為においては、自分の嫌な部分がかなり出てくるものだが、そこを削っていくという作業が大きなウェイトを占めるのではないかと、わたしは常々思っている。おそらく布村さんもまた削るというプロセスをしっかりおさえている詩人であるに違いない。
捨ててきた故郷があり、失った恋と敗北の体験がある。「この迷路を越えたら 水路の果て、港で、/きみに言ってやる(ぼくがいつも上手くしゃべれないとは限らない)」(説明)シャイで、不器用な男性。何をやってもうまくいかない。そういうことを書いた詩が、わたしたちに不思議なやすらぎのようなものを与えてくれる。詩のなかの「ぼく」は駅でわかめそばを食べたり、弟にもらった週刊誌を読んだりする。とてもつつましい生活。そして恋をする。「ぼく」は孤独を抱えた一人の男として女性と向かい合う。女性の歓心を買うようなことはしない。精神的、肉体的な強い結びつきを求めているのに、意中の女性に彼の想いは伝わらず、失った恋の思い出が、彼の人生に加えられていく。
布村さんの詩を読んでわたしたちは、自分自身に忠実に生きるというのはこういうことではないか、と思うのではないだろうか。そして自分に即した生活の、さまざまなシーンを書いていると理解するのだと思う。何か特別なこと、ドラマや感動を書くもの、というのが、おそらく詩というものの一般的なイメージだろう。けれども実際には、人間の一生のほとんどは、生活するための細々した仕事や行為を繰りかえすことに費やされる。布村さんは、そういう自分の姿や思いを、それ以上でも以下でもない大きさで書く。
生きていくなかで、わたしたちは知らないうちに貪欲になっていく。少しでも裕福な暮らしを望み、いいカッコをしようと無理をしてしまうのだが、布村浩一は「精神が折れた後の生」(あとがき)を、ゼロの状態からひとつずついとおしむようにやっていく。他人が見たら何でもないありふれた風景も、「折れた精神」の回復を願う彼にとっては、丸ごと掬う価値のある、大切なものなのだ。そのなかでつぶやきのように漏れる素直な気持ちを書きとめる。
今自分の在る場所、ずっとそこにあるもの、堅い意志、質素な生活。そこから生まれる布村浩一の詩は、体温と声をもったものとして、わたしたちに手渡される。
「ぼくは自分の中をみつめるよりも、窓の外をみつめてしまう。ぼくはそんなふうに
生きている。ぼくの中心は窓の外にあるんだ。」(横浜)
 <詩を読む>牛島敦子『緯線の振子』(砂子屋書房)を読む(三井喬子)へ
<詩を読む>牛島敦子『緯線の振子』(砂子屋書房)を読む(三井喬子)へ
 <詩を読む>長尾高弘詩集『頭の名前』を読む(桐田真輔)へ
<詩を読む>長尾高弘詩集『頭の名前』を読む(桐田真輔)へ