
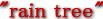 vol.19
vol.19 執筆者紹介(木村恭子)へ
執筆者紹介(木村恭子)へ
「芽キャベツ記」は、散文詩七編、行分け詩十七編で構成された、広島県呉市在住の木川陽子さんの第三詩集である。その第一詩集「眠りのなかまで」は私には忘れられないものであった。夢を題材にしながら、読者を現実世界と夢の世界を行きつ戻りつさせるような技法、誰しもが背負わねばならない、名指し難い悲しみのようなものが漂う内容は、当時まだ、現代詩の何であるかを今ひとつ会得できないでいた私にとって、驚きであると同時に現代詩についての私なりの了解ともなった。
爾来十三年、間にその技法を更に高いものにした詩集「誰?」を経て、木川さんがこの「芽キャベツ記」に彫琢されたものは、技法の有無や効果を問うて学ぼうとする、私の浅薄さをも包むような、慈味とも呼ぶべきものではなかろうか。
「芽キャベツ記」の中で、私が一番心打たれた詩は「戻らなければ」という作品である。木川さんの詩の殆どがそうであるように、この作品にも難解な言葉はどこにも見当たらない。読点と句点が意識的に排除されている事により、 抑制の効いたモノローグが、日常の何気ない呟きのように聞こえてくる。作中のわたしは、実は人工呼吸器に助けられて昏睡している病人であるが、詩人の創造力により、自由な魂を与えられ、今、病室のベッドを離れ、健康であった頃の職場の窓が見える川べりにいる。その事を簡潔に述べた一連から三連を受けた上での、四連は次の通り。
もう戻らなければ 妻が体をふいてくれる時間だ なに
もこたえてやれなくなったわたしにできるのは 妻が看
護するとき そこにわたしがいることだけだから
身近な者が病んだ時、私達は病人を医師や看護婦に託すしかない。そして、自分にできる事は体をふいたり、匙で食事を与えたりする事だけだと感じる。が、詩人は、昏睡状態にある病人の魂にさえも、このように語らせるのだ。/私にできるのは 妻が看護するとき そこにわたしがいること/と・・・。
病人とその妻の愛を俯瞰する、第三者(作者)の視点としてこのフレーズは深く暖かい。
そして、この美しい詩は五連でこのように閉じる。
戻るときちょっとしたこつがいる ほら なわ跳びのな
わに入るように 呼吸を人工呼吸器のリズムにあわせれ
ばいい そうむつかしくはない
この連の巧みさの前で、私はいつもため息をつく。それまでの状況説明から一転、この連によって私達読者も又、なわ跳びの中に一人づつ入ってゆき、次に足を置いた場所はまぎれもない「詩」の中なのだ。
詩集の終わり頃にある「デイケアルーム午後三時」と「草の中」について語るのは、今療養中の作者をどうしても思い出してつらい。
「デイケアルーム午後三時」の一連は、
カップの底に沈んでいた桜桃を
舌の上で
そっと転がしていると
誰かわたしにささやいた
<──もう、いい>
おそらく、一日のリハビリを終えた午後三時のくつろいだ時間。詩人の耳元で、ふと、<──もう、いい>という、ささやくような小さな声が聞こえたのである。二連で詩人はその声の主を探す。隣の席に座る人に尋ねると、「いいえ なにも」とだけ答えるが、詩人には、その小さなささやき声が誰のものかという事が、ふと理解できたのである。
読み方によっては、声の主はその隣人である。しかし、詩人の視野は、ここですべての弱者-----、運命と呼ばれる不可抗力の領域で、苦戦を強いられている、病者をも含む力弱きすべての生きるものの姿を、捕らえたのではないかと、私は思う。詩集の次ページに置かれた「草のなか」を読む事によって、そう思えてくるのだ。
草のなか
ジャコウアゲハの黒い幼虫が這っている
ウマノスズクサを求めずいぶん遠く来たのだ
<食草しか食べられないというのは
知恵なのか 無残なのか>
秋雨の降る前に蛹になるには
まだまだ食べ足りなかった
雨もよいの空の下
小さなちいさな存在が ただ這っている
丈高い草のなか
方向もなく (全文)
「草のなか」は十行に納められた小品である。だがここに置かれた水彩画のようなスケッチの中で、ジャコウアゲハの幼虫は額縁を乗り越えて、読む者のこころにまで懸命にひたすら這い進んでくる。/<食草しか食べられないというのは知恵なのか 無残なのか>/------言ってみれば、この問いかけに答えるために、私達の生はここに現出しているのではないだろうか。
そして、小さなちいさな存在が一生懸命、ただ這っている情景を、その低い低い場所に身を置いて、このようにうたう事のできる木川さんの、技法やテクニックをはるかに越えた慈味に私は打たれる。
木川陽子詩集「芽キャベツ記」
発行2000年11月15日
発行所  夢人館
夢人館
 <詩を読む>第二の男の肖像(
藤富保男詩集『第二の男』を読む)(関富士子)へ
<詩を読む>第二の男の肖像(
藤富保男詩集『第二の男』を読む)(関富士子)へ
 <詩を読む>田中宏輔詩集『The Wasteless Land.』を読む(桐田真輔)へ
<詩を読む>田中宏輔詩集『The Wasteless Land.』を読む(桐田真輔)へ
夢人館