<詩を読む>
 倉田良成詩集『六角橋ストリート・ブルース』を読む 関富士子
倉田良成詩集『六角橋ストリート・ブルース』を読む 関富士子
 見たものを言葉に 宮沢賢治「小岩井農場」を読みながら 関富士子
見たものを言葉に 宮沢賢治「小岩井農場」を読みながら 関富士子
 「恐ろしくて」北村太郎「幼年の日の記憶」を読む 関富士子
「恐ろしくて」北村太郎「幼年の日の記憶」を読む 関富士子
倉田良成詩集『六角橋ストリート・ブルース』を読む
関 富士子
|
わずかに翳ったような黄金色の表紙を開くと、ページの間から「雲霞のような音楽」がたちのぼる。一行の長い倉田良成の詩のスタイルは、幾本もの弦をもつ楽器のようにかき鳴らされ震えて、わたしを黄金の世界にいざなう。
金の陽にまみれた街路樹の黄葉がおののくバス通りで 夕ぐれ
透明な物売りの声を張りあげる鳥屋の老人の背後には
あの、はるかにきらめく大河と海の幻が押し寄せているのではないか 「六角橋ストリート・ブルース」(部分)
実に胸板の厚い詩人である。歌手はからだ全体が楽器であるというが、倉田良成の骨格の大きな屈強な詩形からは、繊細極まりない言葉の旋律が流れるのだ。紙の余白のぎりぎりまで延びせまり、さらに深く降りていく一行が、惜しむかのようについに途切れるとき、ふかぶかと息を吐く詩人の胸のふいご。そして新しい行にかかるとき、胸郭はいっぱいに膨らみ、旋律が自在に起伏を作り、息の続くかぎりまで変化する。それは、金色の蜜に包まれた夢のような世界、「きみと私」の物語だ。
三百年以前のあまい旋律は時をくぐり、ことしの夏を迎えるきみと私の喉笛に流離する
まだ大人になる前に写した少女のきみのおもざしが
まるで千年を隔ててあらわれたみずら髪の少年の淡い肖像のように蘇る 「もし夏の片隅に」(部分)
世紀の半分近くを離ればなれに生きた男女があるとき出会う。女は男にささやく。「次のときもわたしのなかに生まれ変わって」。それが前作『海に沿う街』の物語だった。あれから三年。人と人がめぐり合う不思議、千年前に約束された愛なら、千年後もともに生きたいという願いが、『六角橋ストリート・ブルース』にも変わらず切々と貫かれている。
最愛の女と暮らす幸せのなかで、男は、出会わないで過ぎた年月に思いをはせる。それは、自らの生きてきた時を振り返らせ、他者の時間にわが身を重ならせる行為でもある。そのときいつも彼を導くのは、写真でしか知らない思春期少し前の少女の面影だ。離ればなれの少女と少年だったとき、時代はどのように彼らを過ぎたか。音楽は逝った時を蘇らせ、今この時を寿ぐ。時代の音楽に囲まれて、わたしたちはこの時をどのように生きるのだろう。
ジョン・レノンの「イエスタデイ」の出だしは一小節たりない
いまではどこもおかしくは聞こえないのに、ときみは言う
「青空のためのグラフィティ」(部分)
ブルース、シナトラ、ショパン、ピアソラ、ディキシー、サンポーニャの笛の音……。そして、かたわらで妻が弾くエチュード。音楽に寄せる倉田良成の言葉は、いつ味わっても心を酔わせる。生なままで提示されたものは一つもない。時代への認識に裏づけられ、長い思索のときを過ごしゆっくりと醸成されてから、詩となって浮かび上がるのだ。誠意をこめて吟味された上質な言葉なので、けっして悪酔いしない。描写は叙述的でありながら散文では得られないつややかな色がある。安心して酔いしれながら詩集の後半へきて、ふと音楽が途切れるときがある。背後に迫った死の影、「黒き馬」におののきつつ、妻を彼の生まれ故郷に誘う「国府津まで」の詩人の声。
われわれは徒党を組み、コンバット・ゲームの真似っこに夢中で
青空のあだごとのような少年期の倦怠から、虚弱な体躯のナガサキさんという子を
彼女のバラックの家まで押しかけていって嘲笑い、晒し者にした
「国府津まで」(部分)
たんたんと妻に語りかける口調は、親密でありながらなんと悲しげなのだろう。少年時代の悔恨と父への愛と憎悪を語りながら、すべての存在へのいとおしさと、つかのまの生の寂寥に、やさしくかすれている。
巨きな夕ぐれの、凪、という思想を繋留して、グラスのなかの鮮烈な日没を飲み干す
きみと私の身体が仮のバス停で、ふらつきながらやってくるやくざな異界のバスを待つ間 「MELIORのある町」(部分)
田川紀久雄個人詩誌「漉林」102号掲載予定)
『六角橋ストリート・ブルース』倉田良成詩集
2001年5月11日刊 私家版 \1500
ご注文は "rain tree"関富士子へ。関から倉田さんへお知らせします。 "rain tree"関富士子へ。関から倉田さんへお知らせします。
倉田良成さんの詩は、以下で読むことができます。
"rain tree" vol.7  倉田良成の詩 倉田良成の詩
 清水鱗造HP Booby Trap 清水鱗造HP Booby Trap
|
見たものを言葉に 宮沢賢治「小岩井農場」を読みながら 関 富士子
|
見るとはどういうことだろう。風景を描こうとするとき、言葉は映像にかなわない。人間は、目に映った景色をすべて均等に見ることはできない。見たと自覚できるのはそのほんの一部にすぎない。
「小岩井農場」(宮沢賢治詩集『春と修羅』所収)は、大正時代末の盛岡駅の停車場から農場までの二〇㎞の道中を描いている。手だれの映写技師が写す古いフィルムのように、明るい雨の降る風景が、歩くスピードでくっきりと動いていく。その導入となるパート1に見たもの。
黒塗りのすてきな馬車だ
光沢消しだ
馬も上等のハックニー
このひとはかすかにうなづき
それからじぶんといふ小さな荷物を
載つけるといふ気軽なふうで
馬車にのぼつてこしかける
「わたくし」も乗ったほうがいいのだがと思いながら乗らずに見送り、てくてくと歩きだす。読み手もいっしょに春のぬかるみの農道を行くことになる。新開地を過ぎ畑や野原や牧場や七つ森というように風景が継起する。 頭上ではひっきりなしに鳥が鳴いている。
「わたくし」は、医者や農夫や荷馬車の馬や娘たちに出会い、語りかけ、夢想し、思索し、高揚していく。ウォーカーズ・ハイ。そのとき、歩く人、見る人の脳内に、いったい何が見えるのか。
ユリア ペムペル わたくしの遠いともだちよ
わたくしはずゐぶんしばらくぶりで
きみたちの巨きなまつ白なすあしを見た
詩人がカタカタと回すフィルムに、「巨きなまつ白なすあし」が映っている。人間は目に映るすべてのものを見ることはできないが、ほんとうに見るべきものは必ず見えているのだ。そして読者は、詩人の言葉によってそれを再び見ることができる。
宮沢賢治詩集1(ちくま文庫より)
文集「COLOUR」no.7 2001.7掲載予定
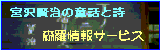
宮沢賢治の童話と詩宮沢賢治の童話と詩 森羅情報サービス で、賢治の詩や童話を読むことができます。 |
「恐ろしくて」 北村太郎「幼年の日の記憶」を読む 関 富士子
|
北村太郎は、鮎川信夫や田村隆一など、ほかの「荒地」の詩人たちに比べると、季節や生物を題材にした作品が多い。日常的な光景を感覚的に書いた詩人という感じがする。そのせいか、時代の変化に磨耗することから免れて、いつ読んでも初めて触れたときと印象が変わらないものが多い。
幼年の日の記憶
北村太郎
はるじょおんだらけの
するどい匂いの野はらも
葉を噛んだ酸っぱいおおばこの味も
首をそむけて逃げたどくだみの暗い繁みも
すっかり忘れた 恐ろしくて
ひろい畠の果ての森のうえ
空は真赤な夕やけだった
ぼくは眼を大きく開いて見ていた
「あの夕やけは幽霊だよ」
ぼくはぶるぶるふるえていた
ぼくたちは汗くさい六人だった
「あれは幽霊だよ」
(「小詩集」『冬の当直』より 現代詩文庫 思潮社刊)
それにしても、「すっかり忘れた 恐ろしくて」が、いつ読んでも何となくひっかかる。忘れた理由というのが「恐ろしくて」なのだから、よほど恐ろしかったのにちがいない。
ところが、「すっかり忘れた」はずのはるじょおんの野原の匂いも、葉の味も暗い繁みも、はっきりとしたリアリティをもって描かれている。読む者の感覚に共振して、嗅覚や味覚や視覚を刺激し、忘れていたこどものころの自然界の恐怖を喚起する。
記憶を持続し、あるいは甦らせて何十年後かに書いているのは詩人自身だ。「首をそむけて逃げた」という身振りまで、ありありと覚えている。夕焼けを見て震えたことをもちろん忘れていない。詩を読むとき、詩の中の一人称は作者自身とほんの少しずれていて、その微妙な隔たりに詩を読むスリルを感じることがある。
「すっかり忘れた」という表現は、矛盾のようで真実な、北村太郎らしい逆説的な言辞だ。彼は忘れることができなかったのだが、その理由もやはり「恐ろしくて」なのだろう。
そんなことを思いながらもう一度詩を読み返すと、ここで最も鮮やかに存在しているのは、あくまでも「すっかり忘れた」「ぼく」である。「ぼく」は、幼年の日に、世界じゅうに遍在する幽霊を全身に感じて、恐怖のあまり「すっかり忘れた」のだ。
「忘れた」は過去形ではなく現在に継続している。今も「恐ろしくて」記憶をなくし続けている者。詩人はそんな「ぼく」を抱えたまま生きている。この詩が何か奇妙に恐ろしい印象を与えるのは、そのせいもあるのかもしれない。 |
紙版「rain tree」no.20 2001.5.25より
倉田良成詩集『六角橋ストリート・ブルース』を読む 関富士子
見たものを言葉に 宮沢賢治「小岩井農場」を読みながら 関富士子
「恐ろしくて」北村太郎「幼年の日の記憶」を読む 関富士子
"rain tree"関富士子へ。関から倉田さんへお知らせします。
倉田良成の詩
清水鱗造HP Booby Trap